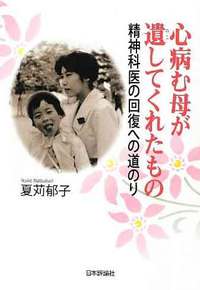脳は平気で嘘をつく 「嘘」と「誤解」の心理学入門

脳は平気で嘘をつく 「嘘」と「誤解」の心理学入門
内容:
第1章 男はなぜ美人に騙されるのか?
第2章 あなたの記憶は捏造されている
第3章 仕種で嘘は見抜けるのか?
第4章 誤解されやすいあなたへの処方箋
第5章 リーダーに求められる「メタ認知能力」ほか
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さんまちゃんの「ほんまでっかTV」の植木先生の本です
考えてみたら、香山リカさんの本は沢山読んでいるけれど、植木先生の本は読んでない?って思って図書館で借りてみました。テレビの印象は「とてもわかりやすい言葉で話す先生だな」って思っていたのですが、本も一般の人にもわかりやすい言葉で書かれていました。
その中で、少し前から私が悩んでいたことが書かれていて1つ悩み事が解決しました。それは、私にとってはとても気になることだったので本当に「ほんまでっか!」って感じでした

・・・世の多くの人は「安寧に過ごしたい」「平穏な時が一番いい」と思っているのだろうが、男女問わず存在する”怒りっぽい人”はそんなことはお構いなしに、周囲の平穏なひとときを自らの怒りで破壊する。
なぜすぐに怒ってしまうのか? それにはいくつか理由がある。 そのひとつとして挙げられるのが「相手への期待感が高い」ということである。
「自分がこう考えているのだから相手も当然そう考えているだろう」という思い込み。 これを心理学では”心の浸潤性”というのだが、研究の結果からすぐ怒る人というのはこの浸潤性が普通の人に比べて格段に高いことが分かっている。
十人十色という言葉があるように、人はそれぞれにいろんな特徴があり、得意なこと、苦手なことも一人ひとり当然異なる。
それなのに、「相手もこのぐらいはするだろう」という思い込みが強ければ、毎日が期待外れの連続になるのは言うまでもないことだろう。 心の浸潤性が高い人は、期待が毎日のように裏切られ続けるから怒ってしまうのである。
逆に浸潤性のあまりない人、「自分は自分、人は人」と割り切って考えられる人は怒ることが少ない。
もうひとつ、すぐ怒る人に共通しているのは「自己主張が下手」ということである。 怒りをぶつけられている方、つまり怒鳴られている方というのは、怒っている人が何を言いたいのかよく分からなかったりする。
怒っている人というのは感情的になってしまっているので当然の話かもしれないが、当の本人は相手に主張がすべて伝わっていると思っている。 これが困ったところなのである。
怒りっぽい人はアサーション(相手も自分も思いやるコミュニケーション方法)の力が欠けているのだ。
怒りを表出しても、そこに主張すべき情報量が少ないから相手は何に対して怒られているのかよく分からない。 それでは相手は「あ、また怒られた」と思うだけで対処の仕様も思いつきようがない。 そんな相手を見て、怒りっぽい人はさらに怒りの度合いを深めてしまうという悪循環にはまっていくのである。・・・
怒る・怒らないは別としても、先日のカラーセラピーの集まりの時にクライアントの方が塗ったものに対して「自分はこうなのに、なぜそうじゃないのかなと思う」という話がありました。彼女はクライアントさんが塗ったものが線からはみ出ているのが嫌(ここまでならいいけれど、これ以上なら嫌というのがある)というのですが、そのクライアントさんの大まかな人物像からは「おおざっぱな性格」を感じる人で、私が「そんなに細かい人じゃないのに、反対に塗ったものがめっちゃ細かかったら変やん」って言ったのですが、彼女はそれが嫌ということ。個人的には私のクライアントさんでも同じような人がいた時に私も「えらい、はみでてるがな!」と思ったけれど、塗っている時の表情やその後の会話にそれまでの付き合いなどから、その方の性格がわかっていたので「大らかな人だからそうなんだろうな」くらいに感じていました。
自分自身は確かに「はみでたくない」とか、線をきちんと引かなければ気に入らないこともありますが、それもその時の気分もあるので「まっ、いいか」という考えになっていました。それとクライアントの人に塗り絵をお願いする時に「自由にぬってください」と言っているのに、自由にぬってもらったものに対して「それは自分の考えとは違う」というのは、あまりにも身勝手な気がします。厳しい言い方ですが、それが自分たちの相手への姿勢だと思っています。
私には、むしろ「それが嫌」と認められないほうに何かがあるような気がしていました
そんな時に見つけたのが植木先生の本でした。こういう出来事ってあると思います。自分が悩んでいる時に偶然、読んだ本に答えを見つける。でも、これってやっぱり偶然ではないのだと思います。案外、私が今まで読んだ本の中にも同じ言葉があったかも知れません。でも自分自身がその事に対して疑問を持っていなければ見つけ出すことや心に響くこともなかったのかも知れないと思います。私は同じような本を何冊も読みます。でも覚えているのはほんの一握りでしかないし、なぜ覚えているか考えるとやっぱりそれは、自分にとって大切だと思っていたからだと思います。だから、繰り返し繰り返し同じような本を読む。
たまに、ほんとに同じ本を図書館で借りていて、びっくりすることもありますが・・・
これって、単純に「ぼけてる・・・」って事なんでしょうね

母性社会日本の病理 ~河合隼雄~
アサーション入門――自分も相手も大切にする自己表現法
心病む母が遺してくれたもの: 精神科医の回復への道のり
シロクマのことだけは考えるな!
本当の気持ち~アサーション~
人の話を聴く技術 対話で心をケアするスペシャリスト《精神対話士》
アサーション入門――自分も相手も大切にする自己表現法
心病む母が遺してくれたもの: 精神科医の回復への道のり
シロクマのことだけは考えるな!
本当の気持ち~アサーション~
人の話を聴く技術 対話で心をケアするスペシャリスト《精神対話士》
2013年09月22日 Posted byすもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・心理学
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。