スポンサーリンク
母性社会日本の病理 ~河合隼雄~

母性社会日本の病理 ~河合隼雄~
<本の紹介>
心理療法をしていて、最近とみに心理的な少年、心理的な老人がふえてきた、と著者はいう。本書は、対人恐怖症や登校拒否症がなぜ急増しているのか、中年クライシスに直面したときどうすればいいのか等、日本人に起こりがちな心の問題を説きながら、これからの日本人の生き方を探る格好の一冊。「大人の精神」に成熟できない日本人の精神病理がくっきり映しだされる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
先日、たまたま町カフェの休憩をしている時に、古本の販売をしている一角を見つけ、ぼ~~~~~っとして、座ったままで見ているとこの本が目に入りました
あれ?これって私が読みたかった本??
で、近づいてみると確かにそうでした
しかも古本だったので、たったの30円!
これは買うしかないな~~と、重たいのに買っていました
読んでみて感じたのは、今の色々な問題点の原点ともいえるような事柄が書かれていました
しかも、この文庫本の出版は1976年です。
その長い歳月の間に、母親との関係性がますます歪んでいったのかな・・・と感じた
そして、それは母と娘だけでなく社会として何かが大きく変化しているように感じました
最近の会社内でのモラハラやパワハラ、そして、企業へのクレームも根本は同じようにも感じます
ただ、母系社会のいいところには「人を許す優しさ」も含まれているようにも感じるのですが・・・
もう1度、社会の中で親との関係や大人とは何か?を考え直す時期がきたのかなって感じた私です
2014年02月04日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・心理学
アサーション入門――自分も相手も大切にする自己表現法

アサーション入門――自分も相手も大切にする自己表現法
本の中で、目からウロコな話が書いてありました
アサーティブは人になるには「ドラえもん」のしずかちゃんを見習うこと。
もしもケシゴムを取られたら、ジャイアンなら「返せよ!」と攻撃的な対応になると思います
それが、のび太くんなら何も言わないでドラえもんに泣きついていそうです
そんな時に、しずかちゃんなら「ケシゴム終わったら返してね」というか
「今度からケシゴム『貸してね』って言ってね」というだろうということでした
自分がしずかちゃんになった気持ちで話してみる。
それが「自分も相手も大切にする自己表現」ですね

2013年12月19日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・心理学
心病む母が遺してくれたもの: 精神科医の回復への道のり

心病む母が遺してくれたもの: 精神科医の回復への道のり
・・・・・「『ラジオ深夜便』聞いて。ほんとに毎朝、大晦日も元旦も雨が降っても雪が降ってもここへ来て、ちょっとシャキッとすんの。もうなんにも楽しみないからね。そうそうあんた、〈深夜便〉でなんども繰り返し放送された話。あれは泣けた。もういっぺん聞きたいんだけどな」
あとで調べた。4時から放送される「明日へのことば」というコーナーで紹介された話だった。タイトルが『統合失調症の母との歩み』という。
私が2歳のとき母は「発症」した。父は外に女をつくり帰ってこない。娘の私は母の料理をいちど「美味しい」といった。母はそれを8年間毎日つくりつづけ、自分はせんべいだけを食べ、ひたすら煙草をすいつづけていた。
夜は寝ずに闇のなかをのそりのそり歩きまわり、わけの分からないことをぶつぶつ呟く。家は貧しい。中学になって、母が制服をつくってくれた。できあがったのは変なもので、あちこち針が残っていた。学校ですさまじいいじめにあった。踊り場から突き飛ばされた。
転げ落ちて、スカートがめくれ、下着が丸見えになった。落ちた痛みより、そのことが恥ずかしかった。私は、突き落とした5人の男女を階段の下から見上げて、心に決めた。「あいつらより絶対にいい人生を生きてやる」
同時に母への怖れが憎しみに変わった。身なりが貧しいからこんな目に遭う。母を恨んだ。見返してやる職業をめざす。医学部に合格し、精神科医になった。精神科の勉強で、母の病気は〈統合失調症〉だったと知る。
だが同時に思う。目的を達成しても、動機が復讐だと心は救われない。私の過去はボロボロだ。そしていまは孤独。母とはまったく会わなかった。もう1分1秒も生きたくない。2度の自殺をはかる。
助かったが、しょんぼりと生きていた。人にいわれた。お母さんとこのまま会わなかったら、あなた自身が幸せになれない。そうだ、母を見捨てたままでは、自分はどうせろくな人生しか生きられない。札幌の奥の方に住んでいた母親に会いに行く。
母は空港まで迎えに来ていた。1台1台のバスに首を突っ込んで、私の名前を呼びながら探している。「いっちゃん、いっちゃん」その姿が目に飛びこんできて私は驚く。なんてちっちゃくなったんだろう。再会への不安も恨みもすべて消し飛んで私は声をあげた。
「お母さん」
ひとり暮らしの家に入ると、あの8年続いた料理が出てきた。母の私への思いは子どものころに止まってしまっていた。
私は50歳を過ぎている。人が回復するのに、締切はない。「もう遅い」といってしまってから、可能性はしぼんでいく。精神科医、夏苅郁子さんの話は、圧倒的な共感を呼んだ。中村プロデューサーも驚いた。
「別の枠で再放送したらまた要望があって再々放送。〈深夜便〉だから長いお話を静かにお届けできて。この時は、若い人からも痛切な感銘が寄せられました」
※週刊ポスト2013年11月1日号
http://www.news-postseven.com/archives/20131027_223487.html
統合失調症の母との歩み 児童精神科医が本出版
http://iryou.chunichi.co.jp/article/detail/20120815152049067
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この記事を読んで、この本が読みたくなりました
少し前に岡田尊司先生の「シックマザー」「母という病」という本を読んでから、私の中で「心を病んだお母さんに育てられるというのは、どういうことなんだろう?」と思っていました
そんな時に出会いました
文章は正直、上手ではないと思いました。そして、少し押し付けがましい部分も感じました
でも、読み終わった後で少しだけホッとしている自分がいました
2013年11月01日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・心理学
シロクマのことだけは考えるな!

「シロクマのことだけは考えるな!」
植木理恵著
心理学の本は、結構読んでいる気がしますが「シロクマ」は本当に面白かったです
その中で、先日も書きましたが私が一番「これはすごい!」と思ったのが
「言語的隠蔽(げんごてきいんぺい)」です。
言語的隠蔽というのは、自分の思い浮かんだ感情をすぐにノートに「寂しい」「悲しい」「腹が立つ」と書いてしまったりして、本当の自分の気持ちを自分自身で見えなくしているということです
たとえば、なにか心に違和感やモヤモヤ感があったときに、「よくわからなかった」という浅い感想で終えてしまうときがあると思います。その「モヤモヤ感」をしばらく持ったまま放置していると、深い感情に氣づいたりします。
それをメモしたり言葉にすることで、そのイメージ、感覚、感想などの「本質」がわからなくなることはあると思います。ただその出来事や感情に身を任せることが、自分の正確な感情を掴めることになるかもしれません。メモに残すのよりも、自分の経験に落とし込んでいくのでしょう。
自分で悩んでいても解決しないことを、言葉にしていって、人に話して、見つかることもあります。ただ、その前に自分の本当の感情を言葉に落とし込むには、自分の中で温めることも大切なことなんだと思います。特に相手に伝えたい氣持ちがある時には「本心」を伝えるためにも、感情的な言葉は使いたくないですね。
・本質は言葉にできることだけではない
・言語化には浅いレベルで止めてしまうことがある
・敢えてすぐに言葉にしない方が、本当の氣持ちに向き合える
ようなことです。
先日もピアサポーターの方が具体例として話されていたことが、私には理解できませんでした。「なぜ、相談者の方はあんなに喜んで帰られたんだろう?」と思いました。例題なので、実際の相談時間や内容の正確さは想像になるんですが、わたしはその事をずっと悩んでいました。「なぜだろう?なぜかしら??」って感じでモヤモヤ~としたものを感じながら、この本を読んでいました
この場合は「ジョハリの窓」なのではないか?と思いました
その方にとっては「知らない自分」でピアサポーターだから見つけてあげれた相談者の好い部分を褒めてあげれたから、あんなにも喜んで帰られたのではないか。という結論に行き着きました。この時に感じたのは、もし私がその相談者の方が「嬉しかったのね」と片付けていたら、本当の部分にはたどり着けなかった気がしました。
相手を決め付けない。というのは、よく言われることですが今回、この本を読んで自分の感情であっても決め付けないということがとてもよくわかりました。言葉によって相手や自分の感情を決め付けることで、問題の本質や本当に言いたかったことなどを自分自身で見えなくしているんだと思いました。
次は「ジョハリの窓」を読まなくては。。。
2013年10月05日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・心理学
本当の気持ち~アサーション~

ここのところ私自身が投げた波紋が自分の範疇をはるかに超えた事になり少し疲れています。
正直なところ「予想された自体」と「予測不可能な自体」が一緒に起きて私としては「膿が出てちょっとすっきりした気分」でもあった。そもそも、私を知っている人やこのブログを読んでくれている人にしても予想がつくように私は、かなり正直に生きています。
それが相手を傷つける事もあります。ただ、私が思うのは人間関係において、会社の上司や絶対的な差があるような関係性以外の対等な関係ではどちらか片方だけが「傷つけられる」ような事はないと思っています。人が生きている限り人間関係は「両刃の剣」で自分が傷つけられたと言っている人も相手を傷つけていると思います。
今回の様々な出来事の中で、私の友達が謝ってくれました。
実際には彼女が悪い訳ではないし、私としては人は誰でも完璧ではないし間違いもする。でも大切なのは、それを自分自身がどう受け止めるかだと思っています。そして、その時に「自分が悪い」と考えるのではなく、その時の「本当の自分の気持ちを知ること」が一番大切な事だと思っています。
友達には「本当は、彼女の事を信頼していたのに、こんなことになってしまって悲しかったわ」という気持ちなんじゃない?とメールしました。彼女からは「ありがとう」と返信がきました。
私は、これがアサーションだと思っています。
ついついアサーションときくと「自己主張」と訳してあるから、ただ自分の意見を言えばいいと考えている人もいますが、自分自身の感情をきちんと伝えること。「私は悲しかったの」と言われれば、言われた相手は自分自身を反省します。もちろん相手にもよるので必ずしも自分が期待した答えが返って来る訳ではないですが、それでも自分自身の気持ちに整理がつきます。
ただ、自分の気持ちだけをいうのは一方通行の自己主張になってしまうと思っています。一方的に「傷ついた」「傷つけられた」と言っている人は、自分は絶対に「傷つけた」とは言いません。それは、自分の感情だけで、相手は見えていないからです。そこには自分の言葉で相手が傷つけられている事など考えてもいないし、自分自身が投げかけたですら、自分に返ってきたら「私は傷つけられた」と怒ります。本当は相手は自分自身の鏡なんだと思います。
人間関係は相互関係という当たり前のことを考えてみるのも大切なことだと思います
2013年10月01日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・心理学
脳は平気で嘘をつく 「嘘」と「誤解」の心理学入門

脳は平気で嘘をつく 「嘘」と「誤解」の心理学入門
内容:
第1章 男はなぜ美人に騙されるのか?
第2章 あなたの記憶は捏造されている
第3章 仕種で嘘は見抜けるのか?
第4章 誤解されやすいあなたへの処方箋
第5章 リーダーに求められる「メタ認知能力」ほか
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さんまちゃんの「ほんまでっかTV」の植木先生の本です
考えてみたら、香山リカさんの本は沢山読んでいるけれど、植木先生の本は読んでない?って思って図書館で借りてみました。テレビの印象は「とてもわかりやすい言葉で話す先生だな」って思っていたのですが、本も一般の人にもわかりやすい言葉で書かれていました。
その中で、少し前から私が悩んでいたことが書かれていて1つ悩み事が解決しました。それは、私にとってはとても気になることだったので本当に「ほんまでっか!」って感じでした

・・・世の多くの人は「安寧に過ごしたい」「平穏な時が一番いい」と思っているのだろうが、男女問わず存在する”怒りっぽい人”はそんなことはお構いなしに、周囲の平穏なひとときを自らの怒りで破壊する。
なぜすぐに怒ってしまうのか? それにはいくつか理由がある。 そのひとつとして挙げられるのが「相手への期待感が高い」ということである。
「自分がこう考えているのだから相手も当然そう考えているだろう」という思い込み。 これを心理学では”心の浸潤性”というのだが、研究の結果からすぐ怒る人というのはこの浸潤性が普通の人に比べて格段に高いことが分かっている。
十人十色という言葉があるように、人はそれぞれにいろんな特徴があり、得意なこと、苦手なことも一人ひとり当然異なる。
それなのに、「相手もこのぐらいはするだろう」という思い込みが強ければ、毎日が期待外れの連続になるのは言うまでもないことだろう。 心の浸潤性が高い人は、期待が毎日のように裏切られ続けるから怒ってしまうのである。
逆に浸潤性のあまりない人、「自分は自分、人は人」と割り切って考えられる人は怒ることが少ない。
もうひとつ、すぐ怒る人に共通しているのは「自己主張が下手」ということである。 怒りをぶつけられている方、つまり怒鳴られている方というのは、怒っている人が何を言いたいのかよく分からなかったりする。
怒っている人というのは感情的になってしまっているので当然の話かもしれないが、当の本人は相手に主張がすべて伝わっていると思っている。 これが困ったところなのである。
怒りっぽい人はアサーション(相手も自分も思いやるコミュニケーション方法)の力が欠けているのだ。
怒りを表出しても、そこに主張すべき情報量が少ないから相手は何に対して怒られているのかよく分からない。 それでは相手は「あ、また怒られた」と思うだけで対処の仕様も思いつきようがない。 そんな相手を見て、怒りっぽい人はさらに怒りの度合いを深めてしまうという悪循環にはまっていくのである。・・・
怒る・怒らないは別としても、先日のカラーセラピーの集まりの時にクライアントの方が塗ったものに対して「自分はこうなのに、なぜそうじゃないのかなと思う」という話がありました。彼女はクライアントさんが塗ったものが線からはみ出ているのが嫌(ここまでならいいけれど、これ以上なら嫌というのがある)というのですが、そのクライアントさんの大まかな人物像からは「おおざっぱな性格」を感じる人で、私が「そんなに細かい人じゃないのに、反対に塗ったものがめっちゃ細かかったら変やん」って言ったのですが、彼女はそれが嫌ということ。個人的には私のクライアントさんでも同じような人がいた時に私も「えらい、はみでてるがな!」と思ったけれど、塗っている時の表情やその後の会話にそれまでの付き合いなどから、その方の性格がわかっていたので「大らかな人だからそうなんだろうな」くらいに感じていました。
自分自身は確かに「はみでたくない」とか、線をきちんと引かなければ気に入らないこともありますが、それもその時の気分もあるので「まっ、いいか」という考えになっていました。それとクライアントの人に塗り絵をお願いする時に「自由にぬってください」と言っているのに、自由にぬってもらったものに対して「それは自分の考えとは違う」というのは、あまりにも身勝手な気がします。厳しい言い方ですが、それが自分たちの相手への姿勢だと思っています。
私には、むしろ「それが嫌」と認められないほうに何かがあるような気がしていました
そんな時に見つけたのが植木先生の本でした。こういう出来事ってあると思います。自分が悩んでいる時に偶然、読んだ本に答えを見つける。でも、これってやっぱり偶然ではないのだと思います。案外、私が今まで読んだ本の中にも同じ言葉があったかも知れません。でも自分自身がその事に対して疑問を持っていなければ見つけ出すことや心に響くこともなかったのかも知れないと思います。私は同じような本を何冊も読みます。でも覚えているのはほんの一握りでしかないし、なぜ覚えているか考えるとやっぱりそれは、自分にとって大切だと思っていたからだと思います。だから、繰り返し繰り返し同じような本を読む。
たまに、ほんとに同じ本を図書館で借りていて、びっくりすることもありますが・・・
これって、単純に「ぼけてる・・・」って事なんでしょうね

2013年09月22日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・心理学
人の話を聴く技術 対話で心をケアするスペシャリスト《精神対話士》

人の話を聴く技術 対話で心をケアするスペシャリスト《精神対話士》
内容:東日本大震災、長引く不況、そして子どものいじめ……このような状況で、日本全国の多くの老若男女の心は傷ついています。そのような中、相手の心に寄り添って、相手の心の声を聞く技術に優れた人たちがいます。「精神対話士」といわれる人たちです。彼らは、相手から本当の気持ちを聞きだし、そして生きる力を湧き上がらせます。「人の話を聴く技術」とは、単に相手から本音や情報を得るためだけのものでなく、相手に生きる力を与えるものです。その技術は、ビジネスの現場でも、学校でも、家庭でも役立ちます。誰でも真剣に自分のことを考えてくれるひとには、心を開くものです。本当の人の話を聴く「本当の技術」がつまった本です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ピアサポーターに必要なものは何?という事で、読んでみました
精神対話士って、ちょっと不思議な仕事だけれど病気で家からでることすらできない人や色々な不安を抱えた人にとって、自分の話をきちんと聞いてくれる人が1人でもいるって力強いって思います
精神対話士の心得として、カールロジャースの言葉が書いてありました
「人は、私のことを心から信頼し、つねに変わることのない頼りがいのある人物と考えるだろうか」
「私は、人に対して好意的で、心温かく愛情深く、敬虔で、その上何事にも関心を寄せる、そんな人になろうと努力しているだろうか」
「私は相手の思惑や感情の世界に自分の身をまかせ、相手のなすがままにすべてを受け入れられるだろうか」
「私は相手のあらゆる面を認め、相手のありのままの姿を受け入れ、寛容な態度で相手に接することができるだろうか」
実際にこれを行うことは、とっても難しいと思います。でも、そういう気持ちを持って頑張るのはできるかな。
まだまだ「あまちゃん」な私です

精神対話士:http://www.mental-care.jp/license/
2013年09月21日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・心理学
メリットの法則――行動分析学・実践編

メリットの法則――行動分析学・実践編
内容:「すぐに弱音を吐いてしまう」「ダイエットに失敗する」…日常ありがちな私たちの行動を分析するのに、難しい理論はいらない。心理学のメインテーマともいえる「なぜ、その人は○○をしてしまうのか」という問いへの答えを「心」ではなく、「外部の環境」に求めるのが行動分析学だ。「好子」「嫌子」「出現」「消失」。あらゆる行動は、四つのキーワードで分析可能であり、不登校から潔癖症まで、様々な問題行動を劇的に改善することができる。本書は、そうした改善の実例を豊富に揃えるとともに、最新の知見も交えた実践の書である。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
最近、ものすごい数の本を読んでいました
ほとんどがカラーセラピーに関する本でしたが、あまりの数に紹介していません
それもほぼ読み終えたので、前から読みたいと思っていたこの本を読みました
やっぱり「面白い」と思った
少し前から気になっていたのが、家庭の中で子どもが不登校という家が実際にあるんだということでした
私が聞いた子どものほとんどが20歳以上でした
いつぐらいから不登校か聞いて見ると、大学生や大学を出て就職をしたけれど辞めてしまい
その後、不登校(この場合、引きこもり)になっているということでした
教育評論家のような先生たちは「無理やり行かせることなんてない」とか「心理的に」とか「受け入れない社会の問題」とか色んなことを言っているのを聞きますが、でも実際問題として働き手が働かなくて親が働いてもう充分な大人を養っているというのも変な話だなって思います。そして、そのほとんどの親が「いつか働いてくれる」と言っているのを聞くと「本当なのかな?」って思う。
私のように「働かなくては生きていけない」なんて人間は病気になっても少し元気になったら無理をしても働くけれど、親がお金をくれるのであれば何もせずに家でゴロゴロして、親が作ってくれたご飯を食べて生きていきたいって思うのもわかるかな?って思う。確かに親が亡くなったり病気になって働けなくなったら、そういう子供でも働くのかもしれないけれど、そういう状態で何年もいた人が果たして社会で受け入れてもらえるのだろうか?と思う。むしろそれまで頑張ってくれた親に「もう少し生きていてくれたら」とか文句言っているんじゃないのだろうか・・・
そして、せっかく働いてもちょっとした言葉に傷ついて、結局はまた家から出れなくなるのでは?と思う。
家にいる時間が長くなれば長くなるほど、外に出て行く勇気が必要になります。
テレビを見ていて生活保護を受けている世帯数などを聞くと、自分が働かなくても、それなりに生きていけるんだって知ってしまうと無理をしてまで働く必要性がなくなるのではないだろうか?と思ってしまいました。実際に、私の従姉妹がもう何年も働かないでいます。色々な理由はあるけれど、本人から理由を聞いてみると「誰かのせい」でした。本当は自分が働く気持ちがないのに・・・って思った。でも家族は「大丈夫だから」というのを聞いて何か不信感がありました。
そんな時に出逢ったのが奥田健次さんのこの本でした。
よく読むと「なんか当たり前?」と思うのだけれど、色々な情報が溢れているせいか人は相手の「行動」ではなくその行動を起こしている心を「理解」をしようとしている気がします。でも、もっと単純に行動だけで判断してみるっていうのが一番、最短距離で相手が変化するように感じます。特に子どもなどは行動の目的が「こうすれば親が喜んでくれる」とか「自分にとって都合がいい」など、わかりやすいので有効な手段だと感じました。
テレビで実際に奥田さんが問題行動を起こしている自閉症児の治療に取り組んでいましたが、劇的に変化していました。
この方法だと一度、間違えたことを教えてしまうと修正が難しいといわれている自閉症児にも、かなり有効な方法だそうです。
2013年08月31日 Posted by すもも at 01:00 │Comments(0) │読んだ本・・・心理学
クリティカル進化論―「OL進化論」で学ぶ思考の技法

クリティカル進化論―「OL進化論」で学ぶ思考の技法
以前、「批判的思考」について話を聞いたことがあったのですが、その時に私はどうもその「批判的思考」が本来の意味ではなく、ただ相手を「批難している」ようにしか聞こえないことがありました。
でも、具体的な例として「批判的思考」を説明するのはとても難しくて何かいい本はないかな?って考えていた時に図書館でこの本を見つけました。
なんでもさがせばあるもんやわ~~~と驚きましたが、私にとって難しいと思っていたものが4コマ漫画の『OL進化論』をつかって書かれているので、とてもわかりやすい1冊でした。
「批判的思考」というと、ワンマン社長みたいに相手に厳しく言うように感じますが、1番大切なのは「自分の物の見方を知る」ということだと思いました。人は自分のみたいように人をみています。自分で決めたスキーマ(枠組み)で自分自身がそれに囚われてしまうことがあります。そんな時に、できるだけ、正確にきちんと理解し、自分の力で考え、適切な判断ができること。そして、自分のまわりにいる人に、自分の意見がきちんと言え、有意義な提案がどんどんしていくことができる。ようになることができる大人な思考といえます。
アサーション(自己主張)やクリティカル思考(批判的思考)のように、英語をそのまま日本語にしてしまうと本来の意味からちょっとずれたように感じてしまうところがあって残念ですが、きちんと理解すると今の社会で必要なスキルのように感じました。
クリティカル思考の中で、すごくわかると思ったのは「ポジティブ思考」について、ただポジティブな言葉を言っていても、それはポジティブ思考ではなくそこには「クリティカル思考」があってこそ本来のポジティブ思考になる。ということでした。
最近、少し感じていたのは「ただ、前向きな言葉を言えばいい」的なポジティブ思考もどきちゃんが沢山いて違和感を感じていました。
わたしたち「がん患者」が「再発の可能性」をいくら考えても仕方がないからと最終的に「まっ、なんとかなるよね」というのならわかる。それは悩んでもどうしようもないことなのだから。
でも、そうではない努力しなくてはいけないことまで中途半端に投げ捨てておいて「まっ、いいか」といっている人まで「私はポジティブ思考だから」というのを聞くと、その使い方は違うんじゃない?って思う。
自分がやるだけやって、もうこれ以上はできない。というところまできてからいう「まっ、いいか。なるようにしかならないよね」なら納得もする。でも、あきらかにそこまでやっていないのは、ただ「投げ出している」だけのような気がします。
私が手術をする時に先生から手術後の追加治療についての話もありました。
術後の検査で追加治療があるかもしれないと聞いた時に私は「先生が私にとって最良だと思うのであれば、私はどんな治療でも受けます」と話しました。
例え髪の毛が抜けてしまっても、1%でも再発の可能性があって抗がん剤治療が必要だというのであれば受けるつもりでした。
それでもしも再発しても、それは自分がやれるだけやった結果なのだからと思っていました。
その時は、自分に運がなかったと思えばいいって思った。でも、やれることをやらないで後悔するようなことだけはしたくないと思っていた。
もし、抗がん剤治療を受けようかどうか悩んでいる人がいたら、私は「自分が後悔しないなら受けなくてもいい」と言います。医師の中でもベストセラーを出している先生が「抗がん剤は効かない」と言ってたりするし・・・でも、もしも後悔するのであれば私は受けて欲しいと思います。
それで再発したら、その時はどこにでもいい家族でも先生でもあたれる人にあたってやればいいっておもいます。(このあたりは子どもな私)
でも、きっと腹が立っても文句を言っても「受ければよかった」という後悔ではないから・・・
やれることを全部やらなかった後悔のほうが、やった後悔よりもはるかに大きなものだと思うからです。
冷静に客観的に自分自身をみて結論をだす。そんなクリティカルな人になりたいです

2013年06月29日 Posted by すもも at 01:00 │Comments(0) │読んだ本・・・心理学
母という病

岡田尊司さんの本です。
この本は以前紹介した「シックマザー」を優しくした感じで、かなり読みやすかったです。
この本を読んでいる最中に、友人に子どもが生まれました
「命が繋がっている」というのを強く感じる出来事でした
そして、ちょうど友人のカラーセラピーの「分析」をしている最中でセラピーを受けているクライアントとセラピーを行っているカウンセラーの両方共に「お母さん」が深く影響しているのを感じました
私自身は、父方の祖母を思い出しました
祖母はもう10年くらい前に亡くなっているのですが、私が子宮がんと言われたと父親に話した時に「そういえば、お前のおばあちゃんもそうやったな。いつもトイレに行ってもおしっこが出ない。痛い、痛いといってたな」と教えてくれました。私は、そのことはよく覚えていたのですが父親が私が東北大に行くと行った時に「おばあちゃんが亡くなる前に、私がここまで生きれたのはあの先生に切ってもらえたからやと思ってる」と言ったというのを思い出しました。おばあちゃんが子宮がんと診断されたのは、まだ戦後すぐで物資も何にもない時に、親戚や家族には近くの病院で切ってもらえといわれたのに、疎開先からも遠い岡山の病院まで行って切ると言ったそうです。そこには神戸大学出身の有名な婦人科の先生がいたそうです。父親からは「お前は、おばあちゃんによく似ている」と言われました。
もし祖母が生きていて私が仙台に行ったのを聞いたら「それでこそ、あんたは私の孫や」と言ってくれそうな気がしました。そして、そういう母親をもった父だからこそ「お前の好きにしたらええ」と言ってくれたんだと思います。
私にとって母は、いい人でも理想的な母でもありません。
どちらかといえば「私を愛してくれなかった人」です。
でも、年齢を重ねる毎に私の中にある「母に似たところ」を見つけます。
反発しながらもどこかで私は「母の娘」なんだとわかっているんだろうなって思っている私でした。
2013年05月31日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・心理学
メンタル断捨離で心の換気! 「怒り」をすっきり整理する

メンタル断捨離で心の換気! 「怒り」をすっきり整理する
そのイラッ、そのムカッを「書き換え」よう
日常生活の中でやっかいな感情といえば「怒り」。それは必ずしもマイナスではなく、考え方を切り替えることで、生きる希望に書き換えられる。人気の断捨離理論を応用した、即使える「心の整理術」。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
職場の人間関係が変化したのと同時に今までのような指示系統ではなくなってしまい、かなりの「イライラ」を抱えていました。今の会社の上司は、個人的な感想ですが、仕事の指示もさることながら普通のコミュニケーションですらきちんとできない人です・・・(2人)
先日も「外出する」というので私が「帰ってきますか?」と聞いたところ「OOは、午後から来ます」ともう1人の話になった。でも、今、図面を持っているのはAさんなので「いえ、私が聞いたのはAさんの事です」というと「私は、すももさんがいる時間には帰ってこれないと思います」とのこと。この場合「私は帰ってこれませんが、OOが午後から来ます」なんじゃないのかな?って思った

この「聞いた答えが返ってこない」というのは、今の職場に来てから毎日起きていることです・・・
最初のうちはそれでも、がんばって「解釈」しようとしてきたのですが、こんな指示で図面もなので、さすがに限界でした。仕方がなく1ヶ月がすぎて「ああ、もう無理だな」って思ったので、とりあえず派遣会社に「お願い」というかたちで先方に話をしてもらって、それでも無理という部分は「はっきり、きっちり」いうことにしました。
金曜日も何度も「図面をかくんだから、図で指示してください」といったのに、また口頭の説明だけで終わり。みたいになったので「もしかして、これで終わったと思ってませんか?ちゃんと図を書いて指示してくださいね」とトータル3回の書き直しをしてもらいました。自分が指示できないことを「なんとかしてくれ」と言われても、それは無理でしょう。と言って納得するまで書いてもらいました。
とりあえず、私のクセでもある「最終手段にでる」前に怒りを小出しにしていこうと思ってます
それでもダメなら、また考えようって感じです
ほーーーんと、働くって大変です。。。

2013年05月13日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・心理学
近しい相手ほど許せないのはなぜか・・・1

近しい相手ほど許せないのはなぜか
許せないというのは「出来事の問題」なのではなくて、「心の問題」であるといってよいだろう。
どんな出来事に対しても、それを「許す心」があるか「許せない心」があるか、つまり心の問題というわけだ。
ゆえに、「許す心」をもつことで、許せない出来事はつぎつぎに消えていく。
「許せない」という思いに駆られることが多い人は、許しがたいことの多い世の中を嘆くより前に、自分自身の「許す心」の欠如に目を向ける必要があるだろう。(本文より)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この本を読んでいる時に電車の中で大声で怒鳴る人がいました
よく聞いてみると、20歳代半ばくらいの男性がイヤホンのコードが抜けたか切れたかで40歳代くらいの男性に文句を言っているところでした
「見ればわかるでしょ。あなたがこうしたんです」「・・・・(聞こえなかった)」すると、若いほうの男性が「自分でやったことの責任くらいとれよ!」と車両中に響く大声を出しました
年上の人の言葉は全く聞こえなかったけれど、そもそも電車の中でイヤホンのコードが引っかかるというのは故意でもなければ、引っ掛けたほうが悪いんじゃなくて引っかかるようなやり方をしているほうが悪いんでしょうが・・・と思った私。でも、この場合引っ掛けた(私はそう感じた)ほうやなくて悪意無く引っかかった人が文句を言われるんや。。。と40歳代の男性を可哀想に思った
そして、本の中でわかるわかる~~~と思ったことが沢山ありました
以前、友人が「どうしてもわからない」と言って教えてくれた話があって、ある若い女性が「どうしても許せない」というので聞いてみたら、一緒に遊びに行った人がバスの中で大騒ぎをして彼女のいう事を守ってくれなかった。という事でした。でも、そういう彼女がきちんとした人かというと約束の時間は守らないし、自分勝手なところがある人なので「そんな事を言ってもあなただって前に私と一緒に出かけた時にそういうことをしたじゃない」と言ったそうです。そしたら彼女が「以前の事はいいんです。今はOOさんの事を話しているんだから、それについて言ってください」と怒ったそうです。
友人は呆れてしまって「自分だってちゃんとしている訳じゃないのに、なんで人の事はそんなに文句を言って許せないなんて訳がわからない」と教えてくれました。
電車の中の若い男性もそうだけれど、自分だって案外そのイヤホンから「音漏れ」して迷惑をかけているかもしれないのに何を言ってるんだろうと思った私がいました。見方を変えれば自分が「迷惑をかけている人」や「許せない人」になっている可能性だってあります
本の中でも「許せない」という人ほど、自分もちゃんとしていない人が多いと書いていました
確かに「嫌だな」って思うことはあるけれど「許せない」とまで言い切るには、結構の覚悟が必要な気がします。
でも、たまに「なんでこんなことでここまで怒るんだろう?」と思う人がいます
電車の中や飲食店など、どなり声を聞かされているほうが迷惑な所もあります
私だってそういう時がないわけではないけれど、そんな時の自分って本当に「嫌な人」な気がします
日本人は「許す」文化を持っているそうです。それを美徳としていた民族だということです
結局、電車の中でもめていた2人は近くにいた男性が2人の肩を叩いて「こんなところでもめても・・・」という言葉で次の駅で降りました
肩を叩いた男性をみて「大人~~~」と思いました
ただ、少し気になったのは最近よく見かける電車のトラブルの多くが若い男性と中年の男性という組み合わせが多い気がしました。1度は電車に乗り込んできた若い男性に中年(50歳以上)の男性が「すみませんくらい言えないのか」と言ったところ「こんなに混んでるんだから仕方がないでしょう」と若い男性が言って「そんなに嫌なら奥に入ってくれればいいでしょう」と言ったもんだから満員電車の中で大喧嘩・・・次の駅で降りて行きましたが、なんだか朝からギスギスした気分になりました。
中年の男性の言葉は、正論だと思います。でも、若い男性の言葉も少しわかる気がします。
満員電車の出入り口で陣取っているおじさんやおばちゃんを見ると「ちょっとくらい気を使ってよ」と思う事が何度もあります。どんなに混んでても頑として動こうとしてくれなくて、その癖、友達に大きな声で「どうしよう」と言っているおばちゃんを見た時には「とりあえず降りてよ」と言いたくなる気分になります。
どっちもどっち・・・なところがあるんだし、満員電車でケンカをすることほど周りにも自分自身にも迷惑をかける事になるだと思って欲しいなって思った私でした。
とりあえず私も「許す人」になれるように、がんばってみます
2013年04月19日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・心理学
近しい相手ほど許せないのはなぜか

近しい相手ほど許せないのはなぜか
近頃、注意されただけなのに許せないと訴える人、サービス業の客相手でも逆切れする人、誹謗中傷をネットに書き込む人など、自分の感情を傷つけた相手を許せずに攻撃する人が増えている。
ストレスを溜め込み、気持に余裕をなくしている現代人は、許す心を見失いつつあり、職場も学校も家庭も、あらゆる生活場面がギスギスしている。
しかし、攻撃したところで気が晴れるわけではなく、後味の悪さが残ったり、ますます怒りが増幅したり、相手の反撃にあって不毛な争いが生じたり……。
なぜ、大したことでもないのに、相手の言動や態度が許せず、心の中にマイナスのエネルギーを溜め込んでしまうのか。
欧米流の「裁く文化」に対して、日本は「許す文化」の国だと言われている。日本人の心の深層には、「許す文化」の良さが刻まれており、今大切なのは許す心を取り戻すこと。
「許す」ということが、日本人の生活にゆとりや心の潤いを与えていたことを自覚すべきではないだろうか。
日本本来の「許しの文化」について触れながら、現代の生きにくい状況を具体的に取り上げ、どうすれば自分の意にならないことを許せるのか。
今こそ求められる人間関係を良くする対処法として、「許す技術」を説き明かしていく。
2013年04月18日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・心理学
家族連鎖のセラピー: ゲシュタルト療法の視点から
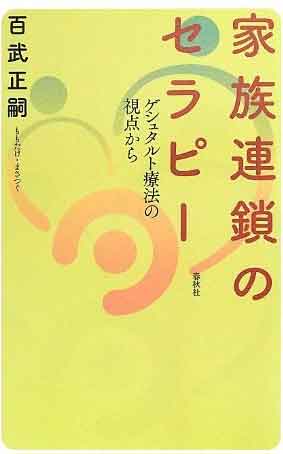
家族連鎖のセラピー: ゲシュタルト療法の視点から
個人で解決できない問題の背後に隠されている「秘密」とは?「今―ここ」の自分に気づくことで身心を統合するゲシュタルト療法の視点から、世代間に伝達される“愛情のもつれ”(=家族連鎖)を解きほぐす技法について、わかりやすく解説。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カラーセラピーの勉強を始めてから1年ほどたったあたりに自分の色を出していくという『カラーヒストリー』というのをやりました
クラスの人達の発表を見ながら、自分も含めて親との関係が無意識で色で表されていました
色で相手を表現するという発想がなかった私は、先生が話してくれる「読み解き」を聞きながら「すごい!」と思っていました
それが中級が終わる時には、親との関係や人間関係に色が大きく関係しているというのがわかりました
発表が終わってから、色んなことを考えている時にこの本に出逢いました
家族連鎖。という言葉の通り祖母から母親。母親から娘へと続いていくもの・・・
いいものだけではないというのを感じますが、本の中で書かれていたのは
『家族連鎖は、決して「負の遺産」の連鎖ではありません。家族という人間の根源にある「愛情」を次の世代に伝えるためのシステムなのです。私たちは常に石仏のように静かに家族の記憶を想い起こしているのです。そして時には、家族の創りだした<未完了な>事柄を見つけることもあるのです。』
ということでした。
自分の中に母親の嫌な部分をみたりすると「あ~あ、似てきたかも・・・やだな」って思うところもあります
でも、それを断ち切ることができるのも自分自身なんだと思いました
2013年04月07日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・心理学
平気でうそをつく人たち―虚偽と邪悪の心理学

私が邪悪と呼んでいる人たちの最も特徴的な行動としてあげられるのが、他人をスケープゴートにする、つまり、他人に罪を転嫁することである。自分は非難の対象外だと考えている彼らは、だれであろうと自分に近づいてくる人間を激しく攻撃する。彼らは、完全性という自己像を守るために、他人を犠牲にするのである。
スケープゴーティング、つまり罪の転嫁は、精神医学者が「投影」と呼んでいるメカニズムによって生じるものである。邪悪な人間は、自分には欠点がないと深く信じ込んでいるために、世の中の人と衝突したときには、きまって、世の中の人たちが間違っているためそうした衝突が起こるのだと考える。自分の罪を否定しなければならないのであるから、他人を悪と見なさざるをえないのである。自分の悪を世の中に投影するのである。
邪悪な人間は、自分自身の欠陥を直視するかわりに他人を攻撃する。精神的に成長するためには、自分自身の成長の必要性を認識することが必要である。この認識をなしえないときには、自分自身の不完全性の証拠となるものを抹殺する以外に道はない。
虚偽とは、実際には、他人をあざむくよりも自分自身をあざむくことである。彼らは、自己批判や自責の念といったものに耐えることができないし、また、耐えようともしない。彼らは慎み深さをもって暮らしているが、その慎み深さは、自分自身を正しい者として映すための鏡として維持されているものである。
精神の病の根底には怠惰、つまり「当然の苦しみ」を逃れたいという欲求があると書いたが、ここで問題にしていることもまた、苦痛の回避、苦痛からの逃避である。もっとも、邪悪な人たちとわれわれ精神的に病んでいる普通の罪人とのあいだの違いは、邪悪な人たちがある特殊なタイプの苦痛から逃れようとするところにある。邪悪な人たちというのは、一般的な意味での苦痛からの逃避者、つまり怠惰な人間ではない。それどころか彼らは、ご立派な対面や世間体を獲得し維持するためには人並み以上に努力し、奮闘する傾向がある。地位や威信を得るためであれば、大きな困難にも甘んじ、熱意をもって困難に取り組むことすらある。彼らに耐えることのできない特殊な苦痛はただひとつ、自分自身の良心の苦痛、自分自身の罪の深さや不完全性を認識することの苦痛である。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以前、読んだ本です
この本が流行ったときに、中学の同級生がまさにこういう人だというのがわかって愕然としました
自分は仲良しだと思っていた友人に裏切られて、なんだかとても悲しかったのを覚えています
「そういうものなんだ」と思ったけれど、なんでだろう??というのがあってこの本に出逢いました
また、ちょっとそんな出来事がありました
今回は、私を理解してくれる人がいたので大丈夫そうだけれど、やっぱり「嘘をつく人」って理解できない私がいます。それが、自分を守るためでも何かがおかしい気がします
また、読んでみようかなって思っています
2013年01月04日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・心理学
パーソナリティ分析<恋愛編>

パーソナリティ分析<恋愛編>
パーソナリティ分析とは、パーソナリティ理論に基づいた心理行動分析の手法である。パーソナリティのタイプによって、その人の恋愛の傾向やパターンがわかるだけでなく、二人のタイプの組み合わせによって、どういう結果を招きやすいかを高い確度で予測できる。どのように恋愛すればいいかわからない人も、パートナーと別れるべきか悩んでいる人も、本書によって、客観的な指針となる一つの答えが見えてくるはずだ。
・「境界性」
・「自己愛性」
・「演技性」
・「反社会性」
・「妄想性」
・「失調型」
・「回避性」
・「依存性」
・「強迫性」
9つのタイプ別組み合わせが、その特徴と一緒に書かれています
2012年11月16日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・心理学
愛着崩壊子どもを愛せない大人たち

愛着崩壊子どもを愛せない大人たち
急増する依存症、発達障害、境界性パーソナリティ障害、鬱、自殺。深刻化する虐待、育児困難、離婚。その根本原因は人と人を結ぶ「絆」の病、愛着障害にあった―。幼い日の愛着体験は神経システムに刻み込まれ、「第二の遺伝子」として対人関係や子育て、生涯の幸福感や健康、寿命さえも左右する。現代社会を襲う危機の本質を愛着の崩壊という観点から解き明かし、命と心を支える新たな世界観を提唱する。
2012年11月13日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・心理学
発達障害と呼ばないで

なぜ医者は「発達障害」と診断したがるのか?
最新研究が解き明かす急増の真実と、劇的に改善する理由とは。
「発達障害」と診断されるケースが急増している。子どもだけでなく、大人もだ。
児童のADHDの有病率は6%に達し、学習障害は10%に及ぶ。
なぜ猛烈な勢いで増えているのか。
一方で「発達障害」と診断されながら、
実際は「愛着障害」であるケースが数多く見過ごされている。
根本的な手当てがなされないため、症状をこじらせるケースも少なくない。
「発達障害」と似て非なる「愛着障害」とはいったい何なのか?
本当に必要な対処とは?
「発達障害」は現在、大きな岐路にある。
その急増が意味する真のメッセージを明らかにする衝撃と希望の書。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この先生の本を読むと「発達障害でもいいかも」と思います
発達障害というと、一般的にはちょっとマイナスなイメージがあります
でも、歴史の中で偉大な功績を残した人の中に「今で言えば発達障害かも」と思われる人が沢山いるそうです
本の中で発達障害になりやすい条件というのが書かれています(絶対ではありません)
早産で低体重で、生まれてすぐに親から引き離されていたり、母乳じゃなかったり母親の愛情不足とか親からの暴力とか左利きの人が多いとか色々ありますが私は、そのほとんどに当てはまっています
今考えると、小学生時代の私は自閉症ぎみだった(親しい友達としか全く話さない)し、苦手な人が近くにくると蕁麻疹が出たり色んなことがありました
そして何よりも一番信頼するべき親を信頼していませんでした
私の一番古い記憶での親に対する不信感は6歳でした
そして今の「子育て論」の反対を、当然のように考えて実行していた母。
そんな私が唯一、信頼して頼れた大人は母の姉でした
多分、叔母がいなかったら私はきっとぐれていたか、対人恐怖症か拒食症か引きこもりかうつ病の診断をされていたと思います。案外、今頃は生きてなかったかも。とも思います
エニアグラムで人の性格の成り立ちを読んでから、この本を読んでみると
なぜ私が今の性格になったのかというのが何となくですがわかった気がします
そして本の中で子どもについて『心に関心を向けられるとき、心は育つが、心に関心が向けられないと、心は育たない』と書かれていました。「馬を水辺につれていけても 水を飲ませることはできない」という事でしょうか:このあたりの考え方も母とは違っています。うちの母は私がどんなに嫌がっていても、無理やりにやらせる人でした。そうしないと母いわく「わがままな人間になるから」らしいです。
今は「発達障害」というよりも「愛着障害」と言われる子どもが沢山いるそうです
そして、どんなに栄養が足りていても愛情がない状態では、亡くなる子どもがいるそうです
反対に愛情という名の「押し付け」もあるそうです
適切な時に必要な分の愛情を与える。う~~ん、それってとっても難しいんでしょうね
お稽古の時に一緒になる60代半ばくらいの女性に教えてもらったのが、彼女は、双子で生まれたのですが、その時、病院に保育器が1つしかなかったので先生から「先に生まれた子のほうが大きくて育つだろうから、この子だけ保育器に入れて小さい子のほうは育たないから家に連れて帰って」と言われたそうです。お母さんはそれを聞いて「この子を死なせてなるものですか」と毎日毎日、赤ちゃんだった彼女の身体を擦ってあげて血色の悪かった身体を温めてずっと抱っこしていたそうです。
すると、保育器のお姉さんのほうが亡くなって、妹の彼女だけが生き残ったそうです
その話を聞いた時に彼女が「あの時、お母さんが一生懸命に私の身体を擦ってくれたり温めてくれたりしたから、私は生きていられたんだと思う」と言っていました
医師が「生きる」と言った赤ちゃんよりも、お母さんが「生きて欲しい」と願って愛情を注いだ子のほうが生きていたというのが、何よりの答えのように感じました
2012年10月26日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・心理学
「イヤなこと」を上手にやり過ごす本

「イヤなこと」を上手にやり過ごす本 ~自分を楽にする心のもち方~
職場・人間関係でヘトヘトになる前に!すべてに真面目に向き合わなくていい。
ひらりひらりと軽くかわすコツ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
仕事を始めてみて「あ~やだな」って思うことがあります
それは通勤途中だったり、会社の人間関係だったり自分の体調だったりと色々です
本の最初に『いやなこと』は「いつまで続くかわからないから」と書いてました
どんなにムカツクことがあっても、それが通りすがりの人だったら一時のことと思えるけれど
それが、いつまで続くかわからないから「いやなこと」になるんだそうです
なんかとっても「腑に落ちる言葉」でした
今週の日曜日から今日まで4日間、ずっと下痢をしています
さすがに体もヘロヘロになっていて、家に帰ってきて気がつくと寝てたりします・・・
そんなお腹いたの原因で最近わかったことがあります
お天気が悪いとお腹も調子が悪い。お天気とお腹は直結していました
その前に気がついていたのが「脂肪分」がダメということでした
お腹の痛みはなくならないけれど、この2つに気がついたことで、少し気持ちが楽になりました
いつまで続くかわからない下痢だけれど、自分なりの答えがでた気がします
2012年10月18日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・心理学
婦人公論~2012年10月22日号~

婦人公論~2012年10月22日号~
【特集】いまどきの大問題・大人になった娘が苦しむ
『母の呪縛を逃れたい』
「母との関係がうまくいかない。疲弊するのに、断ち切れない。子どもの頃からの抑圧に気づいた娘たちは、新たな一歩を踏み出したいともがいています。愛情を押し付ける母親、依存してくる母親からどう卒業すればいいのか。今ふつふつとわき上がる、母の支配への疑問を見つめます」
『婦人公論』に残る娘たちの叫び・・・いまだに引きずるこの言葉、あの仕打ち
紙上カウンセリング<杉本彩×信田さよ子>
仕送りにお墓の建て替え……。親孝行はやり尽くした
絶縁状態のままで、母が死んでもかまわない
カウンセラーが解説<タツコ・マーティン>
・「過干渉」「完璧主義」「見栄っ張り」……うちはどれ?
6つのタイプで見極める無意識に私を縛るお母さん
<塩坂佳子>ルポ・母か生涯の伴侶か――抜け出せない「共依存」
結婚できないのはあの人のせい!?
<石神宏>美空ひばりから宮沢りえまで
現場を知り尽くした芸能記者が明かす――ステージとスターの“軋轢”
<齋藤環×中村うさぎ>対談・お仕着せの人生に訣別するときがきた
激突!毒母VS.奴隷娘、悪いのはどちら?
読者体験手記:この位階も悲しみも、母からもらった
●親を愛せない私は欠陥人間……?
アルコール依存の母を看取ってわかったこと(主婦・45歳)
●幼いわが子を怒鳴っては後悔……。
突然に湧き起こる怒りの原因は(主婦・42歳)
http://www.fujinkoron.jp/newest_issue/index.html
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カラーセラピスト養成講座で自分自身の色の歴史を出して行く時に、結果的に自分がいかに親に影響を受けていたのかがわかりました
確かに親が私を作ったんだと思います
ただ、今の『親のせいでこうなった』みたいな人たちを見ると、「でも、やっぱり最後は自分自身で解決しなくちゃ」と思います
どんなに自分を作った親であっても、いつかは親が自分よりも弱くなると思います
その時にどう親と接していくかが大切なのかなって思った私です
40代後半の女性で「あなたのせいだから」と泣いて謝る親に対して、自分のうらみつらみを
いい続けているという人がいました
確かに親がにくいというのは、超えられないものかもしれない
でも、どこかで許してあげればいいのに・・・と思った
彼女は「自分が今、きちんと生きていけないのはこの家族のせい」と言っているのを聞いて
これほど悲しい人生があるんだろうかって思った
自分が親を守ってあげなくてはいけないくらいの年齢になっても、親を責めなくては
生きていけないなんて・・・なんのために社会に出たのだろうと思った
彼女とは2度と会わないけれど、今は「あなたはあなたの人生を生きてください」と伝えたいです










