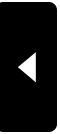スポンサーリンク
がん治療にフルーツ皮の健康食品

がん治療にフルーツ皮の健康食品
フルーツのマンゴスチンの厚い果皮が、がん治療向けの健康食品として普及を図られる。
マンゴスチンの厚い果皮は、抗菌や抗カビ作用があることで知られており、東南アジア地域では古くから伝承薬として用いられてきた。
マンゴスチンの厚い果皮はポリフェノールの一種である「キサントン」という成分を含んでおり、この成分を抽出することで、 がん治療の補完代替医療に役立つ健康食品として実用化したのだ。
培養したヒトのがん細胞と大腸ポリープを発症したラットに対して、抽出したキトサンを加えると、低濃度で48時間後にがん細胞の6~7割が死滅した。
一方、ラットに対しては、0.05%の非常に薄い濃度でエサに混ぜて食べさせたところ、食べないラットにに比べてポリープの数が約半数に減少した。副作用も無かったという。
キサントンには抗酸化や免疫活性化の作用があることから、 がん予防やがん再発を抑えるための機能性食品として販売が開始される。
癌(がん)治療の最新情報:http://blog.kougan.info/?eid=1172144
http://www.1ginzaclinic.com/mangosteen.html
2012年06月01日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん
大腸がんに効く黄色い香辛料とは
大腸がん治療にカレーのスパイスの有効性が試される。
カレーなどの料理に色や香り付けに使われる香辛料である鮮やかな黄色のターメリック。日本では、「ウコン」としての方が有名だ。このターメリック(ウコン)に含まれる成分が、「クルクミン」だ。このクルクミンを含む香辛料ターメリックは、数百年も前からインド料理やタイ料理で頻繁に使用されてきた。
このクルクミンが抗がん剤の持つ大腸がん細胞の殺傷力を高める効果があることは、既に実験室レベルでは確認済みなのだ。
今回は、人間に対する実証実験として、進行性の大腸がん治療に対するカレーのスパイス成分クルクミンの効果を検証する。実験するのは、イギリスのレスター大学(University of Leicester) のがん医療研究センターECMC(Experimental Cancer Medicine Centre)の研究チーム。
大腸がんでは、抗がん剤治療の副作用の負担が大きいために、抗がん治療が長期間続けられないことが多く、 がんの転移が広がった後では治療が難しかった。
クルクミンにがん細胞を抗がん剤の効果を助長する機能が確認されれば、 がん患者へ投与する抗がん剤の量を減らすことができ、それは副作用も減少されるため、治療をより長く続けることが可能となる。
実験の結果を待つまでも無く、大腸がん患者は抗がん剤に平行してターメリックカレーを食べることは有益だろう。
カレーなどの料理に色や香り付けに使われる香辛料である鮮やかな黄色のターメリック。日本では、「ウコン」としての方が有名だ。このターメリック(ウコン)に含まれる成分が、「クルクミン」だ。このクルクミンを含む香辛料ターメリックは、数百年も前からインド料理やタイ料理で頻繁に使用されてきた。
このクルクミンが抗がん剤の持つ大腸がん細胞の殺傷力を高める効果があることは、既に実験室レベルでは確認済みなのだ。
今回は、人間に対する実証実験として、進行性の大腸がん治療に対するカレーのスパイス成分クルクミンの効果を検証する。実験するのは、イギリスのレスター大学(University of Leicester) のがん医療研究センターECMC(Experimental Cancer Medicine Centre)の研究チーム。
大腸がんでは、抗がん剤治療の副作用の負担が大きいために、抗がん治療が長期間続けられないことが多く、 がんの転移が広がった後では治療が難しかった。
クルクミンにがん細胞を抗がん剤の効果を助長する機能が確認されれば、 がん患者へ投与する抗がん剤の量を減らすことができ、それは副作用も減少されるため、治療をより長く続けることが可能となる。
実験の結果を待つまでも無く、大腸がん患者は抗がん剤に平行してターメリックカレーを食べることは有益だろう。
2012年05月17日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(1) │ニュース・・・がん
化粧品に含まれる乳がんリスク成分
化粧品に含まれる乳がんリスク成分
化粧品や食品に含まれる低濃度のカドミウムでも、乳がんを発症・転移するリスクが高まることが判明した。
カドミウムは体内に入ると、女性ホルモンのエストロゲンに似た作用を示すことがあるため、特定の化粧品に含まれることがある。低濃度でもカドミウムに慢性的に曝露された細胞は、高レベルのSDF-1というタンパク質が発生することが判明したのだ。このSDF-1というタンパク質は、がん(腫瘍)の浸潤および癌転移に関連する物質=がんリスク物質として既知なのだ。
化粧品以外にもカドミウムは農業用の肥料に添加されることも多い。食品も、化粧品も、がんリスクを避けるのに越したことは無いだろう。
新たな乳がんリスクに関する研究は、米ドミニカン大学カリフォルニア(サンラファエル)生化学准教授のMaggie Louie氏が、米サンディエゴにて開催された実験生物学(Experimental Biology)学会年次集会で発表した。
癌治療の最新情報:http://blog.kougan.info/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カドミウム摂取量「がんと無関係」 国立がん研究センター調査
発がん性があるとされてきたカドミウムを食事から多く摂取しても、少量しか摂取しない人と比べてがんになるリスクは増えないことが、国立がん研究センターの研究班の調査でわかりました。
秋田県や新潟県、大阪府、高知県、沖縄県など、カドミウムに汚染されていない9府県の45歳〜74歳の男性4万2032人、女性4万8351人、合計9万383人を対象に約9年間に渡って、喫煙や飲酒など他のリスクを除いて、カドミウムの摂取量とがんの発症との関連を調べました。
うち、男性3586人、女性2263人、合計5849人が何らかのがんになりました。米や小麦、野菜、果物など34食品について、どれだけ食べたかを報告してもらい、体内に入ったカドミウムの量を推計。量によって4つのグループに分け、がんの発生リスクを比較しました。その結果、すべてのがんリスクと、カドミウム摂取量の明確な関連はみられませんでした。
さらに、各部位別がんリスクについても調べたところ、男性の胃がんと膵がん、女性の腎がんと子宮体がんでリスクの上昇がみられましたが、いずれも統計学的に有意な関連ではありませんでした。
理由として、食品に含まれるカドミウムの量が少ないことと、肺からの吸入ではなく口からの摂取であることが考えられています。
体内に入ったカドミウムの56パーセントは米から、20パーセントは野菜、13パーセントは大豆から摂取していました。米を主食とする日本人は諸外国と比べ、カドミウムの摂取量が多い傾向にあります。
研究班は、「米を主食とする日本人は、カドミウムの摂取量が欧米人より多いが、普通に食べる範囲では問題がない」としています。
高濃度のカドミウムを肺から吸収すると、肺がんリスクが高まるという先行研究が多くありました。国際がん研究機関は、ダイオキシンやアスベストなどと同じ発がん性があるグループ1に、カドミウムを分類しています。
http://ksj.blog.so-net.ne.jp/2012-04-30-1
「食品に含まれるカドミウム」に関するQ&A
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/12/h1209-1c.html
化粧品や食品に含まれる低濃度のカドミウムでも、乳がんを発症・転移するリスクが高まることが判明した。
カドミウムは体内に入ると、女性ホルモンのエストロゲンに似た作用を示すことがあるため、特定の化粧品に含まれることがある。低濃度でもカドミウムに慢性的に曝露された細胞は、高レベルのSDF-1というタンパク質が発生することが判明したのだ。このSDF-1というタンパク質は、がん(腫瘍)の浸潤および癌転移に関連する物質=がんリスク物質として既知なのだ。
化粧品以外にもカドミウムは農業用の肥料に添加されることも多い。食品も、化粧品も、がんリスクを避けるのに越したことは無いだろう。
新たな乳がんリスクに関する研究は、米ドミニカン大学カリフォルニア(サンラファエル)生化学准教授のMaggie Louie氏が、米サンディエゴにて開催された実験生物学(Experimental Biology)学会年次集会で発表した。
癌治療の最新情報:http://blog.kougan.info/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カドミウム摂取量「がんと無関係」 国立がん研究センター調査
発がん性があるとされてきたカドミウムを食事から多く摂取しても、少量しか摂取しない人と比べてがんになるリスクは増えないことが、国立がん研究センターの研究班の調査でわかりました。
秋田県や新潟県、大阪府、高知県、沖縄県など、カドミウムに汚染されていない9府県の45歳〜74歳の男性4万2032人、女性4万8351人、合計9万383人を対象に約9年間に渡って、喫煙や飲酒など他のリスクを除いて、カドミウムの摂取量とがんの発症との関連を調べました。
うち、男性3586人、女性2263人、合計5849人が何らかのがんになりました。米や小麦、野菜、果物など34食品について、どれだけ食べたかを報告してもらい、体内に入ったカドミウムの量を推計。量によって4つのグループに分け、がんの発生リスクを比較しました。その結果、すべてのがんリスクと、カドミウム摂取量の明確な関連はみられませんでした。
さらに、各部位別がんリスクについても調べたところ、男性の胃がんと膵がん、女性の腎がんと子宮体がんでリスクの上昇がみられましたが、いずれも統計学的に有意な関連ではありませんでした。
理由として、食品に含まれるカドミウムの量が少ないことと、肺からの吸入ではなく口からの摂取であることが考えられています。
体内に入ったカドミウムの56パーセントは米から、20パーセントは野菜、13パーセントは大豆から摂取していました。米を主食とする日本人は諸外国と比べ、カドミウムの摂取量が多い傾向にあります。
研究班は、「米を主食とする日本人は、カドミウムの摂取量が欧米人より多いが、普通に食べる範囲では問題がない」としています。
高濃度のカドミウムを肺から吸収すると、肺がんリスクが高まるという先行研究が多くありました。国際がん研究機関は、ダイオキシンやアスベストなどと同じ発がん性があるグループ1に、カドミウムを分類しています。
http://ksj.blog.so-net.ne.jp/2012-04-30-1
「食品に含まれるカドミウム」に関するQ&A
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/12/h1209-1c.html
2012年05月15日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん
新がん治療法は既存抗がん剤を深夜に
がん治療へ既存薬を用いた「時間治療」が画期的な効果を上げ注目されている。
「時間治療」とは、がん治療に用いる抗がん剤治療薬を「深夜」に投与するだけの治療方法で、抗がん剤は従来と全く同じ。投与する時間を「深夜」へ変えるだけで、 がん患者の生存期間の延長や、関節リウマチのつらい痛みや腫れがおさまるなどの効果が上がっているのだ。
1.5倍の抗がん剤を深夜に投与してがん縮小
健康診断で肝臓にガンが見つかり、抗がん剤治療を受けていた男性も「時間治療」でがん細胞が収縮した。発見時には、ガンが大き過ぎるために手術は無理とされたが、時間治療を導入している病院に転院し、それまでの抗がん剤の1.5倍の量を深夜に投与された結果、数ヶ月後には がん細胞が収縮したのだ。
関節リウマチに対しても、長年苦しんできた70才の女性が、同じ薬を飲む時間を朝昼2回から"夜寝る前の1回に変更"しただけで痛みの症状が軽減された。
このような病状や症状の改善の背景にあるのは、細胞の中で時計のように働く『時計遺伝子』研究の進歩とされる。
「時間治療」は深夜に実施されるために医療スタッフの確保などの課題があるが、がん患者には試す価値が十分にある新治療法と言えるだろう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
現在、抗がん剤治療は入院治療ではなく外来で行われるのが一般的になっています
朝9時からの診察と同じように抗がん剤が投与されます
ほとんどが日帰り投与という中で、深夜の抗がん剤投与というのができるのかな?と思いました
準夜勤・深夜勤の看護婦さんの数は日勤の半分以下だと思います
そんな中で、深夜の投与をするというのは患者さんの体調にもよると思いますが
もしも何かが起きた場合の対処などをどうすればいいのかな?と思いました
1泊2日の入院で抗がん剤治療を行うという体制が整わないと実現が難しいのかな??
患者さんのため。というのもわかるけれど、入院中に深夜に色々と問題が起こった時に少ない人数で大変そうだった看護婦さんたちを思うと「深夜にやればいいでしょ」と簡単にはいえないなって思いました
「時間治療」とは、がん治療に用いる抗がん剤治療薬を「深夜」に投与するだけの治療方法で、抗がん剤は従来と全く同じ。投与する時間を「深夜」へ変えるだけで、 がん患者の生存期間の延長や、関節リウマチのつらい痛みや腫れがおさまるなどの効果が上がっているのだ。
1.5倍の抗がん剤を深夜に投与してがん縮小
健康診断で肝臓にガンが見つかり、抗がん剤治療を受けていた男性も「時間治療」でがん細胞が収縮した。発見時には、ガンが大き過ぎるために手術は無理とされたが、時間治療を導入している病院に転院し、それまでの抗がん剤の1.5倍の量を深夜に投与された結果、数ヶ月後には がん細胞が収縮したのだ。
関節リウマチに対しても、長年苦しんできた70才の女性が、同じ薬を飲む時間を朝昼2回から"夜寝る前の1回に変更"しただけで痛みの症状が軽減された。
このような病状や症状の改善の背景にあるのは、細胞の中で時計のように働く『時計遺伝子』研究の進歩とされる。
「時間治療」は深夜に実施されるために医療スタッフの確保などの課題があるが、がん患者には試す価値が十分にある新治療法と言えるだろう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
現在、抗がん剤治療は入院治療ではなく外来で行われるのが一般的になっています
朝9時からの診察と同じように抗がん剤が投与されます
ほとんどが日帰り投与という中で、深夜の抗がん剤投与というのができるのかな?と思いました
準夜勤・深夜勤の看護婦さんの数は日勤の半分以下だと思います
そんな中で、深夜の投与をするというのは患者さんの体調にもよると思いますが
もしも何かが起きた場合の対処などをどうすればいいのかな?と思いました
1泊2日の入院で抗がん剤治療を行うという体制が整わないと実現が難しいのかな??
患者さんのため。というのもわかるけれど、入院中に深夜に色々と問題が起こった時に少ない人数で大変そうだった看護婦さんたちを思うと「深夜にやればいいでしょ」と簡単にはいえないなって思いました
2012年05月03日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん
胃がん, 食道がん の最先端治療病院
胃がん、食道がん の生存率を高める病院
食道がんや胃がんでは、がんが粘膜の下の方まで進行していると、多くの場合、手術の適応になる。臓器の一部あるいは全部を切除し、がんの進行度合いによってはその周辺のリンパ節も取り除く。治療ガイドラインで定められている治療法で広く普及しているものの、新たな検査方法が確立されれば、どこまで切除すべきかが客観的かつ科学的に示され、より正確な治療法が確立されることになる。
そんな胃がんや食道がんが、最初に転移しやすいのはセンチネルリンパ節という部分。現在、先進医療として、「センチネルリンパ節生検」という検査方法が行われている。
がん病巣の近くに特殊な色素やラジオアイソトープを注入して、がんが最初にリンパ節に到達するセンチネルリンパ節を同定し、転移の有無を顕微鏡で調べる。この検査は、すでに乳がんやメラノーマ(皮膚がん)に対しては、広く行われている。それを食道がんや胃がんへ応用するために、世界に先駆けて1998年から研究を進めているのが慶應義塾大学病院 一般・消化器外科だ。
慶應義塾大学病院は 先進医療の検査はもちろんのこと、小さな傷口で手術を可能とした腹腔鏡を用いた低侵襲の治療でもパイオニアである。
「胃がんや食道がんに対して、センチネルリンパ節生検を行うと、取り残しや余分な組織の切除を省くことができるなど、さまざまなメリットがあります。ただし、その検査に基づく治療で、本当に従来の手術と同じ生存率を確保できるか。その見極めの研究を行っています」と副病院長と腫瘍センター長を兼務する同科の北川雄光教授(51)は言う。
北川教授は、胸腔鏡・腹腔鏡手術のスペシャリストだ。食道がんや胃がんでも、患者にメリットがあれば胸腔鏡・腹腔鏡による手術を積極的に行っている。また、胃の良性腫瘍の胃GISTや、機能障害の一種・食道アカラシア、逆流性食道炎の手術では、全国に先駆けてヘソのひとつの穴から行う「単孔式腹腔鏡下手術」を導入。熟練した技術とチームワークで、低侵襲で確実に治療できる最先端技術を研究している。
「胃がんや食道がんに単孔式腹腔鏡を応用するには、医療機器の進歩を待たなければなりません。また、将来的には、腹腔鏡下手術と内視鏡の治療を組み合わせることで、臓器の温存がこれまで以上に可能になると思います。しかし、それにもまだ数年かかるでしょう」(北川教授)
腹腔鏡下手術でセンチリンパ節生検を行い、転移が見られなければ、内視鏡による治療で臓器を温存する。それは、これまで内視鏡の治療では、再発するのではないかと考えられた症例に対して、手術によって胃を部分切除するだけでなく、胃を残すという選択肢も広がることになる。
「今後、医療機器などがさらに発達することで、治療方法や検査方法の選択肢は増えるでしょう。しかし、手術で治るがんは再発させてはいけません。それを追求するために取り組むべきことはまだ多い」と北川教授。確実に治るがんを増やすために、今も力を注ぎ続けている。
< 2011年の治療実績 >
☆胃がん治療総数379件
☆胃がん手術件数158件
(内腹腔鏡下手術82件)
☆食道がん治療総数182件
☆食道がん手術件数50件
☆センチネルリンパ節生検64件
☆病院病床数1059床
慶應義塾大学病院:早期胃がんのセンチネルリンパ節生検について
http://www.hosp.keio.ac.jp/annai/byoin/kodo/soisenti.htm
http://www.surgery-med-keio.jp/joubushoukakan/trouble/04.php
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
現在、がん治療はがん拠点病院を中心として標準治療ガイドラインにそった治療が行われています
がん拠点病院で受けれる治療は、ほとんど同じと言われている中で唯一、色々な選択肢があると言われているのがリンパ節への転移が認められるかどうかの早期がんに対する治療方法です
リンパ節への転移は患者さんのその後の人生を決定する重要なものです
確実な方法でリンパ節への転移が検査できれば、リンパ節を残せます
現在、アメリカでも大腸がんなどでは日本のようにリンパ節郭清を行うほうがいいのでは?という動きがあるそうです
疑わしきは取らない。というアメリカのリンパ郭清が日本のように疑わしきは郭清というようの変化していくのではないか。と話されていた医師がいました
リンパ節への転移があったまま残してしまうと、それまで1期だった人が次に見つかった場合、いきなりステージが4期になってしまう場合があります
リンパから遠隔転移をする場合があるからです
できるだけ確実な方法でリンパ節への転移を調べた上で、リンパ節を残す治療を行うことが大切だと思います
私が受けた子宮頸がんでのセンチネルリンパ節生検も今では色々な病院で受けれるようです
自分のがんの進行度と病理を知った上で、自分が受けたい治療を探してみてください
食道がんや胃がんでは、がんが粘膜の下の方まで進行していると、多くの場合、手術の適応になる。臓器の一部あるいは全部を切除し、がんの進行度合いによってはその周辺のリンパ節も取り除く。治療ガイドラインで定められている治療法で広く普及しているものの、新たな検査方法が確立されれば、どこまで切除すべきかが客観的かつ科学的に示され、より正確な治療法が確立されることになる。
そんな胃がんや食道がんが、最初に転移しやすいのはセンチネルリンパ節という部分。現在、先進医療として、「センチネルリンパ節生検」という検査方法が行われている。
がん病巣の近くに特殊な色素やラジオアイソトープを注入して、がんが最初にリンパ節に到達するセンチネルリンパ節を同定し、転移の有無を顕微鏡で調べる。この検査は、すでに乳がんやメラノーマ(皮膚がん)に対しては、広く行われている。それを食道がんや胃がんへ応用するために、世界に先駆けて1998年から研究を進めているのが慶應義塾大学病院 一般・消化器外科だ。
慶應義塾大学病院は 先進医療の検査はもちろんのこと、小さな傷口で手術を可能とした腹腔鏡を用いた低侵襲の治療でもパイオニアである。
「胃がんや食道がんに対して、センチネルリンパ節生検を行うと、取り残しや余分な組織の切除を省くことができるなど、さまざまなメリットがあります。ただし、その検査に基づく治療で、本当に従来の手術と同じ生存率を確保できるか。その見極めの研究を行っています」と副病院長と腫瘍センター長を兼務する同科の北川雄光教授(51)は言う。
北川教授は、胸腔鏡・腹腔鏡手術のスペシャリストだ。食道がんや胃がんでも、患者にメリットがあれば胸腔鏡・腹腔鏡による手術を積極的に行っている。また、胃の良性腫瘍の胃GISTや、機能障害の一種・食道アカラシア、逆流性食道炎の手術では、全国に先駆けてヘソのひとつの穴から行う「単孔式腹腔鏡下手術」を導入。熟練した技術とチームワークで、低侵襲で確実に治療できる最先端技術を研究している。
「胃がんや食道がんに単孔式腹腔鏡を応用するには、医療機器の進歩を待たなければなりません。また、将来的には、腹腔鏡下手術と内視鏡の治療を組み合わせることで、臓器の温存がこれまで以上に可能になると思います。しかし、それにもまだ数年かかるでしょう」(北川教授)
腹腔鏡下手術でセンチリンパ節生検を行い、転移が見られなければ、内視鏡による治療で臓器を温存する。それは、これまで内視鏡の治療では、再発するのではないかと考えられた症例に対して、手術によって胃を部分切除するだけでなく、胃を残すという選択肢も広がることになる。
「今後、医療機器などがさらに発達することで、治療方法や検査方法の選択肢は増えるでしょう。しかし、手術で治るがんは再発させてはいけません。それを追求するために取り組むべきことはまだ多い」と北川教授。確実に治るがんを増やすために、今も力を注ぎ続けている。
< 2011年の治療実績 >
☆胃がん治療総数379件
☆胃がん手術件数158件
(内腹腔鏡下手術82件)
☆食道がん治療総数182件
☆食道がん手術件数50件
☆センチネルリンパ節生検64件
☆病院病床数1059床
慶應義塾大学病院:早期胃がんのセンチネルリンパ節生検について
http://www.hosp.keio.ac.jp/annai/byoin/kodo/soisenti.htm
http://www.surgery-med-keio.jp/joubushoukakan/trouble/04.php
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
現在、がん治療はがん拠点病院を中心として標準治療ガイドラインにそった治療が行われています
がん拠点病院で受けれる治療は、ほとんど同じと言われている中で唯一、色々な選択肢があると言われているのがリンパ節への転移が認められるかどうかの早期がんに対する治療方法です
リンパ節への転移は患者さんのその後の人生を決定する重要なものです
確実な方法でリンパ節への転移が検査できれば、リンパ節を残せます
現在、アメリカでも大腸がんなどでは日本のようにリンパ節郭清を行うほうがいいのでは?という動きがあるそうです
疑わしきは取らない。というアメリカのリンパ郭清が日本のように疑わしきは郭清というようの変化していくのではないか。と話されていた医師がいました
リンパ節への転移があったまま残してしまうと、それまで1期だった人が次に見つかった場合、いきなりステージが4期になってしまう場合があります
リンパから遠隔転移をする場合があるからです
できるだけ確実な方法でリンパ節への転移を調べた上で、リンパ節を残す治療を行うことが大切だと思います
私が受けた子宮頸がんでのセンチネルリンパ節生検も今では色々な病院で受けれるようです
自分のがんの進行度と病理を知った上で、自分が受けたい治療を探してみてください
2012年05月02日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん
がん探知犬マリーン、婦人科ほぼ確実に嗅ぎ分け
がん特有のにおいを嗅ぎ分ける訓練を受けた「がん探知犬」が、子宮がんなど婦人科がんをほぼ確実に判別できることを、日本医科大学千葉北総病院の宮下正夫教授(外科)らが確認した。
この犬は、大腸がん判別で既に成果を出しており、乳がんや胃がんについても実証実験が進行中。宮下教授は「自覚症状がない早期がんでも嗅ぎ分けられる。犬が感じているにおい物質を特定し、早期発見の技術につなげたい」と話している。
この探知犬は、千葉県南房総市内の専門施設で訓練を受けた雌のラブラドルレトリバー「マリーン」(10歳)。判別試験では、尿1ミリ・リットルの入った試験管を木箱に入れ、その前を研究者に連れられて歩く。がんのにおいを感じた時は箱の前で座り、それ以外は通り過ぎるように訓練されている。
子宮頸(けい)がんや卵巣がんなど5種類の婦人科がん患者43人の尿では、マリーンはすべてがんと判定。子宮筋腫など、がん以外の婦人科疾患29人の患者の尿では、1人分を誤ってがんと判定したが、それ以外は間違わずに嗅ぎ分けた。
最終更新:4月24日(火)16時15分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120424-00000639-yom-sci
この犬は、大腸がん判別で既に成果を出しており、乳がんや胃がんについても実証実験が進行中。宮下教授は「自覚症状がない早期がんでも嗅ぎ分けられる。犬が感じているにおい物質を特定し、早期発見の技術につなげたい」と話している。
この探知犬は、千葉県南房総市内の専門施設で訓練を受けた雌のラブラドルレトリバー「マリーン」(10歳)。判別試験では、尿1ミリ・リットルの入った試験管を木箱に入れ、その前を研究者に連れられて歩く。がんのにおいを感じた時は箱の前で座り、それ以外は通り過ぎるように訓練されている。
子宮頸(けい)がんや卵巣がんなど5種類の婦人科がん患者43人の尿では、マリーンはすべてがんと判定。子宮筋腫など、がん以外の婦人科疾患29人の患者の尿では、1人分を誤ってがんと判定したが、それ以外は間違わずに嗅ぎ分けた。
最終更新:4月24日(火)16時15分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120424-00000639-yom-sci
2012年04月27日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん
抗がん剤新薬の混合診療が規制緩和へ
既存の抗がん剤を保険承認時の適用外のがんに使う制度がいよいよ開始される見込みだ。
厚生労働省は2013年4月にも、保険診療との併用(事実上の混合診療)を広く認める方針。
現行の制度では、抗がん剤は、保険承認の際に治療対象となるがんが指定されており、保険適用外のがんに使うことは通常はできなかった。(全額自己負担なら可能だった)。抗がん剤は保険が適用できるがんの種類が決まっており、他のがんに使うと治療費が全額自己負担になってしまうのが原則=「混合診療の禁止」だった。しかし、保険適用の範囲を広げられることで、実用化が進んでいる肺がんの薬を卵巣がん治療に使うなど、がん治療の選択肢が保険診療内で広がる。
抗がん剤の保険適用拡大は、手順として2段階で進められる。
第一段階は、保険適用外の抗がん剤の使用を医療機関が国立がん研究センターに申請、審査される。「先進医療」として認定を受ければ、抗がん剤新薬として診察、検査など一般診療部分に保険が適用される。この段階では、抗がん剤新薬の薬代は、まだ保険対象ではない。しかし、「混合診療」が許されることだけでも大きい。 第二段階では、該当する抗がん剤の治療効果を確認されれば、厚労省による正式な薬事承認に先駆けて、抗がん剤新薬の薬剤費も含めて保険適用の対象費用とできる。
米国では、「コンペンディウム」と呼ばれている "承認"と"保険適用"を切り離した制度が参考にされている。
現行制度では、未承認薬をがん治療に用いると、薬代だけでなく、治療費全てが自己負担になるため、がん患者は、治療の断念か、多額の医療費を負担化の判断が強いられていた。
抗がん剤の多くは、資本力が大きく、巨額の開発費を投入できる欧米の製薬会社を中心に研究・開発が進んでいる。自然と開発対象は、欧米人に多い肺がんや大腸がん などのがんが中心となる。一方、日本人に多いのは、胃がんや卵巣がん で、さらには薬の実用化までの規制が強過ぎることから、抗がん剤新薬の応用研究が遅れているという実情があり、国内のがん患者団体が規制緩和を強く求めていた。
日本医師会には反対論・慎重論があるそうだが、がん患者達の永年の希望が達成される見込みは強くなった。
実は、厚労省が保険併用を広く認める背景には、国内の製薬会社の研究・開発を進める狙いがある。抗がん剤をはじめとする医薬品の輸入超過は年間1兆円を超え、貿易赤字の主因となってきており、国内で国内製薬会社による がん新薬の開発が急務となっているからだ。制度を改革し、抗がん剤新薬の研究開発を促すことで、日本をアジア向け抗がん剤新薬の研究・開発拠点に位置付け、医薬品輸出を拡大したい目論見なのだ。
背景はさておき、がん患者と家族にとっては、使える新薬が増え、治療費が抑制できる新制度は朗報と言える。
早期かつ確実な新制度の発足が望まれる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
不思議な事だと思っていたのが、例えば子宮体がんで認可されている薬があるとします
その薬を卵巣がんの人が使おうと思っても、卵巣がんでの認可がないと保険外になるということです
抗がん剤は1回の薬代が5万円などもあります(もっと高額な場合もある)
それを1回という事はほとんどなく、もし仮に6回使えば30万円が患者負担になります
それプラス、治療費になります
なぜ、他のがんで認可されているものが自分のがんで使えないのか?という不満がありました
また、効果があるかもしれないけれど、高額な治療費が払えなくて治療を諦めなくてはならないという現状がありました
医師の慎重論もわかりますが、効果があるかもしれない抗がん剤。しかもそれが他のがんで認可されているのに使えないというのは、やはり変な気がします
がんはお金のかかる病気だと言えます
でも患者は手術・抗がん剤・放射線治療とつらい治療にも耐えています
せめて自分が受けたい治療が受けれるような環境になって欲しいと思います
厚生労働省は2013年4月にも、保険診療との併用(事実上の混合診療)を広く認める方針。
現行の制度では、抗がん剤は、保険承認の際に治療対象となるがんが指定されており、保険適用外のがんに使うことは通常はできなかった。(全額自己負担なら可能だった)。抗がん剤は保険が適用できるがんの種類が決まっており、他のがんに使うと治療費が全額自己負担になってしまうのが原則=「混合診療の禁止」だった。しかし、保険適用の範囲を広げられることで、実用化が進んでいる肺がんの薬を卵巣がん治療に使うなど、がん治療の選択肢が保険診療内で広がる。
抗がん剤の保険適用拡大は、手順として2段階で進められる。
第一段階は、保険適用外の抗がん剤の使用を医療機関が国立がん研究センターに申請、審査される。「先進医療」として認定を受ければ、抗がん剤新薬として診察、検査など一般診療部分に保険が適用される。この段階では、抗がん剤新薬の薬代は、まだ保険対象ではない。しかし、「混合診療」が許されることだけでも大きい。 第二段階では、該当する抗がん剤の治療効果を確認されれば、厚労省による正式な薬事承認に先駆けて、抗がん剤新薬の薬剤費も含めて保険適用の対象費用とできる。
米国では、「コンペンディウム」と呼ばれている "承認"と"保険適用"を切り離した制度が参考にされている。
現行制度では、未承認薬をがん治療に用いると、薬代だけでなく、治療費全てが自己負担になるため、がん患者は、治療の断念か、多額の医療費を負担化の判断が強いられていた。
抗がん剤の多くは、資本力が大きく、巨額の開発費を投入できる欧米の製薬会社を中心に研究・開発が進んでいる。自然と開発対象は、欧米人に多い肺がんや大腸がん などのがんが中心となる。一方、日本人に多いのは、胃がんや卵巣がん で、さらには薬の実用化までの規制が強過ぎることから、抗がん剤新薬の応用研究が遅れているという実情があり、国内のがん患者団体が規制緩和を強く求めていた。
日本医師会には反対論・慎重論があるそうだが、がん患者達の永年の希望が達成される見込みは強くなった。
実は、厚労省が保険併用を広く認める背景には、国内の製薬会社の研究・開発を進める狙いがある。抗がん剤をはじめとする医薬品の輸入超過は年間1兆円を超え、貿易赤字の主因となってきており、国内で国内製薬会社による がん新薬の開発が急務となっているからだ。制度を改革し、抗がん剤新薬の研究開発を促すことで、日本をアジア向け抗がん剤新薬の研究・開発拠点に位置付け、医薬品輸出を拡大したい目論見なのだ。
背景はさておき、がん患者と家族にとっては、使える新薬が増え、治療費が抑制できる新制度は朗報と言える。
早期かつ確実な新制度の発足が望まれる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
不思議な事だと思っていたのが、例えば子宮体がんで認可されている薬があるとします
その薬を卵巣がんの人が使おうと思っても、卵巣がんでの認可がないと保険外になるということです
抗がん剤は1回の薬代が5万円などもあります(もっと高額な場合もある)
それを1回という事はほとんどなく、もし仮に6回使えば30万円が患者負担になります
それプラス、治療費になります
なぜ、他のがんで認可されているものが自分のがんで使えないのか?という不満がありました
また、効果があるかもしれないけれど、高額な治療費が払えなくて治療を諦めなくてはならないという現状がありました
医師の慎重論もわかりますが、効果があるかもしれない抗がん剤。しかもそれが他のがんで認可されているのに使えないというのは、やはり変な気がします
がんはお金のかかる病気だと言えます
でも患者は手術・抗がん剤・放射線治療とつらい治療にも耐えています
せめて自分が受けたい治療が受けれるような環境になって欲しいと思います
2012年04月25日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん
がん・肺炎…医療ネグレクトの子、重症化35人
保護者が必要な治療を受けさせない医療ネグレクトによって症状が悪化した子どもは、2008年秋からの1年間に全国で35人いたことが、厚生労働省研究班のアンケート調査でわかった。
大半は病気に対する親の理解不足が原因だった。20日に福岡市で開かれる日本小児科学会で発表する。
小児科のある全国の病院550施設のうち、160施設が回答。主治医が、育児放棄と呼ばれる虐待の一種、医療ネグレクトと判断した事例は452件に上った。このうち、同研究班が輸血の拒否や入院、手術が必要になった重症例の35人(0~11歳)を分析した。
病気の種類は小児がん、神経疾患などで、3人にまひなどの後遺症が生じたほか、受診の遅れで肺炎が重症化するなどの健康被害があった。ネグレクトとの因果関係は不明だが、6人が死亡していた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
こういう記事を見ると悲しくなります
最近「子供が、親を選んで生まれてきた」とか「生まれてきた意味」なんていうのを聞きますが、こういう子供はどうなのでしょうか?
親の身勝手で亡くならなくてはいけない子供。
親の理解不足といえば、そうかもしれませんが、私は子供は親を選べる訳ではないと思います
子供が病気になった時に「自分が悪い事をしたから病気になった」という事を言うそうです
お母さんやお父さんから「悪い事をしたから怒られた」と同じように病気を自分のせいだと思い込んでしまう。また、親の病気ですら「自分が悪いことをしたから、お母さんが病気になった」という子供もいます
子供は守られなくてはいけないものだと思います
親の身勝手に振り回される子供がいない世の中になって欲しいです
大半は病気に対する親の理解不足が原因だった。20日に福岡市で開かれる日本小児科学会で発表する。
小児科のある全国の病院550施設のうち、160施設が回答。主治医が、育児放棄と呼ばれる虐待の一種、医療ネグレクトと判断した事例は452件に上った。このうち、同研究班が輸血の拒否や入院、手術が必要になった重症例の35人(0~11歳)を分析した。
病気の種類は小児がん、神経疾患などで、3人にまひなどの後遺症が生じたほか、受診の遅れで肺炎が重症化するなどの健康被害があった。ネグレクトとの因果関係は不明だが、6人が死亡していた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
こういう記事を見ると悲しくなります
最近「子供が、親を選んで生まれてきた」とか「生まれてきた意味」なんていうのを聞きますが、こういう子供はどうなのでしょうか?
親の身勝手で亡くならなくてはいけない子供。
親の理解不足といえば、そうかもしれませんが、私は子供は親を選べる訳ではないと思います
子供が病気になった時に「自分が悪い事をしたから病気になった」という事を言うそうです
お母さんやお父さんから「悪い事をしたから怒られた」と同じように病気を自分のせいだと思い込んでしまう。また、親の病気ですら「自分が悪いことをしたから、お母さんが病気になった」という子供もいます
子供は守られなくてはいけないものだと思います
親の身勝手に振り回される子供がいない世の中になって欲しいです
2012年04月21日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん
がん骨転移の痛みを抑える新薬
多発性骨髄腫による骨病変及び固形癌骨転移による骨病変を効能・効果とする「ランマークⓇ皮下注120mg」新発売のお知らせ
第一三共株式会社とアストラゼネカ株式会社は、第一三共が多発性骨髄腫による骨病変及び固形癌骨転
移による骨病変を効能・効果とする「ランマークⓇ皮下注120mg」 (一般名:デノスマブ(遺伝子組換え)、製造販売承認取得日:本年1 月18 日、薬価基準収載日:本年4 月17 日)を発売しましたことをお知らせいたします。
ランマークは破骨細胞の活性を抑制する世界初のヒト型抗 RANKL モノクローナル抗体で、骨転移を有する癌患者および多発性骨髄腫患者の骨関連事象の発生を抑制することが確認されています
第一三共株式会社:http://www.daiichisankyo.co.jp/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
子宮頸がんや乳がんなどは、骨転移を起こしやすいと言われています
もちろん、全てではないし他の臓器への転移もあります
ただ、骨に近い場所のがんということで骨転移を言われます
私の子宮頸がんの病理は扁平上皮がんで固形がんなので抗がん剤が効きにくいと言われています
(効かないのではないし、放射線治療での治療実績もあります)
ただ、放射線の腹部への照射は基本的には1度きり(1回目の照射でほぼ上限のグレイ数をするので)ということが多く、照射ができない場合があります
その場合は、骨への転移があっても放射線治療ができないので痛みを伴う場合があります
「痛い、痛い」と言って亡くなるドラマなどのイメージもあって全てのがんが「痛い」と思われていたりしますが、転移をした場所にも状態にもよるので痛みも「人それぞれ」です
でも、現在でもモルヒネ系を嫌がる医師や患者も多く、日本では痛みに対するケアが諸外国よりも遅れているといわれているなかで破骨細胞の活性を抑制する薬が出てくるのはいいなと思いました
痛みって、どんなに強い人であっても長期に続けば精神的に追い詰められていく気がします
できるだけ痛くないのがいいな
第一三共株式会社とアストラゼネカ株式会社は、第一三共が多発性骨髄腫による骨病変及び固形癌骨転
移による骨病変を効能・効果とする「ランマークⓇ皮下注120mg」 (一般名:デノスマブ(遺伝子組換え)、製造販売承認取得日:本年1 月18 日、薬価基準収載日:本年4 月17 日)を発売しましたことをお知らせいたします。
ランマークは破骨細胞の活性を抑制する世界初のヒト型抗 RANKL モノクローナル抗体で、骨転移を有する癌患者および多発性骨髄腫患者の骨関連事象の発生を抑制することが確認されています
第一三共株式会社:http://www.daiichisankyo.co.jp/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
子宮頸がんや乳がんなどは、骨転移を起こしやすいと言われています
もちろん、全てではないし他の臓器への転移もあります
ただ、骨に近い場所のがんということで骨転移を言われます
私の子宮頸がんの病理は扁平上皮がんで固形がんなので抗がん剤が効きにくいと言われています
(効かないのではないし、放射線治療での治療実績もあります)
ただ、放射線の腹部への照射は基本的には1度きり(1回目の照射でほぼ上限のグレイ数をするので)ということが多く、照射ができない場合があります
その場合は、骨への転移があっても放射線治療ができないので痛みを伴う場合があります
「痛い、痛い」と言って亡くなるドラマなどのイメージもあって全てのがんが「痛い」と思われていたりしますが、転移をした場所にも状態にもよるので痛みも「人それぞれ」です
でも、現在でもモルヒネ系を嫌がる医師や患者も多く、日本では痛みに対するケアが諸外国よりも遅れているといわれているなかで破骨細胞の活性を抑制する薬が出てくるのはいいなと思いました
痛みって、どんなに強い人であっても長期に続けば精神的に追い詰められていく気がします
できるだけ痛くないのがいいな
2012年04月20日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん
再発がんのメカニズムを解明へ
再発がんのメカニズムを解明へ
放射線治療後にがんが再発するメカニズムの一端が解明された。
がんは、がん細胞の周囲の血管から酸素の供給を受けることで増殖する。がんが放射線治療後も死なずに再び増殖してしまうのは、血管から少し離れた低酸素環境でも生存できる特定のがん細胞が原因であると断定された。
この特殊な がん細胞は、血管の周囲のがん細胞が放射線で死滅すると、遺伝子が活性化することで血管の方向へ移動することが観察されたのだ。実験では、治療前のがんには17%しか存在しなかった特定がん細胞が、がんの再発時には60%にまで増えていた。この特定がん細胞を阻害剤で移動抑止すると がんは再発しなかったのである。
将来的な新治療法として、この「低酸素がん細胞」に放射線を集中照射する方法などが検討されており、がん再発の防止は実現にまた一歩近づいた。
がん再発メカニズムは、京都大大学院の原田浩講師らの研究グループが解明し、英科学誌ネイチャー・コミュニケーションズに発表された。
癌(がん)治療の最新情報:http://blog.kougan.info/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
私のがんは、局所的に再発した場合は、手術で切ることができますが
全身へ転移したがんの場合は抗がん剤治療では難しいというのを聞きます
抗がん剤の効果は100%ではないし・・・ね
先日、肛門から大量に出血しました
「ああ、この日が来たのかな・・・(腸への転移)」と思った
でも、ふと「これって放射線治療の時と同じやん」と思った
治療中に腹部だけに照射するとは言っても、腸への照射は避けられません
その時に腸壁が火傷のようになってしまうのと、あまりに回数の多い下痢で直腸に傷が付くらしいです
治療中にはかなりのつらさなので「重カマ」という便を柔らかくするための薬と、浣腸の形をしたステロイド剤を処方してもらいました
今回もそれを思い出して、できるだけ沢山の水分と一緒に「重カマ」を飲みました
すると、出血は止まりました
放射線治療は、そんなに優しいものではないと思います
でも、手術と併用することで治療効果があがります
がんは再発・転移すると難しいと言われています
再発のメカニズムが解明される事で、もっと治療効果があがるといいなと思います
放射線治療後にがんが再発するメカニズムの一端が解明された。
がんは、がん細胞の周囲の血管から酸素の供給を受けることで増殖する。がんが放射線治療後も死なずに再び増殖してしまうのは、血管から少し離れた低酸素環境でも生存できる特定のがん細胞が原因であると断定された。
この特殊な がん細胞は、血管の周囲のがん細胞が放射線で死滅すると、遺伝子が活性化することで血管の方向へ移動することが観察されたのだ。実験では、治療前のがんには17%しか存在しなかった特定がん細胞が、がんの再発時には60%にまで増えていた。この特定がん細胞を阻害剤で移動抑止すると がんは再発しなかったのである。
将来的な新治療法として、この「低酸素がん細胞」に放射線を集中照射する方法などが検討されており、がん再発の防止は実現にまた一歩近づいた。
がん再発メカニズムは、京都大大学院の原田浩講師らの研究グループが解明し、英科学誌ネイチャー・コミュニケーションズに発表された。
癌(がん)治療の最新情報:http://blog.kougan.info/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
私のがんは、局所的に再発した場合は、手術で切ることができますが
全身へ転移したがんの場合は抗がん剤治療では難しいというのを聞きます
抗がん剤の効果は100%ではないし・・・ね
先日、肛門から大量に出血しました
「ああ、この日が来たのかな・・・(腸への転移)」と思った
でも、ふと「これって放射線治療の時と同じやん」と思った
治療中に腹部だけに照射するとは言っても、腸への照射は避けられません
その時に腸壁が火傷のようになってしまうのと、あまりに回数の多い下痢で直腸に傷が付くらしいです
治療中にはかなりのつらさなので「重カマ」という便を柔らかくするための薬と、浣腸の形をしたステロイド剤を処方してもらいました
今回もそれを思い出して、できるだけ沢山の水分と一緒に「重カマ」を飲みました
すると、出血は止まりました
放射線治療は、そんなに優しいものではないと思います
でも、手術と併用することで治療効果があがります
がんは再発・転移すると難しいと言われています
再発のメカニズムが解明される事で、もっと治療効果があがるといいなと思います
2012年04月19日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん
前立腺がんの予防食

日本の伝統的な食事の重要性
前立腺がんを予防できる食事は、ずばり日本食だ。
つい数十年前まで日本人の前立腺がんの発症率は、欧米人に対してわずか4%程度だった。しかし、食文化の西洋化が進んだ近年は著しい増加傾向となっている。
中高年の男性に発症しやすい前立腺がんの要因は、加齢に伴って女性ホルモンが減少し、ホルモンバランスが崩れることが原因とされている。
このホルモンバランスを調整するのが、日本の伝統食、中でも豆類に含まれるイソフラボンという成分。大豆は、ファイトケミカルの一種の“イソフラボン”は、大豆に多く含まれることから、毎食に大豆が原料の味噌汁を飲み、おかずに大豆製品である豆腐や納豆から自然と摂取されていたのだ。
しかし、現代の食生活では、大豆製品を通じてイソフラボンを得る機会が大幅に減ってしまった。毎食摂取する必要はないものの、納豆や豆腐、豆乳などの大豆製品は積極的に摂ることで、前立腺がんの予防には極めて有効。その他にも高い抗酸化作用があるリコピンを豊富に含むトマトなども、前立腺がんの予防に有効だ。
日本食は、前立腺がんだけでなく、乳がんの予防に優れた効果のある食品、積極的に取りいれるべきだ。
癌治療の最新情報:http://blog.kougan.info/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
最近、納豆を食べています
関西人の私は子供の頃から納豆を食べたことがないのですが、45歳からは更年期に気をつけましょうと色々なところで聞くので女性ホルモンを増やさねば!と思って食べ始めました
といっても納豆1パックに対して、キムチ100gなので納豆の味も匂いも全くしませんが・・・
乳がんの人には女性ホルモンを抑えるようにしなくてはいけないけれど、私のように卵巣が1つしかない人は更年期がくるかもしれないのでホルモン補充療法をします
ただ、ホルモン補充療法を受けると乳がんの発症リスクが上がるということでした
まあ、そんなのはがん体験者の私にはあまり関係ないかなって思います
でも、今のところは排卵が起きているようなので(私の場合、右わき腹に卵巣を吊り上げてあるので排卵日には痛くなる)イソフラボンとアロマのイランイランでしばらく頑張ってみます

2012年04月04日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん
70~74歳で患者数最多=5大がんで半数超占める
70~74歳で患者数最多=5大がんで半数超占める―国立センター
時事通信 3月21日(水)12時37分配信
国立がん研究センターは21日、全国のがん診療連携拠点病院370施設で2009年にがんと診断された患者約48万人のデータを公表した。年齢区分別で患者数が最も多かったのは70~74歳で、約7万6000人に上った。
集計結果によると、がんの部位で最も多かったのは大腸で13.5%。胃12.4%、肺11.4%の順で続く。胃、大腸、肝臓、肺、乳房の5大がんが51.7%と半数を超えた。
患者住所と病院所在地の関係を見ると、全体では住所のある都道府県内の病院で診断された患者が90.3%に上った。特に面積の大きい北海道は99.1%とほとんどの患者が道内の病院で診断。一方、最も低かった埼玉では66.9%にとどまり、東京など県外の病院へ足を運ぶ患者が少なくないことがうかがえた。
年齢区分では、70~74歳に続いて65~69歳、75~79歳の順に患者数が多かった。20歳未満の患者は2826人だった。都道府県別の男女比で見ると、46都道府県で男性の方が多かったが、沖縄だけは女性の方が多かった。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
全国の拠点病院で、がん登録が始まって、やっときちんとした数字がでてきました
がん=怖い、死ぬなどといったマイナスイメージや「可哀想に」という同情という名の差別ではなく
客観的にがんを見て欲しいと思います
子供であっても若者でも、がんにはなるんです
こうやって「がん患者」やがんという病気に対する正しい知識が伝わっていけばいいなと思っています
「がん診療連携拠点病院院内がん登録2009年全国集計報告書」「全国がん罹患モニタリング集計2007年(MCIJ2007)」の発行について、詳しい記事は、こちらから:http://www.ncc.go.jp/jp/
時事通信 3月21日(水)12時37分配信
国立がん研究センターは21日、全国のがん診療連携拠点病院370施設で2009年にがんと診断された患者約48万人のデータを公表した。年齢区分別で患者数が最も多かったのは70~74歳で、約7万6000人に上った。
集計結果によると、がんの部位で最も多かったのは大腸で13.5%。胃12.4%、肺11.4%の順で続く。胃、大腸、肝臓、肺、乳房の5大がんが51.7%と半数を超えた。
患者住所と病院所在地の関係を見ると、全体では住所のある都道府県内の病院で診断された患者が90.3%に上った。特に面積の大きい北海道は99.1%とほとんどの患者が道内の病院で診断。一方、最も低かった埼玉では66.9%にとどまり、東京など県外の病院へ足を運ぶ患者が少なくないことがうかがえた。
年齢区分では、70~74歳に続いて65~69歳、75~79歳の順に患者数が多かった。20歳未満の患者は2826人だった。都道府県別の男女比で見ると、46都道府県で男性の方が多かったが、沖縄だけは女性の方が多かった。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
全国の拠点病院で、がん登録が始まって、やっときちんとした数字がでてきました
がん=怖い、死ぬなどといったマイナスイメージや「可哀想に」という同情という名の差別ではなく
客観的にがんを見て欲しいと思います
子供であっても若者でも、がんにはなるんです
こうやって「がん患者」やがんという病気に対する正しい知識が伝わっていけばいいなと思っています
「がん診療連携拠点病院院内がん登録2009年全国集計報告書」「全国がん罹患モニタリング集計2007年(MCIJ2007)」の発行について、詳しい記事は、こちらから:http://www.ncc.go.jp/jp/
2012年03月26日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん
肺がんを2週間で消す方法
がん細胞が2週間でほぼ消滅
肺がん治療は、1980年代以降に分子生物学が発達したことで、がん細胞の増殖や転移に関係するがんに関連する遺伝子の解明が進んだ。しかし、毎年7万人近くが肺がんで命を失っているため、日本人のがん死亡原因の第1位は肺がん。
肺がんには、小細胞がん、腺がん、扁平上皮がん、大細胞がんの4種類があるのだが、 2000年代までは、肺がんは、小細胞がん、もしくは非小細胞がんのわずか2分類で肺がん治療法が決されていた。
しかも、旧来の抗がん剤はがん細胞だけでなく正常細胞も攻撃してしまうために、
治療効果よりも副作用が強い場合が多く、がん細胞に対する効果が不十分な治療が多かったのだ。
その後に新開発された分子標的薬は、がん細胞で活性化している特定の分子だけをターゲットにするため、 がん細胞だけに特異的に作用し、効果が高く副作用が少ないのが特徴とされた。 そして、肺がん治療にも分子標的薬が開発された。 それが肺がん分子標的薬、ゲフィチニブ(2002年:商品名イレッサ)と、エルロチニブ(2007年:商品名タルセバ)だ。それぞれ保険承認を受けている。しかし、当初の肺がん分子標的薬は、副作用が酷く、医療訴訟にまで発展してしまったのだ。
その後、2004年に、イレッサを初めとする分子標的薬の向き不向きに関して、遺伝子内に指標があることが確定された。
日本では肺がんの70%が腺がん だが、この半数近くにEGFR遺伝子の変異が認められるのだ。イレッサやタルセバはEGFR(上皮成長因子受容体)という遺伝子の変異に対する薬だが、 EGFR遺伝子突然変異がある肺がん患者に対して、分子標的薬が劇的な効果があることが判明した。 著効例では、イレッサ投与後の2週間でがん細胞がほぼ消滅した例もある。
反対に、EGFR(上皮成長因子受容体)が認められない場合には、効果効能が期待薄で、もしろ激しい副作用が発現する可能性が高いことから、 分子標的薬の肺がん治療前には遺伝子検査が強く推奨されるようになった。
イレッサ(アストラゼネカ)は日本を含むアジア人、女性、非喫煙者の肺がん、特に腺がんに著効が期待できる、効果が高い特効薬なのだ。
癌治療の最新情報:http://blog.kougan.info/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
当然ですが、薬には良い面だけではありません
それは、イレッサでも同じことです
なんでもそうですが薬には大なり小なり『副作用』があります
また今、なぜイレッサ?と思いました
イレッサは「夢の新薬」と言われたけれど、1錠8000円(金額は、以前なので今は不明です)という高額な薬ということろもあって全ての患者さんが使える訳ではないという面があったり、また新薬ということで医師の説明不足という問題や、副作用などで亡くなった患者さんの遺族が起こした『イレッサ訴訟』というものもありました
でも治る可能性があるものを使いたいという患者や家族の気持ちもわかります
また、ドラッグラグ問題などを考えても、副作用があったからと言って全ての薬を禁止しろとは言えないと思います
そして全ての患者さんに有効という薬はありません
体も、がんも人それぞれです
良い面だけを見て判断するのではなく悪い面もきちんとわかってから医師と相談して使用してください
イレッサについては、こちらから:http://www.iressa.jp/select.asp
http://www.gsic.jp/cancer/cc_20/irs/01/index.html
肺がん治療は、1980年代以降に分子生物学が発達したことで、がん細胞の増殖や転移に関係するがんに関連する遺伝子の解明が進んだ。しかし、毎年7万人近くが肺がんで命を失っているため、日本人のがん死亡原因の第1位は肺がん。
肺がんには、小細胞がん、腺がん、扁平上皮がん、大細胞がんの4種類があるのだが、 2000年代までは、肺がんは、小細胞がん、もしくは非小細胞がんのわずか2分類で肺がん治療法が決されていた。
しかも、旧来の抗がん剤はがん細胞だけでなく正常細胞も攻撃してしまうために、
治療効果よりも副作用が強い場合が多く、がん細胞に対する効果が不十分な治療が多かったのだ。
その後に新開発された分子標的薬は、がん細胞で活性化している特定の分子だけをターゲットにするため、 がん細胞だけに特異的に作用し、効果が高く副作用が少ないのが特徴とされた。 そして、肺がん治療にも分子標的薬が開発された。 それが肺がん分子標的薬、ゲフィチニブ(2002年:商品名イレッサ)と、エルロチニブ(2007年:商品名タルセバ)だ。それぞれ保険承認を受けている。しかし、当初の肺がん分子標的薬は、副作用が酷く、医療訴訟にまで発展してしまったのだ。
その後、2004年に、イレッサを初めとする分子標的薬の向き不向きに関して、遺伝子内に指標があることが確定された。
日本では肺がんの70%が腺がん だが、この半数近くにEGFR遺伝子の変異が認められるのだ。イレッサやタルセバはEGFR(上皮成長因子受容体)という遺伝子の変異に対する薬だが、 EGFR遺伝子突然変異がある肺がん患者に対して、分子標的薬が劇的な効果があることが判明した。 著効例では、イレッサ投与後の2週間でがん細胞がほぼ消滅した例もある。
反対に、EGFR(上皮成長因子受容体)が認められない場合には、効果効能が期待薄で、もしろ激しい副作用が発現する可能性が高いことから、 分子標的薬の肺がん治療前には遺伝子検査が強く推奨されるようになった。
イレッサ(アストラゼネカ)は日本を含むアジア人、女性、非喫煙者の肺がん、特に腺がんに著効が期待できる、効果が高い特効薬なのだ。
癌治療の最新情報:http://blog.kougan.info/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
当然ですが、薬には良い面だけではありません
それは、イレッサでも同じことです
なんでもそうですが薬には大なり小なり『副作用』があります
また今、なぜイレッサ?と思いました
イレッサは「夢の新薬」と言われたけれど、1錠8000円(金額は、以前なので今は不明です)という高額な薬ということろもあって全ての患者さんが使える訳ではないという面があったり、また新薬ということで医師の説明不足という問題や、副作用などで亡くなった患者さんの遺族が起こした『イレッサ訴訟』というものもありました
でも治る可能性があるものを使いたいという患者や家族の気持ちもわかります
また、ドラッグラグ問題などを考えても、副作用があったからと言って全ての薬を禁止しろとは言えないと思います
そして全ての患者さんに有効という薬はありません
体も、がんも人それぞれです
良い面だけを見て判断するのではなく悪い面もきちんとわかってから医師と相談して使用してください
イレッサについては、こちらから:http://www.iressa.jp/select.asp
http://www.gsic.jp/cancer/cc_20/irs/01/index.html
2012年03月22日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん
思春期と若年成人「AYA世代」のがん、課題山積
産経新聞 3月8日(木)20時33分配信
「AYA世代」と呼ばれる15歳から29歳にかけてのがんをメーンテーマにした「第34回近畿小児がん研究会」が10日、大阪府吹田市の大阪大学銀杏(いちょう)会館で開かれる。小児がんと成人がんの境界領域にあるこの世代のがんは、近年ようやく取り組みの必要性が指摘され始めたばかりで、現状把握もほとんどできていない。治療体制や療養環境をはじめ、進学や就職など世代特有の課題も多く、関係者は「(研究会で)埋もれている問題に光をあて、解決に向けた第一歩にしたい」と話している。
■定まらぬ治療法
AYAは「Adolescent and Young Adult(思春期および若年成人)」の略。欧米では1つの世代ととらえられており、この世代のがんの特徴が明らかになりつつあるという。
一方、日本のAYA世代のがんに対する取り組みは心許(こころもと)ない。今回の研究会の会長を務める大阪府立母子保健総合医療センターの小児外科副部長、米田光宏さんによると、この世代の患者をどこで、どう治療すべきかといった基本的な方針さえ定まっていないという。
そのため、小児と成人では、投与量や組み合わせなどが違う抗がん剤の使用について、AYA世代の患者は、受診する施設や診療科によって小児対応になったり成人対応になったりと、同じがんでも治療内容が異なることも。「最初にかかる病院や、次に紹介される病院によって、患者の運命が大きく変わる」(米田さん)現状がある。
■世代特有の悩み
学業の遅れへの懸念、就職など将来への不安、友人関係…。思春期や青年期の患者は世代特有の悩みを抱えているが、それに対応できる療養環境も整備されていない。「AYA世代は、小さい子供たちの間では浮いてしまうし、高齢者ばかりの中では話が合わない。カーテンを引いてベッドにこもる患者は少なくない」と米田さんは指摘する。
そんな状況を改善しようと、同センターは平成22年4月、中学生やAYA世代を対象にした「青少年ルーム」を開設。1500冊の漫画や200巻のDVD、大型テレビ、パソコン、卓球台、キッチン、ソファなどを備えた。
「AYA世代のための部屋の設置は、欧米では当たり前。独特の世代だからこそ、必要な空間と認識されている」と、同センターの後藤真千子さん。家庭にいるような空間を目指した青少年ルームには、車いすや点滴をつけたままの若者たちが訪れ、思い思いの時間を過ごしていく。
後藤さんは「ストレス発散や気分転換になり、病気に立ち向かうエネルギーを獲得しているように思える」と話し、昨年度は延べ約千人が利用したという。
■放置できない問題
AYA世代のがんに目を向ける新しい動きも生まれている。
大阪では昨年3月、府がん診療連携協議会に「AYA部会」が設置され、専門家らが診療状況や治療実績、合併症などの解明や、患者サポートの充実に取り組み始めた。「放置できない問題」(米田さん)との認識も少しずつ広がり、今回の研究会のメーンテーマにつながったという。
当日は学術発表以外に午後1時半から、一般の人も参加できる米国の専門家による講演や、医師、看護師、元患者らさまざまな立場の人によるシンポジウムが行われる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第34回 近畿小児がん研究会公開シンポジウム
日時 2012年3月10日(土) 13:00より受付
場所 大阪大学医学部銀杏会館 アクセス
プログラム
特別講演
13:30~14:30 『Adolescence and Young Adult Oncology in the USA』
講演者 レベッカ ブロック先生
Oregon Health and Science University<通訳:あり>
シンポジウム
14:30~17:00 『小児がんと成人がんの境界領域(AYA世代)のがんの特徴と問題点』
講演者 山田 佳世 先生 奈良県立医科大学 小児科
『大阪府におけるAYA世代のがん-罹患、生存率、そして受療動態』
講演者 井岡 亜希子 先生 (大阪府立成人病センターがん予防情報センター)
『AYA世代に必要な支援を考える~看護師の立場から~』
講演者 柴田 多江子さん (大阪府立母子保健総合医療センター 4階西棟)
『AYA世代の療養環境について-センターでの取り組み-』
講演者 後藤 真千子 さん (大阪府立母子保健総合医療センター ホスピタルプレイ士)
『AYA世代の治療経験者として』
講演者 西村 剛直 さん (AYA世代に治療を受けた経験者)
質疑応答
17:00~17:30 司会
井上雅美先生 (大阪府立母子保健総合医療センター 血液・腫瘍科 部長)
冨森千恵子
(がんの子供を守る会ソーシャルワーカー)
がんの子供を守る会:http://www.ccaj-found.or.jp/news/kansai/info0310-3/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『若いから、がんにならない』や『子供のがんは治らない』など、まるで迷信めいたことをいう人がいます
何の根拠もない話だけれど、その話に傷つけられる人が沢山います
私が入院している時にも高校生の末期がん患者の女の子がいました
彼女は個室で誰とも話すことなく、ずっと病室でお母さんと2人でいました
何度か廊下で見かけたけれど、下を向いたままで体中で「話しかけないで」と言っているようでした
私が退院してからしばらくして、彼女が亡くなったと聞きました
どんな気持ちで、お母さんと彼女はあの部屋で過ごしていたのだろう・・・と思うと切なくなりました
そして、お母さんはどうしているのだろうと思った
自分よりも早く亡くなってしまった娘を受け入れることなどできない気がします
子宮頸がんのワクチン接種には、色々な意見があります
患者でも「受けさせたくない」という人もいます
でも、私は「受けて欲しい」と思います
ワクチンは完全ではないけれど、ワクチンと定期検査を受けることで子宮頸がんや子宮体がんの正しい知識を持ってもらいたい
そして、自分たちと同じ世代の若年性がん患者さんの気持ちを考える機会を持って欲しいと思います
そしたらきっと「若いから、がんにはならない」なんて言えないと思います
今、がんに一番大切なの事は、すべての世代の人が正しい知識を持つことだと思います
「AYA世代」と呼ばれる15歳から29歳にかけてのがんをメーンテーマにした「第34回近畿小児がん研究会」が10日、大阪府吹田市の大阪大学銀杏(いちょう)会館で開かれる。小児がんと成人がんの境界領域にあるこの世代のがんは、近年ようやく取り組みの必要性が指摘され始めたばかりで、現状把握もほとんどできていない。治療体制や療養環境をはじめ、進学や就職など世代特有の課題も多く、関係者は「(研究会で)埋もれている問題に光をあて、解決に向けた第一歩にしたい」と話している。
■定まらぬ治療法
AYAは「Adolescent and Young Adult(思春期および若年成人)」の略。欧米では1つの世代ととらえられており、この世代のがんの特徴が明らかになりつつあるという。
一方、日本のAYA世代のがんに対する取り組みは心許(こころもと)ない。今回の研究会の会長を務める大阪府立母子保健総合医療センターの小児外科副部長、米田光宏さんによると、この世代の患者をどこで、どう治療すべきかといった基本的な方針さえ定まっていないという。
そのため、小児と成人では、投与量や組み合わせなどが違う抗がん剤の使用について、AYA世代の患者は、受診する施設や診療科によって小児対応になったり成人対応になったりと、同じがんでも治療内容が異なることも。「最初にかかる病院や、次に紹介される病院によって、患者の運命が大きく変わる」(米田さん)現状がある。
■世代特有の悩み
学業の遅れへの懸念、就職など将来への不安、友人関係…。思春期や青年期の患者は世代特有の悩みを抱えているが、それに対応できる療養環境も整備されていない。「AYA世代は、小さい子供たちの間では浮いてしまうし、高齢者ばかりの中では話が合わない。カーテンを引いてベッドにこもる患者は少なくない」と米田さんは指摘する。
そんな状況を改善しようと、同センターは平成22年4月、中学生やAYA世代を対象にした「青少年ルーム」を開設。1500冊の漫画や200巻のDVD、大型テレビ、パソコン、卓球台、キッチン、ソファなどを備えた。
「AYA世代のための部屋の設置は、欧米では当たり前。独特の世代だからこそ、必要な空間と認識されている」と、同センターの後藤真千子さん。家庭にいるような空間を目指した青少年ルームには、車いすや点滴をつけたままの若者たちが訪れ、思い思いの時間を過ごしていく。
後藤さんは「ストレス発散や気分転換になり、病気に立ち向かうエネルギーを獲得しているように思える」と話し、昨年度は延べ約千人が利用したという。
■放置できない問題
AYA世代のがんに目を向ける新しい動きも生まれている。
大阪では昨年3月、府がん診療連携協議会に「AYA部会」が設置され、専門家らが診療状況や治療実績、合併症などの解明や、患者サポートの充実に取り組み始めた。「放置できない問題」(米田さん)との認識も少しずつ広がり、今回の研究会のメーンテーマにつながったという。
当日は学術発表以外に午後1時半から、一般の人も参加できる米国の専門家による講演や、医師、看護師、元患者らさまざまな立場の人によるシンポジウムが行われる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第34回 近畿小児がん研究会公開シンポジウム
日時 2012年3月10日(土) 13:00より受付
場所 大阪大学医学部銀杏会館 アクセス
プログラム
特別講演
13:30~14:30 『Adolescence and Young Adult Oncology in the USA』
講演者 レベッカ ブロック先生
Oregon Health and Science University<通訳:あり>
シンポジウム
14:30~17:00 『小児がんと成人がんの境界領域(AYA世代)のがんの特徴と問題点』
講演者 山田 佳世 先生 奈良県立医科大学 小児科
『大阪府におけるAYA世代のがん-罹患、生存率、そして受療動態』
講演者 井岡 亜希子 先生 (大阪府立成人病センターがん予防情報センター)
『AYA世代に必要な支援を考える~看護師の立場から~』
講演者 柴田 多江子さん (大阪府立母子保健総合医療センター 4階西棟)
『AYA世代の療養環境について-センターでの取り組み-』
講演者 後藤 真千子 さん (大阪府立母子保健総合医療センター ホスピタルプレイ士)
『AYA世代の治療経験者として』
講演者 西村 剛直 さん (AYA世代に治療を受けた経験者)
質疑応答
17:00~17:30 司会
井上雅美先生 (大阪府立母子保健総合医療センター 血液・腫瘍科 部長)
冨森千恵子
(がんの子供を守る会ソーシャルワーカー)
がんの子供を守る会:http://www.ccaj-found.or.jp/news/kansai/info0310-3/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『若いから、がんにならない』や『子供のがんは治らない』など、まるで迷信めいたことをいう人がいます
何の根拠もない話だけれど、その話に傷つけられる人が沢山います
私が入院している時にも高校生の末期がん患者の女の子がいました
彼女は個室で誰とも話すことなく、ずっと病室でお母さんと2人でいました
何度か廊下で見かけたけれど、下を向いたままで体中で「話しかけないで」と言っているようでした
私が退院してからしばらくして、彼女が亡くなったと聞きました
どんな気持ちで、お母さんと彼女はあの部屋で過ごしていたのだろう・・・と思うと切なくなりました
そして、お母さんはどうしているのだろうと思った
自分よりも早く亡くなってしまった娘を受け入れることなどできない気がします
子宮頸がんのワクチン接種には、色々な意見があります
患者でも「受けさせたくない」という人もいます
でも、私は「受けて欲しい」と思います
ワクチンは完全ではないけれど、ワクチンと定期検査を受けることで子宮頸がんや子宮体がんの正しい知識を持ってもらいたい
そして、自分たちと同じ世代の若年性がん患者さんの気持ちを考える機会を持って欲しいと思います
そしたらきっと「若いから、がんにはならない」なんて言えないと思います
今、がんに一番大切なの事は、すべての世代の人が正しい知識を持つことだと思います
2012年03月09日 Posted by すもも at 12:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん
末期すい臓がんの延命に効果の新薬
進行すい臓がんに初の治療薬 国際治験で効果を証明
膵臓がんには多くの種類がある。
膵臓がんの80%以上は膵液を運ぶ膵管の細胞から発生する膵管がんである。しかし、1%程度しか発生しない「膵神経内分泌腫瘍(pNET)」というすい臓がんがある。このpNETというすい臓がんに罹ったのが、米アップルのCEOで昨年10月に亡くなったスティーブ・ジョブズ氏だった。
膵臓は、胃や肝臓など多くの臓器に囲まれているため、がんが発生しても見つけるのが非常に難しい。そのため発見時には既に末期がんとなって手遅れというケースが多いことから、すい臓がんは難治がんの代表とされるのだ。
すい臓がんの治療は手術が基本だが、がんが進行していると完全な切除ができず、もはや治療の選択肢は無いというのがこれまでのすい臓がん治療の実情だった。しかし、期待の新薬「エベロリムス」で治療環境は好転している。
エベロリムスは、がん細胞だけを攻撃して正常細胞へのダメージを少なくする「分子標的薬」の一種だ。がんの増殖や成長、血管新生にかかわる「mTOR」というタンパクの働きを選択的に妨げるのが薬効。既に「根治切除不能または転移性の腎細胞がん」に対する治療薬として日本でも10年4月から使われており、すい臓がんpNETの効果効能は追加承認となった。
日本人の膵臓がんに占めるpNETの割合はわずか1.1%で、増加傾向にあるものの国内で治療を受ける患者は年間3千人前後しかいない。これまでこのpNETというすい臓がんに対する治療薬が無かったが、「エベロリムス」(成分名)が初めて2011年12月に承認されたのだ。副作用としては、皮疹や口内炎、感染症、爪の障害、鼻出血、間質性肺炎などがあるが、すい臓がん治療への効果は大きい。
エベロリムスはがんの進行リスクも65%も減少させるされている。さらに、日本人に限ると、「がんが悪化しない期間」を19.45カ月も延長するとされている。つまり2年以上の末期のすい臓がんでさえも2年近い延命が期待できるのだ。実際に治験参加者の中には、すい臓がん発見時に多発肝転移、リンパ節転移、骨転移から切除手術不能=末期がんを宣告されたがん患者だったが、4年近くまだまだご健勝なのである。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
すい臓がん。
そう聞くと、ついつい「末期がん」だと思ってしまいます
事実、私と同じ時期に友人の友人ですい臓がんが見つかった方がいましたが
医師からは治療をせずに、自宅で普通に生活することを勧められたそうです
その後、彼は家族に見送られて亡くなったそうです
長い間、すい臓がんは切ることができないがんだと言われていました
ほとんどのがんが切ることで患者の体力を奪ってしまうし、その中でも特に高難易度手術のがんです
そして、無理をして切っても、あまり効果がないと言われていました
その、すい臓がんの中でも切れる種類のものが、スティーブ・ジョブズ氏のがんでした
でも彼は「切る時期を逃してしまった」と言われています
ある先生が「がんには切れる時期がある。その時に切らなければ、後悔する」と言われていたのを思い出しました
やはりどんなにいい抗がん剤であっても、すべての人に効果が見られる訳ではありません
それを考えても、手術ができるのであれば、できれば手術を受けたほうがいいということです
でも、この薬のように延命効果が得られたというのは、切れない人や体力的に問題がある人であっても
少しでも長く生きることができるということです
「1日でも長く生きたい」
そう願っている人のためにも、嬉しいことだと思います
膵臓がんには多くの種類がある。
膵臓がんの80%以上は膵液を運ぶ膵管の細胞から発生する膵管がんである。しかし、1%程度しか発生しない「膵神経内分泌腫瘍(pNET)」というすい臓がんがある。このpNETというすい臓がんに罹ったのが、米アップルのCEOで昨年10月に亡くなったスティーブ・ジョブズ氏だった。
膵臓は、胃や肝臓など多くの臓器に囲まれているため、がんが発生しても見つけるのが非常に難しい。そのため発見時には既に末期がんとなって手遅れというケースが多いことから、すい臓がんは難治がんの代表とされるのだ。
すい臓がんの治療は手術が基本だが、がんが進行していると完全な切除ができず、もはや治療の選択肢は無いというのがこれまでのすい臓がん治療の実情だった。しかし、期待の新薬「エベロリムス」で治療環境は好転している。
エベロリムスは、がん細胞だけを攻撃して正常細胞へのダメージを少なくする「分子標的薬」の一種だ。がんの増殖や成長、血管新生にかかわる「mTOR」というタンパクの働きを選択的に妨げるのが薬効。既に「根治切除不能または転移性の腎細胞がん」に対する治療薬として日本でも10年4月から使われており、すい臓がんpNETの効果効能は追加承認となった。
日本人の膵臓がんに占めるpNETの割合はわずか1.1%で、増加傾向にあるものの国内で治療を受ける患者は年間3千人前後しかいない。これまでこのpNETというすい臓がんに対する治療薬が無かったが、「エベロリムス」(成分名)が初めて2011年12月に承認されたのだ。副作用としては、皮疹や口内炎、感染症、爪の障害、鼻出血、間質性肺炎などがあるが、すい臓がん治療への効果は大きい。
エベロリムスはがんの進行リスクも65%も減少させるされている。さらに、日本人に限ると、「がんが悪化しない期間」を19.45カ月も延長するとされている。つまり2年以上の末期のすい臓がんでさえも2年近い延命が期待できるのだ。実際に治験参加者の中には、すい臓がん発見時に多発肝転移、リンパ節転移、骨転移から切除手術不能=末期がんを宣告されたがん患者だったが、4年近くまだまだご健勝なのである。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
すい臓がん。
そう聞くと、ついつい「末期がん」だと思ってしまいます
事実、私と同じ時期に友人の友人ですい臓がんが見つかった方がいましたが
医師からは治療をせずに、自宅で普通に生活することを勧められたそうです
その後、彼は家族に見送られて亡くなったそうです
長い間、すい臓がんは切ることができないがんだと言われていました
ほとんどのがんが切ることで患者の体力を奪ってしまうし、その中でも特に高難易度手術のがんです
そして、無理をして切っても、あまり効果がないと言われていました
その、すい臓がんの中でも切れる種類のものが、スティーブ・ジョブズ氏のがんでした
でも彼は「切る時期を逃してしまった」と言われています
ある先生が「がんには切れる時期がある。その時に切らなければ、後悔する」と言われていたのを思い出しました
やはりどんなにいい抗がん剤であっても、すべての人に効果が見られる訳ではありません
それを考えても、手術ができるのであれば、できれば手術を受けたほうがいいということです
でも、この薬のように延命効果が得られたというのは、切れない人や体力的に問題がある人であっても
少しでも長く生きることができるということです
「1日でも長く生きたい」
そう願っている人のためにも、嬉しいことだと思います
2012年03月03日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん
<生殖幹細胞>卵子の元、ヒトで確認…日米チーム
<生殖幹細胞>卵子の元、ヒトで確認…日米チーム
ヒトの卵巣の中から、成長すると卵子になるとみられる細胞を、米ハーバード大マサチューセッツ総合病院と埼玉医大のチームが見つけた。従来、卵巣にある卵子の数は有限で、加齢とともに減少する一方と考えられている。今回発見した細胞は卵子の元になっている「生殖幹細胞」とみられ、ヒトで確認されたのは初めて。抗がん剤治療などで生殖能力を失った人などの不妊治療に役立つ可能性があるという。米科学誌ネイチャー・メディシン(電子版)に27日、論文が掲載された。
埼玉医大のチームは、性同一性障害の治療のため同大で卵巣を摘出した20~30代の女性6人から、研究目的で用いる同意を得た。提供された卵巣を米国へ持って行き、ハーバード大チームが生殖幹細胞とみられる細胞を採取。目印を付け、卵巣組織に注入してマウスの卵巣へ移植した。約1週間後には、卵巣内で目印を付けた細胞が卵子のように成長していた。
高井泰・埼玉医大准教授(産婦人科)は「やむを得ない理由で不妊になる人から事前にこの細胞を採取しておけば、治療後に出産が可能になるかもしれない」と話す。一方で「不妊治療に使うには、倫理的な問題を議論する必要がある」と指摘している。【野田武】
毎日新聞 2月27日(月)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『やむを得ない理由で不妊になる人』というのは、どのような人なのだろう?と思いました
現在、欧米では治療前に手術で卵巣を摘出しておいて、治療後に体内に戻すのが一般的になっているということでした
(日本でも一部の病院で、受けれます)
卵巣自体を取り出すには、手術が必要なので体の負担はあると思いますが、放射線を照射後や抗がん剤治療後の卵巣となると(私の場合、がん治療しか思い浮かばないので)その卵巣が正常に機能してくれるかは、疑問だな?と思った
また、その場合は卵巣機能の問題だけでなく、子宮などの問題はどうなのでしょう?
ただ、この場合「精巣がん」の方はどうだろう?と思いました
精巣がんの罹患年齢はとても若くて、10代前半から30代くらいの方がとても多いです
そういう人が、若くして子供を持てないというのを背負っていくというのは、とてもつらいことだと思います
卵子と同じように精子の元も見つかれば冷凍保存させて、患者さんが成長後にそれを精子に成長させて体外受精などで子供をもてる可能性があるのではと思いました
11歳の男の子のお母さんで、お子さんの精巣がんが見つかったという方からメールを頂いたことがあります
子供の病気は親もとても苦しい思いをするし「変われるものなら、自分がかわってあげたい」と言われていました
その時に「子供にがんであるということ」そして「子供を持つことができないということ」を、どう説明すればいいのかわからないと言われていて、もう少し大きければ病院で精子を保存しておいてもらえるけれど、まだ小さいのでそれもできない。といわれていました
切ないな・・・と思った
今は医学は、毎日毎日、とても進んでいっています
でも、どうしても駄目なこともあるんだと思った
ただ、患者としてみればやはり少しでも可能性があるのなら、それに賭けたいと思うのではと思います
ヒトの卵巣の中から、成長すると卵子になるとみられる細胞を、米ハーバード大マサチューセッツ総合病院と埼玉医大のチームが見つけた。従来、卵巣にある卵子の数は有限で、加齢とともに減少する一方と考えられている。今回発見した細胞は卵子の元になっている「生殖幹細胞」とみられ、ヒトで確認されたのは初めて。抗がん剤治療などで生殖能力を失った人などの不妊治療に役立つ可能性があるという。米科学誌ネイチャー・メディシン(電子版)に27日、論文が掲載された。
埼玉医大のチームは、性同一性障害の治療のため同大で卵巣を摘出した20~30代の女性6人から、研究目的で用いる同意を得た。提供された卵巣を米国へ持って行き、ハーバード大チームが生殖幹細胞とみられる細胞を採取。目印を付け、卵巣組織に注入してマウスの卵巣へ移植した。約1週間後には、卵巣内で目印を付けた細胞が卵子のように成長していた。
高井泰・埼玉医大准教授(産婦人科)は「やむを得ない理由で不妊になる人から事前にこの細胞を採取しておけば、治療後に出産が可能になるかもしれない」と話す。一方で「不妊治療に使うには、倫理的な問題を議論する必要がある」と指摘している。【野田武】
毎日新聞 2月27日(月)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『やむを得ない理由で不妊になる人』というのは、どのような人なのだろう?と思いました
現在、欧米では治療前に手術で卵巣を摘出しておいて、治療後に体内に戻すのが一般的になっているということでした
(日本でも一部の病院で、受けれます)
卵巣自体を取り出すには、手術が必要なので体の負担はあると思いますが、放射線を照射後や抗がん剤治療後の卵巣となると(私の場合、がん治療しか思い浮かばないので)その卵巣が正常に機能してくれるかは、疑問だな?と思った
また、その場合は卵巣機能の問題だけでなく、子宮などの問題はどうなのでしょう?
ただ、この場合「精巣がん」の方はどうだろう?と思いました
精巣がんの罹患年齢はとても若くて、10代前半から30代くらいの方がとても多いです
そういう人が、若くして子供を持てないというのを背負っていくというのは、とてもつらいことだと思います
卵子と同じように精子の元も見つかれば冷凍保存させて、患者さんが成長後にそれを精子に成長させて体外受精などで子供をもてる可能性があるのではと思いました
11歳の男の子のお母さんで、お子さんの精巣がんが見つかったという方からメールを頂いたことがあります
子供の病気は親もとても苦しい思いをするし「変われるものなら、自分がかわってあげたい」と言われていました
その時に「子供にがんであるということ」そして「子供を持つことができないということ」を、どう説明すればいいのかわからないと言われていて、もう少し大きければ病院で精子を保存しておいてもらえるけれど、まだ小さいのでそれもできない。といわれていました
切ないな・・・と思った
今は医学は、毎日毎日、とても進んでいっています
でも、どうしても駄目なこともあるんだと思った
ただ、患者としてみればやはり少しでも可能性があるのなら、それに賭けたいと思うのではと思います
2012年02月28日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(4) │ニュース・・・がん
抗がん剤を体内マイクロチップで自動投与
体内にチップ、自動で投薬 米チーム成功、注射不要に
自動的に薬を放出するマイクロチップを体内に埋め込み、骨粗鬆症(こつそしょうしょう)患者に安全な治療をすることに米ハーバード大などの研究チームが成功した。16日付の米医学誌サイエンス・トランスレーショナル・メディシン電子版で発表した。注射が不要になり、患者の生活の質を重視したがん治療などへの応用も期待される。
このチップ(13ミリ×5ミリ)は、一種の小型コンピューター。外部からの無線通信か内部のプログラムの指示でチップの穴から薬を体内に放出する機能を持つ。今回は骨粗鬆症の治療に応用し、骨を作る働きを活発にする注射薬テリパラチド20日分を1日分ずつ放出できるように工夫。複数のチップがUSBメモリーほどの大きさの容器に入れてある。
65~70歳の女性患者7人の腰回りに埋め込み、様子をみたところ、薬は想定通り放出され、副作用もみられなかった。注射と同様に骨を作る働きを活発にする働きがみられたという。
2012年2月17日
癌(がん)治療の最新情報:http://blog.kougan.info/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
がんによる痛みのモルヒネの投与や乳がんのホルモン療法の薬など、
色々な場面で生かされていってくれればいいなと思います

2012年02月18日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん
新しいがん治療法、米国で臨床試験へ
信大医学部(松本市)内に研究所を置くベンチャー企業「アネロファーマ・サイエンス」(東京)は来春にも、ビフィズス菌を利用したがん治療法の臨床試験を米国で始める。がん組織は酸素の少ない「嫌気的環境」にあるため、嫌気的環境を好むビフィズス菌を薬の「運び屋」として利用。併せてがん組織の内部で抗がん剤を生成する仕組みにすることで正常な組織への影響を抑え、副作用が少ないがん治療法の確立を目指す。
同社が実用化に取り組んでいる治療法は、抗がん剤になる前段階の物質「5―FC」と、5―FCを抗がん剤「5―FU」に変える酵素を作る遺伝子を組み込んだビフィズス菌「APS001F」を患者に投与。ビフィズス菌が集まるがん組織の内部で抗がん剤に転換し、ピンポイントでがん組織を攻撃する。
臨床試験は米国中南部にあるがん専門病院で実施。まず第1段階の試験で、がんの種類を絞らずに、胃がんや大腸がんなどさまざまな固形がんを対象に行う。2年ほど実施した後、続く第2段階の試験で、第1段階で特に効果が高かったがんの種類に絞って投与。両試験で計40~60人の患者に実施する予定だ。
同社はこれまで動物実験で有効性や安全性を確認。臨床試験については米国立衛生研究所や米食品医薬品局と打ち合わせを重ね、それを基に1月中に米食品医薬品局に実施を申請する。順調に進めば、春ころに1人目の患者に投与できる見込みだ。
同社取締役で信大大学院医学系研究科の谷口俊一郎教授=分子腫瘍学=は「がんの種類によって、ビフィズス菌が集まりやすいものと、集まりにくいものがあるかもしれないので、臨床試験を通して見極めたい」と説明。「がん組織という局所だけで大量に5―FUを作ることができるため、副作用を減らすだけでなく、従来は5―FUが効かなかった種類のがんにも効果があるかもしれない」と期待する。
臨床試験が順調に進めば、5―FUだけでなく別のさまざまな薬を運ぶ手法としても注目されそうだ。
同社の三嶋徹也社長は「今までにないまったく新しいコンセプトの治療法を是非、世に出したい」と話している。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日本とアメリカが一緒に治験を行うことで、早く患者さんが使えるようになります
少しでも長く生きる事で、自分にあった抗がん剤ができるかもしれません
そう思うと、頑張る勇気が出てきそうな気がします
癌(がん)治療の最新情報:http://blog.kougan.info/
同社が実用化に取り組んでいる治療法は、抗がん剤になる前段階の物質「5―FC」と、5―FCを抗がん剤「5―FU」に変える酵素を作る遺伝子を組み込んだビフィズス菌「APS001F」を患者に投与。ビフィズス菌が集まるがん組織の内部で抗がん剤に転換し、ピンポイントでがん組織を攻撃する。
臨床試験は米国中南部にあるがん専門病院で実施。まず第1段階の試験で、がんの種類を絞らずに、胃がんや大腸がんなどさまざまな固形がんを対象に行う。2年ほど実施した後、続く第2段階の試験で、第1段階で特に効果が高かったがんの種類に絞って投与。両試験で計40~60人の患者に実施する予定だ。
同社はこれまで動物実験で有効性や安全性を確認。臨床試験については米国立衛生研究所や米食品医薬品局と打ち合わせを重ね、それを基に1月中に米食品医薬品局に実施を申請する。順調に進めば、春ころに1人目の患者に投与できる見込みだ。
同社取締役で信大大学院医学系研究科の谷口俊一郎教授=分子腫瘍学=は「がんの種類によって、ビフィズス菌が集まりやすいものと、集まりにくいものがあるかもしれないので、臨床試験を通して見極めたい」と説明。「がん組織という局所だけで大量に5―FUを作ることができるため、副作用を減らすだけでなく、従来は5―FUが効かなかった種類のがんにも効果があるかもしれない」と期待する。
臨床試験が順調に進めば、5―FUだけでなく別のさまざまな薬を運ぶ手法としても注目されそうだ。
同社の三嶋徹也社長は「今までにないまったく新しいコンセプトの治療法を是非、世に出したい」と話している。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日本とアメリカが一緒に治験を行うことで、早く患者さんが使えるようになります
少しでも長く生きる事で、自分にあった抗がん剤ができるかもしれません
そう思うと、頑張る勇気が出てきそうな気がします
癌(がん)治療の最新情報:http://blog.kougan.info/
2012年01月06日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん
子宮筋腫と子宮がんを9割精度で診断
PET使い子宮筋腫・肉腫を判別
近年に女性の晩婚化や少子化が原因で増えているとされる子宮筋腫は、子宮肉腫や子宮がんへの変異が心配されることが多い。
従来、子宮筋腫と子宮肉腫を見分ける診断は難しいものだった。しかし、陽電子放射断層撮影(PET)を利用することで、患者の負担は最小でも9割以上の高い精度でがん診断することができるようになった。
この「PET診断法」は、福井大産科婦人科の吉田好雄准教授と福井大高エネルギー医学研究センターの岡沢秀彦教授が開発した手法で、米国核医学学会「がん・腫瘍(しゅよう)診断部門」では「最高賞」を獲得している。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「子宮がん」・・・実は、子宮がんという病名はありません
子宮のがんは、子宮の頸部にできる「子宮頸がん」、子宮体部にできる「子宮体がん」になります
まだまだなのかな・・・って思います
近年に女性の晩婚化や少子化が原因で増えているとされる子宮筋腫は、子宮肉腫や子宮がんへの変異が心配されることが多い。
従来、子宮筋腫と子宮肉腫を見分ける診断は難しいものだった。しかし、陽電子放射断層撮影(PET)を利用することで、患者の負担は最小でも9割以上の高い精度でがん診断することができるようになった。
この「PET診断法」は、福井大産科婦人科の吉田好雄准教授と福井大高エネルギー医学研究センターの岡沢秀彦教授が開発した手法で、米国核医学学会「がん・腫瘍(しゅよう)診断部門」では「最高賞」を獲得している。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「子宮がん」・・・実は、子宮がんという病名はありません
子宮のがんは、子宮の頸部にできる「子宮頸がん」、子宮体部にできる「子宮体がん」になります
まだまだなのかな・・・って思います
2011年12月21日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん
前立腺がんの早期発見法
2011.12.07 Wednesday
前立腺は男性特有のもので、ここで精液の主成分が作られています。この前立腺にがんが発生して前立腺がんとなります。
若年での発症は家族性以外はまれで、加齢とともに増加し50歳以上で発症する場合が多くなります。
欧米人での発症率が高く、食生活上の違いが背景にあるとされていますが、人種的には米国黒人男性で最も高い発症というデータがあります。続いて白人、アジア人となります。
しかし、近年日本でも食生活の欧米化に伴い急増しています。困ったことに他のがん同様に早期症状に目立ったものはありません。比較的早期で症状があったとしても、そのほとんどは併発する前立腺肥大症に伴う症状ということになります。
前立腺肥大症のテーマでも以前に触れましたが、主な症状は次の通りです。進行がんとなり転移する場合にはリンパ節と骨の症状が多くなります。
1.尿が出にくい
2.尿の回数が多い
3.排尿後にまだ膀胱に尿が残っている感じがする
4.夜間頻尿
5.排尿したいと思ったらトイレに行くまで我慢できない
6.下腹部不快感
以上のような前立腺肥大症の諸症状から泌尿器科受診して、がんが発見されるケースがほとんどです。
診断には画像診断、直腸診によりがんが疑われる場合に前立腺生検が行われて最終的診断となります。その他採血でPSA、前立腺特異抗原と呼ばれる腫瘍マーカーが早期発見に役立ちます。
これは前立腺肥大症でも上昇することもありますが、4~10np/mlという数字ではグレーゾーンと呼ばれ、定期的な受診により経過観察が必要になります。
10np/ml以上ではその50~80%にがんが発見されています。早期発見のためにまずは健診を!
がん治療の最新情報:http://blog.kougan.info/
前立腺は男性特有のもので、ここで精液の主成分が作られています。この前立腺にがんが発生して前立腺がんとなります。
若年での発症は家族性以外はまれで、加齢とともに増加し50歳以上で発症する場合が多くなります。
欧米人での発症率が高く、食生活上の違いが背景にあるとされていますが、人種的には米国黒人男性で最も高い発症というデータがあります。続いて白人、アジア人となります。
しかし、近年日本でも食生活の欧米化に伴い急増しています。困ったことに他のがん同様に早期症状に目立ったものはありません。比較的早期で症状があったとしても、そのほとんどは併発する前立腺肥大症に伴う症状ということになります。
前立腺肥大症のテーマでも以前に触れましたが、主な症状は次の通りです。進行がんとなり転移する場合にはリンパ節と骨の症状が多くなります。
1.尿が出にくい
2.尿の回数が多い
3.排尿後にまだ膀胱に尿が残っている感じがする
4.夜間頻尿
5.排尿したいと思ったらトイレに行くまで我慢できない
6.下腹部不快感
以上のような前立腺肥大症の諸症状から泌尿器科受診して、がんが発見されるケースがほとんどです。
診断には画像診断、直腸診によりがんが疑われる場合に前立腺生検が行われて最終的診断となります。その他採血でPSA、前立腺特異抗原と呼ばれる腫瘍マーカーが早期発見に役立ちます。
これは前立腺肥大症でも上昇することもありますが、4~10np/mlという数字ではグレーゾーンと呼ばれ、定期的な受診により経過観察が必要になります。
10np/ml以上ではその50~80%にがんが発見されています。早期発見のためにまずは健診を!
がん治療の最新情報:http://blog.kougan.info/