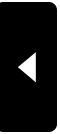スポンサーリンク
微小がん、スプレーで蛍光
微小がん、スプレーで蛍光=内視鏡手術の成功率向上期待―東大と米国立研が試薬開発
時事通信 11月24日(木)4時4分配信
がんの外科手術の際、スプレーすると数分後に微小ながんが緑色の蛍光を発し、見分けられる試薬を開発したと、東大大学院医学系研究科の浦野泰照教授や米国立がん研究所の小林久隆主任研究員らが23日付の米医学誌サイエンス・トランスレーショナル・メディシンに発表した。内視鏡などを使ってがんを切除する際、取り残しを防ぐことができ、手術の成功率が高まると期待される。
研究チームは、正常な細胞には少ないが、がん細胞には非常に多い物質を探し出し、この物質にだけ蛍光試薬を結合させて光らせる方法を考案。健康診断の際、アルコール性肝障害などの指標として利用される「ガンマGTP」によく似た酵素「GGT」を見つけた。
GGTは、肺や肝臓、乳、卵巣などさまざまながん細胞の細胞膜上に多く存在し、がん細胞のエネルギー生産に必要な「グルタチオン」を外部から取り込む役割を果たしている。研究チームは、GGTに結合すると、蛍光物質を生成し、がん細胞内に蓄積される試薬「gGlu―HMRG」を開発した。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
立川談志さんが喉頭がんで亡くなられました。
私は関西なので、談志さんの落語はほとんど見たことがありませんが
落語家さんらしい人生を送られた方だなと思いました
1997年に食道がん、そして、咽頭がん。
何度かの再発を繰り返しているようなので、再発・転移がんだったのでしょうか?
『がん治療は最初の治療が肝心』と、私が治療を受ける時に体験者の友人から言われた言葉です
最初にきちんとした治療をしておくと、再発・転移の確立がぐっと下がるそうです
談志さんが最初に手術を受けた頃よりも、現在では食道がんも見つかりやすくなっているそうです
そして患者さんは、大変な手術をしていたそうですが、段々と早期で見つかるようになると
内視鏡手術もできたりと比較的体に負担のないようになっているそうです
『微小がん、スプレーで蛍光』というのは、すごい事だと思います
私自身、微小浸潤がんということでお腹の中に取りこぼしのがんがあるかも知れないということで
追加の放射線治療を受けているので、もし手術だけでがんが取り除けていればと思います
がん治療の進化は、目覚しいものがあります
できるだけ患者の負担にならないものを望みます
時事通信 11月24日(木)4時4分配信
がんの外科手術の際、スプレーすると数分後に微小ながんが緑色の蛍光を発し、見分けられる試薬を開発したと、東大大学院医学系研究科の浦野泰照教授や米国立がん研究所の小林久隆主任研究員らが23日付の米医学誌サイエンス・トランスレーショナル・メディシンに発表した。内視鏡などを使ってがんを切除する際、取り残しを防ぐことができ、手術の成功率が高まると期待される。
研究チームは、正常な細胞には少ないが、がん細胞には非常に多い物質を探し出し、この物質にだけ蛍光試薬を結合させて光らせる方法を考案。健康診断の際、アルコール性肝障害などの指標として利用される「ガンマGTP」によく似た酵素「GGT」を見つけた。
GGTは、肺や肝臓、乳、卵巣などさまざまながん細胞の細胞膜上に多く存在し、がん細胞のエネルギー生産に必要な「グルタチオン」を外部から取り込む役割を果たしている。研究チームは、GGTに結合すると、蛍光物質を生成し、がん細胞内に蓄積される試薬「gGlu―HMRG」を開発した。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
立川談志さんが喉頭がんで亡くなられました。
私は関西なので、談志さんの落語はほとんど見たことがありませんが
落語家さんらしい人生を送られた方だなと思いました
1997年に食道がん、そして、咽頭がん。
何度かの再発を繰り返しているようなので、再発・転移がんだったのでしょうか?
『がん治療は最初の治療が肝心』と、私が治療を受ける時に体験者の友人から言われた言葉です
最初にきちんとした治療をしておくと、再発・転移の確立がぐっと下がるそうです
談志さんが最初に手術を受けた頃よりも、現在では食道がんも見つかりやすくなっているそうです
そして患者さんは、大変な手術をしていたそうですが、段々と早期で見つかるようになると
内視鏡手術もできたりと比較的体に負担のないようになっているそうです
『微小がん、スプレーで蛍光』というのは、すごい事だと思います
私自身、微小浸潤がんということでお腹の中に取りこぼしのがんがあるかも知れないということで
追加の放射線治療を受けているので、もし手術だけでがんが取り除けていればと思います
がん治療の進化は、目覚しいものがあります
できるだけ患者の負担にならないものを望みます
2011年11月24日 Posted by すもも at 12:00 │Comments(2) │ニュース・・・がん
100倍のがん検出感度でも発見できない理由
島津製作所、がんの目印検出感度100倍に
2011年11月8日 日本経済新聞
島津製作所は8日、病気の目印になる分子を従来の100倍以上の感度で検出できる技術を開発したと発表した。検出に使う抗体たんぱく質の構造を、目印分子に結合しやすいよう改良した。ノーベル化学賞受賞者でもある同社の田中耕一フェローは記者会見し、「がんなどの目印を血液1滴から検出できるようになる。病気の診断や原因解明に役立ち抗体医薬の改良にもつながる」と期待を語った。
抗体は体内で免疫反応を担う。アルファベットの「Y」に似た形のたんぱく質で、2本の“腕”を使って特定の分子に結合する。田中フェローらは腕の付け根部分に、ばねのような形のポリエチレングリコールを組み込んだ抗体を設計した。2本の腕は通常、固定されほとんど動かないが、新しい抗体では回転や伸び縮みするため、目的の分子とより結合しやすい。
アルツハイマー病の原因物質の一つとされる「アミロイドベータ」を使って実験し、結合能力が従来の100倍以上に高まることを確認した。ごく微量しか存在しない分子も検出できるようになる。血中の微量なたんぱく質を検出し、がんやアルツハイマー病などを早期診断する技術につながる。少ない投与量でも高い効果が得られる抗体医薬を開発できる可能性もあるという。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『100倍のがん検出感度でも発見できない理由』という見出しに「なんだろう?」と思ったのは
どんなに性能のいい機械が出てきたとしても「検診率」の低さが早期発見につながらないということだと思います
私自身がそうですが自覚症状がでて初めて重い腰を上げて病院に行きました
子宮頸がんや子宮体がんは、比較的自覚症状がでても早期がんの可能性もありますが
すい臓がんや肝臓がんといった「自覚症状の少ないがん」は早い検診が大切です
どんなにすごい機械ができても、最後は自分自身の行動力だと思います

2011年11月16日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(2) │ニュース・・・がん
抗がん剤新薬の原料とは

毒蛇や毒虫から抗がん剤の新薬と聞くと、何やらおどろおどろしい、マガイモノに聞えてしまいます。しかし、抗がん剤に限らず、世の中に出回る多くの薬(クスリ)と称するモノの多くは、虫や植物から抽出・精製されたモノで、化学合成されたモノは実は少数派だったりします。どちら良いとか悪いとかではなく、効果の有無と大小が問題なのです。
新開発の抗がん剤の殆どはがん細胞に対して有効です。がんに効果のある成分だけを選りすぐっているのですから当たり前といえば当たり前。問題なのは、がん細胞への殺傷能力ではなく、正常細胞への悪影響の度合いなのです。
抗がん剤治療の休止中止の殆どの原因は、がんの増殖を低減もしくは縮小させる兆候が見えつつも、がん患者が副作用による衰弱に耐え切れないことが原因です。(極端な言い方では「抗がん剤ががん患者をコロス」とも)
このニュースのがん新薬が我々の前に抗がん剤新薬として登場するまでには、まだまだ実験が必要で長い年月と費用が掛かります。
それでも、世界中で抗がん剤の新薬候補が日々開発されているという事実が大切なのです。
2011年 10月 25日 イランラジオ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
イラン人研究者、新たな抗がん構造を発見
イラン人研究者が、がん細胞を抑制するための新たな原子構造を発見しました。
この新たな構造は、ICD85と呼ばれ、ラーズィー血清開発ワクチン研究所で、マムシやさそりの毒から作成されました。
ラーズィー血清開発ワクチン研究所のザーレ研究員は、「この新たな構造は、15年に及ぶ研究によって発見されたものであり、乳がん、白血病、腎臓がん、肺がんを抑制する効果がある」と語りました。さらに、「現在、この新たな構造は、ウサギとマウスを対象に実験が行われ、成功を収めている」としました。
また、「この新たな構造は、人間の生きた細胞に対しても実験的に用いられ、好ましい結果が得られている」としています。現在、がんの治療法のひとつに放射線治療がありますが、それは健康な細胞にも害を及ぼします。
ザーレ研究員は、「様々な実験は、この新たな構造なら、ほぼ完全にがん細胞のみを標的にすることができることを示している」と語りました。
さらに、「数々の調査によれば、この新たな原子構造を利用しても、がん患者の脱毛といった副作用を引き起こすことはない」と述べています。
イランは、この科学的な業績を手にした、世界でも限られた国の一つとなっています。
癌治療の最新情報:http://blog.kougan.info/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
自然界の中では、私たち人間が知らないところで命を削ってくれている生物が沢山います
以前「カブトガニ血球抽出成分」がないと医療品の洗浄ができないというのを知りました
カブトガニの血液使って細菌を発見するので、当然、カブトガニからしか採取できません
・・・・・・・・・・カブトガニの血液(青色)は、大腸菌(感染症となりうる腸内細菌)をゲル状に固める性質が発見された。大腸菌など発見のために、血液採取して新薬の開発が進んでいる。
1.内毒素(大腸菌、緑膿菌、サルモネラ菌など)の検査薬
2.医薬品(注射液、ワクチン、人工腎透析まくなど)の内毒素汚染の検査薬
3.食べ物(肉、牛乳など)の細菌汚染の検査薬
4.水質(井戸水、水道水など)の検査薬
また、エイズウイルスの繁殖がおさえられ、その活動が弱まるという研究も進んでいるという。
今では、カブトガニの血液の需要がとても多くなってきている。実際には生きたカブトガニの尻尾から採血した後、また海に返している。病気の人たちのためにわれわれは献血するがが、内毒素の検出のために「生きている化石」のカブトガニから献血(カブトガニにとっては迷惑な話だが)してもらっているのである。・・・・・・・・・・
http://ameblo.jp/aegis-t-operation/entry-10561367667.html
http://www3.famille.ne.jp/~ochi/kabutogani/index.html
昔から『毒と薬は使いよう』と言われていたように、生物が持っている毒も同じです
カブトガニ以外にも、嫌われ物のヘビの毒も実はとても役に立っています
毒蛇の毒は「神経毒」と「出血毒」があります
出血毒は血液が固まらないようにする成分が含まれていて、これが体内に入るともちろん亡くなったりしますが、治療として、脳に血栓ができた人に使うと早期であれば助かります
現在、アメリカやインド、アジアなどガラガラヘビやラッセルクサリヘビ、コブラなど人間の住んでいる場所にヘビが出て大量に殺されています
でも、実は人間がヘビの棲家に踏み込んでいるのだと思います
無条件に殺されていい生き物などいないのだと思います
もしも、新しい抗がん剤や治療薬ができたとして、その生き物が絶滅の危機に瀕していたら?
どんなに毒があって人を殺す力があるとしても、その生き物が人間を治してくれるものである可能性はゼロではないと思います
ヘビの中で毒を持っているものは、2割ほどしかいないそうです
ヘビ好きの私には、その進化の中には何か特別なものがあるんじゃないのかな。って思ってます
2011年10月28日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(2) │ニュース・・・がん
がん再発や転移を完全に抑制
2011年10月12日 日本経済新聞
がん転移の兆し察知 慶応大など研究続々
日本人の死亡原因の1位を占めるがんで、転移を抑える研究が相次いでいる。がんは手術などで切除しても、骨やリンパ節など体のあちこちで再発してしまうと治療が難しい。1カ所にとどまるなら、克服できるがんもある。5日まで名古屋市で開いた日本癌(がん)学会では、がんの治療効果を高めるため、転移の兆しをいち早く探しだし、先手を打って防ぐ試みが発表された。
国立がん研究センターは、がん細胞から微小な分子が血管に流れ込んでいることに着目した。ヒトの乳がん細胞をマウスの乳腺に移植し、がん細胞の酵素の働きを抑えてみた。がん細胞が「マイクロRNA(リボ核酸)」と呼ぶ分子を出さなくなると、転移しやすい肺やリンパ節に3週間たってもがんができなかった。「転移は完全に抑制できた」(小坂展慶研究員)
マイクロRNAが血液を通じて離れた場所にある細胞の遺伝子に入り込むと、そこにがんができやすくなるとみている。がんを呼び寄せる仕組みがあるようだ。
慶応大学の工藤千恵講師は、がん細胞の遺伝子「HERV―H」が転移に関わっていることを突き止めた。この遺伝子が働くとたんぱく質などががん細胞から出てくる。免疫細胞を弱め、がん細胞がほかの臓器に移るきっかけになるという。たんぱく質を壊すと転移を抑えられることがマウスの実験で分かった。
がん転移対策の研究例 研究対象主な成果
▼転移を防ぐ
東京大学医科学研究所、順天堂大など
血液凝固たんぱく質が血液がんの転移を制御する酵素に作用する現象を発見。白血病マウスで治療実験に成功国立がん研究センター
がん細胞から出る微小分子を抑える慶応大
がん細胞が作るたんぱく質などの働きを抑え、免疫力を正常化
▼転移を予測
東京医科歯科大
大腸がん患者で特定遺伝子「PDGFC」が過剰に働くと転移確率が高まることを発見。診断に応用へ
▼転移を可視化
三重大
特殊な顕微鏡で転移を診断
工藤講師は、ほとんどのがんでみられるリンパ節への転移を防ぐ治療薬を開発したいという。
一方、転移しても小さいがんなら治療しやすい。三重大学チームは、組織の奥深くを観察できる特殊な装置「二光子レーザー顕微鏡」を使い、内臓を切らずに転移を調べる技術を開発した。
血液中の血小板や白血球が緑色に光る遺伝子改変マウスの脾臓(ひぞう)に、赤い蛍光を放つようにしたヒトのがん細胞を注射した。がん細胞の一部が血管を通って肝臓に移動し、1~2カ月後には転移がんが育つ様子などが観察できた。抗がん剤の投与でがんが縮む様子も見えた。
東京医科歯科大学のチームは特定の遺伝子を目印に再発や転移のリスクを測るのが目標だ。血液検査で遺伝子を調べ、予防的に抗がん剤を投与できる可能性がある。
がん治療の最新情報:http://blog.kougan.info/?eid=1171954
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『がん再発や転移を完全に抑制』というのを読んで、おおお!って思ったけれど
まだマウスでの実験のようです
でも、こうやって色々なものが解明されていって人への応用ができていけばいいなって思います
がん患者にとって大切なことは「希望がもてること」だと思います
がん転移の兆し察知 慶応大など研究続々
日本人の死亡原因の1位を占めるがんで、転移を抑える研究が相次いでいる。がんは手術などで切除しても、骨やリンパ節など体のあちこちで再発してしまうと治療が難しい。1カ所にとどまるなら、克服できるがんもある。5日まで名古屋市で開いた日本癌(がん)学会では、がんの治療効果を高めるため、転移の兆しをいち早く探しだし、先手を打って防ぐ試みが発表された。
国立がん研究センターは、がん細胞から微小な分子が血管に流れ込んでいることに着目した。ヒトの乳がん細胞をマウスの乳腺に移植し、がん細胞の酵素の働きを抑えてみた。がん細胞が「マイクロRNA(リボ核酸)」と呼ぶ分子を出さなくなると、転移しやすい肺やリンパ節に3週間たってもがんができなかった。「転移は完全に抑制できた」(小坂展慶研究員)
マイクロRNAが血液を通じて離れた場所にある細胞の遺伝子に入り込むと、そこにがんができやすくなるとみている。がんを呼び寄せる仕組みがあるようだ。
慶応大学の工藤千恵講師は、がん細胞の遺伝子「HERV―H」が転移に関わっていることを突き止めた。この遺伝子が働くとたんぱく質などががん細胞から出てくる。免疫細胞を弱め、がん細胞がほかの臓器に移るきっかけになるという。たんぱく質を壊すと転移を抑えられることがマウスの実験で分かった。
がん転移対策の研究例 研究対象主な成果
▼転移を防ぐ
東京大学医科学研究所、順天堂大など
血液凝固たんぱく質が血液がんの転移を制御する酵素に作用する現象を発見。白血病マウスで治療実験に成功国立がん研究センター
がん細胞から出る微小分子を抑える慶応大
がん細胞が作るたんぱく質などの働きを抑え、免疫力を正常化
▼転移を予測
東京医科歯科大
大腸がん患者で特定遺伝子「PDGFC」が過剰に働くと転移確率が高まることを発見。診断に応用へ
▼転移を可視化
三重大
特殊な顕微鏡で転移を診断
工藤講師は、ほとんどのがんでみられるリンパ節への転移を防ぐ治療薬を開発したいという。
一方、転移しても小さいがんなら治療しやすい。三重大学チームは、組織の奥深くを観察できる特殊な装置「二光子レーザー顕微鏡」を使い、内臓を切らずに転移を調べる技術を開発した。
血液中の血小板や白血球が緑色に光る遺伝子改変マウスの脾臓(ひぞう)に、赤い蛍光を放つようにしたヒトのがん細胞を注射した。がん細胞の一部が血管を通って肝臓に移動し、1~2カ月後には転移がんが育つ様子などが観察できた。抗がん剤の投与でがんが縮む様子も見えた。
東京医科歯科大学のチームは特定の遺伝子を目印に再発や転移のリスクを測るのが目標だ。血液検査で遺伝子を調べ、予防的に抗がん剤を投与できる可能性がある。
がん治療の最新情報:http://blog.kougan.info/?eid=1171954
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『がん再発や転移を完全に抑制』というのを読んで、おおお!って思ったけれど
まだマウスでの実験のようです
でも、こうやって色々なものが解明されていって人への応用ができていけばいいなって思います
がん患者にとって大切なことは「希望がもてること」だと思います
2011年10月20日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん
コーヒーでがん予防

2011年9月13日 daizu
朝のコーヒータイムで皮膚がん予防?
「コーヒー」には、抗酸化作用による美肌効果があったり、ダイエットに効果があると言われたりする一方で、胃に悪いとか体に悪いとか言われたりしている。毒にも薬にもなる食物の代表格なのではないだろうか?
そんなコーヒーについて、ラトガース大学での新しい研究によると、朝の一杯のコーヒーが、太陽からの有害なダメージを予防したり、皮膚がんを予防するなど、肌の健康を守るのに役立つという見解が示された。
コーヒーに含まれるカフェインが、タンパク質リン酸化酵素ATRを抑制し、紫外線で損傷した細胞を死滅させる効果があり、ある種の皮膚がんに対する抵抗性があるという理論は、以前から存在していたが、今回の研究結果はこの理論を裏付けるものとなっている。
今回のマウスを使った実験では、カフェイン入りコーヒーを適度に飲んだり、直接皮膚にコーヒーを塗布すると、皮膚がんを引き起こす原因となる紫外線のダメージから肌を守るのに役立つということがわかったそうだ。
というもの、コーヒーには抗酸化物質が含まれており、皮膚がんリスクを軽減させるのに関係していると言われている。以前行われたマウスを使った研究では、カフェイン入りの水を飲んだマウスに、皮膚細胞のDNAを破壊するUVBを放射させたところ、傷ついた細胞の大部分を取り除くことができ、皮膚がんリスクを軽減する効果があるとされていた。
「コーヒーを飲むことは、非黒色腫皮膚癌のリスクの減少と関係性があることは知られているが、今話題のカフェインが日光によって引き起こされる皮膚癌を阻害できるのかどうかの研究を進める必要がある」と語るのは、スーザン・リーマン・カルマン癌研究所のディレクターであるアラン・コニー氏だ。
アメリカの国立がん研究所によると、日光によって引き起こされる皮膚がんがアメリカで最も一般的な癌とされ、毎年100万人以上発症しているそうだ。アメリカ人の食生活における最大の抗酸化物質供給源であるコーヒー飲料の摂取量が増えると、皮膚がん以外にも、前立腺がんや子宮がんなどの癌のリスクを減少させると言われているが、現在のところ、その理由については詳しくは解明されてはいない。
コニー氏によると、「コーヒを飲んだり肌に直接塗布すると、タンパク質リン酸化酵素ATRが抑制されるそうだ。すると、直接肌にダメージを与える紫外線を吸収するので、紫外線を浴びても皮膚がんリスクが大幅に抑制され、がん予防の最大の武器になるかもしれない」との見解を示している。
がん治療の最新情報:http://blog.kougan.info/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以前、乳がんの予防には1日3杯程度のコーヒーがいいというのを読んだことがあります
コーヒーってなかなかの優れものなのかな?って思いました
しかも今回は「朝1杯のコーヒーでいい」というのも、ついつい飲みすぎてしまうと
胃が痛くなる私には、嬉しい話です
色々な「がんに効く」食品などがありますが、自分にとって負担にならない程度のものを生活に取り入れていくっていうのでいいのかな?と思いました
>アメリカの国立がん研究所によると、日光によって引き起こされる皮膚がんがアメリカで最も一般的な癌とされ、毎年100万人以上発症しているそうだ。
日本でも最近は「日焼けをしない」というのを盛んに言われています
日本の5大がんは「胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、肝がん」と言われていますが、これからは皮膚がんも増えていくんでしょうか?
「朝1杯のコーヒー」が嗜好品ではなくて生活改善の方法として取り入れられていくようになるのも時間の問題かもしれないですね
2011年09月16日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん
血液がんの原因遺伝子発見~東大など~

血液がんの原因遺伝子発見=骨髄異形成症候群、薬開発に期待―東大など
時事通信 9月12日(月)2時9分配信
血液をつくり出す細胞に異常が起きる難治性血液がんの一種「骨髄異形成症候群」の原因となる遺伝子を、東京大医学部付属病院の小川誠司特任准教授らの国際共同研究チームが発見した。現在は根本的な治療法は骨髄移植のみだが、遺伝子の発見が治療薬開発につながる可能性があるという。論文は11日付の英科学誌ネイチャー電子版に掲載された。
研究チームは患者29人の遺伝情報を詳細に解析。細胞が遺伝情報をコピーする際、必要な部分だけを選び出す「スプライシング」に関わる複数の遺伝子に、高い確率で変異が生じていることが分かった。
さらに患者316人と、他の血液がん患者266人を比較。これらの遺伝子に変異がある割合は、骨髄異形成症候群で最大85%だったのに対し、他は数%以下だった。変異させた遺伝子をマウスの細胞に導入し、血液をつくる能力が低下することも確認した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110912-00000006-jij-soci
タグ :血液がんの原因遺伝子発見ニュース
2011年09月14日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん
ビタミン剤は女性の がんリスク!?

ビタミン剤ががんを誘引するわけではなく、ビタミン剤に頼るような生活習慣と食生活ががんを誘引していると考えるのが妥当でしょう。
最近ではがん治療にビタミンC療法などが取り上げられたり、伝統的なβグルカン食材が取り上げられたりしていますが、予防に徹するなら多様な食材から少量ずつを摂取するのががん予防だけでなく成人病予防全般に理想的です。
2011年8月25日 日本経済新聞
ビタミン剤1年以上摂取の女性、がんリスク上昇 がんセンター発表
ビタミンサプリメントを過去に摂取した女性はがんになるリスクが高いとの調査結果を国立がん研究センターがまとめ、25日発表した。週に1日以上、1年間以上摂取した経験のある人は、まったく摂取したことがない人に比べてリスクが17%高かった。ただサプリメントの作用と発がんとの因果関係は明らかではないという。
過去にサプリメントを摂取した経験を持つ女性は肥満や高血圧、糖尿病治療の割合も多かった。同センターの笹月静予防研究部室長はサプリメントが原因というよりも、「過去に摂取の経験がある人は不健康な傾向がある場合が多く、その影響も出たのではないか」とみている。
調査は1990~2006年に40~69歳の男女約6万3千人を対象にアンケート方式で実施。期間中がんになった人は4501人。90年時点でサプリメントを摂取し、その後5年以内にやめた女性は摂取経験のない人に比べがんになる確率が17%高かった。
男性ではこうした傾向は見られなかった。「(調査時点で)飲酒や喫煙をしている人の割合が高く、(それらに隠れて)サプリメントの影響が見えにくかった可能性が高い」としている。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2011年8月25日 時事通信
ビタミン剤摂取、がんリスク減=女性のみ、生活習慣も重要-がんセンター
国立がん研究センター(東京都中央区)などの研究班は25日、ビタミン剤の摂取を続けた女性ではがんや循環器疾患の発症リスクが低下するとの調査結果を発表した。男性について関連は認められず、同センターは「男性の場合は、喫煙や飲酒の影響があるのでは」としている。
研究班は全国9地域を対象に、1990年から94年にかけ、40~69歳の調査を開始。このうち、開始5年後にがんや脳卒中などの循環器疾患にならなかった男女6万2629人を追跡調査した。その結果、追跡調査を始めてから7~11年間に4501人は何らかのがんと診断され、1858人が循環器疾患を発症したことが分かった。 研究班は、対象者をビタミン剤の摂取状況に合わせ
(1)調査開始時・5年後とも非摂取
(2)開始時摂取・5年後非摂取
(3)開始時非摂取・5年後摂取
(4)開始時・5年後とも摂取 -の4群に分類。
摂取の定義は、調査開始時は週1日以上、5年後では週1日以上を1年以上継続とした。
女性について(1)のがんリスク値を1.0とした場合、(2)が1.17、(3)が1.24、(4)は0.92。同様に循環器疾患は(2)1.08(3)1.32(4)0.60だった。男性は関連性が一切なかった。 女性の(2)は肥満や喫煙、高血圧の割合が高く、(3)はデータを精査した結果、ビタミン摂取を始めた時に潜在的疾患が既にあり、がん発症と関連はないと結論付けた。(4)の摂取継続者は検診受診率が高く、食事によるビタミン摂取量が多いなどの特徴があったという。
同センターの笹月静予防研究部室長は「男性で差が出ないのは飲酒や喫煙により、ビタミン剤の効果が打ち消されたためと思われる。ビタミン剤以外にも、運動や食事などによる生活習慣の改善が重要だ」としている。
がん治療の最新情報:http://blog.kougan.info/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「ビタミン剤は女性のがんリスク!?」って、見出しだけでも驚きでした
最近は飲んでいませんが、私もちょっとした「ビタミンマニア」でした
サンプルを貰ってきて、それを火で燃やしてみて綺麗に燃えるものは天然素材を使用しているというのを聞いた事があったので、いちいち燃やしてみて確認していたくらいのオタクさんでした
でも、今は「くちの端っこ」が切れてしまったら「あ~あ、ビタミン取らなきゃ」くらいのいい加減さになっています
だって、そんなにお金かけても結局のところ効いているのかどうかって、わかる訳でもないなって・・・
ただ、お店にいくとすごい種類のビタミン剤が売っています
私も少し聞いていましたが「がんにはビタミンC」だから。とか「にんじんジュースが効く」というのがありました。あとは「キノコ」・・・
今はがんは生活習慣病の1つとされています
センセーショナルな見出しですが、やっぱり健康的な食生活が大切なんだなって思います
2011年09月02日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん
効果的ながん予防対策食品
乳酸菌が免疫力を向上させる経験的に人類が知っていたことだが、実験で検証された意義は大きいだろう。免疫細胞を活性化する食品に関する研究は、多くの研究機関で実施と発表が繰り返されている。
最近の発表で注目されたのは、北海道大学による「乳酸菌とβグルカン(ベータグルカン)」を併用した場合の免疫力の飛躍的な向上効果の報告だろう。当時は新型のインフルエンザに対するタミフルの互換かと まで騒がれた程だ。免疫力の向上は、副作用の無いがん対策であることから、乳酸菌とβグルカンでがんの抑制や転移に備えることは非常に意義のあることだと言える。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2011年8月10日 マイコミジャーナル
インフルエンザウイルスや風邪ウイルス、がん細胞等と戦ってくれるナチュラルキラー(NK)細胞を活性化させる「1073R-1乳酸菌」(以下、 R-1乳酸菌)。その働きを示す調査結果が9日、東京・赤坂のホテルニューオータニにて発表された。R-1乳酸菌を長期間摂取した佐賀県有田町に住む小中学生のインフルエンザ感染傾向などが紹介された。
同調査は、佐賀県有田町、山形県舟形町にて実施。健康増進活動の一環として、2010年(有田町は9月、舟形町は6月)から今年3月18日までの間、保育園・幼稚園児、小中学生全員と関係職員全員にR-1乳酸菌を使用したヨーグルトを給食などで継続的に食べてもらい、インフルエンザや風邪の罹患率や欠席率の変動についての継続調査を行った。
昨年12月末までの中間報告によると、佐賀県はインフルエンザの感染レベルが高い地域にも関わらず、有田町は周辺地域、佐賀県(有田町を除く)と比べてインフルエンザの罹患率、欠席率が抑えられた結果となった。また、舟形町ではインフルエンザ感染の報告はなかった。今回公表された3月18日までの有田町のデータでは、隣接する地区と比較してインフルエンザ(A/B/新型)の感染率が低く、統計学的に有意差があることが明らかになった。
これまでにも両町では、60歳以上を対象にした「R-1乳酸菌を使用したヨーグルトの長期摂取」の効果に関する調査を実施。R-1乳酸菌の入ったヨーグルトと牛乳を飲んだ人で比較したところ、NK細胞の活性が低い人の活性が高まることが確認されたほか、「風邪をひくリスク」が低減することが明らかになった。また、マウスを用いた動物実験では、インフルエンザウイルス(A型H1N1亜型)の感染予防に効果があることが確認されている。
今回の調査に協力し、実際に子どもたちを診察した有田共立病院院長の井上文夫先生が登壇し、調査結果を報告した。有田町の調査結果は、2010年 10月1日から今年3月18日まで、小中学生計1,904名が対象。インフルエンザによる欠席児童数を有田町、有田町に隣接する3市(伊万里市、武雄市、嬉野市)と比較したところ、小中学生ともに摂取期間中のインフルエンザ(A/B/新型)の感染率が低かった。小学校に至っては隣接市に比べて10分の1程度で顕著に差が出ており、特に中学校より小学校の方が、インフルエンザ感染率がより低い傾向にあるとした。また、学年ごとに比較しても隣接市より低いことを説明した。
井上先生は、結論としてR-1乳酸菌を使用したヨーグルトは全般的なインフルエンザウイルス感染に対する予防効果がある可能性を示唆した。また、アンケートにより摂取期間を通じて家族が感じたことも調査しており、プレスセミナーでは保護者からの意見も紹介された。「風邪、インフルエンザにかかりにくくなった」「インフルエンザにかかっても症状が軽い」「鼻炎がかるくなった」など好意的な意見が多く寄せられている事実に触れ、「こういった意見を前面に出すと科学的ではないという意見を持たれる人もいるかもしれないが、臨床の最前線に立つ者にとってはこういう声も大事にしたい」と述べた。
有田町での子どもたちのヨーグルト摂取調査について、順天堂大学医学部特任教授(免疫学講座)の奥村康先生は「個々の小学生、中学生のタイプ、インフルエンザワクチンの接種の有無などバックグラウンドの違いも考えられないことではないが、インフルエンザワクチンの摂取率はどの地区でも差がないということは分かっている。そのことを踏まえて今回の調査結果を評価すると、統計的に非常に意味のある結果」とした上で、「我々のNK活性についての理論、動物実験の結果や基礎的な論文の内容にピッタリ合う結果になっていて、我々が明らかにしてきた内容と矛盾のない結果が得られている」と述べた。
癌(がん)治療の最新情報:http://blog.kougan.info/?eid=1171885
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
乳製品、多く摂ると前立腺がんのリスクが高まる 日本人4万3千人を調査(厚生労働省研究班)
乳製品を多く摂る人は前立腺がんになりやすい---。こうした研究結果を厚生労働省研究班が公表した。牛乳、チーズ、ヨーグルトなどの乳製品にはカルシウムや飽和脂肪酸が多く含まれるが、比較研究で、前立腺がんのリスクが高いことが明らかになったという。
「カルシウムか飽和脂肪酸かどちらが影響しているか関連づけられない」
研究は、1995年と1998年に、日本の10府県(岩手、秋田、長野、沖縄、茨城、新潟、高知、長崎、沖縄、大阪)に住む45~74歳の男性約4万3千人を対象に、2004年まで追跡調査した。この間、329人が前立腺がんを発症した。研究では対象者を、乳製品、牛乳、チーズ、ヨーグルトの摂取量で4グループに分け、前立腺がんの発症リスクを調べた。
結果、乳製品、牛乳、ヨーグルトの摂取量が最も多いグループは最も少ないグループに比べ、前立腺がんの発症リスクが、それぞれ約1.6倍、1.5倍、1.5倍となり、摂取量が多いほどリスクが高いことが明らかになった。また、乳製品はカルシウムや飽和脂肪酸が多くふくまれるため、それらの摂取量により4グループに分けたところ、カルシウムおよび飽和脂肪酸についても、前立腺がんリスクを若干上げる傾向にあることがわかったという。
研究班は、「カルシウムよりむしろ飽和脂肪酸との関連が強いようだが、どちらが影響しているか関連づけられない」としている。
欧米の研究でも、乳製品を多く摂ると前立腺がんのリスクが高まることが報告されている。
2000年のAmerican Assoc. for Cancer Research年次総会によると、ハーバード大の研究グループが、男性医師20,885人の11年間の追跡調査(Physicians'Health Study)を分析した(このうち、1千12人が前立腺がんと診断)ところ、全乳、スキムミルク、シリアル、チーズ、アイスクリームなど最も多く摂るグループの20%は、前立腺がんの危険性が34%高かったという。
ただ、一方で、全脂肪乳製品は前立腺がん予防に有用という報告もある。American Journal of Epidmiology誌'07/10月号に掲載された記事によると、ハワイの研究者グループが被験者82,483人を含むMultiethnic Cohort Studyを1993~2002年まで行った。この研究では、食品頻度調査(FFQ)を使って、乳製品の摂取を調べたところ、一般的な全乳の摂取を増加すると前立腺がんの危険性が12%低下することが分った。一方、低脂肪/無脂肪のミルクでは反対に危険性が16%増大したという。
http://www.health-station.com/new101.html
乳がんと牛乳を読むと「牛乳」や「乳製品」は摂取したくなくなります
乳がんと牛乳:http://miyabimari.tamaliver.jp/e155793.html
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
これらを読んでしまうと、自分はどうすればいいのかわからなくなってしまいます
読めばよむほど、そして、知ればしるほど結局のところ「なぜ、がんになるのか」はわからないのかも
と思ってしまいました
「OOだから、がんになる」
ただ、何事もほどほどに・・・ということでしょうか
最近の発表で注目されたのは、北海道大学による「乳酸菌とβグルカン(ベータグルカン)」を併用した場合の免疫力の飛躍的な向上効果の報告だろう。当時は新型のインフルエンザに対するタミフルの互換かと まで騒がれた程だ。免疫力の向上は、副作用の無いがん対策であることから、乳酸菌とβグルカンでがんの抑制や転移に備えることは非常に意義のあることだと言える。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2011年8月10日 マイコミジャーナル
インフルエンザウイルスや風邪ウイルス、がん細胞等と戦ってくれるナチュラルキラー(NK)細胞を活性化させる「1073R-1乳酸菌」(以下、 R-1乳酸菌)。その働きを示す調査結果が9日、東京・赤坂のホテルニューオータニにて発表された。R-1乳酸菌を長期間摂取した佐賀県有田町に住む小中学生のインフルエンザ感染傾向などが紹介された。
同調査は、佐賀県有田町、山形県舟形町にて実施。健康増進活動の一環として、2010年(有田町は9月、舟形町は6月)から今年3月18日までの間、保育園・幼稚園児、小中学生全員と関係職員全員にR-1乳酸菌を使用したヨーグルトを給食などで継続的に食べてもらい、インフルエンザや風邪の罹患率や欠席率の変動についての継続調査を行った。
昨年12月末までの中間報告によると、佐賀県はインフルエンザの感染レベルが高い地域にも関わらず、有田町は周辺地域、佐賀県(有田町を除く)と比べてインフルエンザの罹患率、欠席率が抑えられた結果となった。また、舟形町ではインフルエンザ感染の報告はなかった。今回公表された3月18日までの有田町のデータでは、隣接する地区と比較してインフルエンザ(A/B/新型)の感染率が低く、統計学的に有意差があることが明らかになった。
これまでにも両町では、60歳以上を対象にした「R-1乳酸菌を使用したヨーグルトの長期摂取」の効果に関する調査を実施。R-1乳酸菌の入ったヨーグルトと牛乳を飲んだ人で比較したところ、NK細胞の活性が低い人の活性が高まることが確認されたほか、「風邪をひくリスク」が低減することが明らかになった。また、マウスを用いた動物実験では、インフルエンザウイルス(A型H1N1亜型)の感染予防に効果があることが確認されている。
今回の調査に協力し、実際に子どもたちを診察した有田共立病院院長の井上文夫先生が登壇し、調査結果を報告した。有田町の調査結果は、2010年 10月1日から今年3月18日まで、小中学生計1,904名が対象。インフルエンザによる欠席児童数を有田町、有田町に隣接する3市(伊万里市、武雄市、嬉野市)と比較したところ、小中学生ともに摂取期間中のインフルエンザ(A/B/新型)の感染率が低かった。小学校に至っては隣接市に比べて10分の1程度で顕著に差が出ており、特に中学校より小学校の方が、インフルエンザ感染率がより低い傾向にあるとした。また、学年ごとに比較しても隣接市より低いことを説明した。
井上先生は、結論としてR-1乳酸菌を使用したヨーグルトは全般的なインフルエンザウイルス感染に対する予防効果がある可能性を示唆した。また、アンケートにより摂取期間を通じて家族が感じたことも調査しており、プレスセミナーでは保護者からの意見も紹介された。「風邪、インフルエンザにかかりにくくなった」「インフルエンザにかかっても症状が軽い」「鼻炎がかるくなった」など好意的な意見が多く寄せられている事実に触れ、「こういった意見を前面に出すと科学的ではないという意見を持たれる人もいるかもしれないが、臨床の最前線に立つ者にとってはこういう声も大事にしたい」と述べた。
有田町での子どもたちのヨーグルト摂取調査について、順天堂大学医学部特任教授(免疫学講座)の奥村康先生は「個々の小学生、中学生のタイプ、インフルエンザワクチンの接種の有無などバックグラウンドの違いも考えられないことではないが、インフルエンザワクチンの摂取率はどの地区でも差がないということは分かっている。そのことを踏まえて今回の調査結果を評価すると、統計的に非常に意味のある結果」とした上で、「我々のNK活性についての理論、動物実験の結果や基礎的な論文の内容にピッタリ合う結果になっていて、我々が明らかにしてきた内容と矛盾のない結果が得られている」と述べた。
癌(がん)治療の最新情報:http://blog.kougan.info/?eid=1171885
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
乳製品、多く摂ると前立腺がんのリスクが高まる 日本人4万3千人を調査(厚生労働省研究班)
乳製品を多く摂る人は前立腺がんになりやすい---。こうした研究結果を厚生労働省研究班が公表した。牛乳、チーズ、ヨーグルトなどの乳製品にはカルシウムや飽和脂肪酸が多く含まれるが、比較研究で、前立腺がんのリスクが高いことが明らかになったという。
「カルシウムか飽和脂肪酸かどちらが影響しているか関連づけられない」
研究は、1995年と1998年に、日本の10府県(岩手、秋田、長野、沖縄、茨城、新潟、高知、長崎、沖縄、大阪)に住む45~74歳の男性約4万3千人を対象に、2004年まで追跡調査した。この間、329人が前立腺がんを発症した。研究では対象者を、乳製品、牛乳、チーズ、ヨーグルトの摂取量で4グループに分け、前立腺がんの発症リスクを調べた。
結果、乳製品、牛乳、ヨーグルトの摂取量が最も多いグループは最も少ないグループに比べ、前立腺がんの発症リスクが、それぞれ約1.6倍、1.5倍、1.5倍となり、摂取量が多いほどリスクが高いことが明らかになった。また、乳製品はカルシウムや飽和脂肪酸が多くふくまれるため、それらの摂取量により4グループに分けたところ、カルシウムおよび飽和脂肪酸についても、前立腺がんリスクを若干上げる傾向にあることがわかったという。
研究班は、「カルシウムよりむしろ飽和脂肪酸との関連が強いようだが、どちらが影響しているか関連づけられない」としている。
欧米の研究でも、乳製品を多く摂ると前立腺がんのリスクが高まることが報告されている。
2000年のAmerican Assoc. for Cancer Research年次総会によると、ハーバード大の研究グループが、男性医師20,885人の11年間の追跡調査(Physicians'Health Study)を分析した(このうち、1千12人が前立腺がんと診断)ところ、全乳、スキムミルク、シリアル、チーズ、アイスクリームなど最も多く摂るグループの20%は、前立腺がんの危険性が34%高かったという。
ただ、一方で、全脂肪乳製品は前立腺がん予防に有用という報告もある。American Journal of Epidmiology誌'07/10月号に掲載された記事によると、ハワイの研究者グループが被験者82,483人を含むMultiethnic Cohort Studyを1993~2002年まで行った。この研究では、食品頻度調査(FFQ)を使って、乳製品の摂取を調べたところ、一般的な全乳の摂取を増加すると前立腺がんの危険性が12%低下することが分った。一方、低脂肪/無脂肪のミルクでは反対に危険性が16%増大したという。
http://www.health-station.com/new101.html
乳がんと牛乳を読むと「牛乳」や「乳製品」は摂取したくなくなります
乳がんと牛乳:http://miyabimari.tamaliver.jp/e155793.html
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
これらを読んでしまうと、自分はどうすればいいのかわからなくなってしまいます
読めばよむほど、そして、知ればしるほど結局のところ「なぜ、がんになるのか」はわからないのかも
と思ってしまいました
「OOだから、がんになる」
ただ、何事もほどほどに・・・ということでしょうか
2011年08月22日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん
がん患者団体から厚労省へがん対策意見書
30のがん患者団体 患者の意見に耳を 対策推進基本計画見直しで厚労相らに要望書
全国の30のがん患者団体が、がん対策推進基本計画の見直しに向け、ドラッグ・ラグの解消や治療費などの経済的負担の解消に向けた議論を集中的に行うことなどを盛り込んだ要望書を8月8日付でまとめ、細川律夫厚生労働相らに提出した。
集中議論が必要だとしたテーマは
▽ドラッグ・ラグの解消に向けた議論
▽患者・家族が抱える就労問題、経済的負担の解消に向けた議論
▽科学的根拠に基づくがん検診の普及・啓発・精度管理(偽陽性・過剰診断などの不利益に関する救済を含む)に関する議論
▽サバイバーシップ概念の普及に関する議論(計画内、サバイバーシップの言葉を盛り込む)――。
薬事や就労問題を含めており、省を挙げた取り組みを促す内容。
がん対策推進基本計画は07年度~11年度からの5カ年計画。来年度からの次期計画実施に向け、計画見直しの議論が厚労省のがん対策推進協議会で行われている。しかし団体側によると、その見直しの議論を進めるでは、患者の求めるテーマが議論されることが少ないまま進んでいる。今後の議論にも強い懸念があるとして、議論すべきテーマをまとめ厚労相ほか、同協議会の門田守人会長、同省がん対策室の鈴木健彦室長あてに要望書を提出することになった。
癌(がん)治療の最新情報:http://blog.kougan.info/?eid=1171884
ドラッグ・ラグ問題:欧米で開発・発売された新薬が日本で使用が認められ発売されるまでには、
国内での治験実施と審査などのため、非常に長い時間がかかります。
欧米との発売時間差は約2.5年と言われており、この、日本と欧米との新薬承認の時間差、
あるいは、海外で新薬が先行販売され、国内では販売されていない状態のことを、「ドラッグ・ラグ」と呼びます。
卵巣がん体験者の会スマイリー:http://ransougan.e-ryouiku.net/index.html
患者・家族が抱える就労問題:がんになっても今まで通り働き続けたいと願っているのに、
降格や配置換え、退職を余議なくされる人は少なくありません。
そんな体験者の一人である桜井なおみさんらの「CSRプロジェクト」事務局が、
全国キャラバンのオープニングとして、2010年5月1日のメーデーに、東京で就労問題フォーラム
「がんと一緒に働こう!~治療を受け続けながら働くコツ~」を開催しました。
http://ganseisaku.net/impact/gan_coproduction/reports/20100604_report.html
キャンサーネットジャパン:ネット配信
http://www2.extide.mediasite.co.jp/mslive/Catalog/pages/catalog.aspx?cid=549b390d-b665-4e33-af07-862103eaf5e1
がんと一緒に働こう(がんナビ):http://medical.nikkeibp.co.jp/inc/all/cancernavi/series/csr/
全国の30のがん患者団体が、がん対策推進基本計画の見直しに向け、ドラッグ・ラグの解消や治療費などの経済的負担の解消に向けた議論を集中的に行うことなどを盛り込んだ要望書を8月8日付でまとめ、細川律夫厚生労働相らに提出した。
集中議論が必要だとしたテーマは
▽ドラッグ・ラグの解消に向けた議論
▽患者・家族が抱える就労問題、経済的負担の解消に向けた議論
▽科学的根拠に基づくがん検診の普及・啓発・精度管理(偽陽性・過剰診断などの不利益に関する救済を含む)に関する議論
▽サバイバーシップ概念の普及に関する議論(計画内、サバイバーシップの言葉を盛り込む)――。
薬事や就労問題を含めており、省を挙げた取り組みを促す内容。
がん対策推進基本計画は07年度~11年度からの5カ年計画。来年度からの次期計画実施に向け、計画見直しの議論が厚労省のがん対策推進協議会で行われている。しかし団体側によると、その見直しの議論を進めるでは、患者の求めるテーマが議論されることが少ないまま進んでいる。今後の議論にも強い懸念があるとして、議論すべきテーマをまとめ厚労相ほか、同協議会の門田守人会長、同省がん対策室の鈴木健彦室長あてに要望書を提出することになった。
癌(がん)治療の最新情報:http://blog.kougan.info/?eid=1171884
ドラッグ・ラグ問題:欧米で開発・発売された新薬が日本で使用が認められ発売されるまでには、
国内での治験実施と審査などのため、非常に長い時間がかかります。
欧米との発売時間差は約2.5年と言われており、この、日本と欧米との新薬承認の時間差、
あるいは、海外で新薬が先行販売され、国内では販売されていない状態のことを、「ドラッグ・ラグ」と呼びます。
卵巣がん体験者の会スマイリー:http://ransougan.e-ryouiku.net/index.html
患者・家族が抱える就労問題:がんになっても今まで通り働き続けたいと願っているのに、
降格や配置換え、退職を余議なくされる人は少なくありません。
そんな体験者の一人である桜井なおみさんらの「CSRプロジェクト」事務局が、
全国キャラバンのオープニングとして、2010年5月1日のメーデーに、東京で就労問題フォーラム
「がんと一緒に働こう!~治療を受け続けながら働くコツ~」を開催しました。
http://ganseisaku.net/impact/gan_coproduction/reports/20100604_report.html
キャンサーネットジャパン:ネット配信
http://www2.extide.mediasite.co.jp/mslive/Catalog/pages/catalog.aspx?cid=549b390d-b665-4e33-af07-862103eaf5e1
がんと一緒に働こう(がんナビ):http://medical.nikkeibp.co.jp/inc/all/cancernavi/series/csr/
2011年08月12日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん
「新しい光」でがん治療
新しいがん治療で注目を集めているのに粒子線治療がある。
これまでの放射線治療では困難だった、患部だけを狙い撃ちできるという特長がある
これだと手術のために入院することなく、患者の負担も少なくて済む。
現在、日本に8カ所の治療施設があり、粒子線に必要なレーザー光線が得られれば、
全国に展開できるという
このレーザー光線は「新しい光」と言われ、製作技術で日本は世界のトップレベルをキープしている。
がん治療など医療分野だけでなく、最近では金属の表面100万分の1ミリメートル(ナノスケール)を
観測するためのレーザー技術の応用も目を見張るものがある
先日、兵庫県の理化学研究所で開発、公開された世界最短波長のX線レーザー発振装置
「SACLA(サクラ)」もその産物だ。
全長約700メートルの細長い構造で出口から強いレーザー光線が発射される
「21世紀の科学技術、想像できないような新産業を支える基盤にしたい」と石川哲也同研究所センター長。
原子レベルの超高速運動の観察やたんぱく質、細胞の解析もできる。
スーパーコンピューター「京」との連携も発表された
原子関連技術は今日、原子力発電によるエネルギー供給という面だけがクローズアップされ議論されているが、
実は生活環境の細部にまで入り込み生かされている。
総合的な技術としての原子力の姿を冷静に見詰め、管理していく必要がある。
世界日報:http://www.worldtimes.co.jp/
「夢の光」をついに実現
-X線自由電子レーザー施設 SACLA (サクラ)がX線レーザーの発振に成功―
http://www.riken.jp/r-world/research/results/2011/110607/index.html
これまでの放射線治療では困難だった、患部だけを狙い撃ちできるという特長がある
これだと手術のために入院することなく、患者の負担も少なくて済む。
現在、日本に8カ所の治療施設があり、粒子線に必要なレーザー光線が得られれば、
全国に展開できるという
このレーザー光線は「新しい光」と言われ、製作技術で日本は世界のトップレベルをキープしている。
がん治療など医療分野だけでなく、最近では金属の表面100万分の1ミリメートル(ナノスケール)を
観測するためのレーザー技術の応用も目を見張るものがある
先日、兵庫県の理化学研究所で開発、公開された世界最短波長のX線レーザー発振装置
「SACLA(サクラ)」もその産物だ。
全長約700メートルの細長い構造で出口から強いレーザー光線が発射される
「21世紀の科学技術、想像できないような新産業を支える基盤にしたい」と石川哲也同研究所センター長。
原子レベルの超高速運動の観察やたんぱく質、細胞の解析もできる。
スーパーコンピューター「京」との連携も発表された
原子関連技術は今日、原子力発電によるエネルギー供給という面だけがクローズアップされ議論されているが、
実は生活環境の細部にまで入り込み生かされている。
総合的な技術としての原子力の姿を冷静に見詰め、管理していく必要がある。
世界日報:http://www.worldtimes.co.jp/
「夢の光」をついに実現
-X線自由電子レーザー施設 SACLA (サクラ)がX線レーザーの発振に成功―
http://www.riken.jp/r-world/research/results/2011/110607/index.html
2011年08月11日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん
がんと就労 働きたい:1 順調に出世していたのに
2011年5月13日
午前7時半に起床。ゴミ出しをして、天気がいいと家の周りを30分ほど歩く。自宅に戻り、新聞を読みながらパンと冷蔵庫の残り物で朝食を済ませる。
そこから1時間ほど、パソコンでハローワークの求人情報を検索する。月給15万円以上、職種は事務職……。希望に合う仕事が見つかっても、なかなか次の行動に移せない。
「今は気持ちがなえていて。すぐに仕事は見つかると思っていたんだけどね」。これまでに20社以上を受験し、落ちた。
千葉県に住む男性(54)は2006年2月、肺がんと診断され、手術を受けた。術後も抗がん剤治療を続けながら、仕事と闘病の両立を図ってきた。しかし1年半前、治療に専念するため、約30年間勤めた東証一部上場の会社を退職した。
妻(53)と、大学4年生の息子(21)の3人家族。失業保険も切れ、貯金を取り崩しながらの生活が続く。
大学を卒業後、九州の小倉を振り出しに全国各地の支店を回った。30代前半での支店長就任は、同期の間でも早い方だったという。
「自分で言うのも何だけど、部下の適性を見抜き、育てるのがうまかった。できの悪い社員がいると、『あいつの所に送れ』なんて言われたもんです」
朝8時過ぎには出社し、仕事が終わると取引先や後輩と飲みに行った。順調に出世を重ね、がんが見つかったときは、本社の地域統括部の副部長の役職にあった。
「このままいけば、役員の一歩手前ぐらいにはいけるかな」。そんなことを考えていた矢先、人間ドックで、肺に小さなかげが見つかった。
3日に1箱のペースでたばこを吸ってきたが、大病の経験はなかった。ただ今にして思えば、人間ドックの直前は風邪が1カ月間近く治らなかった。
半信半疑で会社近くのクリニックを受診すると、「東京都内の大学病院で精密検査を受けるように」と言われた。
大学病院でCTや肺の組織を調べた。検査結果を見て、年配の医師が申し訳なさそうに告げた。「左肺の上にがんがあります。手術で切りましょう」。肺がんの中で最も多い、腺がんだった。(岡崎明子)
http://www.asahi.com/health/ikiru/TKY201105130244.html
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
友達から『朝日新聞に、がんと就労ってテーマの連載をしているよ』って教えてもらいました
昨年くらいからHOPEプロジェクトの桜井さんの活動からでしょうか『がんと就労』について
色々な場所で、色々な取組みがされているのを見かけます
そのせいもあったんでしょうね
先日の「心理カウンセラー」の方の対応が、なんか今の社会とちぐはぐな気がしました
でも、実際はこういうものなんじゃないのかな?とも思います
そして一般の人は、今でもやっぱり、がん=死。なんですよね
私はがんにならない。とか検査を受けたって死ぬときは死ぬんだから受けない。などなど
色んな事をいう人がいます
がんになって、気がついたら末期ですぐに死ぬ。と思っている人がいかに多いかということです
自分はそれでもいいと思います。
でも、残された家族はそれを受け入れられるんでしょうか?
治せるなら治してあげたいと望むのが家族だと思います
そして、そういう人は自分が手術して後遺症を抱えたり、ストーマにしたり・・・
なんて想像力が全くないんですよね
でも果たしてそうでしょうか?
自分がどんながんになるかは決まっていません
がんだけでなく、他の病気になるかもしれません
その為の検査でもあるんじゃないでしょうか?
その時に果たしてどうやって仕事をしていくのでしょうか?
がん患者だから特別なのではないと思います
病気を体験した人は、みんな同じです
でも、今は患者数がとても多い。そして、老いも若きも隔てなくなるのががんなんです
がん体験者が受け入れられる社会は、どんな病気の患者であっても受け入れていけるのではないでしょうか?
その為にも、患者に関わる仕事をしている人にはきちんとした社会性を持っていて欲しいと思います
私のこの講師の方に対する対応は『あなたの事はこれからも見ていきます』という発言はパワーハラスメントとして受け取ったという事と『がんと一緒に働こう』の本を読んでもらうつもりです
何がどうパワーハラスメントであったかを理解してもらうには、がん体験者の置かれている社会を知ってもらうことだと思います
午前7時半に起床。ゴミ出しをして、天気がいいと家の周りを30分ほど歩く。自宅に戻り、新聞を読みながらパンと冷蔵庫の残り物で朝食を済ませる。
そこから1時間ほど、パソコンでハローワークの求人情報を検索する。月給15万円以上、職種は事務職……。希望に合う仕事が見つかっても、なかなか次の行動に移せない。
「今は気持ちがなえていて。すぐに仕事は見つかると思っていたんだけどね」。これまでに20社以上を受験し、落ちた。
千葉県に住む男性(54)は2006年2月、肺がんと診断され、手術を受けた。術後も抗がん剤治療を続けながら、仕事と闘病の両立を図ってきた。しかし1年半前、治療に専念するため、約30年間勤めた東証一部上場の会社を退職した。
妻(53)と、大学4年生の息子(21)の3人家族。失業保険も切れ、貯金を取り崩しながらの生活が続く。
大学を卒業後、九州の小倉を振り出しに全国各地の支店を回った。30代前半での支店長就任は、同期の間でも早い方だったという。
「自分で言うのも何だけど、部下の適性を見抜き、育てるのがうまかった。できの悪い社員がいると、『あいつの所に送れ』なんて言われたもんです」
朝8時過ぎには出社し、仕事が終わると取引先や後輩と飲みに行った。順調に出世を重ね、がんが見つかったときは、本社の地域統括部の副部長の役職にあった。
「このままいけば、役員の一歩手前ぐらいにはいけるかな」。そんなことを考えていた矢先、人間ドックで、肺に小さなかげが見つかった。
3日に1箱のペースでたばこを吸ってきたが、大病の経験はなかった。ただ今にして思えば、人間ドックの直前は風邪が1カ月間近く治らなかった。
半信半疑で会社近くのクリニックを受診すると、「東京都内の大学病院で精密検査を受けるように」と言われた。
大学病院でCTや肺の組織を調べた。検査結果を見て、年配の医師が申し訳なさそうに告げた。「左肺の上にがんがあります。手術で切りましょう」。肺がんの中で最も多い、腺がんだった。(岡崎明子)
http://www.asahi.com/health/ikiru/TKY201105130244.html
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
友達から『朝日新聞に、がんと就労ってテーマの連載をしているよ』って教えてもらいました
昨年くらいからHOPEプロジェクトの桜井さんの活動からでしょうか『がんと就労』について
色々な場所で、色々な取組みがされているのを見かけます
そのせいもあったんでしょうね
先日の「心理カウンセラー」の方の対応が、なんか今の社会とちぐはぐな気がしました
でも、実際はこういうものなんじゃないのかな?とも思います
そして一般の人は、今でもやっぱり、がん=死。なんですよね
私はがんにならない。とか検査を受けたって死ぬときは死ぬんだから受けない。などなど
色んな事をいう人がいます
がんになって、気がついたら末期ですぐに死ぬ。と思っている人がいかに多いかということです
自分はそれでもいいと思います。
でも、残された家族はそれを受け入れられるんでしょうか?
治せるなら治してあげたいと望むのが家族だと思います
そして、そういう人は自分が手術して後遺症を抱えたり、ストーマにしたり・・・
なんて想像力が全くないんですよね
でも果たしてそうでしょうか?
自分がどんながんになるかは決まっていません
がんだけでなく、他の病気になるかもしれません
その為の検査でもあるんじゃないでしょうか?
その時に果たしてどうやって仕事をしていくのでしょうか?
がん患者だから特別なのではないと思います
病気を体験した人は、みんな同じです
でも、今は患者数がとても多い。そして、老いも若きも隔てなくなるのががんなんです
がん体験者が受け入れられる社会は、どんな病気の患者であっても受け入れていけるのではないでしょうか?
その為にも、患者に関わる仕事をしている人にはきちんとした社会性を持っていて欲しいと思います
私のこの講師の方に対する対応は『あなたの事はこれからも見ていきます』という発言はパワーハラスメントとして受け取ったという事と『がんと一緒に働こう』の本を読んでもらうつもりです
何がどうパワーハラスメントであったかを理解してもらうには、がん体験者の置かれている社会を知ってもらうことだと思います
2011年06月06日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん
運動すると乳がんリスクが低下- 国立がん研究センター
がんが発病した後でさえ、がんの増殖抑制や転移・再発予防に運動が効果的であることは多くの研究で明らかになっています。
適度な運動は、血流をよくする一方で体温を上昇させることが免疫力の向上を促すためにがんに効果があるというのが、そのメカニズムです。
2011年5月09日 キャリアブレイン
国立がん研究センターはこのほど、「積極的に運動する女性は、しない人に比べて乳がんになりにくい」とする研究結果を発表した。
研究は1990年と93年に岩手、秋田、茨城、新潟、長野、大阪、高知、長崎、沖縄各府県の10保健所地域に住んでいた40-69歳の女性約5万人について、2007年まで追跡した多目的コホート研究。研究開始時と5年後のアンケートから、仕事のほかに余暇運動を行う機会が「月3日以内」「週1-2日」「週3日以上」の3グループに分け、乳がんの発生率との関連を調べた。平均約14.5年間の追跡期間中、対象者約5万人のうち652人が乳がんになった。
調査結果によると、「週3日以上」の余暇運動を行うグループは、「月3日以内」のグループに比べ、乳がんリスクが約3割低下することが分かった。さらに、肥満度を示すBMI(体格指数)25以上と25未満に分けて分析すると、BMI25以上のグループでは、「週1日以上」の余暇運動を行う群の乳がんリスクが「月3日以内」のグループより4割近く低くなることが分かった。 一方、仕事や家事などを含む1日当たりの「総身体活動量」には、乳がんリスクとの関連は見られなかった。ただし、閉経後の女性では、「エストロゲン受容体」と「プロゲステロン受容体」が陽性の乳がんについて、余暇運動と総身体活動量共にリスク低下との関連が認められた。
運動量と乳がんリスクの関連は海外の調査結果で既に報告されており、研究班では「日本人でも、余暇運動に積極的に参加する人は、しない人に比べ、乳がんになりにくいことを裏付けた」と指摘。「特に、閉経後や太り気味の女性は、週1回でも余暇に運動を取り入れることが乳がん予防につながる」とし、生活習慣の改善を訴えている。
癌治療の最新情報:http://blog.kougan.info/
適度な運動は、血流をよくする一方で体温を上昇させることが免疫力の向上を促すためにがんに効果があるというのが、そのメカニズムです。
2011年5月09日 キャリアブレイン
国立がん研究センターはこのほど、「積極的に運動する女性は、しない人に比べて乳がんになりにくい」とする研究結果を発表した。
研究は1990年と93年に岩手、秋田、茨城、新潟、長野、大阪、高知、長崎、沖縄各府県の10保健所地域に住んでいた40-69歳の女性約5万人について、2007年まで追跡した多目的コホート研究。研究開始時と5年後のアンケートから、仕事のほかに余暇運動を行う機会が「月3日以内」「週1-2日」「週3日以上」の3グループに分け、乳がんの発生率との関連を調べた。平均約14.5年間の追跡期間中、対象者約5万人のうち652人が乳がんになった。
調査結果によると、「週3日以上」の余暇運動を行うグループは、「月3日以内」のグループに比べ、乳がんリスクが約3割低下することが分かった。さらに、肥満度を示すBMI(体格指数)25以上と25未満に分けて分析すると、BMI25以上のグループでは、「週1日以上」の余暇運動を行う群の乳がんリスクが「月3日以内」のグループより4割近く低くなることが分かった。 一方、仕事や家事などを含む1日当たりの「総身体活動量」には、乳がんリスクとの関連は見られなかった。ただし、閉経後の女性では、「エストロゲン受容体」と「プロゲステロン受容体」が陽性の乳がんについて、余暇運動と総身体活動量共にリスク低下との関連が認められた。
運動量と乳がんリスクの関連は海外の調査結果で既に報告されており、研究班では「日本人でも、余暇運動に積極的に参加する人は、しない人に比べ、乳がんになりにくいことを裏付けた」と指摘。「特に、閉経後や太り気味の女性は、週1回でも余暇に運動を取り入れることが乳がん予防につながる」とし、生活習慣の改善を訴えている。
癌治療の最新情報:http://blog.kougan.info/
2011年05月13日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん
日経実力病院調査
2011年3月10日の日経新聞の夕刊の記事です

少し前の記事になりますが、よく本屋さんで見かける『いい病院』に似ていますが
こちらは手術の症例数(診療実績)だけではなく
①がん診療連携拠点病院加算-国から拠点病院の指定を受けている病院
②緩和ケア診療加算-常勤や看護師などの専従チームがあるなど
③緩和ケア病棟入院料-緩和ケアを行う病棟があるなど
上記の構造も追加されています
このデータは、2009年7~12月で「手術あり」が70例以上)と少し古いデータです
東京では武蔵野日赤病院が現在は、がん拠点病院ですが、この評価には含まれていません
最高点数は78点で関東では杏林大学病院、中部・東海地区で聖隷浜松病院が評価されていました

本屋さんでも現在は、症例数からわかる病院の実力などといったものが手に入ります
ただ、これはあくまでも調査した地点の数字であるという事です
また、いい病院という評価がついているからといって自分にあった治療ができるとは限りません
日帰りで放射線を受ける場合などは、通院しやすさも考えたほうがいいと思います
この記事に大きな見出しで書かれている「頸がん」、早期は子宮温存ですが
全ての患者さんがそうかはわかりません
またⅠ期と言われたから「早期がん=温存」とは限りません
患者さんが1人1人違うように治療方針もみんな違います
また、病院というか医師との相性もあるように思います
いい評価の病院の医師がいい先生かどうかはわかりません
これはあくまでも病院という設備や症例数等によって導かれた点数です
私が通院している病院はかなり低いです
それは、この地点では専門知識をもった看護師がいなかったからです
例えば抗がん剤専門の看護師さんやリンパマッサージの有資格者などは2009~10年からです
また最新の機器なども2009年度から導入されています
今の病院は動きがとても早いです
現在は国立病院でも治療方法などを公表しています
ここで記事として書かれている治療を全ての病院で受けれるかどうかは不明です
自分が受けたい治療と通いやすい病院などを考えて自分にあった病院を選んでください

少し前の記事になりますが、よく本屋さんで見かける『いい病院』に似ていますが
こちらは手術の症例数(診療実績)だけではなく
①がん診療連携拠点病院加算-国から拠点病院の指定を受けている病院
②緩和ケア診療加算-常勤や看護師などの専従チームがあるなど
③緩和ケア病棟入院料-緩和ケアを行う病棟があるなど
上記の構造も追加されています
このデータは、2009年7~12月で「手術あり」が70例以上)と少し古いデータです
東京では武蔵野日赤病院が現在は、がん拠点病院ですが、この評価には含まれていません
最高点数は78点で関東では杏林大学病院、中部・東海地区で聖隷浜松病院が評価されていました

本屋さんでも現在は、症例数からわかる病院の実力などといったものが手に入ります
ただ、これはあくまでも調査した地点の数字であるという事です
また、いい病院という評価がついているからといって自分にあった治療ができるとは限りません
日帰りで放射線を受ける場合などは、通院しやすさも考えたほうがいいと思います
この記事に大きな見出しで書かれている「頸がん」、早期は子宮温存ですが
全ての患者さんがそうかはわかりません
またⅠ期と言われたから「早期がん=温存」とは限りません
患者さんが1人1人違うように治療方針もみんな違います
また、病院というか医師との相性もあるように思います
いい評価の病院の医師がいい先生かどうかはわかりません
これはあくまでも病院という設備や症例数等によって導かれた点数です
私が通院している病院はかなり低いです
それは、この地点では専門知識をもった看護師がいなかったからです
例えば抗がん剤専門の看護師さんやリンパマッサージの有資格者などは2009~10年からです
また最新の機器なども2009年度から導入されています
今の病院は動きがとても早いです
現在は国立病院でも治療方法などを公表しています
ここで記事として書かれている治療を全ての病院で受けれるかどうかは不明です
自分が受けたい治療と通いやすい病院などを考えて自分にあった病院を選んでください
2011年05月09日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん
ステージIでも進行がん!?手術か化学放射線か──食道がん
ステージIでも進行がん!?
手術か化学放射線か──食道がん
監修 井垣弘康(国立がん研究センター中央病院食道外科外来・病棟医長)
昨年末、歌手の桑田佳祐さんが食道がんから見事に復帰した姿を目の当たりにしたPさん、56歳。同じ病気で闘病中だけに、自らを重ねずにはいられなかった──。
食道がんは膵臓がんと並び、早期発見が難しいがんの一つ。自覚症状もないので、早期発見のほとんどは「たまたま」受けた内視鏡検査によるものだ。しかも、食道がんは患者数が少なく医師の診断経験が限られるため、飛び込みの内視鏡検査では見過ごされることもある。内視鏡検査を受ける機会があれば、日本人の食道がんに多い「扁平上皮がん」の検出感度に優れたヨード染色法で検査をしてもらうとよいだろう。
ちなみに、桑田さんはラジオ番組での本人談によると、毎年きちんと受けていた定期検診で「食道の荒れ」が見つかっていたことに加え、数ヵ月後に「ゲップが出るようになった」ため主治医が早めの検査を勧めたことが発見につながったようだ。
食道は、のどと胃をつなぐパイプの役割を果たす臓器である。壁の厚みが4ミリメートル程度と薄く、血管やリンパ管が集中しているため、リンパ節転移や遠くの臓器へ転移を起こしやすい。このため、食道がんは他のがんなら早期と見なされるステージIでも「進行がん」に分類される。この段階での治療の選択肢は手術か、抗がん剤と放射線治療を並行して行う化学放射線療法だ。
つい10年ほど前まで食道がんの手術は首、胸、腹を切り開き、病変と周辺のリンパ節を8時間以上かけて除去する大がかりなものだった。体力の消耗も激しく、施設によっては術後の合併症で死亡する患者が2割にも上った。
しかし最近は、内視鏡の一種である胸腔鏡や腹腔鏡を使用し、キズや出血を最小限にとどめる手術が一部で行われるようになった。開胸、開腹しないぶん、術後合併症の発生も少なく回復も早い。難点は執刀医の経験と手術チームの技量に治療成績が大きく左右されること。治療施設は慎重に選ぼう。
もう一つの選択肢である化学放射線療法は、手術に匹敵する治療成績が期待できるほか、食道の機能を保持できることが最大の利点だ。再発しても手術という選択肢が残されていることも大きい。食道がんで治療選択に迫られたときは、両者を比較するためにセカンドオピニオンを積極的に活用しよう。
さて、食道がんのリスク要因は酒とタバコ。世界保健機関(WHO)によれば、少量の酒でもすぐに赤くなる人は、赤くならない人に比べ12倍も食道がんを発症しやすいので要注意である。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
食道がんは、以前は術後も大変ながんの1つだったと聞いた事があります
ただ、現在はかなり予後もよくなっていっているようです
私が働いていた時にも食道がんの方がいました
抗がん剤治療もされていましたが、術後1年半で職場復帰をされていて
手術しても、かなりのヘビースモーカーでした
私が告知された時、それまで1度も話をした事がなかったのに
家族の事や病院の事、転院した事など、色々な話をしてくれました
その方も言われていましたが、以前は食道がんは見つけにくいがんの1つだったそうです
日本人は胃がんが多く、どうしても胃を重点的に考えてしまうので、実は食道を見逃してしまうそうです
ただ、現在はビデオを利用して見逃しのないようにと注意している病院もあるそうです
そのためには自分自身が『どこがどのように違和感があるか』というのを伝えることだと思います
こちらは食道がんのチェックリストになります:

http://diamond.jp/articles/-/12110?page=2
手術か化学放射線か──食道がん
監修 井垣弘康(国立がん研究センター中央病院食道外科外来・病棟医長)
昨年末、歌手の桑田佳祐さんが食道がんから見事に復帰した姿を目の当たりにしたPさん、56歳。同じ病気で闘病中だけに、自らを重ねずにはいられなかった──。
食道がんは膵臓がんと並び、早期発見が難しいがんの一つ。自覚症状もないので、早期発見のほとんどは「たまたま」受けた内視鏡検査によるものだ。しかも、食道がんは患者数が少なく医師の診断経験が限られるため、飛び込みの内視鏡検査では見過ごされることもある。内視鏡検査を受ける機会があれば、日本人の食道がんに多い「扁平上皮がん」の検出感度に優れたヨード染色法で検査をしてもらうとよいだろう。
ちなみに、桑田さんはラジオ番組での本人談によると、毎年きちんと受けていた定期検診で「食道の荒れ」が見つかっていたことに加え、数ヵ月後に「ゲップが出るようになった」ため主治医が早めの検査を勧めたことが発見につながったようだ。
食道は、のどと胃をつなぐパイプの役割を果たす臓器である。壁の厚みが4ミリメートル程度と薄く、血管やリンパ管が集中しているため、リンパ節転移や遠くの臓器へ転移を起こしやすい。このため、食道がんは他のがんなら早期と見なされるステージIでも「進行がん」に分類される。この段階での治療の選択肢は手術か、抗がん剤と放射線治療を並行して行う化学放射線療法だ。
つい10年ほど前まで食道がんの手術は首、胸、腹を切り開き、病変と周辺のリンパ節を8時間以上かけて除去する大がかりなものだった。体力の消耗も激しく、施設によっては術後の合併症で死亡する患者が2割にも上った。
しかし最近は、内視鏡の一種である胸腔鏡や腹腔鏡を使用し、キズや出血を最小限にとどめる手術が一部で行われるようになった。開胸、開腹しないぶん、術後合併症の発生も少なく回復も早い。難点は執刀医の経験と手術チームの技量に治療成績が大きく左右されること。治療施設は慎重に選ぼう。
もう一つの選択肢である化学放射線療法は、手術に匹敵する治療成績が期待できるほか、食道の機能を保持できることが最大の利点だ。再発しても手術という選択肢が残されていることも大きい。食道がんで治療選択に迫られたときは、両者を比較するためにセカンドオピニオンを積極的に活用しよう。
さて、食道がんのリスク要因は酒とタバコ。世界保健機関(WHO)によれば、少量の酒でもすぐに赤くなる人は、赤くならない人に比べ12倍も食道がんを発症しやすいので要注意である。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
食道がんは、以前は術後も大変ながんの1つだったと聞いた事があります
ただ、現在はかなり予後もよくなっていっているようです
私が働いていた時にも食道がんの方がいました
抗がん剤治療もされていましたが、術後1年半で職場復帰をされていて
手術しても、かなりのヘビースモーカーでした
私が告知された時、それまで1度も話をした事がなかったのに
家族の事や病院の事、転院した事など、色々な話をしてくれました
その方も言われていましたが、以前は食道がんは見つけにくいがんの1つだったそうです
日本人は胃がんが多く、どうしても胃を重点的に考えてしまうので、実は食道を見逃してしまうそうです
ただ、現在はビデオを利用して見逃しのないようにと注意している病院もあるそうです
そのためには自分自身が『どこがどのように違和感があるか』というのを伝えることだと思います
こちらは食道がんのチェックリストになります:

http://diamond.jp/articles/-/12110?page=2
タグ :食道がん
2011年05月02日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん
乳がん診断に「新兵器」 高い発見能力の「PEM」
乳がん診断に「新兵器」 高い発見能力の「PEM」
2011年4月22日(金)08:00 (産経新聞)
米国で普及し始めた新しい乳がん検査法「陽電子放射乳房撮影(PEM)」をご存じだろうか。
乳房のがん細胞発見を目的に開発された検査方法で、通常の検診に使われているマンモグラフィーなど
より、明確に患部の大きさや位置を捉えると期待が集まっている。(日野稚子)
■「全身病」と考える
「30~64歳女性のがん死亡原因第1位は乳がん。
増加傾向は止められない状況だからこそ、自分の命を守るため検診を考えて」と話すのは、
聖マリアンナ医科大学ブレスト&イメージングセンター(ブレストセンター)の福田護院長だ。
「ピンクリボン運動」を推進するなど乳がん啓発活動を行う「NPO法人乳房健康研究会」の
創設メンバーで、乳がん治療の専門家だ。
乳がん治療は変わってきた。「昔のように乳房単独ではなく全身病と考える。がん細胞の性質に合わせ、患部切除前後で抗がん剤や女性ホルモンの投与、放射線照射などを行うし、乳房温存手術ができる場合もある」(福田院長)。乳がんは、乳腺にある「乳管」内側にできた非浸潤がんと、乳管から外に出た浸潤がんに大別する。浸潤がんは転移可能性が高いが、2センチ以下でリンパ節転移前の「早期がん」の段階で治療を始めれば再発率は低くなる。非浸潤がんは、しこりができるともかぎらない。
■痛みなく高精度
がん細胞を撮影する「陽電子放射断層撮影(PET)」検査は、がん細胞が正常細胞よりも多く取り込む放射性検査薬を体内に注入し、放射線発生部位を撮影する。このPET原理を応用し、乳房専用に開発されたのがPEMだ。
「PET検査は全身撮影で空間分解能が5ミリなので、乳がん細胞はぼんやりとしか撮れない。PEMでは、放射線検出器を胸に当てて撮像するので、明瞭かつ撮影範囲も広い画像になる」と解説するのは、日本初のPEM機器導入施設で、医療法人社団ゆうあい会「ゆうあいクリニック」(横浜市)の片山敦理事長。
乳房の画像診断はX線撮影の「マンモグラフィー」と「超音波診断装置(エコー)」が主流だ。マンモグラフィーは乳房を押し潰すため激痛を伴う場合が多い。乳腺組織と乳がんのしこり両方が白く写り、がん確定診断や若い女性では不向きな面もある。エコー検査は痛みはないが、石灰化病変は不得手という。「右乳房のがんが疑われ、細胞診や切開しての病理検査も陰性だった40代女性をPEMで調べたら、両側乳房にがんがあった。検査を何度受けても偽陽性と偽陰性を行き来する“検査難民”は多い」(片山理事長)
同クリニックでは5月から、一般からもPEM検査の予約を受け付ける。実際にPEM検査を受けてみた。
撮影は片側につき上下・左右2方向で約40分ほどだが、マンモグラフィーで感じる痛みがない分、気が楽だった。
同クリニックは聖マリアンナ医大、昭和大学などとPEM診断の臨床研究中で、がん患者をメーンに4月中旬までに撮影を20例行った。ブレストセンターの福田院長は「診断精度を検証中だが、非常に小さいサイズでの発見能力があるといえるだろう。非浸潤がんも見つかり驚いている。従来の画像診断では難しかったり、精密診断を要する事例では有効かもしれない」と話している。
http://news.goo.ne.jp/article/sankei/life/snk20110422093.html
今朝、田中好子さんが亡くなったニュースを見ました
まだ55歳という若さでした
私はピンクレディ世代ですが、キャンディーズはお姉さんアイドルって感じで好きでした
そんな方が亡くなるなんて・・・って思います
だんなさんと一緒に患者さんのためのサポート活動などをされていたのは知っていましたが
まさか自分自身も乳がんで闘病されていたとは・・・と思います
19年前といえば、今ほど病気に対する理解も得られていなかっただろうし
公表されていないのも、仕方がないことだと思います
自分もそんなに若くはないけれど、でも、若いほうの患者だとは思います
私の友人もほとんどが30代~40代で罹患しています
自分の体に少しでも違和感を持ったら、ぜひ病院に行ってください
2011年4月22日(金)08:00 (産経新聞)
米国で普及し始めた新しい乳がん検査法「陽電子放射乳房撮影(PEM)」をご存じだろうか。
乳房のがん細胞発見を目的に開発された検査方法で、通常の検診に使われているマンモグラフィーなど
より、明確に患部の大きさや位置を捉えると期待が集まっている。(日野稚子)
■「全身病」と考える
「30~64歳女性のがん死亡原因第1位は乳がん。
増加傾向は止められない状況だからこそ、自分の命を守るため検診を考えて」と話すのは、
聖マリアンナ医科大学ブレスト&イメージングセンター(ブレストセンター)の福田護院長だ。
「ピンクリボン運動」を推進するなど乳がん啓発活動を行う「NPO法人乳房健康研究会」の
創設メンバーで、乳がん治療の専門家だ。
乳がん治療は変わってきた。「昔のように乳房単独ではなく全身病と考える。がん細胞の性質に合わせ、患部切除前後で抗がん剤や女性ホルモンの投与、放射線照射などを行うし、乳房温存手術ができる場合もある」(福田院長)。乳がんは、乳腺にある「乳管」内側にできた非浸潤がんと、乳管から外に出た浸潤がんに大別する。浸潤がんは転移可能性が高いが、2センチ以下でリンパ節転移前の「早期がん」の段階で治療を始めれば再発率は低くなる。非浸潤がんは、しこりができるともかぎらない。
■痛みなく高精度
がん細胞を撮影する「陽電子放射断層撮影(PET)」検査は、がん細胞が正常細胞よりも多く取り込む放射性検査薬を体内に注入し、放射線発生部位を撮影する。このPET原理を応用し、乳房専用に開発されたのがPEMだ。
「PET検査は全身撮影で空間分解能が5ミリなので、乳がん細胞はぼんやりとしか撮れない。PEMでは、放射線検出器を胸に当てて撮像するので、明瞭かつ撮影範囲も広い画像になる」と解説するのは、日本初のPEM機器導入施設で、医療法人社団ゆうあい会「ゆうあいクリニック」(横浜市)の片山敦理事長。
乳房の画像診断はX線撮影の「マンモグラフィー」と「超音波診断装置(エコー)」が主流だ。マンモグラフィーは乳房を押し潰すため激痛を伴う場合が多い。乳腺組織と乳がんのしこり両方が白く写り、がん確定診断や若い女性では不向きな面もある。エコー検査は痛みはないが、石灰化病変は不得手という。「右乳房のがんが疑われ、細胞診や切開しての病理検査も陰性だった40代女性をPEMで調べたら、両側乳房にがんがあった。検査を何度受けても偽陽性と偽陰性を行き来する“検査難民”は多い」(片山理事長)
同クリニックでは5月から、一般からもPEM検査の予約を受け付ける。実際にPEM検査を受けてみた。
撮影は片側につき上下・左右2方向で約40分ほどだが、マンモグラフィーで感じる痛みがない分、気が楽だった。
同クリニックは聖マリアンナ医大、昭和大学などとPEM診断の臨床研究中で、がん患者をメーンに4月中旬までに撮影を20例行った。ブレストセンターの福田院長は「診断精度を検証中だが、非常に小さいサイズでの発見能力があるといえるだろう。非浸潤がんも見つかり驚いている。従来の画像診断では難しかったり、精密診断を要する事例では有効かもしれない」と話している。
http://news.goo.ne.jp/article/sankei/life/snk20110422093.html
今朝、田中好子さんが亡くなったニュースを見ました
まだ55歳という若さでした
私はピンクレディ世代ですが、キャンディーズはお姉さんアイドルって感じで好きでした
そんな方が亡くなるなんて・・・って思います
だんなさんと一緒に患者さんのためのサポート活動などをされていたのは知っていましたが
まさか自分自身も乳がんで闘病されていたとは・・・と思います
19年前といえば、今ほど病気に対する理解も得られていなかっただろうし
公表されていないのも、仕方がないことだと思います
自分もそんなに若くはないけれど、でも、若いほうの患者だとは思います
私の友人もほとんどが30代~40代で罹患しています
自分の体に少しでも違和感を持ったら、ぜひ病院に行ってください
2011年04月22日 Posted by すもも at 16:00 │Comments(2) │ニュース・・・がん
劇的な「自転車人生」に幕~アームストロング

2011年3月8日(火)06:03
自転車ロードレースの名選手として鳴らしたランス・アームストロング(39)=米国=が引退を表明し、劇的な競技人生に幕を下ろした。一説には生存率数パーセントとも言われる精巣腫瘍を克服した後、前人未到のツール・ド・フランス7連覇を果たした「超人」。今後は、がん撲滅を目指す活動も積極的に行う。
トライアスロンから自転車のロードに転向し、トップ選手へと歩んでいったが、25歳で悪性の精巣腫瘍を発病。化学療法の苦しみは想像を絶したという。リハビリと過酷な練習を積んで乗り越え、精神的にも成長した。
ロードレースは欧州が主戦場。米国人で、一時は生死をさまよったアームストロングが歴史と伝統を誇る大会で強さを見せつけたことから、ドーピング(禁止薬物使用)が疑われるようになる。その疑惑とも闘った。
2005年にツール・ド・フランス7連覇を達成した後、いったん現役を退いた。復帰した09年の同レースでは総合3位。最後の出場となった今年1月のオーストラリアでの大会は67位だった。
AFP電によると、国際自転車競技連合(UCI)のマッケイド会長は「彼はロードレースの世界的な象徴だった」と賛辞を送った。競技と闘病で培った「不屈の精神」が、人々を勇気づけた。アームストロングは「これからは、がんに苦しむ人たちを救うために設立した団体の運営に多くの時間を費やしたい」と話している。
[時事通信社]
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「ただマイヨ・ジョーヌのためでなく」
私は退院してしばらくしてから、この本を読みました
今、自分がつらいと感じている事がここに書かれている・・・と感じました
現役に復帰するために自転車を走らせている時に「なぜ自分はこんな事をしなきゃいけないんだ」っ
「こんな大変な病気になったんだから、走らなくてもいいじゃないか」って思う
でも、やっぱりその場所にもう1度戻りたいと思い走り始めます
そして、色々なことを乗り越えてツール・ド・フランス7連覇をします
患者が感じる気持ちの変化をとてもわかりやすく書いていて、共感しました
この記事を読んで、本当に引退してしまったんだって思った
ご苦労様でした。
そして、これからも頑張ってくださいね
2011年03月09日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん
幹細胞で乳房再生治験へ、九大が春に研究組織
乳がんで乳房を切除した患者のため、九州大や大阪大などは本人の幹細胞を使って乳房を再生させる治験に乗り出す方針を決めた。2011年春に複数の国立大や医療機関などによる研究組織を設立し、12年3月までに治験を開始する計画。より自然な乳房を回復する取り組みで、健康保険が適用される医療として定着を目指す考えだ。
幹細胞を使う乳房再建は、これまで九州大と九州中央病院(福岡市)で臨床研究を行ったほか、横浜市の民間クリニックなど一部で実施されているが、治験としては初めてとなる。
現在は、シリコーンや本人の脂肪の移植が主流。しかしシリコーンには感染症の危険性、脂肪は体内に吸収され効果が持続しないなどの欠点がある。また健康保険も適用されない。
一方、幹細胞は体を作る大もとの細胞で、特定の細胞に変化したり自分をコピーしたりできる。九州大などの再建法は、本人の腹部から200~400ミリ・リットル前後の脂肪を採取。専用の分離器で幹細胞を多く含む細胞群を取り出し、乳房を失った部分の筋肉と皮膚の間に2~3ccずつ30~40回注入、生着すると修復される。本人の幹細胞なので拒絶反応が起きにくく、より自然な形になるという。
九州大などは10年12月に初会合を開き、基本方針を確認した。名古屋大、金沢大、鳥取大、関東の民間病院など10施設前後が参加する見通し。手術を2年間行い、術後の評価、データ解析、健康保険適用の前提となる薬事法に基づく国への承認申請に各1年の計5年をめどにしている。今後、効果や安全性の評価基準などについて協議する。
計画を統括する九州大病院高度先端医療センターの中西洋一センター長(57)(臨床試験)は「手術が普及すれば患者が自信を持って社会とかかわることができる。幹細胞による再生医療の発展にとっても大きな突破口になる」と話している。
(2011年1月1日 読売新聞)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
乳がんのがん友さんがシリコーンを使って乳房再建手術を受けました
彼女はとても色々な事を考えて、シリコーンという選択をしていました
ただ、シリコーンは高額な医療費がかかります、でも、自家組織法は傷痕が残ったり医師の高度な技術が必要だったりします
どんな手術にも「いい部分、難しい部分」があります
自分にとって最適な方法を考えるというのは必要な事だと思います
自分とは違う、がん種の方の話を聞くと自分とは違う大変さがあるんだなってわかります
女性にとって「乳房」や「子宮」「卵巣」といった性にかかわるがんになるのはつらいです
以前、欧米では美容整形の部門で自分の幹細胞を使った脂肪を使って豊胸手術を行うというのをテレビで見ました
手術を受けていた女性が、自分ものを使って手術ができるのがいいと言われていました
いつか日本でも同じような手術ができるようになるのかなって思ってみていました
この手術は日本では治験です。
でも、これがいつかは日本の標準治療になるかもしれません
女である限り乳がんになる可能性があります(男性の乳がんのあります)
現在、乳がんの患者さんは大腸がんの患者を追い抜いてしまいそうな勢いで増えています
みんなが最適な医療が受けれるようになって欲しいです
幹細胞を使う乳房再建は、これまで九州大と九州中央病院(福岡市)で臨床研究を行ったほか、横浜市の民間クリニックなど一部で実施されているが、治験としては初めてとなる。
現在は、シリコーンや本人の脂肪の移植が主流。しかしシリコーンには感染症の危険性、脂肪は体内に吸収され効果が持続しないなどの欠点がある。また健康保険も適用されない。
一方、幹細胞は体を作る大もとの細胞で、特定の細胞に変化したり自分をコピーしたりできる。九州大などの再建法は、本人の腹部から200~400ミリ・リットル前後の脂肪を採取。専用の分離器で幹細胞を多く含む細胞群を取り出し、乳房を失った部分の筋肉と皮膚の間に2~3ccずつ30~40回注入、生着すると修復される。本人の幹細胞なので拒絶反応が起きにくく、より自然な形になるという。
九州大などは10年12月に初会合を開き、基本方針を確認した。名古屋大、金沢大、鳥取大、関東の民間病院など10施設前後が参加する見通し。手術を2年間行い、術後の評価、データ解析、健康保険適用の前提となる薬事法に基づく国への承認申請に各1年の計5年をめどにしている。今後、効果や安全性の評価基準などについて協議する。
計画を統括する九州大病院高度先端医療センターの中西洋一センター長(57)(臨床試験)は「手術が普及すれば患者が自信を持って社会とかかわることができる。幹細胞による再生医療の発展にとっても大きな突破口になる」と話している。
(2011年1月1日 読売新聞)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
乳がんのがん友さんがシリコーンを使って乳房再建手術を受けました
彼女はとても色々な事を考えて、シリコーンという選択をしていました
ただ、シリコーンは高額な医療費がかかります、でも、自家組織法は傷痕が残ったり医師の高度な技術が必要だったりします
どんな手術にも「いい部分、難しい部分」があります
自分にとって最適な方法を考えるというのは必要な事だと思います
自分とは違う、がん種の方の話を聞くと自分とは違う大変さがあるんだなってわかります
女性にとって「乳房」や「子宮」「卵巣」といった性にかかわるがんになるのはつらいです
以前、欧米では美容整形の部門で自分の幹細胞を使った脂肪を使って豊胸手術を行うというのをテレビで見ました
手術を受けていた女性が、自分ものを使って手術ができるのがいいと言われていました
いつか日本でも同じような手術ができるようになるのかなって思ってみていました
この手術は日本では治験です。
でも、これがいつかは日本の標準治療になるかもしれません
女である限り乳がんになる可能性があります(男性の乳がんのあります)
現在、乳がんの患者さんは大腸がんの患者を追い抜いてしまいそうな勢いで増えています
みんなが最適な医療が受けれるようになって欲しいです
2011年03月03日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん
最後まで闘病の医師は19%
がん、最後まで闘病 患者81%、医師は19% 東京大研究グループ
がん患者や医師らを対象にした死生観に関するアンケートで、望ましい死を迎えるために、がん患者の81%は「最後まで病気と闘うこと」が重要と回答したが、医師は19%だったとの結果を、東京大の研究グループが14日、発表した。
看護師も30%にとどまり、医療側と患者側の意識の違いが浮き彫りになった。
がん患者はどのように死を迎えたいと望んでいるかを探り、終末期医療の在り方に役立てる狙いで調査。
東大病院の放射線科外来に受診中のがん患者と同病院でがん診療に携わる医師、看護師ら計1138人が回答した。
「やるだけの治療はしたと思えること」が重要という回答も患者の92%に対し、医師51%、看護師57%と、大きなギャップがあった。
一方「体に苦痛を感じないこと」「家族と一緒に過ごすこと」などは患者も医師も大半が重要とし、差はなかった。
調査した宮下光令講師は「医療従事者の回答は、現実や実現可能性を反映していると思えるが、自らの価値観と患者らの価値観が必ずしも一致しないことを自覚すべきだ」と話している。
2009年1月14日 日本経済新聞
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
>調査した宮下光令講師は「医療従事者の回答は、現実や実現可能性を反映していると思えるが、自らの価値観と患者らの価値観が必ずしも一致しないことを自覚すべきだ」と話している。
私が入院していた病院で婦長さんと話をしていた時に、同じ事を話したことがあります
患者さんは、最後の最後まで抗がん剤を使うなりして戦いたいと思っている
でも、今の医療現場ではそれすら叶えられない・・・
治療を受けたくても受けれない「がん難民」を生んでいるのも、実は医療現場です
確かに再発・転移した固形がんに関しては、色んな考え方があると思います
このアンケートの医師のように、治療を受けないというのも1つの選択肢だと思います
でも患者は、戦いたいと願ってもいいと思います
そして、医師や病院は患者にその場所を与えて欲しいと思います
患者が望む「理想の医療」とはそういうものなのではないでしょうか
がん患者や医師らを対象にした死生観に関するアンケートで、望ましい死を迎えるために、がん患者の81%は「最後まで病気と闘うこと」が重要と回答したが、医師は19%だったとの結果を、東京大の研究グループが14日、発表した。
看護師も30%にとどまり、医療側と患者側の意識の違いが浮き彫りになった。
がん患者はどのように死を迎えたいと望んでいるかを探り、終末期医療の在り方に役立てる狙いで調査。
東大病院の放射線科外来に受診中のがん患者と同病院でがん診療に携わる医師、看護師ら計1138人が回答した。
「やるだけの治療はしたと思えること」が重要という回答も患者の92%に対し、医師51%、看護師57%と、大きなギャップがあった。
一方「体に苦痛を感じないこと」「家族と一緒に過ごすこと」などは患者も医師も大半が重要とし、差はなかった。
調査した宮下光令講師は「医療従事者の回答は、現実や実現可能性を反映していると思えるが、自らの価値観と患者らの価値観が必ずしも一致しないことを自覚すべきだ」と話している。
2009年1月14日 日本経済新聞
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
>調査した宮下光令講師は「医療従事者の回答は、現実や実現可能性を反映していると思えるが、自らの価値観と患者らの価値観が必ずしも一致しないことを自覚すべきだ」と話している。
私が入院していた病院で婦長さんと話をしていた時に、同じ事を話したことがあります
患者さんは、最後の最後まで抗がん剤を使うなりして戦いたいと思っている
でも、今の医療現場ではそれすら叶えられない・・・
治療を受けたくても受けれない「がん難民」を生んでいるのも、実は医療現場です
確かに再発・転移した固形がんに関しては、色んな考え方があると思います
このアンケートの医師のように、治療を受けないというのも1つの選択肢だと思います
でも患者は、戦いたいと願ってもいいと思います
そして、医師や病院は患者にその場所を与えて欲しいと思います
患者が望む「理想の医療」とはそういうものなのではないでしょうか
2011年02月28日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん
所得低いとがんの死亡リスク高まる-厚労省研究班調査
所得低いとがんの死亡リスク高まる-厚労省研究班調査
厚生労働省の研究班(主任研究者=近藤克則・日本福祉大教授)はこのほど、所得が低いほど悪性新生物(がん)による死亡リスクが高まるとする調査結果を発表した。年間所得で約200万円の差があると、がんによる死亡リスクが約2倍になるとしている。
調査は、愛知県と高知県の高齢者4万372人を対象に2003年から04年にかけて行った調査の回答者2万1236人のうち、要介護認定を受けておらず、がんなどの治療中でもない1万5025人について、最長4年の追跡調査を行った。
調査結果によると、男性では所得「400万円以上」の人に対し、「200万円未満」の人でがんによる死亡のリスクが1.90倍であることが分かった。女性については、「経済的影響を受けづらく、生活習慣も乱れづらい」(研究班)ため、所得格差によるがんの死亡リスクの違いはなかった。飲酒や喫煙の状況を考慮した分析でも、同様の関連が認められたとしている。
研究班は調査結果について、「がんによる死亡が低所得の人ほど多い健康格差があることを示した国内初の研究」としている。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
>がんによる死亡が低所得の人ほど多い健康格差がある
これを読んで「こんなの当たり前でしょ」と思ったのは、がん体験者なのかも知れません
そして、年齢に関わらず低所得者、もしくは正社員ではない人間にとっては調べるまでもないでしょって言いたくなりました
私自身もそうでしたが、年齢が若く、そして正社員ではなかったものにとって
「がん」という病気は「人がなるもの」であって「自分がなるもの」ではありませんでした
健康だけがとりえ。と思っていた人が、いきなり「告知」される事も珍しくありません
また保険の事もあります
この病気になって保険の話をすると沢山の方が保険に入っていませんでした
私は郵便局の簡易保険に入っていましたが、がん保険の話をした時に「若いから」とやめました
また自営業をしている人などは、保険よりも今のお金。という事も・・・
子供の養育費などにお金がかかるから、それが終わったらかけるなんて話をありました
がん保険は掛け捨てが多く、年間何万円かであっても掛け捨てにするのは勿体ないなって・・・
がんの種類によっては手術後に追加治療を受けたり(放射線治療・抗がん剤)
ホルモンに由来するがんでは、ホルモン療法を受けたりします
薬代として、月1万5000円ほどかかります
また、白血病などではずっと高額の薬を飲み続けなくてはいけない方もいます
再発を繰り返すがんでは、何度も抗がん剤を受けなくてはいけない
1回何万円もする抗がん剤を受けなくてはいけない
それを受け続ける事ができない人は、治療をやめるしかない
また、高齢で一人暮らしの方などは「治療を受けても。。。」と言われる人もいます
独身の方に「もし、がんになったらどうするの?」って聞いたら
つらい手術や放射線・抗がん剤を受けるよりは
ほっておいて死ぬのを待つほうがいいと言われた事もあります
受けれる治療があったり、抗がん剤があっても高額なために受けないで死を待つ事を
「静かなる自殺」と呼ばれています
日本にはほとんどの人が治療を受けれる健康保険があります
それでも、手術や抗がん剤や放射線治療には高額な金額がかかります
北欧では高額ながん治療はただで受けれる国もあるそうです
そこまでしてくれとまでは言えないと思います
でも、できれば高額な治療費を払わなくても受けれるような仕組みを作って欲しいし
また高額な治療を受けれるようになって欲しいものです
そして、派遣であっても治療を受けている間くらい休めるような環境が欲しいと思います
厚生労働省の研究班(主任研究者=近藤克則・日本福祉大教授)はこのほど、所得が低いほど悪性新生物(がん)による死亡リスクが高まるとする調査結果を発表した。年間所得で約200万円の差があると、がんによる死亡リスクが約2倍になるとしている。
調査は、愛知県と高知県の高齢者4万372人を対象に2003年から04年にかけて行った調査の回答者2万1236人のうち、要介護認定を受けておらず、がんなどの治療中でもない1万5025人について、最長4年の追跡調査を行った。
調査結果によると、男性では所得「400万円以上」の人に対し、「200万円未満」の人でがんによる死亡のリスクが1.90倍であることが分かった。女性については、「経済的影響を受けづらく、生活習慣も乱れづらい」(研究班)ため、所得格差によるがんの死亡リスクの違いはなかった。飲酒や喫煙の状況を考慮した分析でも、同様の関連が認められたとしている。
研究班は調査結果について、「がんによる死亡が低所得の人ほど多い健康格差があることを示した国内初の研究」としている。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
>がんによる死亡が低所得の人ほど多い健康格差がある
これを読んで「こんなの当たり前でしょ」と思ったのは、がん体験者なのかも知れません
そして、年齢に関わらず低所得者、もしくは正社員ではない人間にとっては調べるまでもないでしょって言いたくなりました
私自身もそうでしたが、年齢が若く、そして正社員ではなかったものにとって
「がん」という病気は「人がなるもの」であって「自分がなるもの」ではありませんでした
健康だけがとりえ。と思っていた人が、いきなり「告知」される事も珍しくありません
また保険の事もあります
この病気になって保険の話をすると沢山の方が保険に入っていませんでした
私は郵便局の簡易保険に入っていましたが、がん保険の話をした時に「若いから」とやめました
また自営業をしている人などは、保険よりも今のお金。という事も・・・
子供の養育費などにお金がかかるから、それが終わったらかけるなんて話をありました
がん保険は掛け捨てが多く、年間何万円かであっても掛け捨てにするのは勿体ないなって・・・
がんの種類によっては手術後に追加治療を受けたり(放射線治療・抗がん剤)
ホルモンに由来するがんでは、ホルモン療法を受けたりします
薬代として、月1万5000円ほどかかります
また、白血病などではずっと高額の薬を飲み続けなくてはいけない方もいます
再発を繰り返すがんでは、何度も抗がん剤を受けなくてはいけない
1回何万円もする抗がん剤を受けなくてはいけない
それを受け続ける事ができない人は、治療をやめるしかない
また、高齢で一人暮らしの方などは「治療を受けても。。。」と言われる人もいます
独身の方に「もし、がんになったらどうするの?」って聞いたら
つらい手術や放射線・抗がん剤を受けるよりは
ほっておいて死ぬのを待つほうがいいと言われた事もあります
受けれる治療があったり、抗がん剤があっても高額なために受けないで死を待つ事を
「静かなる自殺」と呼ばれています
日本にはほとんどの人が治療を受けれる健康保険があります
それでも、手術や抗がん剤や放射線治療には高額な金額がかかります
北欧では高額ながん治療はただで受けれる国もあるそうです
そこまでしてくれとまでは言えないと思います
でも、できれば高額な治療費を払わなくても受けれるような仕組みを作って欲しいし
また高額な治療を受けれるようになって欲しいものです
そして、派遣であっても治療を受けている間くらい休めるような環境が欲しいと思います
2011年02月08日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん
スティーブ・ジョブズ氏の膵臓がん
こちらは中川医師の抜粋になりますが、気になりました
<Dr.中川のがんから死生をみつめる>/91
ジョブズ氏の膵臓がん
そのアップル社の創始者であり、Macの生みの親でもあるスティーブ・ジョブズ最高経営責任者(CEO)が膵臓(すいぞう)がんのため療養に入りました。04年にがん切除手術、09年には肝臓移植のため休養しており、これで3度目の療養となります。
膵臓がんは、手ごわいがんの代名詞です。がん全体の治癒率は5割を超えており、がんは「不治の病」ではなくなっていますが、膵臓がんは、完治する人がほとんどいないのが現状です。全体でみると、平均して1年ほどで亡くなっています。残念ですが、この20年間、治癒率はほとんど改善していません。
実は、膵臓のがんは一つの病気ではありません。20近くのさまざまなタイプの腫瘍が「膵臓がん」としてひとくくりにされています。そして、その腫瘍ごとに治療法も治癒率も異なります。
膵臓には、膵液という消化液を作る外分泌機能と、さまざまなホルモンをつくる内分泌機能があります。膵臓のがんの大部分は、膵液の通り道である膵管から発生しますが、この「普通の」膵臓がんが非常に難治性なのです。
一方、ホルモンをつくるランゲルハンス島細胞から発生するのが内分泌腫瘍で、膵臓のがん全体の2%程度と非常に珍しいものです。内分泌腫瘍にも、良性から悪性までさまざまなタイプがありますが、治癒率は一般的な膵臓がんと比べると、ぐっと良く、悪性のものでも、手術後の5年生存率は6~8割程度です。
ジョブズ氏の膵臓がんは、この悪性内分泌腫瘍で、がんが肝臓に多数転移したため、肝臓移植が行われたのだと思います。米メディアは、がん再発の可能性を報じていますが、その場合、分子標的薬(がんにかかわる遺伝子を狙い撃ちする薬)が有効とのデータもあります。今回も復活をとげてくれると信じています。(中川恵一・東京大付属病院准教授、緩和ケア診療部長)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
こちらはご存知の方も多いかも知れませんが「伝説のスピーチ」と呼ばれているものです
Apple創始者・スティーヴ・ジョブスの伝説のスピーチ(1)
Apple創始者・スティーヴ・ジョブスの伝説のスピーチ(2)
私はこのスピーチを聞いて涙が止まりませんでした
死を意識する事はマイナスな事ばかりではない。と思えたし・・・
このスピーチは、その人が置かれた状況によっても受け取り方はかわると思います
ただ、なぜこれが「伝説のスピーチ」と呼ばれるのか。は、わかります
がんは誰にでも訪れる可能性のある病気です
それは、彼であっても同じです
ただ、彼にはまだまだやりたい事があるような気がします
彼は、がんを告知された人として「後悔」のない人生を送っていると思います
でも「未練」は沢山あるような気がします
できれば、もう1度戻ってきて欲しいと思います
<Dr.中川のがんから死生をみつめる>/91
ジョブズ氏の膵臓がん
そのアップル社の創始者であり、Macの生みの親でもあるスティーブ・ジョブズ最高経営責任者(CEO)が膵臓(すいぞう)がんのため療養に入りました。04年にがん切除手術、09年には肝臓移植のため休養しており、これで3度目の療養となります。
膵臓がんは、手ごわいがんの代名詞です。がん全体の治癒率は5割を超えており、がんは「不治の病」ではなくなっていますが、膵臓がんは、完治する人がほとんどいないのが現状です。全体でみると、平均して1年ほどで亡くなっています。残念ですが、この20年間、治癒率はほとんど改善していません。
実は、膵臓のがんは一つの病気ではありません。20近くのさまざまなタイプの腫瘍が「膵臓がん」としてひとくくりにされています。そして、その腫瘍ごとに治療法も治癒率も異なります。
膵臓には、膵液という消化液を作る外分泌機能と、さまざまなホルモンをつくる内分泌機能があります。膵臓のがんの大部分は、膵液の通り道である膵管から発生しますが、この「普通の」膵臓がんが非常に難治性なのです。
一方、ホルモンをつくるランゲルハンス島細胞から発生するのが内分泌腫瘍で、膵臓のがん全体の2%程度と非常に珍しいものです。内分泌腫瘍にも、良性から悪性までさまざまなタイプがありますが、治癒率は一般的な膵臓がんと比べると、ぐっと良く、悪性のものでも、手術後の5年生存率は6~8割程度です。
ジョブズ氏の膵臓がんは、この悪性内分泌腫瘍で、がんが肝臓に多数転移したため、肝臓移植が行われたのだと思います。米メディアは、がん再発の可能性を報じていますが、その場合、分子標的薬(がんにかかわる遺伝子を狙い撃ちする薬)が有効とのデータもあります。今回も復活をとげてくれると信じています。(中川恵一・東京大付属病院准教授、緩和ケア診療部長)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
こちらはご存知の方も多いかも知れませんが「伝説のスピーチ」と呼ばれているものです
Apple創始者・スティーヴ・ジョブスの伝説のスピーチ(1)
Apple創始者・スティーヴ・ジョブスの伝説のスピーチ(2)
私はこのスピーチを聞いて涙が止まりませんでした
死を意識する事はマイナスな事ばかりではない。と思えたし・・・
このスピーチは、その人が置かれた状況によっても受け取り方はかわると思います
ただ、なぜこれが「伝説のスピーチ」と呼ばれるのか。は、わかります
がんは誰にでも訪れる可能性のある病気です
それは、彼であっても同じです
ただ、彼にはまだまだやりたい事があるような気がします
彼は、がんを告知された人として「後悔」のない人生を送っていると思います
でも「未練」は沢山あるような気がします
できれば、もう1度戻ってきて欲しいと思います