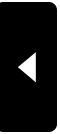スポンサーリンク
寒さがお腹にしみるわ・・・
ここのところ寒いのもあって週に何回か下痢をしています
朝、起きると同時にお腹が痛いな~と思ってトイレに行きます
そこから大体、3回くらいトイレに行ってから仕事に出かけます
それでも、やっぱり通勤途中でお腹が痛くなることもしょっちゅうです
そして月に1回くらいは、トイレに間に合わないって日があります
あ~あ、って思う。
でも、そんな時は「仕方ないよね」と思うことにしています
まあ、トイレがあっただけでもよかったよね。とか、家の中だからよかった~って感じです
入院中は、シャワー室の中で泣くこともありました
でももう、そんなのは日々のことになってしまい、泣くこともなくなりました
外出先で下着を捨ててくることもあります。
そんな時は「あ~あ、もったいないな。でも、何とかなってよかった」と思う私。
どうにもならないことを嘆いてみても、どうにもならない現実は何も変わらない。
それなら「◎◎だったけど、よかった」と考えてみる
幸せは比較によって生まれる感情。と言われた人がいました
自分が「不幸だ」と思うのであれば、もっと不幸な人がいるという現実を考えてみる
ご飯が食べれるだけでも、眠る場所があるだけでも幸せな人もいます
がん患者だと、命が助かったんだから。と言われることも・・・
でも、誰かを羨ましく思ってもどうしようもないものね
朝、起きると同時にお腹が痛いな~と思ってトイレに行きます
そこから大体、3回くらいトイレに行ってから仕事に出かけます
それでも、やっぱり通勤途中でお腹が痛くなることもしょっちゅうです
そして月に1回くらいは、トイレに間に合わないって日があります
あ~あ、って思う。
でも、そんな時は「仕方ないよね」と思うことにしています
まあ、トイレがあっただけでもよかったよね。とか、家の中だからよかった~って感じです
入院中は、シャワー室の中で泣くこともありました
でももう、そんなのは日々のことになってしまい、泣くこともなくなりました
外出先で下着を捨ててくることもあります。
そんな時は「あ~あ、もったいないな。でも、何とかなってよかった」と思う私。
どうにもならないことを嘆いてみても、どうにもならない現実は何も変わらない。
それなら「◎◎だったけど、よかった」と考えてみる
幸せは比較によって生まれる感情。と言われた人がいました
自分が「不幸だ」と思うのであれば、もっと不幸な人がいるという現実を考えてみる
ご飯が食べれるだけでも、眠る場所があるだけでも幸せな人もいます
がん患者だと、命が助かったんだから。と言われることも・・・
でも、誰かを羨ましく思ってもどうしようもないものね
2013年12月17日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │がんとこころ
病気を受け入れるということ・・・
退院してから出会ったがん体験者の中には、違和感を感じる人がいました
「なんやろ・・・?」みたいな言葉には出来ない違和感。
それは「ねばならない」という考えだったりします
「ねばならない」は、そうではない人にとっては「否定されている」という気持ちになります
ただそれは「正しい考え」でもあります
例えば「公務員はこうあらねばならない」とか「学校の先生はこうでなくてはいけない」という事です
でも、そこには相手の「個性」を認めてはいないようにも感じるし、自分の意見を押し付けているようにも感じます
確かに相手が嘘をついていたり、他の人に迷惑をかけていたり詐欺をしている場合は別ですが・・・
そうではない場合においての「ねばならない」は、少しやりすぎな気持ちになります
それは「自分はこうである。だから、あなたもこうしなさい」という命令だからです
そして、そういう人に共通して感じるのは「自分を認めていないのかな?」という気持ちです
確かに誰も彼もを受け入れることはできません
でも、だからといって全ての人を受け入れないのは、少し「いびつな感情」に思えます
それが私が感じる「違和感」です
そして、不思議なくらいそういう人って「やりすぎな食事療法」を実行していたり「体に良い」というものを試していたりします。う~~ん、それって反対に体壊しそう・・・みたいな感じです
がんという病気を受け入れている部分もあれば、受け入れていない部分もあります
でも、そういう自分でいいって言ってくれる人がいてくれないと自分自身の考えだけでは、やっぱり乗り越えられないものがあるように感じます。
「自己開示」は、必要です。でも、そこには必ず「感情を出すこと」と「それを受け止めてくれる人がいる」という関係性が大切な気がします。どちらもがきちんと成立していないと自己開示は、正しくできません。自己開示はただ、話せば良いのはないです。
自分のこころを大切にしてくれる人がいてこそです・・・
「こうあらねばならない」それは大切な気持ちではあるけれど、それは相手に対する(自分自身に対しても)「否定でもある」それも理解して欲しいと思う、今日、この頃でした。
「なんやろ・・・?」みたいな言葉には出来ない違和感。
それは「ねばならない」という考えだったりします
「ねばならない」は、そうではない人にとっては「否定されている」という気持ちになります
ただそれは「正しい考え」でもあります
例えば「公務員はこうあらねばならない」とか「学校の先生はこうでなくてはいけない」という事です
でも、そこには相手の「個性」を認めてはいないようにも感じるし、自分の意見を押し付けているようにも感じます
確かに相手が嘘をついていたり、他の人に迷惑をかけていたり詐欺をしている場合は別ですが・・・
そうではない場合においての「ねばならない」は、少しやりすぎな気持ちになります
それは「自分はこうである。だから、あなたもこうしなさい」という命令だからです
そして、そういう人に共通して感じるのは「自分を認めていないのかな?」という気持ちです
確かに誰も彼もを受け入れることはできません
でも、だからといって全ての人を受け入れないのは、少し「いびつな感情」に思えます
それが私が感じる「違和感」です
そして、不思議なくらいそういう人って「やりすぎな食事療法」を実行していたり「体に良い」というものを試していたりします。う~~ん、それって反対に体壊しそう・・・みたいな感じです
がんという病気を受け入れている部分もあれば、受け入れていない部分もあります
でも、そういう自分でいいって言ってくれる人がいてくれないと自分自身の考えだけでは、やっぱり乗り越えられないものがあるように感じます。
「自己開示」は、必要です。でも、そこには必ず「感情を出すこと」と「それを受け止めてくれる人がいる」という関係性が大切な気がします。どちらもがきちんと成立していないと自己開示は、正しくできません。自己開示はただ、話せば良いのはないです。
自分のこころを大切にしてくれる人がいてこそです・・・
「こうあらねばならない」それは大切な気持ちではあるけれど、それは相手に対する(自分自身に対しても)「否定でもある」それも理解して欲しいと思う、今日、この頃でした。
2013年12月12日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │がんとこころ
ニーバーの祈り
ニーバーの祈り
神よ
変えることのできるものについて、
それを変えるだけの勇気をわれらに与えたまえ。
変えることのできないものについては、
それを受けいれるだけの冷静さを与えたまえ。
そして、
変えることのできるものと、変えることのできないものとを、
識別する知恵を与えたまえ。
日本語訳(翻訳者:大木英夫)
神よ
変えることのできるものについて、
それを変えるだけの勇気をわれらに与えたまえ。
変えることのできないものについては、
それを受けいれるだけの冷静さを与えたまえ。
そして、
変えることのできるものと、変えることのできないものとを、
識別する知恵を与えたまえ。
日本語訳(翻訳者:大木英夫)
2013年12月11日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │がんとこころ
スピリチュアルな苦しみとは
スピリチュアルペイン
スピリチュアルな苦しみとは・・・・・
定義:自己の存在と意味の消滅から生じる苦痛(無意味、無目的、無価値)
「村田久行(京都ノートルダム女子大学 人間文化学部)」
・人生の意味・目的の喪失
・衰弱による活動能力の低下や依存の増大
・自己や人生に対するコントロール感の喪失や不確実性の増大
・家族や周囲への負担
・運命に対する不合理や不公平感
・過去の出来事に対する後悔・恥・罪の意識
・孤独、希望のなさ、あるいは、死についての不安
「森田ほか:終末期がん患者の希死念感と身体的苦痛・実存的苦痛。ターミナルケア10(3)、2000」
がんによるストレスの基礎知識
ストレスとは、ある出来事(ストレッサー)や、その出来事を経験したことで生じる心身の反応のことです。がんが疑われたときや診断、病状の説明、治療の経過、再発や転移など様々な出来事を経験すると、私たちは、不安や落ち込み、悲しみや絶望感を感じ、眠れなくなったり、食欲がなくなり食事が喉を通らなくなるなど、心も体も大きく動揺します。
一方で、私たちは、ストレスを受けて体調を崩しても、一定の休息をとれば、もとの状態に回復する力(ホメオスタシス)も持っています。この力が十分に発揮できるように、ストレスを上手くコントロールすることが大切なのです。
がん患者さんが抱える悩みとして、社会的苦痛とスピリチュアルな苦痛があるそうです
・病気のために仕事に行けなくなった
・家のローンが払えない
・主婦としての役割を果たすことができない
・子どもが小さいけれど、世話ができない
などなどです
みんなが抱く気持ちではあるけれど、年齢によっても社会的な環境によっても変化するように感じました
子育てしている人には子育て中のお母さんの悩み。家族を養っている働きざかりのお父さんには、家族を養っていけるか。自分は働けるのかといった不安などがあります。
そして、何よりそういう自分の気持ちを『話せる場所』がなく頑張っている人も多いように感じます
鎌田實先生ではないけれど『がん患者としての悩み』は、自分だけではないということ
そして『誰かに聞いてもらえること』『自分自身を認めてあげること』が、大切なんだなって思いました
がん患者さんとご家族のこころのサポートチーム:
http://support.jpos-society.org/manual/
スピリチュアルな苦しみとは・・・・・
定義:自己の存在と意味の消滅から生じる苦痛(無意味、無目的、無価値)
「村田久行(京都ノートルダム女子大学 人間文化学部)」
・人生の意味・目的の喪失
・衰弱による活動能力の低下や依存の増大
・自己や人生に対するコントロール感の喪失や不確実性の増大
・家族や周囲への負担
・運命に対する不合理や不公平感
・過去の出来事に対する後悔・恥・罪の意識
・孤独、希望のなさ、あるいは、死についての不安
「森田ほか:終末期がん患者の希死念感と身体的苦痛・実存的苦痛。ターミナルケア10(3)、2000」
がんによるストレスの基礎知識
ストレスとは、ある出来事(ストレッサー)や、その出来事を経験したことで生じる心身の反応のことです。がんが疑われたときや診断、病状の説明、治療の経過、再発や転移など様々な出来事を経験すると、私たちは、不安や落ち込み、悲しみや絶望感を感じ、眠れなくなったり、食欲がなくなり食事が喉を通らなくなるなど、心も体も大きく動揺します。
一方で、私たちは、ストレスを受けて体調を崩しても、一定の休息をとれば、もとの状態に回復する力(ホメオスタシス)も持っています。この力が十分に発揮できるように、ストレスを上手くコントロールすることが大切なのです。
がん患者さんが抱える悩みとして、社会的苦痛とスピリチュアルな苦痛があるそうです
・病気のために仕事に行けなくなった
・家のローンが払えない
・主婦としての役割を果たすことができない
・子どもが小さいけれど、世話ができない
などなどです
みんなが抱く気持ちではあるけれど、年齢によっても社会的な環境によっても変化するように感じました
子育てしている人には子育て中のお母さんの悩み。家族を養っている働きざかりのお父さんには、家族を養っていけるか。自分は働けるのかといった不安などがあります。
そして、何よりそういう自分の気持ちを『話せる場所』がなく頑張っている人も多いように感じます
鎌田實先生ではないけれど『がん患者としての悩み』は、自分だけではないということ
そして『誰かに聞いてもらえること』『自分自身を認めてあげること』が、大切なんだなって思いました
がん患者さんとご家族のこころのサポートチーム:
http://support.jpos-society.org/manual/
2013年12月09日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │がんとこころ
がんで死ぬということ・・・
正直なところ私は、自分が「がん患者」になるまで、人ががんで死ぬということを理解していませんでした
かといって、自分の両親の親、つまりは私のおばあちゃんは2人共が「胃がん」でした
父方の祖母は、子宮がんをして、その後で胃がんで亡くなりました
でも、何かがんは遠い病気で「お年寄りがなる病気」という印象を持っていました
確かに若くて、がんになった友人もいますが幸いにも早期がんで元気でいます
それが、自分ががんで入院して初めて、人ががんで亡くなるんだというのを知った気がしました
入院中に一緒だった人のうち4人が亡くなりました・・・
それほど難しい病気なんだと思います
そして、退院後も親しい人を「同じ病気」で亡くしました
「同じ病気の人が亡くなる」というのは、とてもつらい出来事です
それは、まるで自分自身の死をも現しているかのような気がするからです
そして、親しい人をがんで亡くすというのは、自分自身の分身を失うような気持ちがします・・・
かといって、自分の両親の親、つまりは私のおばあちゃんは2人共が「胃がん」でした
父方の祖母は、子宮がんをして、その後で胃がんで亡くなりました
でも、何かがんは遠い病気で「お年寄りがなる病気」という印象を持っていました
確かに若くて、がんになった友人もいますが幸いにも早期がんで元気でいます
それが、自分ががんで入院して初めて、人ががんで亡くなるんだというのを知った気がしました
入院中に一緒だった人のうち4人が亡くなりました・・・
それほど難しい病気なんだと思います
そして、退院後も親しい人を「同じ病気」で亡くしました
「同じ病気の人が亡くなる」というのは、とてもつらい出来事です
それは、まるで自分自身の死をも現しているかのような気がするからです
そして、親しい人をがんで亡くすというのは、自分自身の分身を失うような気持ちがします・・・
2013年12月06日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │がんとこころ
「乳がんと遺伝の話」~乳がん羅針盤より~
「乳がんと遺伝の話」~乳がん羅針盤より~
先日の乳がんの講演会でもらったパンフレットにかいてあったHPです
「乳がんと遺伝の話」のパンフレットの中身がこちらで読めます
とってもわかりやすくて、ためになる冊子でした
http://www.nyugan-rashinban.jp/index.html
先日の乳がんの講演会でもらったパンフレットにかいてあったHPです
「乳がんと遺伝の話」のパンフレットの中身がこちらで読めます
とってもわかりやすくて、ためになる冊子でした

http://www.nyugan-rashinban.jp/index.html
2013年11月15日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │がんとこころ
がん患者は特別?~2~
私のカラーセラピーの先生は、私と同じ「がん体験者」です
そして、今の私が病気の事を本当に自分の感じたままを話せる「がん友」さんの1人でもあります
金曜日の夜にも、やっぱり長い時間を自分達の病気について話しました
その中で先生から「がんが特別な訳じゃないのよ」と言われました
私は「がん体験者だから」カラーセラピストになろうと思いました
そして、「がん体験」で自分の人生が変わった気がします・・・
その事が自分の支えになっているような気がしていますが、だからといって
「自分が特別」と考えてはいけないということだと思います
色んな病気の人がいると思います。どんな病気であっても同じだと思います
それは以前、同い年のがん友さんと話した時にも同じ事を話していました
先日も2人でランチした時に色んな話をしました
今回は、私の名古屋のピアサポーター養成講座に通っている話などをしていましたが、その時に最近、がん体験者が色々な活動をされているというのを話していましたが、ある団体の資格試験に合格して、患者さんのために活動したいと思っていても、なかなか思うような活動ができないということでした
たまたま、その方が東海地方の方だったのもあって
私が、勿体無いな~~~~って言って「名古屋でやればいいのに~~」と話しました
私が東京ではなく、なぜ名古屋だったか。それが、ここでした。
もちろん、今、きちんとしたピアサポーター養成講座を行っているのがミーネットなのもありますが、その後の活動の場がちゃんとあるというのも大きいと思います
東京の団体の資格を取った方は、何度かそこからの要請で活動したそうですが
その後、呼ばれなくなってしまったそうです
でも同じように資格を取った別の人は呼ばれているということでした
一生懸命に高いお金を出しても、一般の方が活躍する場のない資格。
もちろん、がん患者全てに活動の場が与えられるのではないと思いますが、それでもやはり誰しも自分の「がん体験」があったからこそ、他の悩んでいる患者さんの役に立ちたいと思っているというのもあるのではないでしょうか?
そして、その患者さんの払ったかなり高額なお金はどこに行って何に使われたのでしょうか?
また、どの部分で「活動できる人と出来ない人」に分けられるのでしょうか?
私が以前、聞いた話ではその団体の主催者の方の「好き・嫌い」によって分けられているとのことでした
そして、なぜか不思議な事にその団体で活動されている方に会うと感じる違和感があります
それが先生が言われていた「がん患者は特別」という特権意識のようなものでした
以前、その団体の資格を持って活動している方と話しましたが、その後、とても怖い思いをしました。ある種の押し付けというか「OOでなければ、絶対に許さない」みたいで違和感を感じたのを覚えています
そして、ピンクリボンで活動されている芸能人を見ていると同じ違和感を感じる人がいます
「がんだから特別」ではないと思います。
でも、それと同じにがん体験があったから伝えたい事があるんです
その思いを持った人が平等に活動の場が与えられること。
それこそが、一番大切なことなのではないでしょうか?
以前のブログです:http://miyabimari.tamaliver.jp/e342987.html
そして、今の私が病気の事を本当に自分の感じたままを話せる「がん友」さんの1人でもあります
金曜日の夜にも、やっぱり長い時間を自分達の病気について話しました
その中で先生から「がんが特別な訳じゃないのよ」と言われました
私は「がん体験者だから」カラーセラピストになろうと思いました
そして、「がん体験」で自分の人生が変わった気がします・・・
その事が自分の支えになっているような気がしていますが、だからといって
「自分が特別」と考えてはいけないということだと思います
色んな病気の人がいると思います。どんな病気であっても同じだと思います
それは以前、同い年のがん友さんと話した時にも同じ事を話していました
先日も2人でランチした時に色んな話をしました
今回は、私の名古屋のピアサポーター養成講座に通っている話などをしていましたが、その時に最近、がん体験者が色々な活動をされているというのを話していましたが、ある団体の資格試験に合格して、患者さんのために活動したいと思っていても、なかなか思うような活動ができないということでした
たまたま、その方が東海地方の方だったのもあって
私が、勿体無いな~~~~って言って「名古屋でやればいいのに~~」と話しました
私が東京ではなく、なぜ名古屋だったか。それが、ここでした。
もちろん、今、きちんとしたピアサポーター養成講座を行っているのがミーネットなのもありますが、その後の活動の場がちゃんとあるというのも大きいと思います
東京の団体の資格を取った方は、何度かそこからの要請で活動したそうですが
その後、呼ばれなくなってしまったそうです
でも同じように資格を取った別の人は呼ばれているということでした
一生懸命に高いお金を出しても、一般の方が活躍する場のない資格。
もちろん、がん患者全てに活動の場が与えられるのではないと思いますが、それでもやはり誰しも自分の「がん体験」があったからこそ、他の悩んでいる患者さんの役に立ちたいと思っているというのもあるのではないでしょうか?
そして、その患者さんの払ったかなり高額なお金はどこに行って何に使われたのでしょうか?
また、どの部分で「活動できる人と出来ない人」に分けられるのでしょうか?
私が以前、聞いた話ではその団体の主催者の方の「好き・嫌い」によって分けられているとのことでした
そして、なぜか不思議な事にその団体で活動されている方に会うと感じる違和感があります
それが先生が言われていた「がん患者は特別」という特権意識のようなものでした
以前、その団体の資格を持って活動している方と話しましたが、その後、とても怖い思いをしました。ある種の押し付けというか「OOでなければ、絶対に許さない」みたいで違和感を感じたのを覚えています
そして、ピンクリボンで活動されている芸能人を見ていると同じ違和感を感じる人がいます
「がんだから特別」ではないと思います。
でも、それと同じにがん体験があったから伝えたい事があるんです
その思いを持った人が平等に活動の場が与えられること。
それこそが、一番大切なことなのではないでしょうか?
以前のブログです:http://miyabimari.tamaliver.jp/e342987.html
2013年10月12日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │がんとこころ
「肯定的物語」と「否定的物語」
以前、心理学を勉強していた時のノートを見つけました
あの時は、何もわからず、ただただ一生懸命ノートに書いていましたが、もう1度読み直してみると面白い先生がいたり、ためになることが沢山、書いてありました。
その中に「わかるわ~」と、今更ながら納得したことがあります
「肯定的物語」と「否定的物語」
自分の人生を語るときに「肯定的」に話をするか「否定的」に話すかで、相手がどう受け止めるかが変化します。それと同じように肯定的に話すことができる人は、自分の人生を肯定的にとらえることができるということです。当たり前かも知れないですが、これががん患者には結構、難しい・・・
カラーセラピーの初級の最後の課題で、自分の人生を色で見ていくというのがありました
発表の時に「暗く話す人」もいれば、ここで笑ってもいいのかな?って考えてしまうような大変な人生なのに明るく話す人もいます。自分の人生をどう話すか。は、自分の人生を「肯定的物語」として受け止めているのか「否定的物語」として受け止めているのかで変化する気がします。
さだまさしさんの曲の中に「主人公」というのがあります
その中に「自分の人生の中では 自分が主人公」という歌詞があります
本当にそうだなって思う。
がんになる事は、嬉しいことではないし受け止めるのも難しいと思う
でも、きっとこの病気になった意味はある気がします。そうでなければ、あまりにも理不尽で悲しい・・・
そして自分の人生も病気も自分がどう考えるかなんじゃないのかなって思う、今日この頃でした。
あの時は、何もわからず、ただただ一生懸命ノートに書いていましたが、もう1度読み直してみると面白い先生がいたり、ためになることが沢山、書いてありました。
その中に「わかるわ~」と、今更ながら納得したことがあります
「肯定的物語」と「否定的物語」
自分の人生を語るときに「肯定的」に話をするか「否定的」に話すかで、相手がどう受け止めるかが変化します。それと同じように肯定的に話すことができる人は、自分の人生を肯定的にとらえることができるということです。当たり前かも知れないですが、これががん患者には結構、難しい・・・
カラーセラピーの初級の最後の課題で、自分の人生を色で見ていくというのがありました
発表の時に「暗く話す人」もいれば、ここで笑ってもいいのかな?って考えてしまうような大変な人生なのに明るく話す人もいます。自分の人生をどう話すか。は、自分の人生を「肯定的物語」として受け止めているのか「否定的物語」として受け止めているのかで変化する気がします。
さだまさしさんの曲の中に「主人公」というのがあります
その中に「自分の人生の中では 自分が主人公」という歌詞があります
本当にそうだなって思う。
がんになる事は、嬉しいことではないし受け止めるのも難しいと思う
でも、きっとこの病気になった意味はある気がします。そうでなければ、あまりにも理不尽で悲しい・・・
そして自分の人生も病気も自分がどう考えるかなんじゃないのかなって思う、今日この頃でした。
2013年10月07日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │がんとこころ
約束
昨日のブログを書いて、1晩ずっと考えていました
それは多分、ここ何年間かずっと外来に感じていた違和感だったのだと思いますが・・・
私には退院時に話していた事は『約束』だと思っています。先生と約束したのにって気持ちでした。でも、実際には守られていないので私の感情としては「嘘をつかれた」という気持ちなのだと思います。それなら、なぜそうなってしまったんだろう?と考えてみました。
私の結論として、それはきっと『守られるべき約束』ではなく『守られたらいい約束』だったのかな?って思った
『守られるべき約束』であれば、例え、その時に外来に以前、診て頂いた先生がいなくても次の外来でそういう先生がいれば、また元に戻れるんだと思います。でも、それが『守られたらいい約束』なら、破られた瞬間からそれは無効になるように感じます。
例えば、がんの手術の前に患者が「先生、絶対に治してくださいね」と言ったとします。先生は「努力してみます」と答えたとする。患者は「先生は、治してくれるって約束した」と思うけれど、その後、再発がわかり余命宣告を受けてしまうとします。その場合、患者としては「先生、絶対に治してくれるって言ったじゃないですか!」って事になって、まるでとても酷い裏切りにあった気持ちになる。でも、医師としては「私は努力します」とは言ったけれど「治す」とは言っていない。っていう気持ちなのではないかな?って思う。
この例題が正しいのかは、ちょっとわからないけれど・・・そんな感じ?って気がします。
患者にとっては『守られるべき約束』と、医師にとっての『守れたらいい約束』その違いなのかな?って思った。
そう考えれば、少し納得できる気がしました
そして、患者は『あ~あ、嘘つかれたんや。なんて嫌な気分』って思って、先生は『あ~あ、あんな事言わなきゃよかった』って感じなんだろうか?って思った。
最後のところは、本当ならちょっと悲しいかな・・・
それは多分、ここ何年間かずっと外来に感じていた違和感だったのだと思いますが・・・
私には退院時に話していた事は『約束』だと思っています。先生と約束したのにって気持ちでした。でも、実際には守られていないので私の感情としては「嘘をつかれた」という気持ちなのだと思います。それなら、なぜそうなってしまったんだろう?と考えてみました。
私の結論として、それはきっと『守られるべき約束』ではなく『守られたらいい約束』だったのかな?って思った
『守られるべき約束』であれば、例え、その時に外来に以前、診て頂いた先生がいなくても次の外来でそういう先生がいれば、また元に戻れるんだと思います。でも、それが『守られたらいい約束』なら、破られた瞬間からそれは無効になるように感じます。
例えば、がんの手術の前に患者が「先生、絶対に治してくださいね」と言ったとします。先生は「努力してみます」と答えたとする。患者は「先生は、治してくれるって約束した」と思うけれど、その後、再発がわかり余命宣告を受けてしまうとします。その場合、患者としては「先生、絶対に治してくれるって言ったじゃないですか!」って事になって、まるでとても酷い裏切りにあった気持ちになる。でも、医師としては「私は努力します」とは言ったけれど「治す」とは言っていない。っていう気持ちなのではないかな?って思う。
この例題が正しいのかは、ちょっとわからないけれど・・・そんな感じ?って気がします。
患者にとっては『守られるべき約束』と、医師にとっての『守れたらいい約束』その違いなのかな?って思った。
そう考えれば、少し納得できる気がしました
そして、患者は『あ~あ、嘘つかれたんや。なんて嫌な気分』って思って、先生は『あ~あ、あんな事言わなきゃよかった』って感じなんだろうか?って思った。
最後のところは、本当ならちょっと悲しいかな・・・
2013年09月15日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │がんとこころ
障害って何?普通って何?
私にとって「障害を持っている人」というので一番最初に覚えているのは、
小学5・6年の担任の先生です
5年生になった最初の学級会で先生が「私は右耳が聞こえません。みなさん左耳に話しかけてください」と言われました。今の年齢の私ならどんな事を考えるんだろう?と思った。先生の言葉には「して欲しいことだけ」が話されています。それ以上何かをしてくれと言っている訳でもないし、気を使ってくれといっているのでもない。
ただ「左耳に話しかけてください」ということだけでした
これって、今考えるととてもシンプルでわかりやすい言葉だったなって思います
それからの私たちは、休み時間になると、みんなが当たり前の事として先生の左側で話しかけていました
でも、それ以外は全て他の先生と同じようにしていました。
障害がある人とどう接していくか。悩む必要などはないのだと思った
ただ、相手が望むことだけをしてあげればいいということだと思いました
障害がある人と普通に接してあげて欲しい。という考えもあります。でも先生のように「右耳が聞こえない」という障害がある人に右耳側に座ってどんなに大きな声で話しかけても聞こえません。それは、やはり相手を思いやってあげることが必要なのだと思います。手術をした後でほんの少し歩く速度を遅くして欲しいとか色々ありました。入院中にも色んな人が来てくれたけれどその時に感じたのは「必要なことだけでいい」という事でした。
先日、介護資格を勉強中の友人が話してくれたのは先輩の介護士さんから「どんなに家が散らかっていても相手が片付けて欲しいと言わなければ、やる必要はないということ。それは、私たちには散らかっているように思えてもその人には何があるかわかっている場合もあるから、例え親切でやってあげたとしても相手にとっては迷惑なこともあるんだと教えてもらったの」ということでした。
明らかに障害があるからといって、その人が全てをやってもらいたいと思っているとは限らない。
でも、障害がある部分だけをカバーして欲しいという気持ちはあると思います。
以前にも書きましたが、目が見えなくて盲導犬を連れている人と調剤薬局で一緒になった時にその人が隣の人と話しているのをみて私が「盲導犬は外にいる時はお仕事中だから話しかけてはいけません。とか触ってはいけないっていうけれど・・・」と聞いて見ると「そんなこと言われたら私は外に出ても誰とも話せないじゃない」と言われました。犬だってこうやっている時は触ってあげてもいいのよ。って言われた。盲導犬は人が好きな犬だから喜んでいるのよって。
その考え方は彼女だけかもしれません。
その後、盲導犬の訓練に関わっていた人にも「話しかけたり触っちゃいけないのよ」と言われたし。
でも、考えたら盲導犬の犬って「人が好き」な犬が選ばれているはずなのになって思った。
人のために働いてくれる犬ってことは人がとっても好きだからなんだと思う
それなのに飼い主さん以外には、相手にしてもらえないって寂しくないかな?って思った
他の犬たちは、お散歩の途中で「大好きなおばあちゃん」とか「大好きな子ども」や「仲間」がいたりするのに・・・って思った。そしたら、仕事を休んでいる間なら盲導犬にも人間にも話しかけてもいいのよって言っていた彼女の言葉のほうが真実味を感じました。
がん治療のあとでは、ほとんどの人が「何かをなくして」います。
それが体の一部である場合もあるし、心の問題だったりもします
抗がん剤治療のあとなどでは、手の痺れや体調不良など目に見えない障害も沢山あります
がん患者の人が治療後に悩む大きな問題として『普通って何?』というのがあります
今までの自分じゃない自分のココロと体。もう私って「普通じゃないの?」・・・
でも、それなら『普通って何?』『障害って何?』って思う
先生のように右耳が聞こえないのは障害です。でも、他は日常生活に支障があったとは思えなかったです
障害があるからないからというくくりではなく、障害も「個性」なのだと思えばいい。と言われたことがあります。
でも、子どもの世界の中にも大人の世界の中にもある「いじめ」という現実。
それって実は相手と自分が違う人間であるということを認めていないことから起きているように思います
「自分はこう思っている。でも、あの子は違う」その自他の区別がついていないのかな?って思った
障害であっても、それも個性。それなら、何も相手を「差別」する必要はないのだと思う
自分と他人は違うことを知っている、それは「差別」ではなく「区別」なのだと思います
私自身は、いじめの元は相手を認めないという「差別する心」なのだと思います
相手と自分が相容れないと思えば、ただ離れていけばいいと単純に考えればいいのだと思う
そして絶対に自分を見ていてくれる人はいる。私はそう思っています。
小学5・6年の担任の先生です
5年生になった最初の学級会で先生が「私は右耳が聞こえません。みなさん左耳に話しかけてください」と言われました。今の年齢の私ならどんな事を考えるんだろう?と思った。先生の言葉には「して欲しいことだけ」が話されています。それ以上何かをしてくれと言っている訳でもないし、気を使ってくれといっているのでもない。
ただ「左耳に話しかけてください」ということだけでした
これって、今考えるととてもシンプルでわかりやすい言葉だったなって思います
それからの私たちは、休み時間になると、みんなが当たり前の事として先生の左側で話しかけていました
でも、それ以外は全て他の先生と同じようにしていました。
障害がある人とどう接していくか。悩む必要などはないのだと思った
ただ、相手が望むことだけをしてあげればいいということだと思いました
障害がある人と普通に接してあげて欲しい。という考えもあります。でも先生のように「右耳が聞こえない」という障害がある人に右耳側に座ってどんなに大きな声で話しかけても聞こえません。それは、やはり相手を思いやってあげることが必要なのだと思います。手術をした後でほんの少し歩く速度を遅くして欲しいとか色々ありました。入院中にも色んな人が来てくれたけれどその時に感じたのは「必要なことだけでいい」という事でした。
先日、介護資格を勉強中の友人が話してくれたのは先輩の介護士さんから「どんなに家が散らかっていても相手が片付けて欲しいと言わなければ、やる必要はないということ。それは、私たちには散らかっているように思えてもその人には何があるかわかっている場合もあるから、例え親切でやってあげたとしても相手にとっては迷惑なこともあるんだと教えてもらったの」ということでした。
明らかに障害があるからといって、その人が全てをやってもらいたいと思っているとは限らない。
でも、障害がある部分だけをカバーして欲しいという気持ちはあると思います。
以前にも書きましたが、目が見えなくて盲導犬を連れている人と調剤薬局で一緒になった時にその人が隣の人と話しているのをみて私が「盲導犬は外にいる時はお仕事中だから話しかけてはいけません。とか触ってはいけないっていうけれど・・・」と聞いて見ると「そんなこと言われたら私は外に出ても誰とも話せないじゃない」と言われました。犬だってこうやっている時は触ってあげてもいいのよ。って言われた。盲導犬は人が好きな犬だから喜んでいるのよって。
その考え方は彼女だけかもしれません。
その後、盲導犬の訓練に関わっていた人にも「話しかけたり触っちゃいけないのよ」と言われたし。
でも、考えたら盲導犬の犬って「人が好き」な犬が選ばれているはずなのになって思った。
人のために働いてくれる犬ってことは人がとっても好きだからなんだと思う
それなのに飼い主さん以外には、相手にしてもらえないって寂しくないかな?って思った
他の犬たちは、お散歩の途中で「大好きなおばあちゃん」とか「大好きな子ども」や「仲間」がいたりするのに・・・って思った。そしたら、仕事を休んでいる間なら盲導犬にも人間にも話しかけてもいいのよって言っていた彼女の言葉のほうが真実味を感じました。
がん治療のあとでは、ほとんどの人が「何かをなくして」います。
それが体の一部である場合もあるし、心の問題だったりもします
抗がん剤治療のあとなどでは、手の痺れや体調不良など目に見えない障害も沢山あります
がん患者の人が治療後に悩む大きな問題として『普通って何?』というのがあります
今までの自分じゃない自分のココロと体。もう私って「普通じゃないの?」・・・
でも、それなら『普通って何?』『障害って何?』って思う
先生のように右耳が聞こえないのは障害です。でも、他は日常生活に支障があったとは思えなかったです
障害があるからないからというくくりではなく、障害も「個性」なのだと思えばいい。と言われたことがあります。
でも、子どもの世界の中にも大人の世界の中にもある「いじめ」という現実。
それって実は相手と自分が違う人間であるということを認めていないことから起きているように思います
「自分はこう思っている。でも、あの子は違う」その自他の区別がついていないのかな?って思った
障害であっても、それも個性。それなら、何も相手を「差別」する必要はないのだと思う
自分と他人は違うことを知っている、それは「差別」ではなく「区別」なのだと思います
私自身は、いじめの元は相手を認めないという「差別する心」なのだと思います
相手と自分が相容れないと思えば、ただ離れていけばいいと単純に考えればいいのだと思う
そして絶対に自分を見ていてくれる人はいる。私はそう思っています。
2013年09月02日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │がんとこころ
サザンオールスターズの新曲
サザンオールスターズの新曲がでました
CMで流れていた曲を2日のミュージックステーションで桑田さんが歌っていました
私とサザンの出会いは、私がまだ小学6年生?中学1年生??の時でした
聖子ちゃんのデビューもすごかったけれど、この意味の分からない人たちの歌(叔母がよく言っていました)も、あの時には衝撃だった気がします。それからは、サザンは私にとって「当たり前に存在している歌」でした。仲のいい女友達が車を買ったよ。っていうと、一番に海にドライブに行っていました。姫路市は瀬戸内海沿岸だから、当たり前のように海があったし、でもちょっとお洒落な海水浴場といえば超汚いのに須磨に海水浴に行っていました。そんな時に聞いていたのがサザンオールスターズと明石家さんまでした。きっと、海ならサザンとユーミンだろうけれど、そこはさんまちゃんは譲れない・・・なんて言いながら♪
でも、ある時からサザンのアルバムを聞かなくなって、そこからはずっとシングルしか聞いていませんでした。
そんな私が久しぶりに何だかとっても好きだと思ったのが「栄光の男」です。この歌には「人生の悲哀を描いた最新作」というのが書かれていました。
その歌詞の中で私は、
生まれ変わってみても 栄光の男にゃなれない
鬼が行き交う世間 渡り切るのが精一杯
老いていく肉体は 愛も知らずに満足かい?
喜びを誰かと 分かち合うのが人生さ
ここが好きかな。
桑田さんが食道がんを公表する時に、病理とステージを一緒に公表しました。今は芸能人でがんを公表している人は多いと思います。でもその中で病理とステージをきちんと出した人って記憶がありません。がんは病理とステージが大切なものになります。それが、桑田さんが「どう病気と向き合っているか」と「どうファンの人と向き合っているのか」を垣間見た気がしました。
私が感じていることは、がんに罹患したからといってみんなが死ぬ訳じゃない。
でも、ついついドラマのように「若くて綺麗ながん患者が健気に仲間を励まして、友達に囲まれて綺麗に死んでいく」のを想像していると思います。そんなの「ドラマだけ」です。つらい時に相手にあたりたい時だってあると思う。それが「普通の人」だと思います。でも、それでも「あたる家族がいるだけでも幸せ」なんだと思う。見送ってくれる家族がいない人だっています。みんながみんなヒーローなんかにはなれやしない・・・でも、ちゃんと与えられた人生を生きているんだと思う。
そういう人が大切にしてもらえるような社会がいいなって思います。
CMで流れていた曲を2日のミュージックステーションで桑田さんが歌っていました
私とサザンの出会いは、私がまだ小学6年生?中学1年生??の時でした
聖子ちゃんのデビューもすごかったけれど、この意味の分からない人たちの歌(叔母がよく言っていました)も、あの時には衝撃だった気がします。それからは、サザンは私にとって「当たり前に存在している歌」でした。仲のいい女友達が車を買ったよ。っていうと、一番に海にドライブに行っていました。姫路市は瀬戸内海沿岸だから、当たり前のように海があったし、でもちょっとお洒落な海水浴場といえば超汚いのに須磨に海水浴に行っていました。そんな時に聞いていたのがサザンオールスターズと明石家さんまでした。きっと、海ならサザンとユーミンだろうけれど、そこはさんまちゃんは譲れない・・・なんて言いながら♪
でも、ある時からサザンのアルバムを聞かなくなって、そこからはずっとシングルしか聞いていませんでした。
そんな私が久しぶりに何だかとっても好きだと思ったのが「栄光の男」です。この歌には「人生の悲哀を描いた最新作」というのが書かれていました。
その歌詞の中で私は、
生まれ変わってみても 栄光の男にゃなれない
鬼が行き交う世間 渡り切るのが精一杯
老いていく肉体は 愛も知らずに満足かい?
喜びを誰かと 分かち合うのが人生さ
ここが好きかな。
桑田さんが食道がんを公表する時に、病理とステージを一緒に公表しました。今は芸能人でがんを公表している人は多いと思います。でもその中で病理とステージをきちんと出した人って記憶がありません。がんは病理とステージが大切なものになります。それが、桑田さんが「どう病気と向き合っているか」と「どうファンの人と向き合っているのか」を垣間見た気がしました。
私が感じていることは、がんに罹患したからといってみんなが死ぬ訳じゃない。
でも、ついついドラマのように「若くて綺麗ながん患者が健気に仲間を励まして、友達に囲まれて綺麗に死んでいく」のを想像していると思います。そんなの「ドラマだけ」です。つらい時に相手にあたりたい時だってあると思う。それが「普通の人」だと思います。でも、それでも「あたる家族がいるだけでも幸せ」なんだと思う。見送ってくれる家族がいない人だっています。みんながみんなヒーローなんかにはなれやしない・・・でも、ちゃんと与えられた人生を生きているんだと思う。
そういう人が大切にしてもらえるような社会がいいなって思います。
2013年08月04日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │がんとこころ
私、何年目??
私、今年で何年目??
がん患者になって今年で初めて、自分が仙台で入院した日と手術した日を忘れていました
おおお~~~自分でもびっくり
多分、これはひとえにマイコプラズマ肺炎のお陰 というか他にあまりにも大変なことが起きたせいなんだろうけれど、これってすごいなって思った。あんなに自分の中で「2009年7月1日に入院して3日に手術」って覚えていたのに・・・これが本当に意味で『病院から離れていく』という感覚なのかな?って思った。物質的にも感覚的にも離れていく。病気のことよりも日常が大切になっていくってことなのかなって思った。
というか他にあまりにも大変なことが起きたせいなんだろうけれど、これってすごいなって思った。あんなに自分の中で「2009年7月1日に入院して3日に手術」って覚えていたのに・・・これが本当に意味で『病院から離れていく』という感覚なのかな?って思った。物質的にも感覚的にも離れていく。病気のことよりも日常が大切になっていくってことなのかなって思った。
その上で、私って何年目??と悩んだ・・・
何年目っていうのは、治療終了日(私の場合は、放射線治療の最終日)から数えるんだけれど、その場合2009年は含まれる?含まれない?と真剣に悩んでいた私。で、思わず2009年を入れて友達に「次の9月で5年目検診だ~~ 」とメールしたら「ええ~そんなになるんだ。早いね」と言われて喜んでいた私。
」とメールしたら「ええ~そんなになるんだ。早いね」と言われて喜んでいた私。
でも、仲良しのがん友さんに確認したところ実際には9月のは「4年目検診」でした
そんなに甘くなかった・・・ちょっと残念な私です
今日の『おのくん』・・・三鷹の森ジブリ美術館の看板から~

おのくんは、宮城県東松島市「小野駅前応急仮設 住宅」の人々の奥松島の復興を願って生まれたキャラクターです。「おのくん」を色々な場所に連れて行って写真をブログで紹介されている方がいました。せっかく私の家にもやってきたのだから、せめて三鷹市の紹介をおのくんにお願いしようかなって思っています。
で、最初はやっぱり『ジブリ』からです
http://re-tohoku.jp/blog/9108
がん患者になって今年で初めて、自分が仙台で入院した日と手術した日を忘れていました

おおお~~~自分でもびっくり

多分、これはひとえにマイコプラズマ肺炎のお陰
 というか他にあまりにも大変なことが起きたせいなんだろうけれど、これってすごいなって思った。あんなに自分の中で「2009年7月1日に入院して3日に手術」って覚えていたのに・・・これが本当に意味で『病院から離れていく』という感覚なのかな?って思った。物質的にも感覚的にも離れていく。病気のことよりも日常が大切になっていくってことなのかなって思った。
というか他にあまりにも大変なことが起きたせいなんだろうけれど、これってすごいなって思った。あんなに自分の中で「2009年7月1日に入院して3日に手術」って覚えていたのに・・・これが本当に意味で『病院から離れていく』という感覚なのかな?って思った。物質的にも感覚的にも離れていく。病気のことよりも日常が大切になっていくってことなのかなって思った。その上で、私って何年目??と悩んだ・・・

何年目っていうのは、治療終了日(私の場合は、放射線治療の最終日)から数えるんだけれど、その場合2009年は含まれる?含まれない?と真剣に悩んでいた私。で、思わず2009年を入れて友達に「次の9月で5年目検診だ~~
 」とメールしたら「ええ~そんなになるんだ。早いね」と言われて喜んでいた私。
」とメールしたら「ええ~そんなになるんだ。早いね」と言われて喜んでいた私。でも、仲良しのがん友さんに確認したところ実際には9月のは「4年目検診」でした
そんなに甘くなかった・・・ちょっと残念な私です

今日の『おのくん』・・・三鷹の森ジブリ美術館の看板から~

おのくんは、宮城県東松島市「小野駅前応急仮設 住宅」の人々の奥松島の復興を願って生まれたキャラクターです。「おのくん」を色々な場所に連れて行って写真をブログで紹介されている方がいました。せっかく私の家にもやってきたのだから、せめて三鷹市の紹介をおのくんにお願いしようかなって思っています。
で、最初はやっぱり『ジブリ』からです

http://re-tohoku.jp/blog/9108
2013年07月22日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │がんとこころ
書けない私。
3月にカラーセラピーの論文を書きました
その時に私が1番考えたのが「私は自分が納得しないと書けない」という事でした
人によっては経験が少ししかなくても、ちゃんと本質を理解して文章を書ける人がいると思いますが私は無理やわって思った。だから、何度も何度もカラーセラピーを体験してもらった友人にメールをしたり長い時間、話をしたりしました。
そして、実際に書いた論文(40枚)よりもそこに行き着くまでの気持ちや会話、資料を書き溜めたノートが3倍くらいあります。それだけ考えて、やっと書き上げることができました。でも、提出後にも『保留』にしていた「ぬり絵」が届いたりして、その後、何枚かを追加・差し替えさせてもらいました。
カラーセラピーの論文を書いて感じた事は、これは「自分が相手とどのように向き合うか」という事だったのだと感じました。だから私は「自分らしいカラーセラピストとは」という『自分』をテーマに選んだのだと思いました。私以外の人たちも、やはりその人らしいテーマ選びだったし、論文の内容もそうでした。
書き上げる間、自分と向き合う時間が長かったせいか、今の私は『がん患者』なのか『健常者(この場合、がん体験者以外という意味)』なのか自分の立ち位置がわからなくなっていることに気がつきました。
私は今でも文章を書くのがとても苦手です。小学生の時に先生と交換日記をしていて、その文章がいいと先生から花丸をもらえました。花丸は友達は毎月発行される「学校新聞」に書いたものが紹介される印でもありました。でも、私は2年間で1度も花丸をもらえませんでした。それから自分は文章をかくのが苦手。と思っていたので、このブログを書き始めた時にも(婦長さんに書きなさいと言われた)かくまでに、とても長い時間がかかりました。でも、自分と一緒に戦って亡くなってしまった人たちの声をきちんと残しておきたい。と思って書き始めました。だから、がん友さんから「書いて」と言われても「私がちゃんと納得するまで書けないけどいい?でも、絶対にかくからね」といっています。自分が納得しないと文章が書けない私には、想像で文章が書ける人が羨ましい・・・でも、このブログには、そういう「自分じゃないもの」は乗せたくないと思っていました。
それはもし、本物の私に会った人が「こんな人だと思わなかった」と思われないためにも、私はちゃんと私自身の言葉で書きたいと思っているからです。違和感のある人にはなりたくないから・・・でも、だからこそ、今の自分の状態がよくわからないのだと思います。
これが「病院から離れていく」ということなのかな?って思う。
それは患者としては嬉しいことかもしれません。
でも、どこかで自分が属する場所がなくなっていくような気がしてしまいます。
これって、退院後の患者が経験する気持ちなのかな。。。
その時に私が1番考えたのが「私は自分が納得しないと書けない」という事でした
人によっては経験が少ししかなくても、ちゃんと本質を理解して文章を書ける人がいると思いますが私は無理やわって思った。だから、何度も何度もカラーセラピーを体験してもらった友人にメールをしたり長い時間、話をしたりしました。
そして、実際に書いた論文(40枚)よりもそこに行き着くまでの気持ちや会話、資料を書き溜めたノートが3倍くらいあります。それだけ考えて、やっと書き上げることができました。でも、提出後にも『保留』にしていた「ぬり絵」が届いたりして、その後、何枚かを追加・差し替えさせてもらいました。
カラーセラピーの論文を書いて感じた事は、これは「自分が相手とどのように向き合うか」という事だったのだと感じました。だから私は「自分らしいカラーセラピストとは」という『自分』をテーマに選んだのだと思いました。私以外の人たちも、やはりその人らしいテーマ選びだったし、論文の内容もそうでした。
書き上げる間、自分と向き合う時間が長かったせいか、今の私は『がん患者』なのか『健常者(この場合、がん体験者以外という意味)』なのか自分の立ち位置がわからなくなっていることに気がつきました。
私は今でも文章を書くのがとても苦手です。小学生の時に先生と交換日記をしていて、その文章がいいと先生から花丸をもらえました。花丸は友達は毎月発行される「学校新聞」に書いたものが紹介される印でもありました。でも、私は2年間で1度も花丸をもらえませんでした。それから自分は文章をかくのが苦手。と思っていたので、このブログを書き始めた時にも(婦長さんに書きなさいと言われた)かくまでに、とても長い時間がかかりました。でも、自分と一緒に戦って亡くなってしまった人たちの声をきちんと残しておきたい。と思って書き始めました。だから、がん友さんから「書いて」と言われても「私がちゃんと納得するまで書けないけどいい?でも、絶対にかくからね」といっています。自分が納得しないと文章が書けない私には、想像で文章が書ける人が羨ましい・・・でも、このブログには、そういう「自分じゃないもの」は乗せたくないと思っていました。
それはもし、本物の私に会った人が「こんな人だと思わなかった」と思われないためにも、私はちゃんと私自身の言葉で書きたいと思っているからです。違和感のある人にはなりたくないから・・・でも、だからこそ、今の自分の状態がよくわからないのだと思います。
これが「病院から離れていく」ということなのかな?って思う。
それは患者としては嬉しいことかもしれません。
でも、どこかで自分が属する場所がなくなっていくような気がしてしまいます。
これって、退院後の患者が経験する気持ちなのかな。。。

2013年05月25日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │がんとこころ
赤ちゃん
日曜日に友達が3400グラムの元気な赤ちゃんを産みました
メールがきて、さすがに産んだ日に行くのはお母さんも大変だろうと思って今日、行って来ました
新生児室のは小さくて可愛い赤ちゃんが4人並んでいました。友達の赤ちゃんよりも2日前に生まれた子は、ちょっとしっかりした顔をしていてお兄ちゃんが見に来た時には少しだけれど目を開けました。まだ見えていないんだろうけれど、一生懸命声のするほうを見ている気がしました
私が入院していた病院は産科が6階で婦人科が7階だったので、産まれたばっかりの赤ちゃんを見ることはありませんでしたが、あの時の私だったらどういう気持ちで見ていたんだろうと思った
子宮がん(頸がん・体がん)の患者さんの中には、妊娠と同時にがんが見つかる患者さんもいます
そういう方は、残念だけれど赤ちゃんと子宮を一緒に取らなくてはいけなくなるそうです
私が入院していた時にも、そういうお母さんがいました。赤ちゃんは生まれてこれなかったのに母乳は出るので飲んでくれる子どもがいなくてもお乳を出さなくてはいけないので、泣きながら出していたと聞きました。なんて切ないんだろう・・・と思った。
友人が乳がんの手術を受けた病院は、がんで子宮を失った患者さんも出産したお母さんも一緒の階だったそうです。今の私なら、友達の赤ちゃんを見て「なんて可愛いんだろう」と思えるけれど、手術をした時はどうだったんだろう?と思います。そして、友達の赤ちゃんじゃなかったら・・・と思った。でも今は、生まれてきたことは、やっぱり奇跡なのかもしれないなって思う。
まだまだ患者さんの気持ちに配慮していない病院もあります。
でも、あまりにも自分を「かわいそうな私」としてしまっている患者さんもいるように感じます
難しいけれど、生めなかった自分には自分の役割があると思って欲しいなって思います。う~~~ん、でも、やっぱり難しいのかな・・・
メールがきて、さすがに産んだ日に行くのはお母さんも大変だろうと思って今日、行って来ました
新生児室のは小さくて可愛い赤ちゃんが4人並んでいました。友達の赤ちゃんよりも2日前に生まれた子は、ちょっとしっかりした顔をしていてお兄ちゃんが見に来た時には少しだけれど目を開けました。まだ見えていないんだろうけれど、一生懸命声のするほうを見ている気がしました
私が入院していた病院は産科が6階で婦人科が7階だったので、産まれたばっかりの赤ちゃんを見ることはありませんでしたが、あの時の私だったらどういう気持ちで見ていたんだろうと思った
子宮がん(頸がん・体がん)の患者さんの中には、妊娠と同時にがんが見つかる患者さんもいます
そういう方は、残念だけれど赤ちゃんと子宮を一緒に取らなくてはいけなくなるそうです
私が入院していた時にも、そういうお母さんがいました。赤ちゃんは生まれてこれなかったのに母乳は出るので飲んでくれる子どもがいなくてもお乳を出さなくてはいけないので、泣きながら出していたと聞きました。なんて切ないんだろう・・・と思った。
友人が乳がんの手術を受けた病院は、がんで子宮を失った患者さんも出産したお母さんも一緒の階だったそうです。今の私なら、友達の赤ちゃんを見て「なんて可愛いんだろう」と思えるけれど、手術をした時はどうだったんだろう?と思います。そして、友達の赤ちゃんじゃなかったら・・・と思った。でも今は、生まれてきたことは、やっぱり奇跡なのかもしれないなって思う。
まだまだ患者さんの気持ちに配慮していない病院もあります。
でも、あまりにも自分を「かわいそうな私」としてしまっている患者さんもいるように感じます
難しいけれど、生めなかった自分には自分の役割があると思って欲しいなって思います。う~~~ん、でも、やっぱり難しいのかな・・・

2013年05月14日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │がんとこころ
最近の私。
がん患者になって、自分が今までとは違う生き方をしなきゃいけない気がしてた。
「若くして、こんな病気になってしまったのには何か意味があるんじゃないか?」ってね。だから、色んな患者会の人と話しをしたし、嫌な事も言われた。
そんな時にある患者会の人に言われたのが「みんな違ってみんないい」だった。
「あなたにはあなたの個性があるんだから、誰かのようになんて考えなくていい」って言われたんよね。
確かに「若くして、がん患者」の私だからできる事もある。
でも実際は、やっぱり普通に生きていく事が大切なんやと思った。
生活していくには、きちんと「普通の人」(この場合は病気をしていない健康な人)と一緒に働いてこそなんやないやろか?と思った。
自分がちゃんと自分の足で立ってこそ、人を助けてあげれるんやと思ったんよね。
だから私は仕事して、自分が働いたお金でやりたい事を見つけていこうって決めたんよね。
カラーセラピーは、その1つやと思う。
がんになって考えたのは、自分はどう生きたいか。だった。
それは一緒に「どう死にたいか」も考えるきっかけになったかな。
でも、だからといって「人に優しくない私」や「キレてる私」も同時にいます。
そんな病気しても「仏様」みたいにはなれません…
それでも、やっぱり間違いなく、生きてるんよね~~。
それでええんと違うやろかね…。
「若くして、こんな病気になってしまったのには何か意味があるんじゃないか?」ってね。だから、色んな患者会の人と話しをしたし、嫌な事も言われた。
そんな時にある患者会の人に言われたのが「みんな違ってみんないい」だった。
「あなたにはあなたの個性があるんだから、誰かのようになんて考えなくていい」って言われたんよね。
確かに「若くして、がん患者」の私だからできる事もある。
でも実際は、やっぱり普通に生きていく事が大切なんやと思った。
生活していくには、きちんと「普通の人」(この場合は病気をしていない健康な人)と一緒に働いてこそなんやないやろか?と思った。
自分がちゃんと自分の足で立ってこそ、人を助けてあげれるんやと思ったんよね。
だから私は仕事して、自分が働いたお金でやりたい事を見つけていこうって決めたんよね。
カラーセラピーは、その1つやと思う。
がんになって考えたのは、自分はどう生きたいか。だった。
それは一緒に「どう死にたいか」も考えるきっかけになったかな。
でも、だからといって「人に優しくない私」や「キレてる私」も同時にいます。
そんな病気しても「仏様」みたいにはなれません…
それでも、やっぱり間違いなく、生きてるんよね~~。
それでええんと違うやろかね…。
2013年05月09日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │がんとこころ
がん患者は特別?
『がん患者は特別?』という疑問は、2年が過ぎたあたりから感じていました。
先日、がん友さんが東京マラソンでゴスペルを歌いました。彼女が「沢山の応募の中から選ばれて歌えるようになったのよ」と教えてくれた時に、正直、そういう事がよくわからない私は「そうなの??」と聞いたら「書類選考があってテーマなんかを書いて出して、選ばれるんだよ」とのこと。
乳がん体験者の人たちの活動は、婦人科がんの私たち(体験者で話した時にもそういう話題がでるので)に比べると、とっても同じようには出来ないな…と思う事があります。でも、若くして「がん体験者」になった人がこれだけいるんだよ。というのを知ってもらえる事は、大切な活動だと思います。
ただ最近、自分自身も含めて感じているのは『がん患者は特別』なのだろうか??という事です。
東京マラソンで沢山の中から選ばれる理由が『がん体験者』だから。なんじゃないのかな?と思った。もしかしたら、書類選考じゃなく実際に歌ったら、彼女たちよりはるかに上手な人たちがいたかもしれないし…。
友達は「せっかく発表の場を与えてもらえたんだから、頑張って歌わなきゃ」と言っていました。
私自身、がん患者になってしばらくは、心のどこかで「私はがんなんだから」「私は大変な病気になったんだから、○○してもらっても当たり前」という気持ちがなかったとは言えない気がします。
あるがんの講演会の主催者の方が教えてくれた話で、講演会の会場の空調の温度調整が効かずにすごく寒かったそうです。すると夫婦で来られていた人の旦那さんのほうが「(がん患者の)妻が風邪をひいたらどうするんだ!」と言ってきたそうです。それからチラシには「空調の関係で寒くなることがありますので上着をお持ちください」と書くようにしたと話してくれました。
これが公共の交通機関なら、旦那さんは言っただろうか?と思った。そしてこれが、がんの講演会だからなんじゃないのかな?って思った。そうでなければ「がん患者の」とは言わない気がします。
でも患者にも色々な人がいます。暑がりの「がん体験者さん」だっています。
私は退院後、すぐにお腹を壊すから長い時間公共の交通機関を利用する時は膝かけを用意しています。また退院後しばらくは仙台まで新幹線を利用するときには必ず「多目的室」の近くの席を予約しました。
退院すれば、それは一般の人と同じようにしなきゃいけないところがあります。でもどこかで「自分はがん体験者なんだから」という『特別な意識』があるような気がします(自分も含めて)
退院後、いろんな病気の患者さんや障害をもつお子さんの親と話しました。
がんだけが病気ではないんだと考えさせられた事が何度もありました。
確かに「がん」は命を奪う病気だし、手術後の後遺症もあります。
でも、退院した後は基本的には自分の事は自分自身で背負わなければいけない気がしました。
入院中に一緒だった患者さんと電話で話した時、外来の先生に嫌な気持ちにさせられた話をしてくれました。そして「私たちはN先生に診てもらえて本当によかったわよね」と言った時に、なんだか退院後の外来で先生に会えないと文句を言ってた自分自身が少し恥ずかしいと思った。
Iさんがいうように、私たちはN先生に診てもらって助けてもらったんだから、これから先は自分で何とかしていかなきゃ。と思った。そして先生が最優先するのは私たちみたいに退院した患者ではなくて、今まさに告知されて病院に来た患者さんなんだと思った。それでなくても「見えないところで忙しい」先生たちだし。
患者は患者のできる事を自分の与えられた場所でがんばる。それも「がん患者学」なのかな。と感じた私でした。
先日、がん友さんが東京マラソンでゴスペルを歌いました。彼女が「沢山の応募の中から選ばれて歌えるようになったのよ」と教えてくれた時に、正直、そういう事がよくわからない私は「そうなの??」と聞いたら「書類選考があってテーマなんかを書いて出して、選ばれるんだよ」とのこと。
乳がん体験者の人たちの活動は、婦人科がんの私たち(体験者で話した時にもそういう話題がでるので)に比べると、とっても同じようには出来ないな…と思う事があります。でも、若くして「がん体験者」になった人がこれだけいるんだよ。というのを知ってもらえる事は、大切な活動だと思います。
ただ最近、自分自身も含めて感じているのは『がん患者は特別』なのだろうか??という事です。
東京マラソンで沢山の中から選ばれる理由が『がん体験者』だから。なんじゃないのかな?と思った。もしかしたら、書類選考じゃなく実際に歌ったら、彼女たちよりはるかに上手な人たちがいたかもしれないし…。
友達は「せっかく発表の場を与えてもらえたんだから、頑張って歌わなきゃ」と言っていました。
私自身、がん患者になってしばらくは、心のどこかで「私はがんなんだから」「私は大変な病気になったんだから、○○してもらっても当たり前」という気持ちがなかったとは言えない気がします。
あるがんの講演会の主催者の方が教えてくれた話で、講演会の会場の空調の温度調整が効かずにすごく寒かったそうです。すると夫婦で来られていた人の旦那さんのほうが「(がん患者の)妻が風邪をひいたらどうするんだ!」と言ってきたそうです。それからチラシには「空調の関係で寒くなることがありますので上着をお持ちください」と書くようにしたと話してくれました。
これが公共の交通機関なら、旦那さんは言っただろうか?と思った。そしてこれが、がんの講演会だからなんじゃないのかな?って思った。そうでなければ「がん患者の」とは言わない気がします。
でも患者にも色々な人がいます。暑がりの「がん体験者さん」だっています。
私は退院後、すぐにお腹を壊すから長い時間公共の交通機関を利用する時は膝かけを用意しています。また退院後しばらくは仙台まで新幹線を利用するときには必ず「多目的室」の近くの席を予約しました。
退院すれば、それは一般の人と同じようにしなきゃいけないところがあります。でもどこかで「自分はがん体験者なんだから」という『特別な意識』があるような気がします(自分も含めて)
退院後、いろんな病気の患者さんや障害をもつお子さんの親と話しました。
がんだけが病気ではないんだと考えさせられた事が何度もありました。
確かに「がん」は命を奪う病気だし、手術後の後遺症もあります。
でも、退院した後は基本的には自分の事は自分自身で背負わなければいけない気がしました。
入院中に一緒だった患者さんと電話で話した時、外来の先生に嫌な気持ちにさせられた話をしてくれました。そして「私たちはN先生に診てもらえて本当によかったわよね」と言った時に、なんだか退院後の外来で先生に会えないと文句を言ってた自分自身が少し恥ずかしいと思った。
Iさんがいうように、私たちはN先生に診てもらって助けてもらったんだから、これから先は自分で何とかしていかなきゃ。と思った。そして先生が最優先するのは私たちみたいに退院した患者ではなくて、今まさに告知されて病院に来た患者さんなんだと思った。それでなくても「見えないところで忙しい」先生たちだし。
患者は患者のできる事を自分の与えられた場所でがんばる。それも「がん患者学」なのかな。と感じた私でした。
2013年04月20日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │がんとこころ
仙台に行ってきました・・・ピアサポーター

お世話になっている仙台の友達のお母さんが大腸がんになったので、外来の後で、お見舞いに行く予定でしたが、友達いわく『ベガルタの試合があるの』ということで今回は見送りになりました
そしたら、名古屋のミーネットの花井さんが仙台に来られるという事で急遽、参加してきました
花井さんからはピアサポーターのことは「もう何度も聞いた話でしょ」と言われましたが、確かに1年目・2年目・3年目、そして今回と聞いていますが、多分、お話の内容は同じようなものですが受け取る私の気持ちの変化があったのか、なんだか今までとは違うものを感じました
そして、最後に話をされた『ヘルパーセラピー』という言葉が心に残りました
ピアサポーター活動を続けている方が、実は自分が元気をもらっていると言われていたということです
私も、自分の状況が悪くても私を励ましてくれていた人を沢山みてきたから、その気持ちってわかるって思った。人が自分以外の人を思いやることって実はとても難しいと思います
ましてやそれが、自分も体調が悪い時はわかっていても自分のつらさが優先な気がします
でも、そんな状況でも励ましてくれる人はいる。それってすごいなって思った
会社のもめごとが起きた時に、ずっと言われていた言葉があります
『私は大丈夫だから』でした
同じ職種の人に、私は大丈夫だから。と言われるたびに大丈夫だと思えない自分自身がとても惨めに思えた
それは、今までもあるけれど本当に大変だから相談している時に言われると、これほどつらい言葉ってないなって思った
『私は大丈夫だから』は、本当は、全否定なんだと思った
私は大丈夫なのに、なぜあなたはそう思えないの。と言っているんだと感じた
相手の事がわかる完全なピアサポーターっていないと思う
でも、一生懸命相手を理解しようとしてくれていることは相手にも通じる気がしました
そして、今回、病院の入院中にお世話になった患者会の方と話をすることで早い段階でのピアサポーターがとても大切なんだと思いました。自分の目指す姿を入院中に知ることで、患者になった自分でも患者さんのために何かができるということが形としてわかる気がします
その時は、具体的に見えていなくても、段々と形ができていく部分もあるし・・・
私のように4年目がきて、やっと形がわかってきたかな?って人もいます
あせらずに、一歩一歩、歩いていけたらいいなって思っています
2013年03月21日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │がんとこころ
怒る私?
私の病気のことを知っている会社の上司に告知の時の話をしました
そして「今の医療現場では、どんなに最悪な事でも伝えるんだよ」というのも話した
告知のあと、K大学病院の医師に「40すぎたら子宮はいらないでしょ」と言われて「先生、何いってるんですか。この病院にも不妊治療の患者さんが沢山きてるでしょ」と言った話をしました
上司には「先生にも怒ってたんだ~~」と笑いながら言われて、怒ってる?
う~~ん、これって「怒っている」なのかな?って思った
怒るって感情のままにいうことなんじゃないのかな?
まあ、確かにハラワタは煮えくり返るくらいに怒っているけれど、かなり理性的な言葉だと思うんだけど・・・と思った
告知される前からだったけれど、基本的に頭のどこかで冷めている気がする。
告知を聞いた時に「今日は皮膚科に行かなきゃ」って考えていたり「これで親との関係が変化するのかな?」とか「少しほっとした自分」も感じました
がんで死ぬのなら、それも自分の人生なのかな・・・と思ったし・・・
唯一の後悔は「もう、これで本当に子どもは産めないんだな」っていうことでした
でも、もしも子どもがいてがん患者になったら大変だったから、そう考えればよかったのかなって思ったし「いいこと」と「悪いこと」のどちらも考えていました
結構、みんな冷静なんじゃないのかな??
でも「怒る人」って思われるのは、ちょっと嫌だな・・・
そして「今の医療現場では、どんなに最悪な事でも伝えるんだよ」というのも話した
告知のあと、K大学病院の医師に「40すぎたら子宮はいらないでしょ」と言われて「先生、何いってるんですか。この病院にも不妊治療の患者さんが沢山きてるでしょ」と言った話をしました
上司には「先生にも怒ってたんだ~~」と笑いながら言われて、怒ってる?
う~~ん、これって「怒っている」なのかな?って思った
怒るって感情のままにいうことなんじゃないのかな?
まあ、確かにハラワタは煮えくり返るくらいに怒っているけれど、かなり理性的な言葉だと思うんだけど・・・と思った
告知される前からだったけれど、基本的に頭のどこかで冷めている気がする。
告知を聞いた時に「今日は皮膚科に行かなきゃ」って考えていたり「これで親との関係が変化するのかな?」とか「少しほっとした自分」も感じました
がんで死ぬのなら、それも自分の人生なのかな・・・と思ったし・・・
唯一の後悔は「もう、これで本当に子どもは産めないんだな」っていうことでした
でも、もしも子どもがいてがん患者になったら大変だったから、そう考えればよかったのかなって思ったし「いいこと」と「悪いこと」のどちらも考えていました
結構、みんな冷静なんじゃないのかな??
でも「怒る人」って思われるのは、ちょっと嫌だな・・・
2013年03月13日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(2) │がんとこころ
病気の真実を知ることの意味~告知~
病気の真実を知ることの意味-インフォームド・コンセントとは-
真実を知っていることはいかに大切か
1:自分の病気の正確な情報を得ることで、いたずらな不安を抱かずに済む
2:医者や家族に疑念を抱くことがなく、心底信じることができる
3:隠し事がないので、何事を率直に聞きやすいし、答えやすい
4:精神的につらい時期に、医師、看護師、家族の精神的援助を得やすい
5:医師と診断から終末期までトータルなつきあいができる
6:事実を知らされないまま不本意な治療をうけることがきる
7:自分の人生観、死生観、価値観に基づいて治療法の選択ができる(無治療の洗濯も含めて)
8:病院や医師を選ぶことができる
9:治療後の人生設計を行える
10:病気や治療をよく理解していることで、治療に伴う一時的な苦痛を耐え抜くことができる
11:再発した場合も、何も知らなかった場合より衝撃が少ない
12:病気を契機に、生死の問題を考え直すことができる。「いかに生きるか」
13:病気を完治する希望がなくなった時点でも、生きる希望をもつことができる
14:突然「がん」という病名だけ知ってしまうという「最悪の事態」の心配がない。
このきわめて危険な事態がいつおこるかわからないのが告知を受けていない患者さんを取り巻く現状である。→治療法や薬からカルテや診断書から聞こえてしまった聞いてはいけない話、家族がつらくなって話してしまう・・・
がん告知というと、とても大変なことだと思いますがふと自分の事を冷静に考えてみると、そうすぐに「死ぬ」と考えてなかった気がします
一番最初は(町の産婦人科で検査をして大学病院を紹介してもらいました)、むしろ告知された後で「この後、皮膚科に行きます」と先生に言って「何言っているの、今からすぐに紹介状をかくからK大学病院に行って」と言われました。その先生は、とっても優しくてわざわざ病院からバス停まで教えてくれました。そこまで、驚いてはいないんだけどな~と思ったのを覚えています
自分の「死」について考えたのは、もう少し後だったと思います
それよりは検査の結果がでるのがあまりにも長くて、その事が精神的負担が大きかったです
今の私が言えるのは、人はそんなに弱くはない。ということです
どんな病気であっても、向き合える強さを持っているものだと思っています
むしろ、嘘をついたら家族も負担になるし、相手の嘘がわかっている患者もつらいと思います。そして、それが偶然、本当に最悪な事態だと知ってしまったらもっとつらいと思う。それは「優しい嘘」だとわかっていてもだと思います
告知の内容よりも、告知の方法。が大切なのだと思う私でした
「何を伝えるか」ではなく「どう伝えるか」なんじゃないのかな。。。
第4回 市民公開講演会「がんについて」
病気の真実を知ることの意味-インフォームド・コンセントとは-
http://www.ncc.go.jp/jp/ncch/division/lecture/19971025.html
真実を知っていることはいかに大切か
1:自分の病気の正確な情報を得ることで、いたずらな不安を抱かずに済む
2:医者や家族に疑念を抱くことがなく、心底信じることができる
3:隠し事がないので、何事を率直に聞きやすいし、答えやすい
4:精神的につらい時期に、医師、看護師、家族の精神的援助を得やすい
5:医師と診断から終末期までトータルなつきあいができる
6:事実を知らされないまま不本意な治療をうけることがきる
7:自分の人生観、死生観、価値観に基づいて治療法の選択ができる(無治療の洗濯も含めて)
8:病院や医師を選ぶことができる
9:治療後の人生設計を行える
10:病気や治療をよく理解していることで、治療に伴う一時的な苦痛を耐え抜くことができる
11:再発した場合も、何も知らなかった場合より衝撃が少ない
12:病気を契機に、生死の問題を考え直すことができる。「いかに生きるか」
13:病気を完治する希望がなくなった時点でも、生きる希望をもつことができる
14:突然「がん」という病名だけ知ってしまうという「最悪の事態」の心配がない。
このきわめて危険な事態がいつおこるかわからないのが告知を受けていない患者さんを取り巻く現状である。→治療法や薬からカルテや診断書から聞こえてしまった聞いてはいけない話、家族がつらくなって話してしまう・・・
がん告知というと、とても大変なことだと思いますがふと自分の事を冷静に考えてみると、そうすぐに「死ぬ」と考えてなかった気がします
一番最初は(町の産婦人科で検査をして大学病院を紹介してもらいました)、むしろ告知された後で「この後、皮膚科に行きます」と先生に言って「何言っているの、今からすぐに紹介状をかくからK大学病院に行って」と言われました。その先生は、とっても優しくてわざわざ病院からバス停まで教えてくれました。そこまで、驚いてはいないんだけどな~と思ったのを覚えています
自分の「死」について考えたのは、もう少し後だったと思います
それよりは検査の結果がでるのがあまりにも長くて、その事が精神的負担が大きかったです
今の私が言えるのは、人はそんなに弱くはない。ということです
どんな病気であっても、向き合える強さを持っているものだと思っています
むしろ、嘘をついたら家族も負担になるし、相手の嘘がわかっている患者もつらいと思います。そして、それが偶然、本当に最悪な事態だと知ってしまったらもっとつらいと思う。それは「優しい嘘」だとわかっていてもだと思います
告知の内容よりも、告知の方法。が大切なのだと思う私でした
「何を伝えるか」ではなく「どう伝えるか」なんじゃないのかな。。。
第4回 市民公開講演会「がんについて」
病気の真実を知ることの意味-インフォームド・コンセントとは-
http://www.ncc.go.jp/jp/ncch/division/lecture/19971025.html
2013年03月11日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │がんとこころ
死を考える
死を
三人称(彼ら/彼女ら)の観点から
ヒトの肉体が活動を停止したことと
とらえているかぎり、
死について考えたことにはならない。
これは科学技術の立場から見た死である。
死について考えるとは
心の問題なのであり、
身体の問題なのではない。
http://mag.gto.ac.jp/cat8/cat9/post-5.html
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以前、インド人と一緒に働いたことがあります
ある日、彼が『父親が危篤なのでインドに帰る』と言いました
彼が帰ってから、しばらくしてお父さんが亡くなったという知らせが入りました
それから、待てど暮らせど彼が帰ってこない・・・
システムエンジニアの彼がいないと納期が間に合わない。という事で、インドの会社に何度も連絡しているんだけれど、一向に彼からの連絡はないし・・・
しばらくして、インドから別のエンジニアが着ました
その時に『インドでは身内が亡くなる2週間くらい前から仕事を休んで、なくなってからも仕事を休むのが当たり前なのに、日本人はなんでそれが待てない』と言われました
その時は、文化の違いはわかるけれど、えええ~~~、じゃあ納期は~~~~って思った
でも今になると、大切な人の死を受け入れるって、そういうものなのかなって思う
昔は、初七日も四十九日もちゃんとやっていた気がします
それが、今はほとんど一緒くたになってしまいました
せっかちに生きている日本人は、死を受け入れるのに必要な時間までも早回しにしているみたいな気がします
三人称(彼ら/彼女ら)の観点から
ヒトの肉体が活動を停止したことと
とらえているかぎり、
死について考えたことにはならない。
これは科学技術の立場から見た死である。
死について考えるとは
心の問題なのであり、
身体の問題なのではない。
http://mag.gto.ac.jp/cat8/cat9/post-5.html
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以前、インド人と一緒に働いたことがあります
ある日、彼が『父親が危篤なのでインドに帰る』と言いました
彼が帰ってから、しばらくしてお父さんが亡くなったという知らせが入りました
それから、待てど暮らせど彼が帰ってこない・・・
システムエンジニアの彼がいないと納期が間に合わない。という事で、インドの会社に何度も連絡しているんだけれど、一向に彼からの連絡はないし・・・
しばらくして、インドから別のエンジニアが着ました
その時に『インドでは身内が亡くなる2週間くらい前から仕事を休んで、なくなってからも仕事を休むのが当たり前なのに、日本人はなんでそれが待てない』と言われました
その時は、文化の違いはわかるけれど、えええ~~~、じゃあ納期は~~~~って思った
でも今になると、大切な人の死を受け入れるって、そういうものなのかなって思う
昔は、初七日も四十九日もちゃんとやっていた気がします
それが、今はほとんど一緒くたになってしまいました
せっかちに生きている日本人は、死を受け入れるのに必要な時間までも早回しにしているみたいな気がします