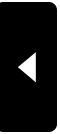スポンサーリンク
ガミガミな私

ここのところ自分の中にこんな猫がいるのに気がついています
『ガミガミ、ガミガミ・・・・・』言いたくないし、知らん顔していたいけれど
あ~あ、と思いながら言ってしまう自分がいます
これを日曜日の夜に塗ってみて「明日は、仕事だわ」って思うと、ちょっと楽になりました
でも、今日もまたちょっと怒ってました。。。

2012年11月07日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │カラーセラピー
「子どもを傷つける親 癒す親」・・・2

「子どもを傷つける親 癒す親―シスター鈴木秀子の親と子の愛の絆12のステージ
問題は子どもにではなく、心配し、不安を抱える親にある。まず、親である自分が変わること。本の中の様々な事例が、自分の問題に気づき、子どもに対する考え方、対応の仕方を変えさせ、愛を深める助けとなる。・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
暗い夜道で、暴漢に襲われそうになった女性がいます
彼女は、通りがかった大学生に助けてもらい事なきを得たけれど
彼女を心配して、一緒に帰ってくれているその男性にも恐怖を覚えてしまいそうになりました
そんな彼女を、彼女のお父さんとお母さんが何も言わずに迎えてくれたそうです
人心地ついた彼女に、お父さんが
「覚えておきなさい。今日は何事もなくてよかった。
人間は人間として一人ひとり大切なのだが、世の中には悪い行動をする人もいる。また、いろいろな状況から悪い行動に走ってしまう人たちもいる。
けれども、男の人が、全部そういうようなことをするというわけではない。
だから人間に対する信頼を失ってはだめだ。人間はすべての人がいつも正しいことをするとは限らないということを、頭にしっかりと覚えておきなさい。と同時に人間は信頼に足る人たちだということも肝に銘じておきなさい。
一人ひとり人間としての存在が大切なんだ。けれども、いろいろな事情があったり、気がむしゃくしゃしていたりすると、よくない行動にも走りがちになる。それが人間だ。
世の中に出て行けば、よくない行動をする人にも会うことがあるだろう。
しかし、そういう行動をする人を見て、すべての男の人が全部そうだというわけではないことをはっきり覚えておくがいい。
そして、自分でしっかりと状況を判断して、自分で自分の行動に責任を持って、自分で身を守っていくということに、頭を働かせる必要がある。」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
昔、仕事帰りに中央線に乗っているとちょっと「変な人」がいました
彼は、私の真後ろに立っていたんですが、なんとも言えない妙な違和感を感じました
それで、私は彼が立っていた出入り口の反対側に移動して、彼を見ていました
私が降りる2つ前に駅で、若い女性が乗ってきました
その時にも、何となく「嫌な予感」がしたけれど、彼女はそのまま彼の前に立っていました
駅に着く少し前に、男性が急に彼女に「すみません、すみません」と言って頭を下げました
「ええ?」って彼女が言って驚いていると、電車が駅に着きました
彼女は私と同じ駅で降りました
すると、彼女が降りた瞬間に、その男性が彼女を飛び蹴りしました
びっくりした私と、前のめりに倒れこむように座り込んだ彼女・・・
とっさに「何やっての!!」とどなっていた私でした
私の声に反応したのかわからないけれど、全速力でホームの端に走っていった彼を見てから
慌てて彼女に駆け寄ると、身体が大きく震えていました
ホームには、彼女と外国人のカップルと私だけで他の人は誰もいませんでした
彼女と一緒に改札口を出て行く時も、震えていた彼女を見て「一緒にいてあげたいけれど
友達と約束してるから、ごめんね」と言いました
「大丈夫です」と言いながら震えていた彼女の事を思い出すと「ちゃんと電車に乗ってるかな?」
「無事に仕事に行ってるかな?」って思います
あの時、せめて家まで一緒に帰ってあげるなり、お茶でも飲んであげればよかったかなって思います
そして彼女にも、こんなお父さんがいたらなって思う私でした
「みんなが同じではない」というのは、理屈ではわかります
でも、やっぱりこんな体験をしてしまうと恐怖が残ってしまうそうです
ちなみに、私はその後、電話で母にこの事を言ったら「あんたは何をやってんの!そんな事言って刺されたらどうすんの!」と、こっぴどく怒られてました。。。

2012年11月06日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(2) │読んだ本・・・エニアグラム
病院別がん5年生存率 数字だけで病院を選ぶのは危険?
病院別がん5年生存率 数字だけで病院を選ぶのは危険?〈週刊朝日〉
がんの治療を受けるとき、「病院によって生存率が3割以上違う」と聞けば、生存率の高い病院を選びたくなるのが人情だろう。全国がんセンター協議会は10月22日、がん診療を受けた患者の、病院と部位ごとの5年生存率などを発表した。このデータをどう見れば、「いい病院」を選べるだろうか。
今回のデータは、全国のがん診療の中核的な役割を担う28病院を対象にしたもの。それでも、がんの5年生存率のトップの病院と最下位で比べると、胃がんで24ポイント、肺がんで33.3ポイントといった大きな差になった。
だが、この数字だけで病院を選ぶのは、早計である。
発表されたデータは生存率だけではない。今回発表された「1期/4期比」という数字も重要だ。
この数字は、最も早期の1期と最も進行した4期のがん患者数の比だ。この数字が大きいほど、「早期患者が多い」ことになる。逆に小さいと、がんが進行した患者を多く診療していることになり、生存率は悪くなりやすい。
最もわかりやすい結果が出ているのは、胃がんの生存率だ。トップの大阪府立成人病センターの生存率は80.2%で1期/4期比は6.5と高く、早期の患者が多いことがわかる。一方で生存率最下位の茨城県立中央病院は56.2%だが、1期/4期比は1.9と小さい。胃がんは進行の度合いによって、生存率が大きく変化してくるため、強い相関関係が出ている。
また、全体の傾向として、がん治療に特化する「がんセンター」が上位にランクインする一方、県立病院が下位に低迷しているのがわかる。これは、それぞれの病院が置かれた状況が異なるためだ。
今回の調査結果をまとめた、千葉県がんセンターがん予防センターの三上春夫部長がこう話す。
「がん治療に特化した病院は早期にがんを発見して、治療できるインフラがしっかりしている。さらに、医療機関同士の連携がうまく機能していると考えられる。一方、県立病院は、重度のがん患者や行き場のない患者を積極的に受け入れているので、どうしても生存率が低くなってしまう。だから、上位グループと下位グループの治療技術の差は小さいだろう」
※週刊朝日 2012年11月9日号
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20121103-00000000-sasahi-ent
がんの治療を受けるとき、「病院によって生存率が3割以上違う」と聞けば、生存率の高い病院を選びたくなるのが人情だろう。全国がんセンター協議会は10月22日、がん診療を受けた患者の、病院と部位ごとの5年生存率などを発表した。このデータをどう見れば、「いい病院」を選べるだろうか。
今回のデータは、全国のがん診療の中核的な役割を担う28病院を対象にしたもの。それでも、がんの5年生存率のトップの病院と最下位で比べると、胃がんで24ポイント、肺がんで33.3ポイントといった大きな差になった。
だが、この数字だけで病院を選ぶのは、早計である。
発表されたデータは生存率だけではない。今回発表された「1期/4期比」という数字も重要だ。
この数字は、最も早期の1期と最も進行した4期のがん患者数の比だ。この数字が大きいほど、「早期患者が多い」ことになる。逆に小さいと、がんが進行した患者を多く診療していることになり、生存率は悪くなりやすい。
最もわかりやすい結果が出ているのは、胃がんの生存率だ。トップの大阪府立成人病センターの生存率は80.2%で1期/4期比は6.5と高く、早期の患者が多いことがわかる。一方で生存率最下位の茨城県立中央病院は56.2%だが、1期/4期比は1.9と小さい。胃がんは進行の度合いによって、生存率が大きく変化してくるため、強い相関関係が出ている。
また、全体の傾向として、がん治療に特化する「がんセンター」が上位にランクインする一方、県立病院が下位に低迷しているのがわかる。これは、それぞれの病院が置かれた状況が異なるためだ。
今回の調査結果をまとめた、千葉県がんセンターがん予防センターの三上春夫部長がこう話す。
「がん治療に特化した病院は早期にがんを発見して、治療できるインフラがしっかりしている。さらに、医療機関同士の連携がうまく機能していると考えられる。一方、県立病院は、重度のがん患者や行き場のない患者を積極的に受け入れているので、どうしても生存率が低くなってしまう。だから、上位グループと下位グループの治療技術の差は小さいだろう」
※週刊朝日 2012年11月9日号
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20121103-00000000-sasahi-ent
2012年11月05日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん
「子どもを傷つける親 癒す親」・・・1

「子どもを傷つける親 癒す親―シスター鈴木秀子の親と子の愛の絆12のステージ
問題は子どもにではなく、心配し、不安を抱える親にある。まず、親である自分が変わること。本の中の様々な事例が、自分の問題に気づき、子どもに対する考え方、対応の仕方を変えさせ、愛を深める助けとなる。・・・・
いつものように、電車の中でこの本を読んでいました
鈴木秀子先生は「エニアグラムの先生」のイメージだったのですが
実は、シスターだそうで「子育て本」も沢山書かれています
その中で、いいな~~と思ったのを書いておきます
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
中学生の男の子が、ムシャクシャして部屋で生きたカマキリの手足をもいでいた時でした
偶然、部屋の外を通りかかったお父さんが彼に言った言葉です
「和夫、人間には誰にもそういう残酷な面があるんだよね。
お父さんだって会社の中でむしゃくしゃしたとき、お前みたいにやったら、
気持ちいいだろうと思うことがあるよ。
人間は自分の中にいたたまれないぐらいもやもやがたまってくると、
それを発散させてすっきりしたいために、普段は眠っている残酷な面が姿を現してくるんだよね。
人間の中にそういう残酷な面があるということを、いまのうちに、お前、気づいてよかったね。
もしも、人間は自分の中には残酷な面なんか何もないんだと、自分の残酷さに気づかないでいると、人は何をしでかすかわからない。
残酷な面があるということを知ってさえいれば、それがひょいと頭をもたげたときに、
それに乗っ取られて暴力や残酷なひどい行為に突っ走らないですむ。
「ああ、俺の中にもそういう面があるんだ」ということをいち早く捉えると、
「でも、これをやったらまずいぞ」という感覚が働きだすんだ。
人間はバランスをとって、本能的に自分のいちばんいい生き方をしようとするものなんだ。
だからそういう残酷さが自分の中にあることをいうことを知っていさえすれば、
それが頭をもたげたときには、それに乗っ取られて、結局後で辛い思いをするより、
自分をコントロールして、もっといい方法で自分の鬱積した気持ちを発散しようと本能的に
バランスをとるものなんだよ。
和夫は今それに気づいてよかったね。」
和夫さんにはドアを出て行く父親の背中が大きく見えたそうです。
「私はその体験から、自分がとことん落ち込んだり、とことん偏っていったり、破滅的な力に引きずられそうになったときには、あの大きな父の背中を思い出します。
そして自分でバランスをとる力が、あのとき以来与えられていることに感謝しています」
読み終えた時に、ふと涙ぐみそうになっていました
子どもの頃、私もアリやコウロギの足をちぎった経験があります
その時、コウロギに手を咬まれて血がでて「痛い
 」って思った
」って思ったそしたら、なんか怖くなって止めよう・・・って思いました
子どもって、大人が考えるよりも残酷な面を持っていたりします
それを直接見てしまうと「ぎょっ」とするかもしれません
でも、「怒る」よりも大切な事がある気がします
そして、子どもなりの感覚で受け止めれる気がします
もっと小さい子どもでも、きちんと説明をすればわかる気がします
でも、その時にどの言葉で伝えるかで、その子のその後も変化するような気がします
2012年11月04日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・エニアグラム
子どものアレルギーショック、低い母の認識
子どものアレルギーショック、低い母の認識-ファイザー調査で判明
食物アレルギーのある子どもを持つ母親の9割近くが、重篤なアレルギー反応による血圧低下などで死亡することもある「アナフィラキシーショック」を、自分の子どもが起こす可能性は高くないと考えていることが、ファイザーの実施した食物アレルギー認識調査で明らかになった。また、約7割の母親が補助治療薬のアドレナリン自己注射を「知らない」と答えるなど、アレルギーによるショック症状への備えや認識が十分浸透していないことも、同調査で浮き彫りになった。
この調査は、9月10日から2日間、小学1年生から6年生までの食物アレルギーと診断された子どもを持つ母親と、症状のない子どもを持つ母親、それぞれ824人、計1648人を対象にインターネットを通じて実施した。
アナフィラキシーショックについての認識を問う質問に対して、食物アレルギーがある子どもの母親のうち、76.1%に当たる627人が「どのような症状のことをいうのか説明できる」と回答。症状への関心が高い一方で、自分の子どもが食物アレルギーでアラフィラキシーショックを起こす可能性について聞くと、「可能性が高いと思う」との答えは102人(12.4%)にとどまった。「可能性は低いと思う」は459人(55.7%)、「可能性はない」は136人(16.5%)、「分からない」は127人(15.4%)で、自分の子どもが発症する可能性は高くないと考える母親が全体の9割近くを占めた。
今回の調査結果について、国立病院機構相模原病院臨床研究センターの海老澤元宏・アレルギー性疾患研究部長は、「小学生で食物アレルギーを持つ人は誰でもアナフィラキシーを発現する可能性がある。補助治療薬のアドレナリン自己注射を所持することが、有用な自己防衛の方法になる。2011年に自己注射が保険適用されたが、海外に比べてまだまだ浸透していない。日本でも今後、広く浸透していくことを望む」とコメントした。【新井哉】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121101-00000000-cbn-soci
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
手術後、食物アレルギー持ちになってしまった私は、生まれてすぐに「敗血症」になりました
その理由が「しっしん」でした
私が生まれてすぐに撮られた写真を見ると「全身、真っ白け」の赤ちゃんが写っています
残念ながら、白黒写真なんですでに白黒の区別というよりは「セピア色」になっていますが・・・
以前、年配の看護婦さんに病歴を聞かれて「アトピー」と言って、いつからと聞かれて
生まれてすぐにというと「生まれてすぐに赤ちゃんは、お母さんの免疫があるからアトピーになんてならないから違う」と言われたことがありますが、実際に、アトピー(しっしん)からばい菌が入って敗血症を併発しました
そんなアレルギー持ちの私としては、色んなものが食べれなかったりできなかったりしました
一番最初(幼稚園まで)は、卵と小麦粉に牛乳でした
でも、母が「小学校に行ったら、なんでも食べなさい」と家では食べてはいけないものも残さずに食べるように言われて「何か変」と思っていても、子どもの私にはどうすることもできなかったので給食は食べていました
ただ、その3つは牛乳を飲むとお腹をこわすくらいで無事でしたが、その後に禁止と言われていた「カレーとチョコレート(刺激物)」は、かなり厳しかったです
カレーもチョコも食べてしばらくすると体中がかゆくなるので、授業中もイライラするし掻きたいし・・・
でも「掻いちゃだめ」って言われるから、余計にイライラ・・・
今でも母のように「掻いちゃだめ」って言う人に出会うと、正直ムッとします
どんだけ痒いかしらんやろ!!て思う私です
そんなカレーもチョコも無事に収まったけれど、長期の花粉症とアトピー性皮膚炎も相変わらずです
そして、手術後にでるわでるわでてきたのが「食べ物アレルギー」です
手術後、3日目か4日目にきた「さくらんぼ」を皮入りに、すもも、りんご、梨と「りんごの花のアレルギー」がやってきて、その後で大豆かな?豆乳アレルギーに、そら豆に今週は、とうとう「イチジク」まで・・・
でも、駄目でも好きなものが多いから「死なないから食べる」と言ってたんだけれど・・・
ちょっと怖いのかなって思い始めた私です
食物アレルギーのある子どもを持つ母親の9割近くが、重篤なアレルギー反応による血圧低下などで死亡することもある「アナフィラキシーショック」を、自分の子どもが起こす可能性は高くないと考えていることが、ファイザーの実施した食物アレルギー認識調査で明らかになった。また、約7割の母親が補助治療薬のアドレナリン自己注射を「知らない」と答えるなど、アレルギーによるショック症状への備えや認識が十分浸透していないことも、同調査で浮き彫りになった。
この調査は、9月10日から2日間、小学1年生から6年生までの食物アレルギーと診断された子どもを持つ母親と、症状のない子どもを持つ母親、それぞれ824人、計1648人を対象にインターネットを通じて実施した。
アナフィラキシーショックについての認識を問う質問に対して、食物アレルギーがある子どもの母親のうち、76.1%に当たる627人が「どのような症状のことをいうのか説明できる」と回答。症状への関心が高い一方で、自分の子どもが食物アレルギーでアラフィラキシーショックを起こす可能性について聞くと、「可能性が高いと思う」との答えは102人(12.4%)にとどまった。「可能性は低いと思う」は459人(55.7%)、「可能性はない」は136人(16.5%)、「分からない」は127人(15.4%)で、自分の子どもが発症する可能性は高くないと考える母親が全体の9割近くを占めた。
今回の調査結果について、国立病院機構相模原病院臨床研究センターの海老澤元宏・アレルギー性疾患研究部長は、「小学生で食物アレルギーを持つ人は誰でもアナフィラキシーを発現する可能性がある。補助治療薬のアドレナリン自己注射を所持することが、有用な自己防衛の方法になる。2011年に自己注射が保険適用されたが、海外に比べてまだまだ浸透していない。日本でも今後、広く浸透していくことを望む」とコメントした。【新井哉】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121101-00000000-cbn-soci
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
手術後、食物アレルギー持ちになってしまった私は、生まれてすぐに「敗血症」になりました
その理由が「しっしん」でした
私が生まれてすぐに撮られた写真を見ると「全身、真っ白け」の赤ちゃんが写っています
残念ながら、白黒写真なんですでに白黒の区別というよりは「セピア色」になっていますが・・・
以前、年配の看護婦さんに病歴を聞かれて「アトピー」と言って、いつからと聞かれて
生まれてすぐにというと「生まれてすぐに赤ちゃんは、お母さんの免疫があるからアトピーになんてならないから違う」と言われたことがありますが、実際に、アトピー(しっしん)からばい菌が入って敗血症を併発しました
そんなアレルギー持ちの私としては、色んなものが食べれなかったりできなかったりしました
一番最初(幼稚園まで)は、卵と小麦粉に牛乳でした
でも、母が「小学校に行ったら、なんでも食べなさい」と家では食べてはいけないものも残さずに食べるように言われて「何か変」と思っていても、子どもの私にはどうすることもできなかったので給食は食べていました
ただ、その3つは牛乳を飲むとお腹をこわすくらいで無事でしたが、その後に禁止と言われていた「カレーとチョコレート(刺激物)」は、かなり厳しかったです
カレーもチョコも食べてしばらくすると体中がかゆくなるので、授業中もイライラするし掻きたいし・・・
でも「掻いちゃだめ」って言われるから、余計にイライラ・・・
今でも母のように「掻いちゃだめ」って言う人に出会うと、正直ムッとします
どんだけ痒いかしらんやろ!!て思う私です
そんなカレーもチョコも無事に収まったけれど、長期の花粉症とアトピー性皮膚炎も相変わらずです
そして、手術後にでるわでるわでてきたのが「食べ物アレルギー」です
手術後、3日目か4日目にきた「さくらんぼ」を皮入りに、すもも、りんご、梨と「りんごの花のアレルギー」がやってきて、その後で大豆かな?豆乳アレルギーに、そら豆に今週は、とうとう「イチジク」まで・・・
でも、駄目でも好きなものが多いから「死なないから食べる」と言ってたんだけれど・・・
ちょっと怖いのかなって思い始めた私です
2012年11月03日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │その他・・・病気
誰かのせい

誰かがなんとかしてくれると思わない方が賢明。
生き方としても、仕事をする姿勢としても、誰かが何とかしてくれる、または、誰々が何々をしてくれない、という考え方をしない方がいいようです。自分でやる。できないときに自分のせいだと考えることができるかどうかで、一人前の企業人、仕事人になれるかどうかが決まります。
最近、仕事の事でちょっとイライラしています
「誰かのせい」にするよりも「自分のせい」と思って欲しいなと思う時がある
病気になって仕事を始めて考えたことが「善きサマリア人の法」だった
善きサマリア人の法は、「災難に遭ったり急病になったりした人など(窮地の人)を救うために無償で善意の行動をとった場合、良識的かつ誠実にその人ができることをしたのなら、たとえ失敗してもその結果につき責任を問われない」という趣旨の法である。誤った対応をして訴えられたり処罰を受ける恐れをなくして、その場に居合わせた人による傷病者の救護を促進しよう、との意図がある。・・・Wikipediaより
これって、仕事も同じような気がします
私は基本的には、自分の上司以外に間違えた事を言われても文句は言わない。相手だって貴重な時間を割いてくれたわけだし、そもそも聞いた自分が悪い訳だし、それに文句を言うのは、間違いだと思っています
それを責めていたら自分もイライラするし、第一、一所懸命言ってくれた相手に申し訳ないかな。
といっても、神ではないので、ちょっとは怒ってますが。。。
誰かがなんとかしてくれると思わない方が賢明の全文は、こちらです
http://www.caput.co.jp/staff/message_of_women/soho_kennmei.html
2012年11月02日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │その他
低出生体重児への「手あて」 落ち着かせる効果、科学的に証明
低出生体重児への「手あて」 落ち着かせる効果、科学的に証明
■脳の血流が大幅に抑えられる
出生時の体重が2500グラム未満の「低出生体重児」。NICU(新生児集中治療室)で過ごす赤ちゃんたちは、検査のための採血など不快な刺激にさらされることも少なくない。そんなとき、医療者が赤ちゃんの全身を両手で包み込む「手あて」を行ったところ、通常は痛み刺激に対して増加する脳の血流が大幅に抑えられていることが、近畿大学医学部付属病院リハビリテーション部理学療法士、本田憲胤(のりつぐ)さんらの研究で分かった。スキンシップの効能を科学的に裏付けることとなった研究に注目が集まっている。(岸本佳子)
◆リスクを軽減
この研究は、同病院内で10人の赤ちゃんを対象に行われた。10人はいずれも低出生体重児で、平均週数36・2週の赤ちゃんたち。
ミルクを飲み終わって、よく眠っている赤ちゃんたちに、近赤外線を利用して脳の血流の変化を測る装置「光トポグラフィ」を装着。左右のかかとに1秒間ずつ、感覚検査で使われる「知覚針」を使って刺激を与えた。その際、知覚針を当てる1分前から、両手で全身を包み込む「手あて」を行い、そのままの状態で刺激を与えた場合と「手あて」をせずに刺激を与えた場合のデータを計測した。
その結果、手あてが行われなかったケースでは、痛み刺激が与えられた直後から血流が大きく増加。一方、大人に両手で全身を包み込んでもらった場合には大きな血流の増減が見られなかった。両群の平均値の比較では、最大で約10倍の開きが見られたという。
研究を行った本田さんによると、一般的に低出生体重児において、疼痛(とうつう)刺激が繰り返されることによる脳の血流の頻繁な増減は、脳の発達には好ましくない影響を与えると考えられている。
「赤ちゃんに『手あて』をすることで、そのリスクを軽減させることができるということが明らかになった」(本田さん)
◆環境の改善に
低出生体重児が過ごすNICUはさまざまな合併症を避けるため、高度な医療が行われている。ただ、赤ちゃんにとってはお母さんの胎内とは大きく異なり、決して快適とはいえない環境だという。
「人工呼吸器のアラーム音、保育器を開閉する音、医療スタッフの足音、引き出しの開閉音。それに1日数回の採血もあります」と本田さん。そのため、赤ちゃんが泣いたり、手足をばたつかせて落ち着かなかったりといった状況に陥ることも少なくない。
そんなとき、理学療法士としてNICUで赤ちゃんに接してきた本田さんは、看護師たちが赤ちゃんを安心させようと、習慣的に体にそっと手をあてることで赤ちゃんが落ち着く様子を何度か見てきた。それが今回の研究に結びついた。
本田さんは「痛みが予想される採血などの場合であれば、その少し前から手あてをしてあげるだけで、赤ちゃんをめぐる環境がぐんと良くなる。NICUではなかなか難しい部分もあるが、手あての良さが認識され、広がってほしい」と話している。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121031-00000525-san-soci
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「手あて」とは、よく言ったな~~って思います
手術後、なかなかお腹の痛みが取れなかった私に友達のお母さん(元看護婦)が
「これ、使いなさい」とレンジでチンして温める「ゆたぽん」を貸してくれました
少し温めるだけで、随分とお腹の痛みがよくなるのでびっくりしました
その後、放射線治療で入院した時には、病棟の「ゆたぽん」を貸し出ししてもらっていました
「湯たんぽ」もいいけれど、冷めてしまうと温めるのも大変だし
何より、体調が悪い時に熱湯を扱うのってちょっと不安です
それに「ゆたぽん」は、レンジがあれば会社でも使えるので便利です
本当は、お母さんの手があったらいいのに~と思うけれど、それは無理なので・・・
でも「手あて」が本当なら、おばあちゃんが漬けた梅干しが美味しい理由も
科学的に証明される日もくるのかな?なんて思った私でした
■脳の血流が大幅に抑えられる
出生時の体重が2500グラム未満の「低出生体重児」。NICU(新生児集中治療室)で過ごす赤ちゃんたちは、検査のための採血など不快な刺激にさらされることも少なくない。そんなとき、医療者が赤ちゃんの全身を両手で包み込む「手あて」を行ったところ、通常は痛み刺激に対して増加する脳の血流が大幅に抑えられていることが、近畿大学医学部付属病院リハビリテーション部理学療法士、本田憲胤(のりつぐ)さんらの研究で分かった。スキンシップの効能を科学的に裏付けることとなった研究に注目が集まっている。(岸本佳子)
◆リスクを軽減
この研究は、同病院内で10人の赤ちゃんを対象に行われた。10人はいずれも低出生体重児で、平均週数36・2週の赤ちゃんたち。
ミルクを飲み終わって、よく眠っている赤ちゃんたちに、近赤外線を利用して脳の血流の変化を測る装置「光トポグラフィ」を装着。左右のかかとに1秒間ずつ、感覚検査で使われる「知覚針」を使って刺激を与えた。その際、知覚針を当てる1分前から、両手で全身を包み込む「手あて」を行い、そのままの状態で刺激を与えた場合と「手あて」をせずに刺激を与えた場合のデータを計測した。
その結果、手あてが行われなかったケースでは、痛み刺激が与えられた直後から血流が大きく増加。一方、大人に両手で全身を包み込んでもらった場合には大きな血流の増減が見られなかった。両群の平均値の比較では、最大で約10倍の開きが見られたという。
研究を行った本田さんによると、一般的に低出生体重児において、疼痛(とうつう)刺激が繰り返されることによる脳の血流の頻繁な増減は、脳の発達には好ましくない影響を与えると考えられている。
「赤ちゃんに『手あて』をすることで、そのリスクを軽減させることができるということが明らかになった」(本田さん)
◆環境の改善に
低出生体重児が過ごすNICUはさまざまな合併症を避けるため、高度な医療が行われている。ただ、赤ちゃんにとってはお母さんの胎内とは大きく異なり、決して快適とはいえない環境だという。
「人工呼吸器のアラーム音、保育器を開閉する音、医療スタッフの足音、引き出しの開閉音。それに1日数回の採血もあります」と本田さん。そのため、赤ちゃんが泣いたり、手足をばたつかせて落ち着かなかったりといった状況に陥ることも少なくない。
そんなとき、理学療法士としてNICUで赤ちゃんに接してきた本田さんは、看護師たちが赤ちゃんを安心させようと、習慣的に体にそっと手をあてることで赤ちゃんが落ち着く様子を何度か見てきた。それが今回の研究に結びついた。
本田さんは「痛みが予想される採血などの場合であれば、その少し前から手あてをしてあげるだけで、赤ちゃんをめぐる環境がぐんと良くなる。NICUではなかなか難しい部分もあるが、手あての良さが認識され、広がってほしい」と話している。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121031-00000525-san-soci
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「手あて」とは、よく言ったな~~って思います
手術後、なかなかお腹の痛みが取れなかった私に友達のお母さん(元看護婦)が
「これ、使いなさい」とレンジでチンして温める「ゆたぽん」を貸してくれました
少し温めるだけで、随分とお腹の痛みがよくなるのでびっくりしました
その後、放射線治療で入院した時には、病棟の「ゆたぽん」を貸し出ししてもらっていました
「湯たんぽ」もいいけれど、冷めてしまうと温めるのも大変だし
何より、体調が悪い時に熱湯を扱うのってちょっと不安です
それに「ゆたぽん」は、レンジがあれば会社でも使えるので便利です

本当は、お母さんの手があったらいいのに~と思うけれど、それは無理なので・・・
でも「手あて」が本当なら、おばあちゃんが漬けた梅干しが美味しい理由も
科学的に証明される日もくるのかな?なんて思った私でした