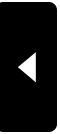スポンサーリンク
わが家の母はビョーキです
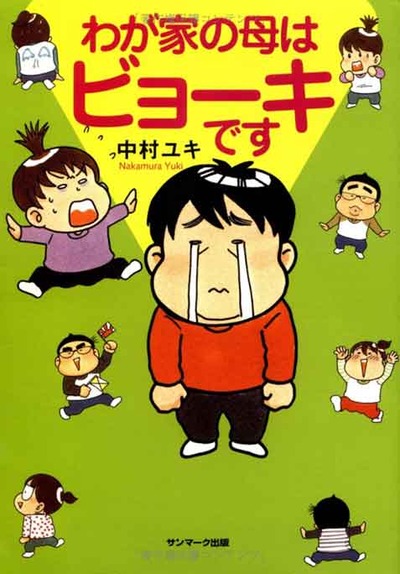
わが家の母はビョーキです
これは、精神病にかかったお母さんを持つ、著者の実話を描いたコミックエッセイです。
近年、「うつ」という言葉が一般に浸透したことで、実は、とても多くの人が心の病気で悩んでいるということが明らかになりました。著者のお母さんもその一人……。ただし、診断の結果は「うつ」ではなく、うつに次いで多い「統合失調症(トーシツ)」です。
昔は「精神分裂病」と言われていたこの病気、なんと100人に1人の割合で発症しています。これはがん患者と同じ割合です。でも、どうしてあんまり聞いたことがないのでしょうか。その裏には家族のやりきれない想いがあったのです……。
本書では「統合失調症」とはどんな病気なのか、どうやって回復するのか、どんな思いを抱いているのか、そして当事者とどう関わっていけばいいのかを家族の視点から描きました。また、看病されるお母さんと看病する娘の、心と心のぶつかり合い、通じ合いを深く鮮明に描いた作品にもなっています。
「ときにはイヤになるけれど、今では幸せな生活を送っています」。そんな著者の姿が、間違いなく胸を打つ一冊です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お母さんが自殺未遂をしようとした時に、まだ小さかった娘さんが「死んじゃヤダ~~、ユキがゴハン作ってあげるから!!」「何もしないでも生きててくれるだけでいいの~~」と言うシーンがあります
それに対してお母さんが「お母さんにはユキちゃんがいるんだもんね」と娘のために生きていかなきゃと思ったそうです
このマンガを読んでいて思ったのは、病気に対する自分自身の無知さもあるけれど、100人に1人という発症率ですが、統合失調症は脳の病気で回復が望める病気であるということをあまりにも知らないということでした
お母さんが統合失調症という環境の中で、守って欲しいはずの子供が「お母さんを守らなきゃ」と言って支えていく。本の中では子供だったユキさんが、色々な問題に対処しながらお母さんと共に生きていく姿が書かれています
入院するにしても、病院にかかるにも、生活するにもお金がかかります
人が追い詰められていく要因の1つに金銭問題があるように思います
それから、相談できる相手がいること。社会的に受け入れてくれる場があること。が大切な気がします
それらのことに、どのようにしたらいいかなどもかかれています
うつ病や統合失調症の家族を抱えた人と話す事がありますが、医師でない家族が入院を決意するのは難しいことだと思いました
以前、お母さんが自殺未遂をして措置入院をしたという娘さんがいましたが、彼女は私と同じ「がん患者」でした。その事を悩んだお母さんが、将来を悲観して自殺未遂をしたそうです
いつも明るい彼女からは、想像もできない出来事でしたが少しずつ、でも確実に状況は悪くなっていったそうです。でも、その日がくるまではわからなかったそうです
幸い、お母さんは発見が早く、またいいカウンセラーの先生とめぐり会えて今は、状況がよくなっているそうです
がん患者でも問題になっていますが、治療を必要としているのに、治療を受けない医療ネグレストをいう状態の人が沢山います。特に精神的な問題を抱えた人は、自分自身で判断する冷静さを持って居なかったりするので悪化してから病院にかかる人も多いそうです。また、薬を飲むと仕事ができないなどの理由で勝手に薬を止めてしまう人もいます
この本の中でも、お母さんが薬を飲まなかったりして状態が悪化していったりします
本の最後には、ユキさんが結婚した相手がとても楽天家の人で「まっ、いいんじゃない」と明るく言ってくれることでお母さんと娘さんの関係も良い方向に向っていっていると書かれていました
旦那さんや地域相談センターのスタッフさんという第3者が入ることで、お互いに相手の見方が変化していったからかなと思いました
どうしても自分と相手だけだとイライラしたり、許せないと思っていたことが「まっ、いいんじゃない」と言われることで気持ちが軽くなることってある気がします
どんな時でも自分1人で悩まないこと。って大切な気がしました
そして「ちょっと無理かな」と思ったら相手との距離をとってみるのもいいのかもと思います
不思議なもので「がん」になってから色々な病気を抱えた人やその家族の方と話すことが多くなりました
正直、私にはわからないことが多いけれどこうやって本を読んだりすることで「こういう辛さがあるんだ」「ここは似ているな」など色々なことを知るようになりました
難しい専門書なら読むのも大変だと思うけれど、マンガならすぐに読めるしいいなと思いました
2012年05月12日 Posted by すもも at 00:00 │読んだ本・・・心理学
精神科医の綴る幸福論
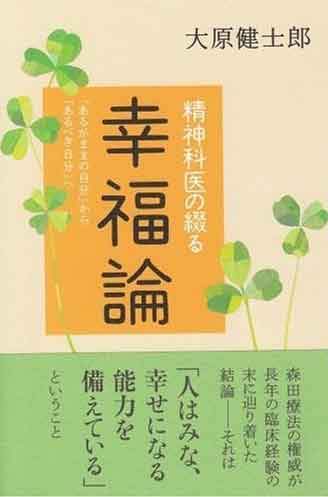
精神科医の綴る幸福論―「あるがままの自分」から「あるべき自分」へ
森田療法の権威による幸福論。幸福とは何か、それは得がたいものなのか、病人や老人に幸せはないのか……といった問題について、長年の臨床経験をもとに書き綴った。
著者は「どんなに絶望した人でも、幸せになることはできる」と言う。患者さんや自らの体験から多くのエピソードを紹介し、幸せをつかむための具体的アドバイスを贈る。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
最近、香山リカさんの本を読んでいたのでちょっと違う先生の本も読んでみようと思いました
この著者も精神科医ですが、この本を書かれた時にはすでに70歳を超えていました
色々な患者さんと接していたこともありますが、自分自身も死を予感するような大病をしていたり、20年前に奥さんを50歳で亡くすなど色々な経験をされていて、この本を書くことになったそうです
私が以前から少し気になっていた「森田療法」についても書かれていました
その中で「日記療法」というのがあるそうです
毎日、いいことを日記に書く。そのためにいいことをする。そうです
なんとなく「幸せだから笑う」のではなく「笑うから幸せになる」に似ているなと思った
表面だけでもいいから、行動することで結果が変わっていくそうです
私が入院する前に「介護日記」で「いい事は赤文字で、悪いことは普通の黒文字」というの知りました
私も闘病日記に生かしたのですが、たまにですが自分の日記を読み直すことがあります
その時に赤い文字しか読んでいないことがわかりました
そして、その時に私自身も「明日は赤い文字が増えるといいな」と思って楽しいことや嬉しいことを見つけては書いていきました
「今日は病棟をO周歩いた」とか「今日はOOが食べれた」とか・・・
普通に考えたらどうってことないことなのに、そんなことでも嬉しいことでした
でも、それを書くことで段々と元気になっていくことを実感することができました
元気な人にとっては、そんなことくらいで・・・と思う事でも病気や精神的に疲れた人には大切なことが沢山あるのかなと思った
そして、それを感じることができるのも、やっぱりつらいことを体験したからかなって・・・思う私でした
そしたら、つらい体験も捨てたもんやない気がしました
2012年05月11日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・心理学
40歳からの心理学
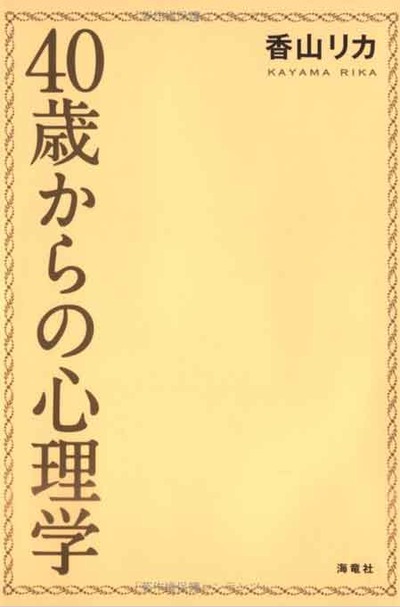
30代以降の結婚だからこそ変化を恐れず愚直になれ!自分の人生の責任を取れるのは自分だけ。人生は“勝ち”“負け”と単純に二分できない。年齢に縛られず、いつでもスタートしよう。大切な人生を見つめなおすための必読書。
「これでよかったの?」と問い続ける女性に、すべてを手に入れようとせず、自分にとってほしいもの、いらないものをはっきり見極めながら過ごす方法を伝授。同じ40代の著者が贈る、大切な人生を見つめなおすための必読書。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「40歳からの・・・」というタイトルに惹かれて借りました
20年来の友達と話をしていた時に「そういやSくんって、どうしてるんやろな?」と聞いてみた
共通の友人でもあるSくんとは、少し前から連絡が取れなくなっています
学生時代にモデルをしていたくらい男前だった彼は、いつも女性のうわさがありました
1度「付き合ってみる?」と私と話した事があるけれど、彼からは「すももは刹那的やからやめとく」といわれ、私は「あなたは破滅的だから、無理やろな」と言って終わりました
その後、彼は私の友人の中では一番早く、神戸のお嬢さんと結婚しました
そんな彼の人生は本当に波乱万丈でした
3歳で自分の目の前で両親を事故で亡くしました
彼はその記憶を持ったままで、お母さんの妹夫婦に育てられました
結婚式でお母さんに会ったけれど、とっても明るい朗らかないい人でした
でもどこかで「本当の親ではないからな」と言っていました
そんな彼が一番最初に結婚したのは、家庭が欲しかったのかな?と思っていました
でも、震災のあとから仕事が続かなくなって、段々と連絡も取れなくなってしまい今ではハガキを送っても奥さんに電話をしても連絡がつかなくなってしまいました
友人が「40歳を過ぎたら男って色々になっていると思うから、学生時代の友人でも連絡できない奴がいっぱいいる」と言いました
女性は子育て中や独身といったくらいかもしれないけれど、男は大きな会社の部長になってたり出世してる奴もいるけど、やばい奴は、本当にやばいからな。と言っていました
確かにそんな気がするかもと思った
私の知り合いでも借金苦で逃げた人もいるし・・・
こうやって「40歳からの心理学」と書けるだけ女性のほうが、まだいいのかな?と思った私でした
そして、彼に「刹那的」と言われた私も、やっぱりそうなのかな?と思ったりしました
2012年05月10日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・心理学
就活失敗し自殺する若者急増…4年で2・5倍に
就職活動の失敗を苦に自殺する10~20歳代の若者が、急増している。
2007年から自殺原因を分析する警察庁によると、昨年は大学生など150人が就活の悩みで自殺しており、07年の2・5倍に増えた。
警察庁は、06年の自殺対策基本法施行を受け、翌07年から自殺者の原因を遺書や生前のメモなどから詳しく分析。10~20歳代の自殺者で就活が原因と見なされたケースは、07年は60人だったが、08年には91人に急増。毎年、男性が8~9割を占め、昨年は、特に学生が52人と07年の3・2倍に増えた。
背景には雇用情勢の悪化がある。厚生労働省によると、大学生の就職率は08年4月には96・9%。同9月のリーマンショックを経て、翌09年4月には95・7%へ低下。東日本大震災の影響を受けた昨年4月、過去最低の91・0%へ落ち込んだ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
せっかく就職をしても、すぐに辞めてしまう人が多い時代に仕事が決まらないことで命を絶つ人がいるというのは、なんだかとっても切ない気がします
私が病気をした時に決めたことがあります
「自分で決定できないことには悩まない」ということです
手術前に色々なことを言われます。その時に必ず「OOだったら、こうなります」という最悪な事でした
でも、その最悪な事もそうでないことも自分では何1つ決めれないんだという事でした
しかも先生にもわからないので「手術してみてから」「検査してから」という事でした
自分の体なのに、自分も医師さえもわからない・・・
もしもこれが受験勉強なら、自分の努力だと思います
でも、自分では決めれないのなら「例え、最悪な事でも自分のせいではない」と思うことにしました
仕事でも同じような気がします
企業がどういう人材を求めているのかは、実際のところわからないと思います
確かに断られた時には自分の人格も否定されたような気がします
でも「自分には合わなかっただけ」と思う気持ちも大切な気がします
そして「10社落ちたんだから、それなら旅行にでも行こうかな。」とか頑張った自分に対するご褒美をあげてもいいような気がします。ちょっと後ろめたい気持ちもあるかもしれないけれど、それもいいやん。という考え方でもいいかな
仕事も恋愛もそうだけれど、相手があるものにくよくよ悩んでも仕方がないと思う私です
ただ、その時に家族から「早く仕事を決めなさい」とか「なんで落ちたの」と言われるとつらいかな・・・
2007年から自殺原因を分析する警察庁によると、昨年は大学生など150人が就活の悩みで自殺しており、07年の2・5倍に増えた。
警察庁は、06年の自殺対策基本法施行を受け、翌07年から自殺者の原因を遺書や生前のメモなどから詳しく分析。10~20歳代の自殺者で就活が原因と見なされたケースは、07年は60人だったが、08年には91人に急増。毎年、男性が8~9割を占め、昨年は、特に学生が52人と07年の3・2倍に増えた。
背景には雇用情勢の悪化がある。厚生労働省によると、大学生の就職率は08年4月には96・9%。同9月のリーマンショックを経て、翌09年4月には95・7%へ低下。東日本大震災の影響を受けた昨年4月、過去最低の91・0%へ落ち込んだ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
せっかく就職をしても、すぐに辞めてしまう人が多い時代に仕事が決まらないことで命を絶つ人がいるというのは、なんだかとっても切ない気がします
私が病気をした時に決めたことがあります
「自分で決定できないことには悩まない」ということです
手術前に色々なことを言われます。その時に必ず「OOだったら、こうなります」という最悪な事でした
でも、その最悪な事もそうでないことも自分では何1つ決めれないんだという事でした
しかも先生にもわからないので「手術してみてから」「検査してから」という事でした
自分の体なのに、自分も医師さえもわからない・・・
もしもこれが受験勉強なら、自分の努力だと思います
でも、自分では決めれないのなら「例え、最悪な事でも自分のせいではない」と思うことにしました
仕事でも同じような気がします
企業がどういう人材を求めているのかは、実際のところわからないと思います
確かに断られた時には自分の人格も否定されたような気がします
でも「自分には合わなかっただけ」と思う気持ちも大切な気がします
そして「10社落ちたんだから、それなら旅行にでも行こうかな。」とか頑張った自分に対するご褒美をあげてもいいような気がします。ちょっと後ろめたい気持ちもあるかもしれないけれど、それもいいやん。という考え方でもいいかな
仕事も恋愛もそうだけれど、相手があるものにくよくよ悩んでも仕方がないと思う私です
ただ、その時に家族から「早く仕事を決めなさい」とか「なんで落ちたの」と言われるとつらいかな・・・
2012年05月09日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・その他
ゼイタク病
先日の「かまわれたい人々」でも書かれていましたが、自分の幸わせに気がついていなくて悪口や愚痴を言っている人を見ることがあります
少し前に、ものすごく久しぶりに大阪時代の友達に電話をしました
かれこれ何年ぶり??と思ったけれど、なぜ彼女に電話をしなかったのかは
話し始めてすぐに気がつきました
2時間半のうち2時間は、旦那さんの悪口と高校受験に失敗した娘さんの話でした
娘さんのは「あの子が受験を失敗したのは、小学校の時の担任のいじめのせい」ということで
その担任に対する悪口と、自分がいなければ高校にもまともに行かないという娘さんへの不満。そしてご近所さんの愚痴でした
「ぜいたく病やな」と思った
結婚してすぐに妊娠した彼女は、20年以上1度も働きに行く事もなく郊外に一軒家を買って娘も大学生に高校生。そして平日には近所の奥さんとお菓子教室に通っています。何の不満もないはずがどうしたらこんなに愚痴や不満や悪口が出てくるのかな?と思いました
人はどんなに自分が幸せであっても、幸せな自分を認めてあげなければわからないものなんだなと思った
幸福論は実は「不幸論」というように「こういうことが不幸なんだよ」と言われないと自分の幸せに気がつかない人たち・・・うらやましいなと思ったりします
子供がいて、だんながいて、自分が必死に働きにでることもなくご飯が食べれて・・・
当たり前の日常の中でも幸せってあるような気がします
病気になって貯金もほとんどなくなってしまったけれど「なんとかなるよね~~」と思う私
反対に、仕事もあって貯金もあって何も困っていないのに「お金がない」という人
お金はいくらあってもいいと思う
でも「いくらあったら満足なんやろ?」と思う人もいます
そこそこに生きていけたらいいんと違う?と思います
人を好きになっただけでも「幸せやわ」と思う人もいるけれど、自分の目の前に好きな人がいてくれるのにその大切さがわからない人もいる・・・
なんでやろなと思った
「今、生きていること」それだけでもいいんと違うやろか。。。
今日から新しい職場で働いています。ご褒美にビールを飲みました
「至福の時」でした
少し前に、ものすごく久しぶりに大阪時代の友達に電話をしました
かれこれ何年ぶり??と思ったけれど、なぜ彼女に電話をしなかったのかは
話し始めてすぐに気がつきました
2時間半のうち2時間は、旦那さんの悪口と高校受験に失敗した娘さんの話でした
娘さんのは「あの子が受験を失敗したのは、小学校の時の担任のいじめのせい」ということで
その担任に対する悪口と、自分がいなければ高校にもまともに行かないという娘さんへの不満。そしてご近所さんの愚痴でした
「ぜいたく病やな」と思った
結婚してすぐに妊娠した彼女は、20年以上1度も働きに行く事もなく郊外に一軒家を買って娘も大学生に高校生。そして平日には近所の奥さんとお菓子教室に通っています。何の不満もないはずがどうしたらこんなに愚痴や不満や悪口が出てくるのかな?と思いました
人はどんなに自分が幸せであっても、幸せな自分を認めてあげなければわからないものなんだなと思った
幸福論は実は「不幸論」というように「こういうことが不幸なんだよ」と言われないと自分の幸せに気がつかない人たち・・・うらやましいなと思ったりします
子供がいて、だんながいて、自分が必死に働きにでることもなくご飯が食べれて・・・
当たり前の日常の中でも幸せってあるような気がします
病気になって貯金もほとんどなくなってしまったけれど「なんとかなるよね~~」と思う私
反対に、仕事もあって貯金もあって何も困っていないのに「お金がない」という人
お金はいくらあってもいいと思う
でも「いくらあったら満足なんやろ?」と思う人もいます
そこそこに生きていけたらいいんと違う?と思います
人を好きになっただけでも「幸せやわ」と思う人もいるけれど、自分の目の前に好きな人がいてくれるのにその大切さがわからない人もいる・・・
なんでやろなと思った
「今、生きていること」それだけでもいいんと違うやろか。。。
今日から新しい職場で働いています。ご褒美にビールを飲みました

「至福の時」でした
あなたの中の異常心理
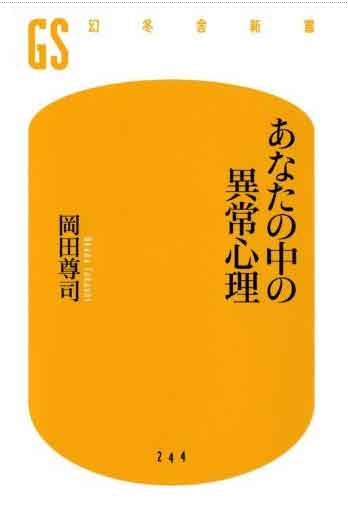
あなたの中の異常心理
なぜ悪は快感なのか?
人の心はミステリーよりミステリアス。現代人の精神の闇を解き明かす
誰もが心にとらわれや不可解な衝動を抱えている。そして正常と異常の差は紙一重でしかない――。
精神科医で横溝賞作家でもある著者が、正常と異常の境目に焦点をあて、現代人の心の闇を解き明かす。
完璧主義、依存、頑固、コンプレックスが強いといった身近な性向にも、異常心理に陥る落とし穴が。
精神的破綻やトラブルから身を守り、ストレス社会をうまく乗り越えるにはどうすればいいのか。現代人必読の異常心理入門。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この先生の本、ちょっと面白いかもって思いました
「シック・マザー」もこの先生が書いたものでしたが、心理学用語が多いし複雑な内容かと思ったけれど、不思議とサクサクと読めました
ここのところ、ずっとこういう本ばかり読んでいたので何だか気持ちが滅入ることもあったけれど、この先生の本をあと何冊か読んだら、次は歴史小説でも読んでみようかなって思っています
少し前に「ノーマル」と「アブノーマル」って何だろう?と思ったことがあった
たとえば、相手が必要なものであれば相手が許してくれれば、それは2人の間での「ノーマル」になるけれど、他人から見たら違っていることも沢山ある気がします
以前、テレビで「家族でいる時は裸」という話をしている人がいて驚いたけれど、もしもずっと家族が裸だったら違和感なく「普通」なのかもしれないなって思いました
でも、そのままで外に出て行ってしまったら、それは「異常」なんだと思います
本の中で「自己絶対視」について書かれていました
自分の意見が正しいと決め付けて人にもそのように求める人(過剰に)という感じだと思います
私は、昔から「デザイナー」や「作家」「先生」と言われる人と話したりする事がとても多かったです
先日も、そういう人と飲んでいて珍しいくらいに怒ったそうです
なんでもかんでも自分が正しい。という言い方をされて、さすがに切れた・・・そうです
これは、友達からの目線で私としては「事実」を言っただけだったんですが・・・
作家やデザイナー、もしくは教師や医師といった「先生」と呼ばれる人って「変人」が多いなって思います
確かに「先生」と呼ばれているし、すごい人なのかもしれないけれど・・・
一般的にみて「それってどうなん?」って思うことも多い
しかも自分が絶対に正しいと思っているから、押し付けもすごいし・・・
先日、心理学の教室で先生が「人の話を聞くのが嫌だから、お稽古が続かない」と言うのを聞いて、ある生徒さんが「先生って呼ばれる人って、人の話を聞かないで自分の話ばっかりするのよね」と言いました
何となくわかる気がします
そして、自分に対してだけなら、どんなことであってもいいけれど他人を巻き込んだり押し付けたりするのは、やはり異常なことだと思います(相手が望んでもいない話を延々とするのも)
「発言小町」のような不特定多数の人に相談しているものの回答?というのを読んだことがありますが、何だか異常な「決め付け感」を感じます
どちらも知らない人なのに、なんでこんなに知っているかのような回答ができるんだろう・・・と思うと、気味が悪いと思った
本当に大切な事は、自分と話してみればいいのに・・・と思う私でした
2012年05月07日 Posted by すもも at 00:00 │読んだ本・・・心理学
かまわれたい人々

◎「家族」はペットのネコだけ
◎ひとりぼっちの「男性おひとりさま」
◎「仕事」に依存する会社人間
◎「お客様相談室」に人生相談をもちかける
◎性的な遊びをせず、「お喋り」のためだけに風俗嬢に貢ぎ続ける
現代社会に生み出された『かまわれたい人々』、
「孤独」の底に隠された「願望」を探る。
多くの日本人は、「誰かにかまってほしい」という気持ちを持っています。
これは正確に言えば、
「誰かにかまってほしい。だけど、ひとりの時間がほしい」、
「ほうっておいてほしいけど、ひとりぼっちは嫌だ」という矛盾した
願望のあらわれだと言えます。
こうした葛藤は、「自由」と「孤独」の板ばさみから生まれています。
現代社会は「自由」の価値を声高に叫ぶ社会です。
そしてこの「自由」の大半は、他人から「かまわれない自由」です。
この「自由」には「孤独」の影がつきまといます。
なぜなら、他人から「かまわれない自由」は、
「かまわれない孤独」に容易に転化するからです。
そして、『かまわれたい人々』は、この「孤独」に耐えきれなかった人たちです。
本書は、こうした「自由」と「孤独」の葛藤から生まれた
『かまわれたい人々』を分析するものです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
退院後に、まだまだ体調が悪いけれど、ずっと家にいるのも気がめいってしまうのでお稽古に通い始めました。一番若い人でも50歳台から、上は80歳台までという幅の広さだったので色々な話が出来て、楽しかったです
そして、それまではご近所に親しい人は大家さんだけだったのが今では沢山できました
先日も、旦那さんが筍嫌いで自分だけでは作らないと言ってた人がいて私が「筍が食べたい~~」というと作ってくれて、おすそ分けしてくれました
ちょっと母親に似た味付けで、とても美味しかったです
「かまわれない自由」は、とても楽な気がします
でも、その反面「かまわれない孤独」もある。というのは、とてもよくわかります
色々な年代の人と話をすると自分が抱えている問題が「案外、大丈夫かも」と思うことが沢山あります
そして、自分にとっては「一生を左右するくらいに大変なこと」が、年齢を重ねた人からすると「乗り越えたこと」だったりもします
「おひとりさま」と言いながら、どこかで繋がっていたいと願っている人が沢山いる気がします
ただ、その中でもルールがあって「自分や家族の自慢話はしない」「詮索をしない」「楽しい顔をする」「暗い話や愚痴は言わない」など最低限守るべきことがある気がしました
本当の意味で「かまわれない自由」というのは、基本的な人間関係を持った上で成り立つような気がしました
2012年05月06日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │読んだ本・・・心理学
手術数でわかる いい病院 2012
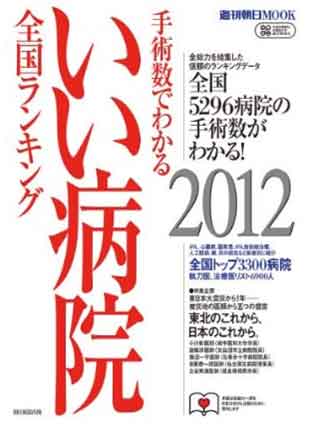
症例数=いい病院。というわけではないと思うし、東京のように病院が沢山ある地域では患者が1つの病院に偏るということがあまりないと思います
それに比べて、地方では1つの病院に患者が集中していたりしますが、症例数が多いというのは、医師の技術が高いという利点もあると思います
また、がん種別に最新治療が取り上げられているというのも参考になります
病院を選ぶ基準の1つと考えてみるのにはいいと思います
2012年05月05日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │その他
スピリチュアルケアと臨床パストラルケア
スピリチュアルケアとは
人は病気のとき身体的な苦痛のみではなく、精神的(心理的)、社会的、更に霊的(スピリチュアル)苦痛を含む「全体的痛み」を苦しみます。それぞれの苦痛に対して身体的ケア、精神的(心理的)ケア、社会的ケア、そして霊的ケア(スピリチュアルケア)が必要です。
霊的(スピリチュアル)苦痛とは、霊(魂、心)が求める欲求(ニーズ)が満たされない時に痛みが発生しその痛みが「叫び」によって表現されます。その叫びに応対する(ケアする)のが霊的ケア(スピリチュアルケア)です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
霊的欲求(ニーズ)には哲学的ニーズと宗教的ニーズがあります。
哲学的ニーズとは:人生の意義や意味を求めることです。 すなわち、生きる事、死ぬ事、働く事、楽しむ事、苦しむ事、悲しむ事、無力である事、孤独である事、疎外されていること等の意味付けです。
宗教的ニーズとは:超自然の存在や神、永遠の生命、死後の世界、天国と地獄、魂や霊の働き、祈ること、希望、良心、罪や罪悪感、罪の許し、感謝と賛美、のようなものです。
臨床パストラルケアとは
現在では「パストラルケア」という言葉は「スピリチュアルケア」と殆んど同義語である、と考えられます。 しかし歴史的に見ますと、イギリスやアメリカの医療施設には「パストラルケア(pastoral care)部」があります。従来、この部門で働く人は殆んど全てキリスト教のPastor(牧師)である上、更に臨床的に患者の霊的(スピリチュアル)苦痛をケアするための専門的コースを習得して資格認定された人達だったのです。 従ってpastorが患者のスピリチュアルケアをする、と言う意味でパストラルケアと呼ばれてきたわけです。 語源的には、パスターは「羊飼い」とか「牧者」という意味であり、キリスト教関係でそれが使われるのは、聖書のキリストの言葉、「わたしは良い牧者である」に由来している。 従って「パストラルケア」はパスター(羊飼い)が羊を親身になって世話するように人々をケアするという意味から出た言葉です。 キリスト教圏の国々の医療施設では呼び方は違っても似たような部門を持ち患者のスピリチュアルケアに当っています。 キリスト教以外の宗教でも人のスピリチュアル面は当然重視しますから、似たような仕事(ケア)は存在します。
従って、このような歴史を踏まえて、本センターの名称のように、組織や団体の名前に使われているのは良いとして、そこで行われている「ケア」の本質は1990年のWHO専門委員会報告書にあるように、「スピリチュアルケア」という言葉で言い表した方が現在は一般的であると思われます。 世界的にも「パストラルケア」よりは宗教色の少ない「スピリチュアルケア」という言葉の方が広く使われていく傾向にあります。
しかしながら、「パストラルケア」はスピリチュアルケアに加えて、特定の宗教(例えばキリスト教)の信者や求道者に「宗教的ケア」をも行う場合がある。 その場合には「パストラルケア」はスピリチュアルケアを中心とした上で宗教的ケアも行うと理解すれば良いと思われる。
臨床パストラルケア教育研究センター:http://pastoralcare.jp/spiritual.html
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
がんとスピリチュアルを検索すると「スピリチュアルケア」というのが出てきます
海外の緩和ケアの本を読んでみると、ほとんどの病院に牧師さんがいたりカウンセラーがいたり
また、必要な時に呼ぶことができます
がん患者と精神的なケアが密接につながっていると感じます
日本では、病棟で牧師さんを見たりすることはないので末期がんの患者さんがもしも「牧師さんを呼んでください」と言ったとしても、叶うのかな?という気がします
完全なキリスト教系のホスピスであれば叶うかと思いますが、大学病院やがんセンターなどではどうでしょうか?
末期がんと言われて、すぐに亡くなる人もいますが、告知を受けてもゆっくりと進行していくがんもあります
人にはそれぞれ受け入れる時間が必要。というのは感じます
また、長くても短くても受け入れることができる人と、そうでない人がいる気がします
どんな人でもあっても自分の話を聞いて欲しいという気持ちがある気がします
がん体験者の先輩や末期がんの人の話を聞くと、自分が生きていた証を知って欲しい。という強い気持ちを感じます
そういう私もその1人なのだと思いました
日本の医療機関の中で、スピリチュアルケアという考えがもっと浸透してくれたらいいかなと思います
人は病気のとき身体的な苦痛のみではなく、精神的(心理的)、社会的、更に霊的(スピリチュアル)苦痛を含む「全体的痛み」を苦しみます。それぞれの苦痛に対して身体的ケア、精神的(心理的)ケア、社会的ケア、そして霊的ケア(スピリチュアルケア)が必要です。
霊的(スピリチュアル)苦痛とは、霊(魂、心)が求める欲求(ニーズ)が満たされない時に痛みが発生しその痛みが「叫び」によって表現されます。その叫びに応対する(ケアする)のが霊的ケア(スピリチュアルケア)です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
霊的欲求(ニーズ)には哲学的ニーズと宗教的ニーズがあります。
哲学的ニーズとは:人生の意義や意味を求めることです。 すなわち、生きる事、死ぬ事、働く事、楽しむ事、苦しむ事、悲しむ事、無力である事、孤独である事、疎外されていること等の意味付けです。
宗教的ニーズとは:超自然の存在や神、永遠の生命、死後の世界、天国と地獄、魂や霊の働き、祈ること、希望、良心、罪や罪悪感、罪の許し、感謝と賛美、のようなものです。
臨床パストラルケアとは
現在では「パストラルケア」という言葉は「スピリチュアルケア」と殆んど同義語である、と考えられます。 しかし歴史的に見ますと、イギリスやアメリカの医療施設には「パストラルケア(pastoral care)部」があります。従来、この部門で働く人は殆んど全てキリスト教のPastor(牧師)である上、更に臨床的に患者の霊的(スピリチュアル)苦痛をケアするための専門的コースを習得して資格認定された人達だったのです。 従ってpastorが患者のスピリチュアルケアをする、と言う意味でパストラルケアと呼ばれてきたわけです。 語源的には、パスターは「羊飼い」とか「牧者」という意味であり、キリスト教関係でそれが使われるのは、聖書のキリストの言葉、「わたしは良い牧者である」に由来している。 従って「パストラルケア」はパスター(羊飼い)が羊を親身になって世話するように人々をケアするという意味から出た言葉です。 キリスト教圏の国々の医療施設では呼び方は違っても似たような部門を持ち患者のスピリチュアルケアに当っています。 キリスト教以外の宗教でも人のスピリチュアル面は当然重視しますから、似たような仕事(ケア)は存在します。
従って、このような歴史を踏まえて、本センターの名称のように、組織や団体の名前に使われているのは良いとして、そこで行われている「ケア」の本質は1990年のWHO専門委員会報告書にあるように、「スピリチュアルケア」という言葉で言い表した方が現在は一般的であると思われます。 世界的にも「パストラルケア」よりは宗教色の少ない「スピリチュアルケア」という言葉の方が広く使われていく傾向にあります。
しかしながら、「パストラルケア」はスピリチュアルケアに加えて、特定の宗教(例えばキリスト教)の信者や求道者に「宗教的ケア」をも行う場合がある。 その場合には「パストラルケア」はスピリチュアルケアを中心とした上で宗教的ケアも行うと理解すれば良いと思われる。
臨床パストラルケア教育研究センター:http://pastoralcare.jp/spiritual.html
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
がんとスピリチュアルを検索すると「スピリチュアルケア」というのが出てきます
海外の緩和ケアの本を読んでみると、ほとんどの病院に牧師さんがいたりカウンセラーがいたり
また、必要な時に呼ぶことができます
がん患者と精神的なケアが密接につながっていると感じます
日本では、病棟で牧師さんを見たりすることはないので末期がんの患者さんがもしも「牧師さんを呼んでください」と言ったとしても、叶うのかな?という気がします
完全なキリスト教系のホスピスであれば叶うかと思いますが、大学病院やがんセンターなどではどうでしょうか?
末期がんと言われて、すぐに亡くなる人もいますが、告知を受けてもゆっくりと進行していくがんもあります
人にはそれぞれ受け入れる時間が必要。というのは感じます
また、長くても短くても受け入れることができる人と、そうでない人がいる気がします
どんな人でもあっても自分の話を聞いて欲しいという気持ちがある気がします
がん体験者の先輩や末期がんの人の話を聞くと、自分が生きていた証を知って欲しい。という強い気持ちを感じます
そういう私もその1人なのだと思いました
日本の医療機関の中で、スピリチュアルケアという考えがもっと浸透してくれたらいいかなと思います
2012年05月04日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │がんとこころ
新がん治療法は既存抗がん剤を深夜に
がん治療へ既存薬を用いた「時間治療」が画期的な効果を上げ注目されている。
「時間治療」とは、がん治療に用いる抗がん剤治療薬を「深夜」に投与するだけの治療方法で、抗がん剤は従来と全く同じ。投与する時間を「深夜」へ変えるだけで、 がん患者の生存期間の延長や、関節リウマチのつらい痛みや腫れがおさまるなどの効果が上がっているのだ。
1.5倍の抗がん剤を深夜に投与してがん縮小
健康診断で肝臓にガンが見つかり、抗がん剤治療を受けていた男性も「時間治療」でがん細胞が収縮した。発見時には、ガンが大き過ぎるために手術は無理とされたが、時間治療を導入している病院に転院し、それまでの抗がん剤の1.5倍の量を深夜に投与された結果、数ヶ月後には がん細胞が収縮したのだ。
関節リウマチに対しても、長年苦しんできた70才の女性が、同じ薬を飲む時間を朝昼2回から"夜寝る前の1回に変更"しただけで痛みの症状が軽減された。
このような病状や症状の改善の背景にあるのは、細胞の中で時計のように働く『時計遺伝子』研究の進歩とされる。
「時間治療」は深夜に実施されるために医療スタッフの確保などの課題があるが、がん患者には試す価値が十分にある新治療法と言えるだろう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
現在、抗がん剤治療は入院治療ではなく外来で行われるのが一般的になっています
朝9時からの診察と同じように抗がん剤が投与されます
ほとんどが日帰り投与という中で、深夜の抗がん剤投与というのができるのかな?と思いました
準夜勤・深夜勤の看護婦さんの数は日勤の半分以下だと思います
そんな中で、深夜の投与をするというのは患者さんの体調にもよると思いますが
もしも何かが起きた場合の対処などをどうすればいいのかな?と思いました
1泊2日の入院で抗がん剤治療を行うという体制が整わないと実現が難しいのかな??
患者さんのため。というのもわかるけれど、入院中に深夜に色々と問題が起こった時に少ない人数で大変そうだった看護婦さんたちを思うと「深夜にやればいいでしょ」と簡単にはいえないなって思いました
「時間治療」とは、がん治療に用いる抗がん剤治療薬を「深夜」に投与するだけの治療方法で、抗がん剤は従来と全く同じ。投与する時間を「深夜」へ変えるだけで、 がん患者の生存期間の延長や、関節リウマチのつらい痛みや腫れがおさまるなどの効果が上がっているのだ。
1.5倍の抗がん剤を深夜に投与してがん縮小
健康診断で肝臓にガンが見つかり、抗がん剤治療を受けていた男性も「時間治療」でがん細胞が収縮した。発見時には、ガンが大き過ぎるために手術は無理とされたが、時間治療を導入している病院に転院し、それまでの抗がん剤の1.5倍の量を深夜に投与された結果、数ヶ月後には がん細胞が収縮したのだ。
関節リウマチに対しても、長年苦しんできた70才の女性が、同じ薬を飲む時間を朝昼2回から"夜寝る前の1回に変更"しただけで痛みの症状が軽減された。
このような病状や症状の改善の背景にあるのは、細胞の中で時計のように働く『時計遺伝子』研究の進歩とされる。
「時間治療」は深夜に実施されるために医療スタッフの確保などの課題があるが、がん患者には試す価値が十分にある新治療法と言えるだろう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
現在、抗がん剤治療は入院治療ではなく外来で行われるのが一般的になっています
朝9時からの診察と同じように抗がん剤が投与されます
ほとんどが日帰り投与という中で、深夜の抗がん剤投与というのができるのかな?と思いました
準夜勤・深夜勤の看護婦さんの数は日勤の半分以下だと思います
そんな中で、深夜の投与をするというのは患者さんの体調にもよると思いますが
もしも何かが起きた場合の対処などをどうすればいいのかな?と思いました
1泊2日の入院で抗がん剤治療を行うという体制が整わないと実現が難しいのかな??
患者さんのため。というのもわかるけれど、入院中に深夜に色々と問題が起こった時に少ない人数で大変そうだった看護婦さんたちを思うと「深夜にやればいいでしょ」と簡単にはいえないなって思いました
2012年05月03日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん
占い
先日、友達と横浜の中華街に行ってきました
その時に「手相占い」をしてもらいました
占い師さんに「だんなさん?」と聞かれて「いいえ」と言って
「彼氏?」と聞かれて「いえいえ、違います」と言って不思議な顔をされたので
私が「飲み友達です」友達が「くされ縁です」と答えました
25年の付き合いだけど、友達以上にはならない2人はお互い別々に占ってもらいました
私の性格の時に「竹を割ったような性格で男っぽい人ですね」と言うのを聞いて
隣で大笑いしていました
運命線を見てもらっている時に「50歳からの線がないですね」と言われました
占い師さんには「これからできていく線ですね」と言われました
自分の中で自分の人生は48歳でいいと思っていました
私の好きな織田信長が48歳で亡くなったと知った時に「私も48歳でいい」と思った
(実際には、49歳で本能寺の変です)
そしたら、42歳でがん患者になった
5年生存率を生きたら47歳か・・・と思った
48歳になったら自分の人生をもう1度考えてみようかなって思っています
今月、検査に行きます
検査が近づいてくると、ちょっと不安になります
いいことと最悪なことを考えてしまう私でした
その時に「手相占い」をしてもらいました
占い師さんに「だんなさん?」と聞かれて「いいえ」と言って
「彼氏?」と聞かれて「いえいえ、違います」と言って不思議な顔をされたので
私が「飲み友達です」友達が「くされ縁です」と答えました
25年の付き合いだけど、友達以上にはならない2人はお互い別々に占ってもらいました
私の性格の時に「竹を割ったような性格で男っぽい人ですね」と言うのを聞いて
隣で大笑いしていました
運命線を見てもらっている時に「50歳からの線がないですね」と言われました
占い師さんには「これからできていく線ですね」と言われました
自分の中で自分の人生は48歳でいいと思っていました
私の好きな織田信長が48歳で亡くなったと知った時に「私も48歳でいい」と思った
(実際には、49歳で本能寺の変です)
そしたら、42歳でがん患者になった
5年生存率を生きたら47歳か・・・と思った
48歳になったら自分の人生をもう1度考えてみようかなって思っています
今月、検査に行きます
検査が近づいてくると、ちょっと不安になります
いいことと最悪なことを考えてしまう私でした
2012年05月03日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │その他
胃がん, 食道がん の最先端治療病院
胃がん、食道がん の生存率を高める病院
食道がんや胃がんでは、がんが粘膜の下の方まで進行していると、多くの場合、手術の適応になる。臓器の一部あるいは全部を切除し、がんの進行度合いによってはその周辺のリンパ節も取り除く。治療ガイドラインで定められている治療法で広く普及しているものの、新たな検査方法が確立されれば、どこまで切除すべきかが客観的かつ科学的に示され、より正確な治療法が確立されることになる。
そんな胃がんや食道がんが、最初に転移しやすいのはセンチネルリンパ節という部分。現在、先進医療として、「センチネルリンパ節生検」という検査方法が行われている。
がん病巣の近くに特殊な色素やラジオアイソトープを注入して、がんが最初にリンパ節に到達するセンチネルリンパ節を同定し、転移の有無を顕微鏡で調べる。この検査は、すでに乳がんやメラノーマ(皮膚がん)に対しては、広く行われている。それを食道がんや胃がんへ応用するために、世界に先駆けて1998年から研究を進めているのが慶應義塾大学病院 一般・消化器外科だ。
慶應義塾大学病院は 先進医療の検査はもちろんのこと、小さな傷口で手術を可能とした腹腔鏡を用いた低侵襲の治療でもパイオニアである。
「胃がんや食道がんに対して、センチネルリンパ節生検を行うと、取り残しや余分な組織の切除を省くことができるなど、さまざまなメリットがあります。ただし、その検査に基づく治療で、本当に従来の手術と同じ生存率を確保できるか。その見極めの研究を行っています」と副病院長と腫瘍センター長を兼務する同科の北川雄光教授(51)は言う。
北川教授は、胸腔鏡・腹腔鏡手術のスペシャリストだ。食道がんや胃がんでも、患者にメリットがあれば胸腔鏡・腹腔鏡による手術を積極的に行っている。また、胃の良性腫瘍の胃GISTや、機能障害の一種・食道アカラシア、逆流性食道炎の手術では、全国に先駆けてヘソのひとつの穴から行う「単孔式腹腔鏡下手術」を導入。熟練した技術とチームワークで、低侵襲で確実に治療できる最先端技術を研究している。
「胃がんや食道がんに単孔式腹腔鏡を応用するには、医療機器の進歩を待たなければなりません。また、将来的には、腹腔鏡下手術と内視鏡の治療を組み合わせることで、臓器の温存がこれまで以上に可能になると思います。しかし、それにもまだ数年かかるでしょう」(北川教授)
腹腔鏡下手術でセンチリンパ節生検を行い、転移が見られなければ、内視鏡による治療で臓器を温存する。それは、これまで内視鏡の治療では、再発するのではないかと考えられた症例に対して、手術によって胃を部分切除するだけでなく、胃を残すという選択肢も広がることになる。
「今後、医療機器などがさらに発達することで、治療方法や検査方法の選択肢は増えるでしょう。しかし、手術で治るがんは再発させてはいけません。それを追求するために取り組むべきことはまだ多い」と北川教授。確実に治るがんを増やすために、今も力を注ぎ続けている。
< 2011年の治療実績 >
☆胃がん治療総数379件
☆胃がん手術件数158件
(内腹腔鏡下手術82件)
☆食道がん治療総数182件
☆食道がん手術件数50件
☆センチネルリンパ節生検64件
☆病院病床数1059床
慶應義塾大学病院:早期胃がんのセンチネルリンパ節生検について
http://www.hosp.keio.ac.jp/annai/byoin/kodo/soisenti.htm
http://www.surgery-med-keio.jp/joubushoukakan/trouble/04.php
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
現在、がん治療はがん拠点病院を中心として標準治療ガイドラインにそった治療が行われています
がん拠点病院で受けれる治療は、ほとんど同じと言われている中で唯一、色々な選択肢があると言われているのがリンパ節への転移が認められるかどうかの早期がんに対する治療方法です
リンパ節への転移は患者さんのその後の人生を決定する重要なものです
確実な方法でリンパ節への転移が検査できれば、リンパ節を残せます
現在、アメリカでも大腸がんなどでは日本のようにリンパ節郭清を行うほうがいいのでは?という動きがあるそうです
疑わしきは取らない。というアメリカのリンパ郭清が日本のように疑わしきは郭清というようの変化していくのではないか。と話されていた医師がいました
リンパ節への転移があったまま残してしまうと、それまで1期だった人が次に見つかった場合、いきなりステージが4期になってしまう場合があります
リンパから遠隔転移をする場合があるからです
できるだけ確実な方法でリンパ節への転移を調べた上で、リンパ節を残す治療を行うことが大切だと思います
私が受けた子宮頸がんでのセンチネルリンパ節生検も今では色々な病院で受けれるようです
自分のがんの進行度と病理を知った上で、自分が受けたい治療を探してみてください
食道がんや胃がんでは、がんが粘膜の下の方まで進行していると、多くの場合、手術の適応になる。臓器の一部あるいは全部を切除し、がんの進行度合いによってはその周辺のリンパ節も取り除く。治療ガイドラインで定められている治療法で広く普及しているものの、新たな検査方法が確立されれば、どこまで切除すべきかが客観的かつ科学的に示され、より正確な治療法が確立されることになる。
そんな胃がんや食道がんが、最初に転移しやすいのはセンチネルリンパ節という部分。現在、先進医療として、「センチネルリンパ節生検」という検査方法が行われている。
がん病巣の近くに特殊な色素やラジオアイソトープを注入して、がんが最初にリンパ節に到達するセンチネルリンパ節を同定し、転移の有無を顕微鏡で調べる。この検査は、すでに乳がんやメラノーマ(皮膚がん)に対しては、広く行われている。それを食道がんや胃がんへ応用するために、世界に先駆けて1998年から研究を進めているのが慶應義塾大学病院 一般・消化器外科だ。
慶應義塾大学病院は 先進医療の検査はもちろんのこと、小さな傷口で手術を可能とした腹腔鏡を用いた低侵襲の治療でもパイオニアである。
「胃がんや食道がんに対して、センチネルリンパ節生検を行うと、取り残しや余分な組織の切除を省くことができるなど、さまざまなメリットがあります。ただし、その検査に基づく治療で、本当に従来の手術と同じ生存率を確保できるか。その見極めの研究を行っています」と副病院長と腫瘍センター長を兼務する同科の北川雄光教授(51)は言う。
北川教授は、胸腔鏡・腹腔鏡手術のスペシャリストだ。食道がんや胃がんでも、患者にメリットがあれば胸腔鏡・腹腔鏡による手術を積極的に行っている。また、胃の良性腫瘍の胃GISTや、機能障害の一種・食道アカラシア、逆流性食道炎の手術では、全国に先駆けてヘソのひとつの穴から行う「単孔式腹腔鏡下手術」を導入。熟練した技術とチームワークで、低侵襲で確実に治療できる最先端技術を研究している。
「胃がんや食道がんに単孔式腹腔鏡を応用するには、医療機器の進歩を待たなければなりません。また、将来的には、腹腔鏡下手術と内視鏡の治療を組み合わせることで、臓器の温存がこれまで以上に可能になると思います。しかし、それにもまだ数年かかるでしょう」(北川教授)
腹腔鏡下手術でセンチリンパ節生検を行い、転移が見られなければ、内視鏡による治療で臓器を温存する。それは、これまで内視鏡の治療では、再発するのではないかと考えられた症例に対して、手術によって胃を部分切除するだけでなく、胃を残すという選択肢も広がることになる。
「今後、医療機器などがさらに発達することで、治療方法や検査方法の選択肢は増えるでしょう。しかし、手術で治るがんは再発させてはいけません。それを追求するために取り組むべきことはまだ多い」と北川教授。確実に治るがんを増やすために、今も力を注ぎ続けている。
< 2011年の治療実績 >
☆胃がん治療総数379件
☆胃がん手術件数158件
(内腹腔鏡下手術82件)
☆食道がん治療総数182件
☆食道がん手術件数50件
☆センチネルリンパ節生検64件
☆病院病床数1059床
慶應義塾大学病院:早期胃がんのセンチネルリンパ節生検について
http://www.hosp.keio.ac.jp/annai/byoin/kodo/soisenti.htm
http://www.surgery-med-keio.jp/joubushoukakan/trouble/04.php
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
現在、がん治療はがん拠点病院を中心として標準治療ガイドラインにそった治療が行われています
がん拠点病院で受けれる治療は、ほとんど同じと言われている中で唯一、色々な選択肢があると言われているのがリンパ節への転移が認められるかどうかの早期がんに対する治療方法です
リンパ節への転移は患者さんのその後の人生を決定する重要なものです
確実な方法でリンパ節への転移が検査できれば、リンパ節を残せます
現在、アメリカでも大腸がんなどでは日本のようにリンパ節郭清を行うほうがいいのでは?という動きがあるそうです
疑わしきは取らない。というアメリカのリンパ郭清が日本のように疑わしきは郭清というようの変化していくのではないか。と話されていた医師がいました
リンパ節への転移があったまま残してしまうと、それまで1期だった人が次に見つかった場合、いきなりステージが4期になってしまう場合があります
リンパから遠隔転移をする場合があるからです
できるだけ確実な方法でリンパ節への転移を調べた上で、リンパ節を残す治療を行うことが大切だと思います
私が受けた子宮頸がんでのセンチネルリンパ節生検も今では色々な病院で受けれるようです
自分のがんの進行度と病理を知った上で、自分が受けたい治療を探してみてください
2012年05月02日 Posted by すもも at 00:00 │Comments(0) │ニュース・・・がん
ミラクルガール~大塚弓子著~
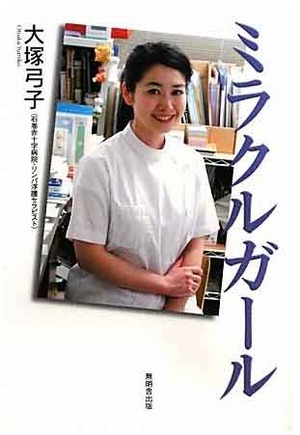
4月28日のNHKのグランジュテで、大塚弓子さんの紹介をされました
リンパ浮腫マッサージをされている看護師さんで「ミラクルガール」~医療系セラピストという本も出されています
自身も17歳で甲状腺がん、そして、再発などの経験をしながら同じようにリンパ浮腫で悩む患者さんのために活動されています
リンパ浮腫の悩みは、手術した場所によっても様々です
乳がんの方は、手のひらから腕にかけて子供の手のようにぷっくりとした感じになります
可愛らしいけれど、バックを持ったりするのでかなりつらいそうです
また左右差がわかりやすい場所だし、夏場などは半そでが着れないなどの悩みがあります
婦人科がんの私は、手術後は外陰部と腹部の浮腫でしたが、今でも左足の浮腫と外陰部の腫れ・痺れ・痛みなどは残っていますが、それでも少しは慣れてきました
ただ、足のむくみが強い人は乳がんの方と同じように短いスカートやパンツは履けません
リンパをしめつけないように、下着などの悩みもあります
婦人科がんの外陰部の浮腫は、なかなかマッサージがしにくい場所だと思います
医師にも言いにくい場所だし・・・
私はリンパ外来で「外陰部が・・・」と言ったところ横になって下着を取って、下から先生が覗き込むようにして見られていました。う~~~ん、これってかなり恥ずかしくないか。。。と思った(男の先生だったし)
また、もしも浮腫があっても気がつきにくい場所だとも思います
自分で触ってみて「ぷにょぷにょ」した感触があったり、また左右差があったりするとリンパ浮腫かもしれません
その場合は、お風呂に入った時に、お尻から外陰部のほうに優しく流してあげるなど、少しマッサージしてみるのもいいと思います(できるだけ優しく、力を入れないようになでてあげてください)
また甲状腺がんの方は顔が浮腫むそうです
リンパ浮腫はリンパを1つでも取った人はなると思っていてください
ただ、これにも個人差があります。全ての人が重篤化するものではありませんし手術の方法によっても差があります。他の人がなっているから自分も。というものではありません
違和感がある場合は、必ずリンパ外来に行ってみてください
そして少しの時間でもいいからマッサージをしてみてください(上肢・下肢編を見てください)
2010年の12月にミラクルガールの本について書いた自分のブログを読むと、まだまだ体調の悪い私がいます。やっぱり元気になったな~~。なんて思いました
どんなにつらくても、やっぱり元気になっていくんだな。と思いました
ミラクルガール:http://miyabimari.tamaliver.jp/e146817.html
リンパドレナージュ上肢編:http://miyabimari.tamaliver.jp/e147695.html
リンパドレナージュ下肢編:http://miyabimari.tamaliver.jp/e147697.html
鍼灸やリンパドレナージの有用性に着目:http://mag.gto.ac.jp/cat8/cat9/---4-9.html